スマドリ株式会社様
「酒を飲まない人」にもベストな顧客体験を届けるために。実験&共創型コミュニティの挑戦

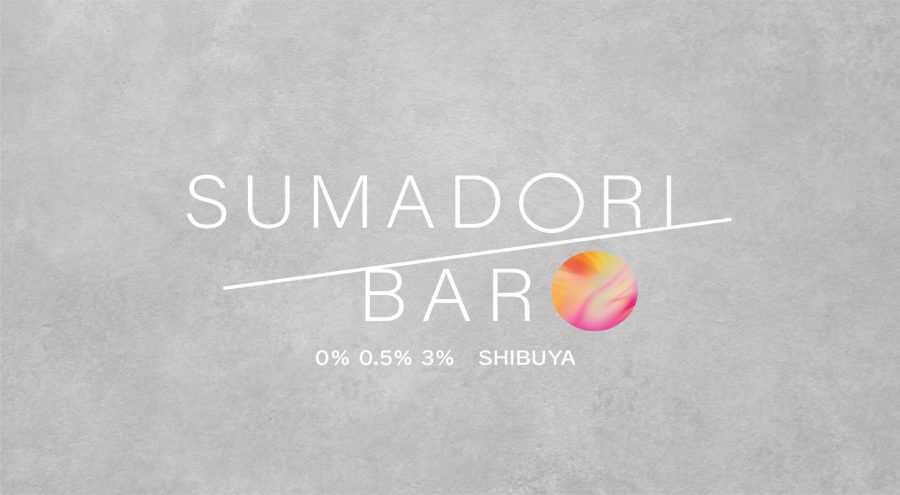

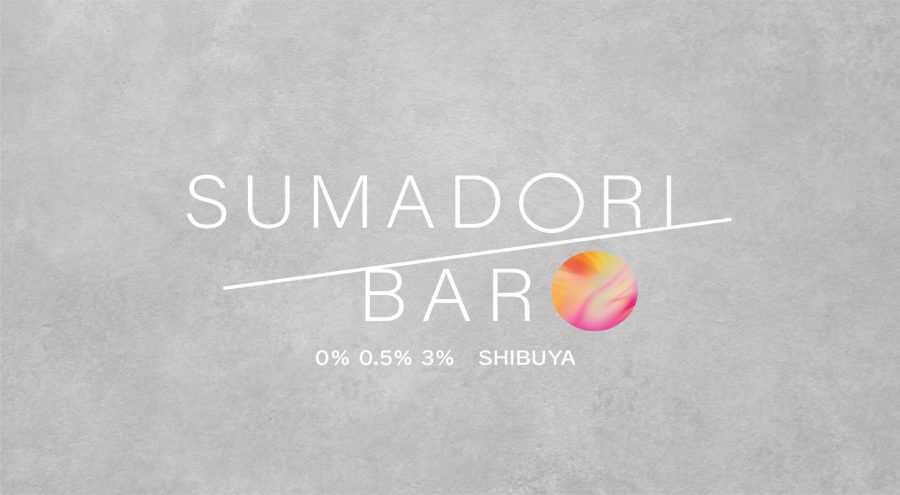
- 概要
- スマドリ株式会社は、アサヒビールと電通デジタルが2022年1月に設立した合弁会社で、お酒を飲む人も飲まない人も楽しめる新しい飲食文化「スマートドリンキング」の普及、推進を行っています。2022年に実店舗「SUMADORI-BAR SHIBUYA」をオープンした後、2024年5月に熱量の高いファンとの共創を目的としたコミュニティ「SUMADORI-LAB.」を開設。ファンの声を商品開発や企画に反映し、お酒を飲めない人のニーズ可視化とスマートドリンキングの浸透を図っています。コミュニティづくりの経緯と成果をスマドリ株式会社の吉岡様にお聞きしました。
- 運用体制
- ・電通デジタルのプランナーやエディターなど3名が日常的な運用や企画立案を担当
・スマドリの担当者2名が主にコンテンツの承認や企画方針の決定を担当
- 導入の決め手
- ・Communeからの戦略立案や他社事例の共有、運用サポートへの信頼感
・ファンの声を商品開発や企画に活かすための共創の場にできると感じた
課題
-
スマドリカルチャーにより深く共感してくれるファン層の可視化
-
ファンの意見を商品開発や店舗運営に効果的に反映させる仕組み作り
-
スマドリカルチャーを広げていくための熱量の高い支持者層の形成が必要
活用方法
-
月1回程度のリアルイベント開催
-
ファンからの提案によるメニュー開発と店舗での提供
-
コミュニティ内での活発な情報交換やフィードバックの収集
成果/これからの目標
-
コミュニティの基礎となる熱心なファン120名が参加
-
ファン考案のドリンクが人気メニューとなるなど、商品開発の成果
-
「スマートドリンキング」文化の共創と発信の基盤づくり
「飲めない人」の顧客体験を可視化したい
はじめに貴社事業の概要を教えてください。
スマドリ株式会社は、2022年1月にアサヒビールと電通デジタルが共同で設立した合弁会社です。弊社はお酒を飲む人も飲まない人も楽しめる場や体験を提供し「スマートドリンキング」という新しい飲食文化の創造を目指しています。この背景には、日本人の半数が『お酒を飲めない』という実態がアサヒビールの調査によって判明した点があげられます。この結果を受け、従来のアルコール好きへのアプローチだけでなく、飲めない人々にも目を向ける必要性を認識しました。
そうした飲めない方々のニーズを理解し、適切な価値を提供するために、「SUMADORI-BAR SHIBUYA」(以下、スマドリバー)を運営しています。ここは単なる飲食店ではなく、飲めない方々の顧客体験の研究施設としての側面があります。様々な飲食プランを提案し、そこから得られるデータやフィードバックを基に、よりよいサービスの開発に取り組んでいます。
マーケティングや研究の場として店舗がある一方で、コミュニティ「SUMADORI-LAB.」(以下、スマドリラボ)を立ち上げようと思ったのはなぜですか?
スマドリバーをスマドリ文化における「聖地」として位置づけ、その周りにファンコミュニティを作りたいと考えました。新しいカルチャーの認知を広げ、共感を得ていくには、強力なファン、支持者の存在が不可欠です。

スマドリ株式会社
アライアンスマネージャー
吉岡 敦史様
スマドリバーにも常連のお客様はいらっしゃいますが、利便性が高いからという理由で来店されている可能性もあり、スマドリというコンセプトへの理解度や熱量が見えづらい状況でした。また、店舗はあくまで飲食を楽しむ場所なので、お客様同士の交流や意見交換などスマドリの意識を醸成する雰囲気を作り出すのは難しかったのです。
そこで、より深くブランドに共感してくれる方々が集まり、アイデアを出し合える場として「SUMADORI-LAB」を立ち上げることにしました。ここでは単にコミュニティへの投稿やお知らせを受け取るだけでなく、新商品開発や企画立案にも参加していただき、より深い形でスマートドリンキングの普及に関わっていただくことを目指しています。
成功への道筋を示すコミューンをパートナーに
Communeを選んでいただいた経緯をお聞かせください。
実は当初、他社のプラットフォームも含めて検討していたのですが、そもそもコミュニティを立ち上げることに対して社内の同意をなかなか得られませんでした。一部には、コミュニティの意義を問うような指摘もありました。
その中で、コミューンさんだけが、社内の説得材料となる資料作成や具体的な成功事例の提示など、伴走型でのサポートを提供してくれました。他社にない形で「こうした反応が予想されます。そのときは、こうしたデータを示すといいです」など、伴走しながら具体的な提案をしてくれました。
また、どんなKPIを設定して追えばよいかなど、運用に関する細かなアドバイスもありがたかったです。単にプラットフォームを提供するだけの存在ではなく、コミュニティ運営の成功に向けて道筋を示してくれるパートナーになってくれると確信し、Communeを選択しました。
運用の体制について教えてください。
現在、5名体制で運営を行っています。弊社の2名と、電通デジタルからプランナー、プロジェクトマネージャー、エディター兼ディレクターが参画しています。電通デジタルのメンバーが日常的な運営や企画立案を担当し、私を含めたスマドリ社のメンバーが内容を確認・承認する形式です。
「今月はこういうイベントを実施したい」「このような投稿を予定している」といった提案について、スマドリ社で検討し承認を行います。また、親会社であるアサヒビールとも密接に連携しており、必要に応じてコンテンツのレビューを行っています。
店舗とコミュニティの関係性についてお聞かせください。
スマドリバーは、よい顧客体験を生み出す源泉でありたいと考えています。一方でスマドリラボではメンバーとの対話を通じて、最適な顧客体験を探る場として機能しており、コミュニティで生まれた仮説を店舗に持ち返って検証するという流れを大切にしています。

客層については、店舗では20代の女性が7~8割を占めているのに対し、コミュニティは幅広い年齢層の方々が参加されています。当初、コミュニティの参加者はバーの常連客を想定していました。しかしスマドリラボは、スマートドリンキングというカルチャーの認知拡大も目的としているため、常連客に限らず、コンセプトに共感する方々にも積極的に参加を呼びかけることにしました。より多くの人と交流することで、コンセプトへの理解や共感の広がりを可視化し、多様なアイデアを共有できると考えたためです。その結果、店舗の客層とは異なるメンバーがコミュニティに集まりました。
来店経験がなくてもコミュニティに参加してくださっている中高年層の方も多く、過去にアルコールハラスメントを受けた、または目の当たりにした経験から、コンセプトに強く共感してくださっているのだと推測しています。
共創が形に ファンの声から生まれた新メニュー
コミュニティでは定期的にイベントを開催しているとお聞きしました。
イベントは月1回程の頻度で開催しており、メンバーが主体的に関わる企画には特に手応えを感じています。例を挙げると、オリジナルカクテルの開発ワークショップですね。コミュニティメンバーが考案したドリンクが実際に店舗で販売されるメニューとなり、プロが作ったロングセラーの人気メニューと肩を並べるほどの好評を得ています。コミュニティの企画から生まれたメニューがこれほどの成果を上げるのは画期的な出来事だと思います。

またバーテンダーが毎日行う仕込み作業を見学する「裏側ツアー」も企画中です。通常は見ることのできない商品の仕込み工程を見学することで、どのようにアルコール飲料やノンアルコール飲料が生み出されているかを知り、スマドリへの理解と愛着を深める機会となっています。人の意見を聞くだけではなく、メンバー自身が何かを生み出したり、普段できない体験をする企画のほうが、高い満足度につながる傾向に気づきました。
こうしたインサイトはコミュニティがなければ得られなかった発見だったと考えています。イベントでの体験や交流を通じて、メンバーの声をより深く理解し、それを商品開発やサービス改善に活かしていく。そうした循環を作っていけることが、コミュニティの大きな価値だと感じています。
ただし、熱心なファンが集まるのは非常にありがたい一方で、コミュニティにおいて肯定的な意見しか聞けなくなるという課題も出てきています。改善点を尋ねても「現状のままで完璧です」といった答えが多くなってしまうんです。やはり少数派の声や、時には耳の痛い意見も聞けないと一部の意見に偏ったり固定化したりするので、常に新しい風を取り入れなければならないと感じています。
コミュニティを起点にスマートドリンキングを社会へ届ける
スマドリラボ立ち上げ後の、コミューンのサポートはどのように評価されていますか。
定例会議での提言が大変役に立っています。こちらからの相談を待つのではなく、他社の事例を活用しながら、自ら積極的に提案してくれる姿勢は、豊富な知識と経験があってこそだと思います。「初期はコミュニティのオーナーやユーザーがこういうところでつまずくはず」という予測がしっかりしていて、先回りした提案ができるのはすごいですよね。
数値目標の設定や追跡についても実践的なサポートをいただいています。例えば、アクティブ率やイベント参加率、アンケート回答率といったKPIについて、この規模のコミュニティならどの程度が適切な目標値なのか、どういった頻度でモニタリングすべきかなど、具体的なアドバイスをいただいています。まだ道半ばですが、ファンパワー、ファンレベルを把握できるようになってきた手ごたえはありますので、これを次の施策に活かさなくてはなりませんね。
今後に向けた展望をお聞かせください。
私たちの目標は「飲めない人の可視化」であり、お酒を飲まなくても楽しめる環境を提供していくことです。コミュニティを通じて、飲めない方にとって最適なスマドリ体験を明らかにし、実店舗での提供にもつなげていきたいと考えています。
それにはやはり、コミュニティ活動自体の規模を拡大していく必要があります。現在120名程度の会員数をより増やし、イベントの開催頻度を上げ、より活発な活動を展開していきたいと考えています。また、バーの多店舗展開なども計画したいところです。これまでコミュニティを通じて得られた発見や、ここでしか得られなかった情報の価値は社内でも評価されています。この実績を基に、より大きなスケールでの展開を目指すことでスマドリという新しい文化の定着が実現できると信じています。
コミュニティに「ラボ」と名づけたとおり、スマドリ普及に向けたさまざまな実験が展開されることを期待しています。今日は、ありがとうございました。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeをご利用いただいている事例を活用方法ごとに整理!自社と同じ課題・導入目的を持った企業の事例がわかります!
Communeをどう使う?活用ケース分類


