コラム
マーケティング
ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは? 優良顧客との違い・重要性、育成・維持のポイントを解説
2024/07/03
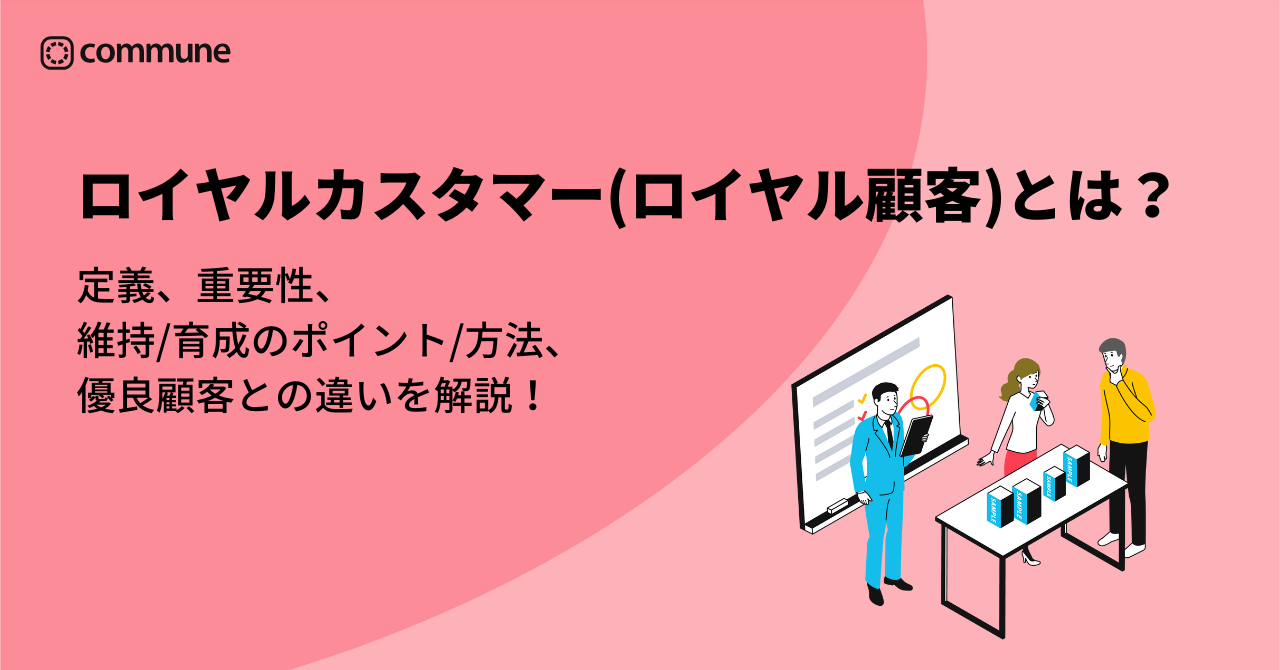
ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは一般的な優良顧客よりも一歩深く、企業やブランドそのものに強い信頼と愛着を抱き、自発的に応援し続けてくれる顧客のことを指します。購入頻度や金額が高いだけでなく、口コミの発信、商品改善への協力、友人への推薦など、企業の成長に直接的な貢献をもたらす存在です。
新規獲得コストの上昇やSNSによる口コミ拡散の加速など、環境変化が大きい今、ロイヤルカスタマーの育成と維持は多くの企業にとって避けられないテーマとなっています。しかし、「優良顧客との違いが曖昧」「顧客ロイヤルティをどう測ればいいのか」「育成の具体的なステップがわからない」といった課題も少なくありません。
本記事では、ロイヤルカスタマーの定義と優良顧客との違い、重視される背景、顧客ロイヤルティの測定方法(NPS・CES・RFM)などを体系的に整理します。そのうえで、ロイヤルカスタマーを維持・育成するための実務的なポイントや、コミュニティを活用して成果を上げている企業の事例もご紹介します。
LTV向上や顧客エンゲージメントの強化を目指す企業にとって、実践的なヒントとなる内容を網羅しています。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)とは
ロイヤルカスタマーとは、企業やブランドへのロイヤルティが特に高い顧客のことで、わかりやすくいえば「熱心なファン」に近い存在です。継続的な利用や高い売上貢献はもちろん、企業そのものへの強い信頼や愛着を抱いている点が最大の特徴です。
ビジネスでは顧客をさまざまな名称で分類しますが、そのなかでも最上位に位置づけられるのがロイヤルカスタマーです。彼らは単なる優良顧客を超え、ブランド価値の共創にまで関わってくれる、企業にとって最も重要な顧客層といえます。
ロイヤルカスタマーと優良顧客の違い

多くの企業が顧客の囲い込みを重視するなかで、「優良顧客」と「ロイヤルカスタマー」という言葉はよく使われます。一見すると似た概念に見えますが、両者には本質的な違いがあります。ここでは、その違いを“心理面”と“行動面”の2つの軸から整理します。
心理ロイヤルティ(心理面)
ロイヤルカスタマーの最大の特徴は、企業やブランドへの強い信頼と愛着です。単に商品・サービスに満足しているだけでなく、企業の理念や価値観に共感し、「このブランドと関わり続けたい」という感情的な結びつきを持っています。
この心理的ロイヤルティは、一時的な不満や競合の魅力的なオファーがあっても容易に離れない強さがあります。ブランドストーリーを自分ごとのように感じ、その成長を自らの喜びとして受け取る傾向すらあります。
行動ロイヤルティ
行動面では、ロイヤルカスタマーは継続的な購買にとどまらず、企業にとって多面的な価値を生み出します。新商品の先行購入、SNSでの積極的な推奨、友人・家族への紹介など、自発的にブランドの拡張を担う存在です。
一方、優良顧客は購入金額や頻度は高いものの、必ずしも企業に愛着があるとは限りません。より良い条件を提示する競合が現れれば容易に離脱する可能性があります。
また、ロイヤルカスタマーは継続利用の中でサービス改善のための建設的なフィードバックを積極的に提供するケースも多く、企業にとっては価値共創のパートナーとなり得る存在です。
このようにロイヤルカスタマーは単なる購買者を超え、ブランド価値の共創に関わる重要な顧客層です。心理的・行動的ロイヤルティの両面を兼ね備えていることが、優良顧客との決定的な違いといえます。
■ロイヤルカスタマーの貢献、可視化できていますか?Commune Engageは顧客のあらゆる貢献行動を可視化し、還元し、売上につなげます。
↓3分でわかるCommune Engage解説資料をDLする↓
https://commune.co.jp/wp/engage_introduction/
ロイヤルカスタマーが注目される背景
企業の成長戦略において、ロイヤルカスタマーの育成と維持がこれまで以上に重要視されています。その背景には、近年のビジネス環境の変化が大きく影響しています。
SNSの普及による口コミ影響力の拡大
SNSの普及により、顧客の声(VoC)がビジネスにもたらす影響は飛躍的に高まりました。かつて商品やサービスに関する情報は、広告やマスメディアから企業が一方的に発信するものでした。しかし現在は、顧客自身がSNSを通じて体験談や評価、改善要望を自由に発信する時代です。
特にロイヤルカスタマーによるレビューや使用感の共有は、実体験に基づく信頼性の高い情報として、潜在顧客の購買判断に大きな影響を与えています。企業にとって、こうした“自発的に推奨してくれるアドボケイト”の存在は、従来の広告に代わる強力なマーケティング資源となりつつあります。
さらに、VoCによって形成される商品評価は、企業が自ら発信する広告やPR以上に説得力を持つため、製品開発やサービス改善における重要なインプットとして活用されています。
顧客獲得コストの上昇
デジタル広告の競争激化や消費者のプライバシー意識の高まりにより、新規顧客の獲得コストは年々上昇しています。広告費の高騰に加え、個人情報保護規制の強化によってターゲティング広告の精度も低下し、「広告を出せば獲得できる」時代ではなくなりつつあります。その結果、企業は新規獲得偏重の戦略から、既存顧客との関係性を深める戦略へとシフトせざるを得なくなっています。
とりわけ、継続的にブランドを利用し続けるロイヤルカスタマーは、追加獲得コストをかけずとも安定的な収益を生み出す存在として価値が高まっています。加えて、彼らは新商品のフィードバックを早期に提供するなど、商品開発の効率化にも貢献します。ロイヤルカスタマーからのフィードバックは市場調査よりも具体性と信頼性が高く、的確な改善につながるケースが多いことがわかっています。
さらに、彼らの紹介によって獲得された新規顧客は、広告経由の顧客と比べ離脱率が低く、LTVも高いという特徴があります。こうした背景から、ロイヤルカスタマーは“最も費用対効果の高い顧客資産”として注目されているのです。
消費者価値観の変化
現代の消費者は商品やサービスの機能性だけでなく、企業の社会的責任(CSR)や環境配慮、理念・姿勢といった“価値観の一致”を重視するようになっています。特にミレニアル世代やZ世代は、自身の価値観と合致する企業を積極的に選び、そのような企業には高いロイヤルティを示す傾向が強いとされています。
この変化は、企業がロイヤルカスタマーを重視すべき理由をさらに強くしています。なぜなら、価値観を共有する顧客は、購買だけでなくブランドの活動そのものに協力し、共に価値をつくる“共創者”へと成長するからです。実際に、環境配慮型製品の開発過程への参加、企業の地域活動への自主的な協力など、単なる消費者を超えた関わり方が広がっています。
こうした共創的な関係は、企業のESG評価の向上にも寄与し、投資家からの評価にもポジティブな影響をもたらしています。企業の持続可能な成長を支えるうえで、価値観を共有し、共に未来をつくるロイヤルカスタマーの存在は欠かせません。
ロイヤルカスタマーを重視すべき理由

持続的な企業成長を実現するうえで、ロイヤルカスタマーは単なる優良顧客以上の価値をもたらします。ここでは、その重要性を具体的な観点から整理します。
LTV向上
LTVとは、顧客がブランドと接点を持ってから関係が終了するまでにもたらす収益の総額です。ロイヤルカスタマーは企業への強い愛着と信頼を持っているため、長期間にわたって継続的に利用してくれる傾向があります。
そのため一人あたりの収益が高く、事業の安定を支える基盤となります。また、彼らは商品の良さを自発的に周囲に伝え、肯定的なレビューや体験を共有してくれるケースが多くあります。「家族や友人が推しているから買ってみよう」という心理が働くため、紹介経由の新規顧客が増えるという効果も生まれます。
企業が高額な広告費を投じなくても、口コミを通じて自然に商品が広がる状態をつくれることこそ、ロイヤルカスタマーの存在がもたらす最大の利点です。
積極的な情報発信者としての役割
ロイヤルカスタマーは、アドボカシーマーケティングにおける中心的存在です。SNSやブログでの体験共有、商品の魅力の発信、使用方法の紹介など、彼らの情報発信は“広告以上に響くリアルな声”として機能します。
特に以下の点で大きな価値があります。
-
実体験に基づくレビューの信頼性
-
商品理解が深いため、説明の質が高い
-
他のユーザーからの共感を得やすい
従来の広告では生み出しにくい説得力と熱量を備えており、ブランド認知の拡大や購入検討の後押しに大きく寄与します。
新しい顧客の紹介源としての役割
ロイヤルカスタマーによる紹介は、最も費用対効果の高い顧客獲得チャネルといえます。紹介された側は、すでにブランドの価値を“信頼できる人を通じて”理解しているため、以下の特徴があります。
-
成約率が高い
-
初期離脱率が低い
-
LTVが高い傾向がある
-
高確率で新たなアドボケイトへ成長する
企業側が広告を打つよりも、はるかに高い質の見込み客を連れてきてくれるのがロイヤルカスタマーです。こうした好循環を生むアドボカシープログラムの中心にいる存在が、事業成長の強力な推進力となります。
サービス/プロダクトのフィードバックを取得できる
サービスや商品の改善において、顧客からのフィードバックは欠かせません。そのなかでも、ロイヤルカスタマーの声は特に価値が高いものです。長く愛用してきたからこそ見える視点や、実体験に根ざした具体的な指摘は、一般的なアンケートでは得られない深い示唆を含んでいます。
こうした良質なフィードバックは、サービス品質の向上だけでなく、新機能の追加や商品開発の方向性を決める重要なヒントにもなります。企業にとってロイヤルカスタマーは“最も信頼できる開発パートナー”でもあり、その意見を取り入れることが競争力向上につながります。
■ロイヤルカスタマーの貢献、可視化できていますか?Commune Engageは顧客のあらゆる貢献行動を可視化し、還元し、売上につなげます。
↓3分でわかるCommune Engage解説資料をDLする↓
https://commune.co.jp/wp/engage_introduction/
ロイヤルカスタマーと優良顧客の違いを分ける「顧客ロイヤルティ」とは?
ロイヤルカスタマーと企業の間に形成される信頼や貢献の度合いは、専門的には「顧客ロイヤルティ」と呼ばれます。これは大きく 心理的ロイヤルティ と 行動的ロイヤルティ の2つに分けて考えることができます。
心理的ロイヤルティ(感情の結びつき)
心理的ロイヤルティは、企業・ブランド・商品に対する好意的な感情を指します。例えば、
-
「新作が出たら真っ先に試したい」
-
「この企業の商品なら間違いない」
といった考え方がこれに該当します。ブランドの理念や価値観に共感し、「この企業が好きだから選ぶ」という状態です。
行動的ロイヤルティ(行動の継続)
行動的ロイヤルティは、購入金額・購入頻度・継続利用といった、直接的な貢献度を表します。つまり、「実際にどれだけ行動で支持しているか」を示す指標です。
顧客ロイヤルティは段階的に醸成される
顧客ロイヤルティの形成は、企業と顧客の関係性を段階的に整理した「顧客満足型マーケティングの展開フレーム」で理解しやすくなります。顧客との関係は次の4段階で進みます。
-
獲得フェーズ(Get customer)
初回購入によって、顧客データを獲得する段階。 -
関係構築フェーズ(Build relationship)
継続購入してもらえるよう、商品・サービスとの接点を増やし関係性を築く段階。 -
育成フェーズ(Grow relationship)
コミュニケーションを通じて、顧客との関係をより深める段階。 -
維持フェーズ(Keep customer)
長期的な関係を維持し、心理面・行動面のロイヤルティが最大化される段階。ここに到達した顧客がロイヤルカスタマーです。
段階が上がるほど顧客数は減る一方で、ロイヤルティの質は高まります。④まで育ったロイヤルカスタマーは、心理的にも行動的にも企業の強力な支援者となります。
ロイヤルカスタマーは“自然には育たない”
新規顧客を獲得しただけで放置してしまうと、ロイヤルカスタマーには育ちません。ブランドに興味を持ち続けてもらい、愛着を育てるための継続的な働きかけが必要です。
そのためには、
-
顧客のニーズを丁寧に把握する
-
提供価値をアップデートし続ける
-
顧客と対話する機会を継続的に設計する
といったアプローチが欠かせません。企業の努力によって初めて、顧客ロイヤルティは積み上がっていきます。
■ロイヤルカスタマーの貢献、可視化できていますか?Commune Engageは顧客のあらゆる貢献行動を可視化し、還元し、売上につなげます。
↓3分でわかるCommune Engage解説資料をDLする↓
https://commune.co.jp/wp/engage_introduction/
顧客ロイヤルティの分析方法
顧客ロイヤルティを適切に測定し、分析することは、効果的なカスタマーエクスペリエンス戦略の立案において重要です。ここでは、実務で活用されている主要な分析手法について解説していきます。
NPS(Net Promoter Score)による推奨度測定
NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客ロイヤルティを測定する最も一般的な指標の一つです。「この商品・サービスを友人や同僚に推奨する可能性はどのくらいありますか?」という質問に対して、0から10の11段階で回答を得ます。9-10点を「推奨者」、7-8点を「中立者」、0-6点を「批判者」と分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引いた値がNPSとなります。この手法は、シンプルながら顧客の推奨意向を定量的に把握でき、継続的なモニタリングが容易という特徴があります。
カスタマーエフォートスコア(CES)による利便性評価
RFM分析による顧客行動の多角的評価
RFM分析は、Recency(最終購買日)、Frequency(購買頻度)、Monetary(購買金額)の3つの指標から顧客の行動を総合的に評価する手法です。各指標にスコアを設定し、顧客をセグメント化することで、ロイヤルカスタマーの特定や育成施策の立案に活用できます。例えば、全指標が高いグループは最優良顧客として特別なケアを行い、一部指標が低下傾向にある顧客には早期にアプローチするなど、顧客に合わせた効果的な施策展開が可能となります。
■ロイヤルカスタマーの貢献、可視化できていますか?Commune Engageは顧客のあらゆる貢献行動を可視化し、還元し、売上につなげます。
↓3分でわかるCommune Engage解説資料をDLする↓
https://commune.co.jp/wp/engage_introduction/
ロイヤルカスタマーを維持するために必要なコミュニケーション戦略は?
顧客ロイヤルティを維持かつ向上するには、適切なコミュニケーション戦略が不可欠です。多くの顧客離反の背景には、企業とのコミュニケーション不足や「大切にされていない」という感覚があることが指摘されています。このことは、戦略的なコミュニケーションの重要性を示唆しています。効果的なロイヤルカスタマーとのコミュニケーション戦略は、以下の3つの要素で構成されます。
第一に、パーソナライズされたコンテンツの提供です。顧客の購買や利用履歴、問い合わせ履歴などを分析し、一人ひとりの興味や関心に合わせた情報を適切なタイミングで届けることが重要です。これには、新商品の先行案内や、関連商品のレコメンデーション、使用方法のヒントなど、顧客にとって価値のある情報が含まれます。
第二に、双方向のコミュニケーションチャネルの確立です。顧客の声を積極的に聞き、それに対して迅速かつ適切に対応できる体制を整えることが必要です。これには、カスタマーサポートの質の向上だけでなく、開発への顧客意見の反映や、フィードバックに基づくサービス改善など、顧客の声を実際のアクションにつなげる仕組みづくりも含まれます。
第三に、特別な体験や価値の提供です。ロイヤルカスタマー限定のイベントや、早期利用キャンペーン、特別な限定サービスの提供など、一般顧客とは異なる特別な待遇を通じて、顧客の帰属意識や満足度を高めることが重要です。これらの施策は、心理的ロイヤルティを強化し、顧客との長期的な関係構築に貢献します。これらの戦略を効果的に実行することで、ロイヤルカスタマーとの継続的な関係を維持し、さらなる価値創造につなげることが可能となります。
ロイヤルカスタマーを創出・育成する方法

顧客をロイヤルカスタマーに育成するのは、簡単ではありません。以下では4つのステップに分けて具体的な方法を解説します。
顧客が求める価値の定義
ロイヤルカスタマーを育成するためには、顧客が求める価値を改めて確認することが大切です。提供価格を下げたり、キャンペーンを打ったりすることで、相対的に価値を高めるのは簡単です。しかし、それは本質的に顧客が求めていることとは限りません。
顧客の愛着を形成するためには、製品やサービスを通して顧客の価値を増幅することが重要です。「顧客が求めているもの」「利用してみての課題」など、顧客体験を改めて見直すことがはじめの一歩といえます。顧客とのコミュニケーションを通して、価値を掘り下げるのも1つの方法です。
現状の顧客ロイヤルティの把握
現状の顧客ロイヤルティを把握することは、非常に重要なステップです。顧客がどれだけ愛着や信頼を感じてくれているのかを客観的に知ってはじめて、新たな施策を打つことができます。
方法の1つとして有名なのが、「顧客推奨度調査」です。サービス利用後に行われるアンケートのなかに、「周りに勧めたいと思いますか?」という内容の質問がよく設けられています。それこそが「顧客推奨度調査」です。
勧めたいかどうかを0〜10の11段階で評価してもらうことによって、顧客満足度を定量的に把握し、戦略に活かすことができます。以下のように、数値によって顧客ロイヤルティの度合いがわかります。
・0~6と評価している人:批判者
・7~8と評価している人:中立者
・9~10と評価している人:推奨者
優先ターゲットの選定
現状の顧客ロイヤルティを把握したところで、優先ターゲットを選定します。顧客のなかにもさまざまな顧客がいるため、顧客をセグメントに分けることで、施策が検討しやすくなります。顧客推奨度と収益性のデータをもとに分類すると、以下の6つにわけられます。
A:収益性が高い推奨者
収益性が高く、顧客推奨度が高い顧客は、ロイヤルカスタマー。ここに属する人たちは最優良顧客層といえ、企業にとって最重要のセグメントといえます。
B:収益性が高い中立者
ロイヤルカスタマー候補者層。収益性は高いけど、人に勧めるまではしない顧客。ロイヤルカスタマーに移行してもらうために施策を講じる必要があります。
C:収益性が高い批判者
お金を使ってくれているにも関わらず、顧客推奨度が低い層。優良顧客ではあるが、ロイヤルカスタマーとはいえない顧客です。重要な顧客であるため、ロイヤルカスタマーに移行してもらうために、顧客のロイヤルティ向上策を検討する必要があります。
D:収益性が低い推奨者
他人には勧めるにも関わらず、自分では買わない層。「高額で手が届かない」「近くにお店がない」などの何らかの理由があることが考えられます。
E:収益性が低い中立者
お金を使わず、他人にも勧めない顧客。企業に対しての関心が感じられないため、優先順位は低めです。
F:収益性が低い批判者
ロイヤルカスタマーからもっとも遠い層。優先順位がもっとも低い顧客です。
顧客を分類したあとは、どこまでの顧客をフォローするかを検討し、施策を考えます。優先順位は企業の状況やセグメントの比率によっても異なります。
■ロイヤルカスタマーの貢献、可視化できていますか?Commune Engageは顧客のあらゆる貢献行動を可視化し、還元し、売上につなげます。
↓3分でわかるCommune Engage解説資料をDLする↓
https://commune.co.jp/wp/engage_introduction/
ロイヤルカスタマー育成のポイント
顧客をロイヤルカスタマーへと育成するためには、長期的な視点に立った戦略的なアプローチが必要です。以下では、成功のための重要なポイントを解説します。
一貫性のあるカスタマーエクスペリエンスの提供
顧客の信頼を獲得し、維持するためには、すべてのタッチポイントにおいて一貫性のある質の高い体験を提供することが重要です。これは商品やサービスの品質だけでなく、カスタマーサポート、ウェブサイト、実店舗、SNSなど、あらゆるタッチポイントにおける体験の質を意味します。特に重要なのは、顧客の期待値を常に把握し、それを上回る価値を提供し続けることです。また、問題が発生した際の対応の質も、ロイヤルティ形成に大きな影響を与えます。迅速で誠実な対応は、むしろ信頼関係を強化する機会となり得ます。
顧客インサイトに基づく継続的な改善
ロイヤルカスタマーを育成するためには、顧客の声に真摯に耳を傾け、そこから得られるインサイトを活用することが重要です。定期的な顧客調査やフィードバックの収集、行動データの分析を通じて、顧客のニーズや課題、期待を深く理解する必要があります。そして、それらの知見を製品開発やサービス改善に活かすことで、顧客との関係性を深化させることができます。特に、顧客の潜在的なニーズを発見し、先回りして対応することは、顧客の期待を超える体験を創出する上で重要です。
エモーショナルな繋がりの構築
単なる取引関係を超えて、顧客との感情的な繋がりを築くことは、ロイヤルティ形成において極めて重要です。顧客に対して、ブランドの価値観や理念を明確に示し、それに共感する顧客との絆を深めていく必要があります。また、顧客一人ひとりの特別な瞬間(誕生日や記念日など)を逃さず、パーソナライズされたメッセージや特典を提供することで、より深い心理的な繋がりを築くことができます。さらに、コミュニティの形成を支援し、顧客同士の交流を促進することで、ブランドへの帰属意識を高めることも効果的です。
ロイヤルカスタマー育成に「Commune(コミューン)」を活用している事例
多くの企業がCommune(コミューン)を活用してロイヤルカスタマーの育成に成功しています。ここでは、特に効果的な活用事例をご紹介します。
日本ケロッグ合同会社
日本ケロッグ合同会社は、ロングセラー商品「オールブラン」のロイヤルカスタマー育成を目的に、Commune(コミューン)を活用したコミュニティ「オールブラン腸活部」を立ち上げました。コミュニティでは、商品の食べ方やレシピの共有、腸活に関する情報交換など、部員同士の活発な交流が行われています。
立ち上げ時は約70名の小規模なクローズドコミュニティからスタートし、質の高いコミュニケーションを重視しましたが。「オールブランすっきりチャレンジ」などの企画を通じて参加者を徐々に拡大し、約700名規模のコミュニティへと成長しました。その結果、部員の平均喫食回数が1.6倍に増加し、ブランド内での買い回り率も向上。全5種中3種以上の商品を購入する部員が44%を占めるまでになりました。
さらに、部員から寄せられる商品活用法や改善要望は、製品開発にも活かされており、双方向のコミュニケーションを通じた価値共創の場として機能しています。

*日本ケロッグ合同会社の事例インタビューをみる
喫食回数1.6倍!ロングセラー商品のコミュニティで実現する顧客インサイトの獲得とロイヤルカスタマー化
株式会社LIXIL
LIXILは、猫用キャットウォーク「猫壁(にゃんぺき)」の開発・販売において、ユーザーとの関係構築を目的にCommune(コミューン)を活用したコミュニティ「猫壁ひろば」を立ち上げました。当初SNSでの顧客接点づくりを試みたものの、継続的な交流が難しかったことから、専用のコミュニティプラットフォームの必要性を認識したことがきっかけです。
コミュニティでは、製品の使用方法の共有や猫との暮らしについての情報交換が活発に行われています。特筆すべきは、コミュニティメンバーの声を直接製品開発に活かしている点です。2023年夏には会員を開発拠点に招き、新製品の色選定に参加してもらうなど、ユーザーの声を製品仕様に反映。このような取り組みを通じて、高単価製品ならではのロイヤルカスタマー育成に成功しています。
さらに、コミュニティ内での安心感のある交流や製品開発への参加体験が、購買意欲の向上にもつながっており、D2C(Direct to Consumer)の実践の場としても機能しています。

*株式会社LIXILの事例インタビューをみる
コミュニティの意見を製品へダイレクトに反映!高単価製品だからこそ大切なブランドロイヤルティの向上方法とは
ロイヤルカスタマー(ロイヤル顧客)の育成ならCommune(コミューン)
これまで見てきたように、ロイヤルカスタマーの育成には、双方向のコミュニケーションとエモーショナルな繋がりの構築が不可欠です。顧客との深い信頼関係を築き、維持していくためには、適切なコミュニケーション基盤が必要となります。
Commune(コミューン)は、このニーズに応えられる、新しい形のコミュニティサクセスプラットフォームです。従来の一方的な情報発信だけでなく、顧客との継続的な対話を可能にし、それぞれの顧客に合わせたパーソナライズされた体験を提供します。従来の一方通行とは違う、双方向コミュニケーションで顧客からのフィードバックを収集・分析する機能も備えており、継続的な改善活動にも活用できます。顧客一人ひとりに寄り添い、長期的な信頼関係を築きたい企業にとって、Commune(コミューン)は強力なパートナーとなるでしょう。ロイヤルカスタマーの育成に本気で取り組むなら、まずはCommune(コミューン)を検討してみてはいかがでしょうか。
以下のフォームから「3分でわかるCommune」資料を無料でダウンロードできます。気になる方は、ぜひご確認ください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
