コラム
マーケティング
単純接触効果(ザイオンス効果)とは?広告・営業で好意を育てる仕組みと正しい活用法
2026/01/08
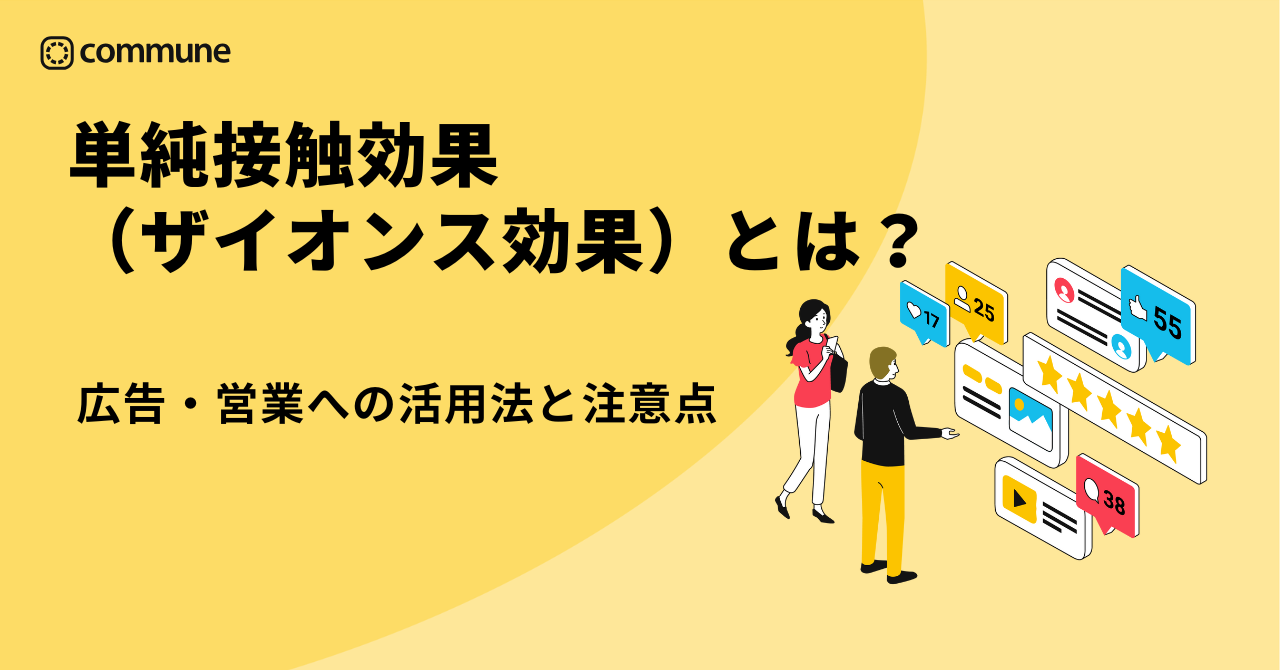
単純接触効果(ザイオンス効果)とは、人が同じ対象に繰り返し接することで、無意識のうちに親近感や好意を抱きやすくなる心理現象です。広告で何度も目にするブランドに安心感を覚えたり、営業で顔を合わせる回数が増えるほど話しやすく感じたりする背景には、この効果が働いています。
この心理は、特別な説得や強い訴求を行わなくても作用するため、広告、営業、SNS、イベントなど、あらゆるマーケティング施策に応用可能です。一方で、「接触回数を増やせば増やすほど効果が高まる」という単純なものではなく、使い方を誤ると逆に嫌悪感を生んでしまうリスクもあります。
だからこそ重要なのは、接触の“量”ではなく“設計”です。どのチャネルで、どのタイミングで、どのような文脈で接触するのか、その積み重ねが、好意や信頼につながるかどうかを左右します。本記事では、単純接触効果の基本的な仕組みから、広告・営業における具体的な活用法、そして見落とされがちな注意点や効果を高めるコツまでを整理して解説します。
顧客との接点設計、お困りではありませんか?
顧客との接点設計、お困りではありませんか?
- 接触回数を増やしたが、好意や信頼につながっている実感がない
- 広告やメールが「うるさい」と受け取られてしまう
- 顧客との関係が単発で終わり、積み上がらない
- 接点づくりが、担当者の感覚や属人的な工夫に依存している
Communeは、単純接触効果が自然に働く顧客接点をコミュニティとして設計。
専門チームが戦略設計からKPI設計、運営実務までを伴走し、
「なんとなく好印象」を「選ばれ続ける関係」へと育てます。
Communeは、継続的な顧客接点をコミュニティとして設計。
専門チームが戦略設計からKPI設計、運営実務までを伴走し、
「なんとなく好印象」を「選ばれ続ける関係」へと育てます。
目次
1章:「接点設計」がマーケティング成果を左右する
「接触回数」だけで成果は出ない
マーケティングや営業の現場では、「露出を増やす」「接点を増やす」といった施策が重視されがちです。しかし現実には、広告費を投下しても、営業訪問を重ねても、必ずしも好意や信頼につながるとは限りません。
その理由は明確で、接触の“回数”だけを増やし、接触の“意味”や“文脈”が設計されていないケースが多いからです。人は単に何度も見たものを無条件に好きになるわけではなく、接し方次第で印象は大きく変わります。
好意は「慣れ」から生まれる
ユーザーの好意や信頼は、強いメッセージや論理的な説得によって生まれるとは限りません。むしろ、「よく見る」「なんとなく知っている」「見慣れていて安心できる」といった感覚的な要素が、意思決定に大きく影響します。
こうした“慣れ”や“親しみ”は、本人が自覚しないまま形成されることが多く、購買や選好の判断に静かに作用します。この無意識のプロセスを理解することが、接点設計の質を高める鍵になります。
心理学の視点が施策設計の精度を高める
人の感情や判断のクセを理解するうえで、有効なヒントを与えてくれるのが心理学の知見です。なかでも単純接触効果(ザイオンス効果)は、「なぜ繰り返し接するだけで印象が変わるのか」「なぜ逆効果が起こることがあるのか」を説明する代表的な理論です。
本記事では、この単純接触効果を起点に、広告・営業・ブランド構築における“接触の設計”をどのように考えるべきかを整理していきます。
2章:単純接触効果(ザイオンス効果)とは
繰り返し接することで好意が高まる心理現象
単純接触効果(ザイオンス効果)とは、人がある対象に繰り返し接することで、無意識のうちに親近感や好意を抱きやすくなる心理現象を指します。1968年に心理学者ロバート・ザイオンスによって提唱され、英語では mere exposure effect と呼ばれています。
この効果の特徴は、特別な説得や合理的な説明がなくても作用する点にあります。広告、ロゴ、人物、ブランド名など、意味を深く理解していなくても、「何度も見た」「よく接している」という事実そのものが、評価を徐々に好意的な方向へと動かします。
「好きになる前段階」で働く効果
単純接触効果が働くのは、強い好意が生まれた後ではなく、「好きでも嫌いでもない」ニュートラルな状態のときです。最初は関心のなかった広告やブランドでも、繰り返し目にするうちに「見覚えがある」「知らないものではない」という安心感が生まれ、評価のベースがプラス寄りに傾いていきます。
この点が重要で、単純接触効果は「ファンを一気につくる魔法」ではありません。あくまで、好意や信頼が芽生える土台をつくる効果であり、その後の体験や価値提供によって初めて、ロイヤルティや購買行動へとつながっていきます。
すでに嫌悪感がある場合は逆効果に
単純接触効果には明確な前提条件があります。それは、初期印象が極端に悪くないことです。すでに不快感や嫌悪感を抱いている対象に対して接触を重ねると、好意が高まるどころか、むしろネガティブな感情が強化されてしまう場合があります。
たとえばしつこい営業メールや、違和感のある広告表現を何度も見せられると、「またこれか」「うるさい」という印象が増幅されるでしょう。これは単純接触効果が働いていないのではなく、マイナスの初期印象が反復によって固定化されている状態です。
このため、単純接触効果を活用する際には、「最初の接点でどのような印象を与えているか」を丁寧に設計することが不可欠になります。
3章:単純接触効果が起こる仕組み
「見慣れている=安全」という本能的判断
単純接触効果の根底にあるのは、人間の警戒心を下げる仕組みです。人は本来、未知のものに対して無意識に不安や警戒を抱きます。しかし、同じ対象に何度も接していると、脳はそれを「危険ではない」「予測可能な存在」と判断し、警戒レベルを下げていきます。
この「安全だと判断された状態」は、そのまま安心感につながり、結果として好意的な感情が生まれやすくなります。マーケティングや営業の文脈では、「知らない企業」から「見覚えのある企業」へと認識が変わるだけで、心理的ハードルが大きく下がるのはこのためです
情報処理が楽になると好感が生まれる
単純接触効果は、「知覚的流暢性(フルエンシー)」という考え方でも説明されます。これは、情報を処理しやすいものほど、脳が快と感じやすいという性質です。
初めて見るロゴや聞き慣れないサービス名は、理解するために少なからず認知的な負荷がかかります。一方、何度も目にしているものは、瞬時に認識でき、考えなくても処理できます。この“楽に理解できる状態”が、無意識のうちに「好き」「心地よい」という感情と結びつくのです。
つまり、繰り返し接触することで、対象は「判断しやすい存在」になり、結果として選ばれやすくなります。
無意識レベルで評価が蓄積されていく
単純接触効果が厄介であり、同時に強力なのは、その多くが無意識下で進行する点です。
広告やSNS投稿、ロゴ、社名などは、必ずしも注意深く読まれているわけではありません。しかし、意識していなくても、繰り返し接触した情報は記憶の奥に蓄積されていきます。
「詳しくは知らないが、聞いたことがある」「なぜか安心感がある」こうした感覚は、意思決定の場面で静かに影響を及ぼします。購買や契約の最終段階では、論理的な比較だけでなく、この無意識の評価が背中を押すケースも少なくありません。
そのため単純接触効果は、短期的な成果よりも、中長期でのブランド形成や信頼醸成において特に力を発揮します。
4章:マーケティングでの活用法
広告・コンテンツは「刈り取り前の下地」として設計する
単純接触効果がもっとも分かりやすく活用されているのが広告領域です。リターゲティング広告やSNS広告は、まさに「繰り返し目に触れさせる」ことで親近感を醸成する仕組みと言えます。
ここで重要なのは、広告を即時のコンバージョンを狙う施策だけで評価しないことです。
初回接触時に購入や問い合わせに至らなくても、「見覚えがある」「知っている」という状態をつくること自体が、次の接点の成功確率を高めます。広告は刈り取りのための武器というより、判断を楽にするための下地づくりとして位置づける方が、単純接触効果を活かしやすくなります。
営業・商談では「頻度」より「顔が浮かぶ状態」をつくる
営業活動においても、単純接触効果は強く作用します。ただし、重要なのは訪問回数や連絡回数の多さではありません。目指すべきは、「相手の頭の中で顔や名前が自然に思い浮かぶ状態」をつくることです。
短時間でも定期的に接点を持つ、オンラインミーティングで顔を合わせる、簡単なフォロー連絡を入れるなど、心理的距離を縮める接触を積み重ねることで、商談のハードルは確実に下がります。逆に、目的のない訪問や一方的な売り込みは、接触回数が増えるほど逆効果になりやすいため注意が必要です。
SNS・コミュニティは「自然な接触」を積み上げられる場
SNSやコミュニティは、単純接触効果を最も“摩擦なく”発揮できるチャネルです。ユーザーは広告として構えず、タイムラインやコミュニティ内の投稿として、自然に企業やブランドの情報に触れます。
特にコミュニティでは、企業からの一方通行の発信だけでなく、ユーザー同士の会話や成功体験の共有を通じて、間接的な接触が何度も生まれます。この「押しつけ感のない反復接触」が、親近感や信頼感をゆっくりと育てていきます。
単純接触効果は、強いメッセージで一気に印象を変える施策ではありません。広告・営業・コミュニティといった複数の接点を通じて、「いつの間にか好意的に感じている」状態をつくる。それこそが、マーケティングにおける理想的な活用形です。
5章:活用時の注意点
初期印象が悪いと接触は逆効果になる
単純接触効果が成立する大前提は、初期印象がフラット、もしくはプラス寄りであることです。最初の接点で不快感や不信感を与えてしまうと、その後いくら接触回数を増やしても好意は生まれません。むしろ、「またこれか」「しつこい」という感情が強化されていきます。
広告表現が押しつけがましい、営業メールが一方的、対応が雑、こうしたマイナスの第一印象は、単純接触によって修正されるのではなく、固定化されやすい点に注意が必要です。単純接触効果は、印象を“底上げ”する効果であって、“反転”させる魔法ではありません。
接触回数には「最適解」がある
単純接触効果は、回数を増やせば増やすほど比例して高まるわけではありません。心理学の研究では、接触回数が一定数を超えると好意の上昇が鈍化し、場合によっては飽きや嫌悪に転じることが示唆されています。
実務においても、同じ広告が何度も表示されたり、頻繁すぎる営業連絡を受けたりすると、ネガティブな印象を持たれやすくなります。重要なのは、「どれだけ接触したか」ではなく、相手の記憶に残りつつ、不快にならない頻度を見極めることです。
「しつこさ」と「存在感」は紙一重
単純接触効果を狙った施策が失敗する最大の理由は、「存在感を出したい」という意図が強くなりすぎることです。本来の目的は、相手の判断を楽にし、安心感をつくることにあります。しかし、接触が一方的になると、その安心感は簡単に「圧」に変わってしまいます。
特に注意したいのは、
- 毎回同じ内容・同じトーンでの発信
- 相手の状況を無視したタイミングでの接触
- 価値提供のない反復
こうした接触は、単純接触効果ではなく、広告疲れや心理的反発を生む原因になります。
「目立つこと」と「好かれること」は別物である、という前提を常に意識する必要があります。
6章:単純接触効果を高めるコツ
接触の「回数」よりも「質」を設計する
単純接触効果を高めるうえで最も重要なのは、接触回数そのものではなく、一回一回の接触がどのような体験として記憶されるかです。内容が薄い、関係のない情報が多い、毎回同じメッセージが繰り返される——こうした接触は、回数を重ねるほど評価を下げてしまいます。
逆に、短くても「役に立った」「気づきがあった」と感じられる接触は、好意を上書きしていきます。単純接触効果は量のテクニックではなく、価値ある接触を積み重ねた結果として生まれる現象だと捉えるべきです。
複数チャネルで“文脈を変えて”接触する
同じ内容を同じ場所で繰り返すと、人は慣れるより先にスルーするようになります。
単純接触効果を持続させるためには、チャネルや文脈を少しずつ変えながら接触することが有効です。たとえば、
- 広告で存在を知る
- SNSで考え方や姿勢に触れる
- 記事や事例で理解を深める
といったように、異なる文脈で同じブランドに触れることで、「知っている」から「理解している」へと認識が進みます。この段階的な接触設計が、単純接触効果をより強固な信頼へとつなげます。
「押さない接触」を意識的につくる
単純接触効果がもっとも自然に働くのは、売り込み感がない接触です。人は説得されることには抵抗しますが、情報に触れること自体には抵抗しません。だからこそ、すべての接点をコンバージョン目的にしない設計が重要になります。
役立つ知識の共有、他社事例の紹介、ユーザー同士の会話など、「自分に関係がありそう」「今すぐ判断しなくていい」接触が積み重なることで、心理的な距離は自然と縮まります。
結果として、いざ比較・検討のフェーズに入ったとき、「なんとなく信頼できる」という感覚が意思決定を後押しします。
7章:単純接触効果を「仕組み」として活かすには
個人依存の接点設計には限界がある
ここまで見てきたように、単純接触効果はマーケティングや営業において非常に有効な心理原理です。しかし実務に落とし込もうとすると、多くの企業が同じ壁に突き当たります。それは、接点設計が属人化しやすいという問題です。
営業担当者のこまめなフォローや、SNS担当者の継続的な発信によって好意が醸成されるケースは確かに存在します。一方で、その成果は個人のスキルや熱量に依存しやすく、担当者が変われば接点の質も途切れてしまいがちです。単純接触効果を継続的に活かすには、「頑張る人」に頼らない仕組みが必要になります。
好意は「企業との会話量」から蓄積される
単純接触効果が最も安定して機能するのは、企業とユーザーの間に自然な接触が継続的に生まれている状態です。
それは広告や営業だけでなく、ユーザー同士の会話、成功体験の共有、ちょっとした気づきの発信など、「企業を中心としたコミュニケーションの総量」が増えている状態とも言えます。
このような環境では、ユーザーは「売られている」と感じることなく、何度も企業やブランドに触れることになります。結果として、単純接触効果が押しつけではなく、関係性の副産物として蓄積されていきます。
コミュニティは単純接触効果を再現可能にする
こうした接触を仕組みとして実現する手段のひとつが、コミュニティの活用です。
コミュニティでは、企業からの一方通行の発信だけでなく、ユーザー同士の対話やナレッジ共有が日常的に発生します。その中で企業名やサービス、価値観に何度も自然に触れる機会が生まれ、単純接触効果が無理なく働きます。
Communeは、こうしたコミュニケーションを継続的に生み出すためのコミュニティプラットフォームです。顧客や従業員との接点を「点」で終わらせず、会話が循環する「場」として設計することで、好意や信頼が時間とともに蓄積されていく状態を支援します。
単純接触効果を“知っている理論”で終わらせるのではなく、再現可能な仕組みとして組み込む。
その選択肢として、コミュニティというアプローチを検討してみてはいかがでしょうか。
顧客との接点設計、お困りではありませんか?
顧客との接点設計、お困りではありませんか?
- 接触回数を増やしたが、好意や信頼につながっている実感がない
- 広告やメールが「うるさい」と受け取られてしまう
- 顧客との関係が単発で終わり、積み上がらない
- 接点づくりが、担当者の感覚や属人的な工夫に依存している
Communeは、単純接触効果が自然に働く顧客接点をコミュニティとして設計。
専門チームが戦略設計からKPI設計、運営実務までを伴走し、
「なんとなく好印象」を「選ばれ続ける関係」へと育てます。
Communeは、継続的な顧客接点をコミュニティとして設計。
専門チームが戦略設計からKPI設計、運営実務までを伴走し、
「なんとなく好印象」を「選ばれ続ける関係」へと育てます。
