コラム
マーケティング
ROASとは何か?広告の費用対効果を正しく理解し、成果につなげる
2025/06/24
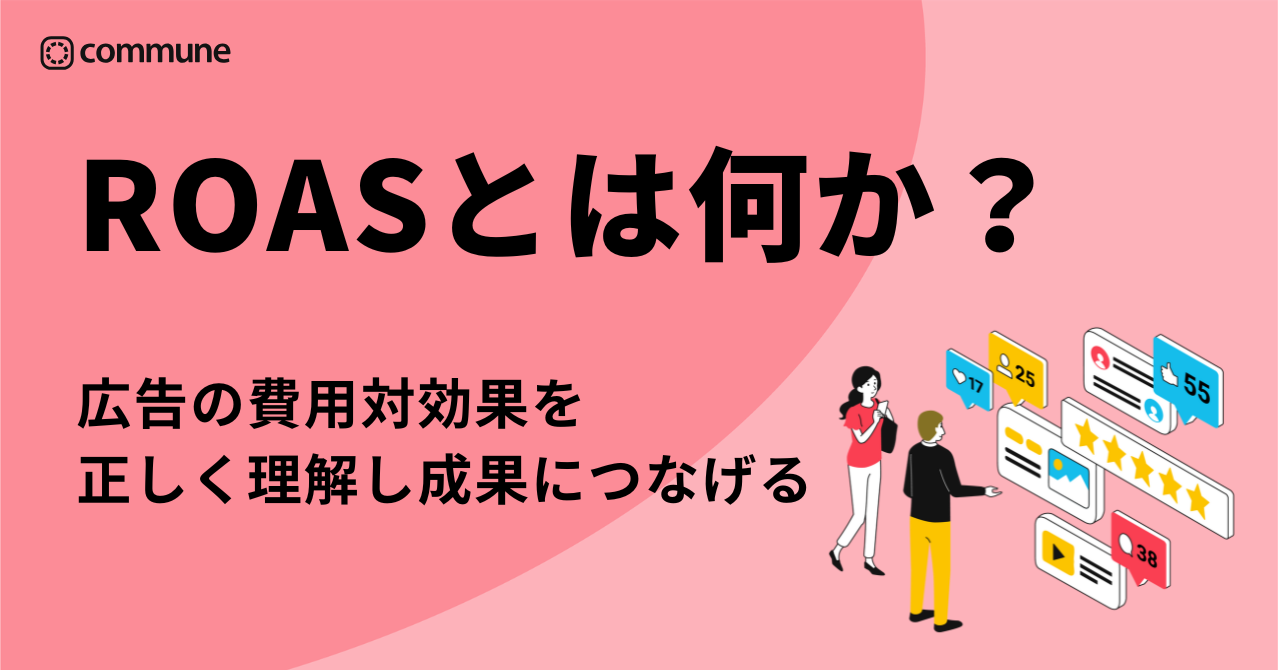
広告にかけた費用が、どれだけの売上を生み出したのか。その効果を定量的に示す重要な指標が「ROAS(Return On Advertising Spend)」です。ROASの意味や計算方法を正しく理解しなければ、広告施策は「なんとなく良さそう」で終わってしまい、費用対効果の最適化にはつながりません。本記事ではROASの基礎から実践的な使い方、さらにはよくある勘違いや改善施策まで、体系的に解説していきます。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
第1章:ROASとは何か?定義と計算式を理解する
ROAS(Return On Advertising Spend)は「広告費用に対してどれだけの売上を生んだか」を示す指標です。広告の効果測定において、最も基本的かつ重要な指標の一つといえるでしょう。
主なポイント
-
ROASは「売上 ÷ 広告費 × 100」で算出される
-
ROAS100%は広告費と売上が同額、つまり収支トントン
-
一般的にROASが100%未満だと赤字、100%以上が黒字とされる
-
売上ベースの指標である点が、ROI(利益ベース)との違い
たとえば、10万円の広告費で30万円の売上があれば、ROASは300%になります。つまり、1円の広告費が3円の売上を生み出したことになります。非常にシンプルな指標ですが、「何を広告成果とするか(購入?リード?)」という前提設定がずれると、数値の解釈も変わるため注意が必要です。
ROASはGoogle広告やYahoo!広告などのプラットフォームでも自動的に算出されますが、その意味を深く理解していなければ、数字を見ても適切な判断ができません。
第2章:ROASと混同しやすい指標——ROI・CPAとの違い
ROASを正しく理解するためには、混同しやすい他の指標との違いを明確に把握しておくことが不可欠です。特に混乱が生じやすいのが、ROI(投資利益率)とCPA(顧客獲得単価)という2つの指標です。それぞれの定義と主な違いは以下の通りです。
主な指標の違い
- ROAS(Return on Advertising Spend):広告費に対して、どれだけの「売上」を生み出したかを示す比率。計算式は「売上 ÷ 広告費」で、売上ベースの指標です。
- ROI(Return on Investment):広告費や仕入原価などの投資に対して、どれだけの「利益」を得たかを示す比率。計算式は「利益 ÷ 費用(投資額)」で、利益ベースの指標です。
- CPA(Cost Per Acquisition):1件の顧客やコンバージョンを獲得するのにかかったコスト。計算式は「広告費 ÷ 獲得件数」で、成果の“数”を重視する指標です。
たとえば、ROASが300%であっても、取り扱っている商品にかかる原価が高く、利益率が低ければ、ROIは著しく低下します。逆に、同じROASでも利益率が高い商品であれば、より多くの利益を残すことができます。つまり、ROASは“売上の大きさ”を評価する指標であり、それだけでは「どれだけ儲かったのか」は見えてきません。
一方、CPAは「1件あたりの獲得コスト」に注目し、施策によって何人の顧客を得られたかという“量的成果”にフォーカスする指標です。これに対してROASは、同じ獲得でも「どれだけの金額を生み出したか」という“質的成果”に焦点を当てています。
そのため、ROASだけに注目して施策を評価すると、「見た目には高ROASでも、実際には利益が出ていない」といった、本末転倒な状況に陥るリスクがあります。広告効果を適切に判断するためには、ROASだけでなく、ROIやLTV(顧客生涯価値)といった他の重要指標と組み合わせて、多角的に評価する視点が欠かせません。
ROASはあくまで“入口”であり、最終的な目的である「利益の最大化」や「持続的な顧客関係の構築」といったゴールを見失わないためには、全体像の中での位置づけを理解することが重要です。
関連記事:インサイトとは何か?顧客の「理屈」ではなく「気持ち」に耳を澄ませる
┗ROASの“質的評価”に不可欠な、顧客の深層心理に迫る視点を補完できます。
第3章:ROASの目標設定と業界別の目安
「ROASが高ければ良い」と一概に言い切るのは危険です。その理由は、ビジネスごとに利益率やコスト構造が異なり、「どの水準のROASで黒字になるのか」が一律ではないからです。ROASの数値そのものが高くても、事業全体として利益が出ていなければ本末転倒です。したがって、ROASを正しく評価するためには、まず自社の利益構造を明確に把握した上で、適切な目標水準を設定する必要があります。
損益分岐点ROASを理解しよう
ROASの真価を見極めるうえで重要なのが、「損益分岐点ROAS」という考え方です。これは、広告費に対して利益が出るために必要な最低限のROASを示す指標で、以下のように求められます。
損益分岐点ROAS(%)= 100 ÷ 粗利率(%)
たとえば、自社の粗利率が20%である場合、損益分岐点となるROASは 500% になります。これは、広告費1円に対して最低でも5円の売上を上げなければ利益が出ない、ということを意味します。
仮に粗利率が30%であれば、損益分岐点ROASは 約333%。つまり、広告費1円あたり少なくとも3.33円以上の売上が必要になります。いくらROASが「300%」で高いように見えても、それが損益分岐点を下回っていれば、事業全体としては赤字になってしまうのです。
固定費や間接コストも無視できない
損益分岐点ROASを算出する際には、単に粗利率だけでなく、固定費や間接費の影響も忘れてはなりません。たとえば、広告費以外にも人件費、管理費、物流コスト、システム運用費などが多くかかる事業モデルでは、より高いROASを求められる傾向にあります。逆に、構造がシンプルで可変費が中心のビジネスでは、比較的低めのROASでも黒字化が可能な場合もあります。
業界別ROASの目安(参考値)
あくまで一例にすぎませんが、一般的に見られる業界別のROAS目安は以下の通りです。
- EC(アパレル):300〜500%
- BtoBサービス:400〜600%
- 美容・健康系:250〜400%
- 教育・スクール系:200〜350%
これらはあくまで「平均的な目安」であり、自社の実際の利益率やコスト構造とは必ずしも一致しません。そのため、これらの数字を鵜呑みにするのではなく、自社独自の損益分岐点ROASを算出し、それに基づいて目標ROASを設定することが極めて重要です。
関連記事:パーセプションとは?「認識」の本質と実践
┗見かけの数値に惑わされず、顧客の“認識ギャップ”を評価軸に組み込む思考法が得られます。
第4章:ROASをKPIとして使うときの注意点
ROASは広告施策の効果を測るうえで便利な指標ですが、その数値だけに頼りすぎると、大きな落とし穴にはまる可能性があります。特に広告運用におけるKPI(重要業績評価指標)を設定する際には、ROASの特性と限界を正しく理解しておくことが重要です。
まず注意したいのは、ROASはあくまで「売上ベース」の指標であり、利益や顧客の長期的な価値を直接反映するものではないという点です。ROASの数値が良好でも、それが必ずしも利益の最大化や持続的な成長につながっているとは限りません。
たとえば、以下のような落とし穴が存在します。
- 短期的な売上成果ばかりに目が向き、LTV(顧客生涯価値)やブランド価値の蓄積を軽視してしまう
- 粗利率の低い商品ばかりが売れた結果、ROASが高くても利益がほとんど残らない
- 単価の安い商品を中心に配信を最適化した結果、顧客ポートフォリオが偏り、リピート性やアップセルの余地が失われていく
- CPA(顧客獲得単価)やROI(投資利益率)などの他指標と併用していないため、事業全体の健全性を把握しきれない
たとえば「ROASは目標を超えているのに利益が出ていない」という状況は、広告経由の売上が伸びていても、1件あたりの利益が極めて薄かったり、購入が初回だけでリピートにつながらなかったりすることが原因です。ROASは売上金額の大きさを評価する指標であって、利益性や顧客との関係の深さまでは把握できません。
このような背景を踏まえると、ROASをKPIとして設定する際には、いくつかの工夫が求められます。たとえば、
- LTV(顧客生涯価値)やROIとあわせて複数の指標で評価すること
- 新規顧客とリピート顧客を分けてROASを見ること
- 広告チャネルや商品カテゴリごとに適正な目標ROASを定義すること
といったアプローチが有効です。ROASはあくまで全体の一側面を捉える指標にすぎません。ビジネスの持続的な成長を目指すのであれば、数字の表面的な良し悪しではなく、「なぜその数値が出ているのか」「裏側にどのような顧客行動があるのか」といった背景まで含めて、立体的に評価していく視点が欠かせないのです。
第5章:ROASを改善するための具体的施策
ROASは自然に改善されるものではありません。その成果を高めるには、広告の各プロセスを丁寧に見直し、目的に応じた適切な打ち手を講じる必要があります。 単に広告費を増やすのではなく、構造的な最適化が求められるのです。
以下に、ROAS改善に有効とされる主な施策を紹介します。
- 広告クリエイティブの精査(A/Bテストの実施、訴求軸の見直し)
- ターゲティングの最適化(年齢、地域、興味・関心データの活用)
- LP(ランディングページ)のCVR改善(構成・コピー・UIの改善)
- 入札単価や配信スケジュールの調整(時間帯や曜日別の最適化)
たとえば、ある事例では、広告バナーを「価格訴求型」から「ベネフィット訴求型」に切り替えたところ、CTR(クリック率)が大幅に改善され、それに伴ってROASも向上しました。
また別のケースでは、LPの読み込み速度を3秒から1秒に短縮しただけでCVR(コンバージョン率)が1.5倍に上昇し、ROASが最終的に200%改善されたという具体的な成果も報告されています。
このように、ROASの改善は広告の中身だけでなく、ユーザーが広告を見てから購入に至るまでの「顧客体験全体の設計」を見直すことによって実現されるのです。広告の最適化と同時に、ユーザー導線や心理的ハードルへの配慮も欠かせません。最終的にROASを高める鍵は、個々の施策を断片的に見るのではなく、全体の流れを俯瞰して改善点を発見する視点にあります。
関連記事:顧客インサイトとは?見つけ方・成功事例まとめ
┗広告クリエイティブ・LP改善・UX設計の前提となる「顧客理解」の技法が学べます。
第6章:事例で学ぶROASの成功と失敗
ROASという指標を本当に活用するためには、抽象的な定義や理論だけでなく、実際に企業がどのようにROASを使い、成功や失敗を経験してきたのかを知ることが重要です。具体的な事例から学ぶことで、自社の広告運用にリアリティある改善策を取り入れることができます。
以下は、ROASに関連する代表的な成功例と失敗例です。
成功例①:リターゲティング広告の強化でROASが200%から450%に改善
既存の訪問者データをもとにリターゲティングを強化。接触回数を最適化し、購買意欲の高いユーザーへの訴求を重点化した結果、広告効果が飛躍的に向上。
成功例②:EFO(エントリーフォーム最適化)ツールを導入し、フォームCV率が改善。ROASが2.5倍に拡大
入力の手間や離脱ポイントを特定し、フォームの設計を見直すことでCV率が改善。広告の費用対効果が大幅に向上。
失敗例①:ROAS至上主義に陥り、利益率の低い顧客ばかりを獲得して赤字に転落
広告効果は高く見えたが、実際には粗利の低い商品ばかりが売れたことで利益が残らず、最終的に赤字決算に。「売上=成功」と短絡的に判断した結果、収益性を見誤ったケース。
失敗例②:CPAは良好だったがCVの質が低く、LTVが伸びなかった
一件あたりの獲得コストは抑えられていたものの、実際に獲得した顧客の多くが一度きりの購入にとどまり、長期的な利益にはつながらなかった。
こうした事例から読み取れる教訓は、「ROASが高い=成功」とは限らないということです。CV(コンバージョン)の質が伴わなければ、高ROASでもLTV(顧客生涯価値)視点では赤字になるという矛盾も十分に起こりえます。
したがって、ROASを正しく活用するためには、数値の裏側にある「顧客の質」や「利益構造」まで含めて評価する視点が不可欠です。
関連記事:なぜコミュニティが、ユーザーインサイト獲得に効くのか?
┗施策の成果を数字だけで測らず、“ユーザーの声”から本質的な改善につなげたい方に。
第7章:これからのマーケターに求められるROASとの向き合い方
これからの時代、マーケティングは「単発の売上」ではなく、「長期的な顧客価値の創出」へと重心を移しつつあります。この変化は、ROASのような広告指標を活用する際にも、欠かすことのできない視点となっています。
ROASを“使いこなす”とは、単に数値を追いかけるのではなく、その先にある顧客との関係性や、ブランドとしての成長を見据えた運用にほかなりません。
- ROASは“目安”であって“答え”ではない
- 数値の裏側にある顧客の行動や心理を読み解くことが重要
- 定量データ(ROAS、CPA、LTVなど)と定性情報(顧客の声や文脈)のバランスをとって判断する
- LTV(顧客生涯価値)やブランド構築といった長期的な視点も常に意識する
たしかに数字は嘘をつきません。しかし同時に、数字だけを信じることで大きな誤解が生まれることもあります。
ROASは極めて有用な指標である一方、それ単体でビジネスの健全性を判断することはできません。
だからこそ、「なぜこの数値になったのか」「他の指標とどう関係しているのか」を常に問い続ける姿勢が、これからのマーケターには不可欠です。ROASという指標を適切に扱えるようになることは、単なる“広告運用者”から、“戦略を描けるマーケター”へと進化するための第一歩です。
目先の数値に一喜一憂するのではなく、顧客理解を起点に、事業の長期的成長を見据えた意思決定を行う視点こそが、これからのマーケティングの本質といえるでしょう。
あわせて読みたい
- インサイトとは何か?顧客の「理屈」ではなく「気持ち」に耳を澄ませる
┗ROASを“質”で評価したいマーケターに最適な補足記事。 - パーセプションとは?「認識」の本質と実践
┗「顧客の認識と成果のズレ」を修正したい方に。 - 顧客インサイトとは?見つけ方・成功事例まとめ
┗数値改善の前提として必要な「深い顧客理解」を獲得できます。 - なぜコミュニティが、ユーザーインサイト獲得に効くのか?
┗“数字では測れない声”を拾い、広告設計に活かしたい場合に有効です。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
