コラム
マーケティング
インサイトとは何か?顧客の「理屈」ではなく「気持ち」に耳を澄ませる
2025/06/24
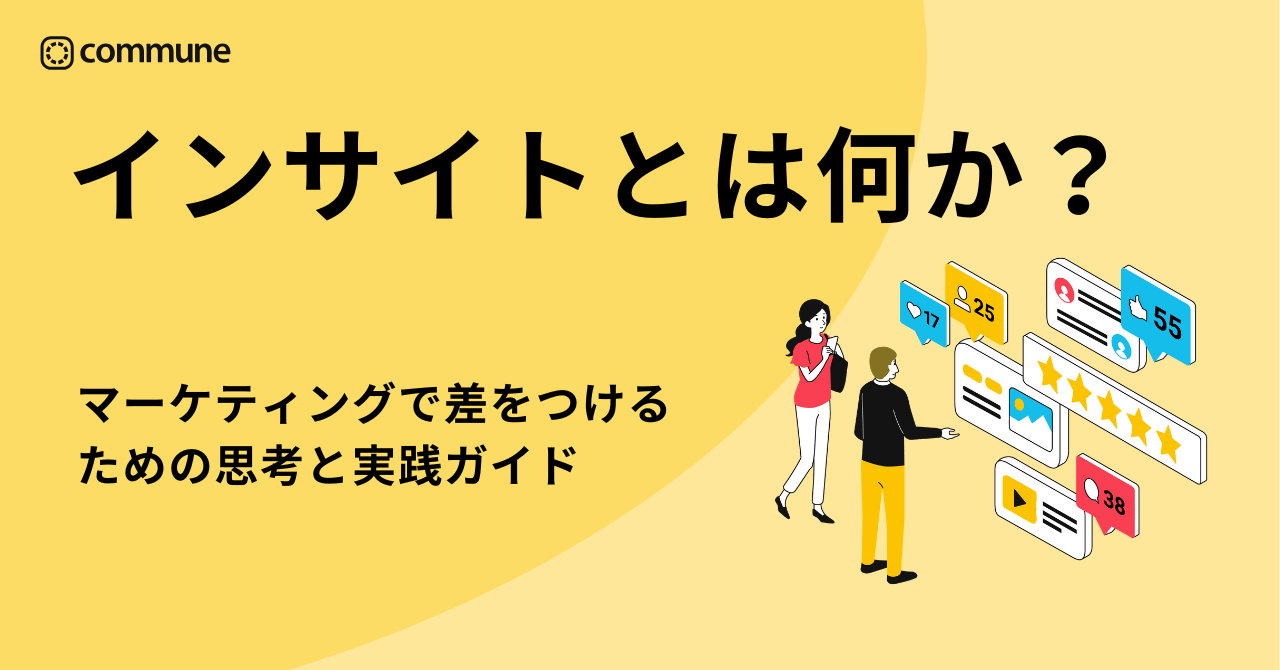
インサイトとは、簡単にいえば「消費者自身も気づいていない、本音や欲求」です。この記事では、インサイトの意味をただ説明するのではなく、「ニーズ」や「ウォンツ」との違いから始まり、なぜ今あらためて注目されているのか、どのように活用すれば成果につながるのかまで、実務に直結する知識を体系的に解説していきます。さらに、有名企業による活用事例や、現場で実践できるインサイトの見つけ方についても具体的に紹介します。
読み終える頃には、「インサイトとは何か?」という問いではなく、「どう活用するか?」という視点で、マーケティングを見直すきっかけになるはずです。
インサイト、“数字だけ”で見抜けますか?
インサイト、“数字だけ”で見抜けますか?
- アンケートや行動データはあるのに、「本音」が見えにくい
- 定性インタビューは一度きり、継続的なインサイトが蓄積されない
- “生の声”を拾いたいが、どこから手をつければいいか分からない
- 現場の気づきやUGCが、社内共有されず埋もれてしまっている
Commune は、コミュニティを起点に顧客のつぶやき・投稿・レビューといった“生の声”を継続的に集め、インサイトとして可視化・活用できるプラットフォームです。
Commune は、コミュニティを起点に顧客のつぶやき・投稿・レビューといった“生の声”を継続的に集め、インサイトとして可視化・活用できるプラットフォームです。
目次
第1章:インサイトとは何か?本当の意味を掘り下げる
インサイト(Insight)とは、直訳すれば「洞察」や「物事の本質」を意味します。しかし、マーケティングにおいての「インサイト」は単なる観察や気づきにとどまらず、消費者自身も気づいていない“無意識の本音や欲求” を指します。それは、顕在化されたニーズよりもさらに深い領域にある、購買行動の根底を支える心理的な動機です。
インサイトの定義と、マーケティングでの重要な構成要素
- 消費者が「言語化していない」あるいは「自覚していない」本音
- 行動や選択の背景にある深層の心理的動機
- マーケターやプランナーが観察・分析・解釈を通じて導き出すもの
- 顧客の「なぜそれを選んだのか?」という問いに対する核心的な答え
たとえば「おしゃれな靴が欲しい」というのは顕在ニーズですが、その裏には「周囲からセンスの良い人と思われたい」といった感情が潜んでいるかもしれません。このように、インサイトは感情・価値観・社会的背景と密接に結びついています。
ポイントは、インサイトとは「最初から見えているもの」ではなく、観察と洞察を通じて“見出す”ものであるということです。だからこそ、同じユーザーを見ていても、インサイトを深く捉えられるかどうかで、商品のヒットやキャンペーンの成果が大きく変わってくるのです。
第2章:ニーズ・ウォンツとインサイトの違い
「ニーズ」「ウォンツ」「インサイト」――この3つの概念は似ているようで本質的に異なります。マーケティングの現場ではしばしば混同されがちですが、戦略を立てるうえでこの違いを正しく理解することは非常に重要です。それぞれの定義を端的に整理すると、以下のようになります。
-
ニーズ:生活上の課題や必要性。
例:「移動手段がほしい」 -
ウォンツ:ニーズを満たすための具体的な欲望。
例:「かっこいい自転車がほしい」 -
インサイト:その選択や行動の背景にある、無意識の感情や価値観。
例:「人に見られて誇らしく思える乗り物がほしい」
この3層の関係性を理解するには、よく知られる「氷山モデル」が有効です。水面に見えているのがウォンツ、すぐ下にあるのがニーズ、そして最も深く沈み込んでいるのがインサイトです。インサイトは視認しづらい領域にありますが、実は消費者行動全体を支える“本質的な核”でもあります。
多くのマーケティング施策がウォンツやニーズにしかアプローチできていないのは、企業にとって分かりやすく、データとしても取りやすいからです。しかし、そこにとどまっていては他社にすぐ真似され、差別化は難しくなります。
インサイトまで掘り下げてはじめて、本当の意味での独自価値が生まれます。模倣されにくいブランドやプロダクトをつくるためには、この“深層”にこそ向き合う視点が欠かせないのです。
第3章:なぜ今、インサイトが重要なのか?
かつては「良いモノを作れば売れる」時代がありました。高品質・低価格といったスペックの優位性だけで、商品が選ばれていた時代です。しかし、現代の消費者は「なぜそれを選ぶのか?」という問いに対して、機能や価格だけでは説明できない動機で行動しています。
では、なぜ今、これほどまでに「インサイト」が重視されるようになったのでしょうか?その背景には、マーケティング環境の大きな変化が関係しています。
現代マーケティングを取り巻く3つの構造変化:
-
市場の成熟と商品の飽和
どの業界も競争が激化し、商品・サービスの機能や品質に大きな違いがなくなりつつある。結果、「何を選んでもそれなりに満足できる」状況に。 -
SNSやUGC(ユーザー生成コンテンツ)の普及により、ブランド価値が“消費者の声”に委ねられるようになった
企業発信だけではブランドはつくれない。ユーザーの体験やレビュー、共感によってブランドの印象が形成される時代に。 -
生活者の価値観の多様化と感性化
「年齢・性別・年収」でセグメントできた時代は終わり、今や一人ひとりの価値観や世界観に寄り添うアプローチが求められるように。数字だけでは読みきれない“感情の文脈”が鍵となっている。
こうした変化によって、企業が顧客とつながるには、単なる情報提供や機能訴求では不十分になりました。「自分の気持ちを理解してくれている」――そう感じてもらえる共感ベースのコミュニケーションが、ますます不可欠になっているのです。
そして、この“共感”の土台となるのが、まさにインサイトです。
広告コピー、商品コンセプト、UX設計、顧客対応…あらゆるマーケティング活動において、インサイトが的確に捉えられているかどうかが、顧客との共鳴度(=選ばれる理由)を大きく左右します。
インサイトを読み解ける企業こそが、共感を武器に選ばれる時代へ。その重要性は今後、ますます高まっていくでしょう。
第4章:インサイトを活かしたマーケティング事例5選
理論や定義を学んでも、「インサイトが実際にどう活用されているのか?」が見えてこなければ、ピンとこない方も多いでしょう。ここでは、顧客インサイトを見抜き、それを商品開発やマーケティング施策に応用して成功を収めた代表的な5つの事例をご紹介します。
1. SUBARU「ぶつからないクルマ」
インサイト:「安全に運転したいが、複雑な技術には不安がある」
SUBARUは、ドライバーの“事故を防ぎたい”というニーズと、“先進技術は難しそう”という心理的ハードルのあいだにある本音に着目。そこで、先進安全技術「EyeSight(アイサイト)」を、「ぶつからないクルマ」という極めて直感的かつシンプルなコピーで訴求。テクノロジーの機能説明を省き、感覚的な安心感を前面に出すことで、広範なユーザー層の支持を獲得しました。
2. 日清食品「カップヌードルPRO」
インサイト:「健康は気になるが、たまにはカップ麺を罪悪感なく楽しみたい」
ダイエットや健康志向の高まりにより、カップ麺は敬遠されがちでした。しかし日清は、「本当は食べたいけれど罪悪感がある」という矛盾した本音に着目。そこで、糖質オフ・高タンパク仕様の「カップヌードルPRO」を開発。おいしさはそのままに、栄養バランスを調整し、“罪悪感ゼロ”という新たなポジショニングを獲得しました。
3. Got Milk?(アメリカ)
インサイト:「牛乳は積極的に飲まないけれど、クッキーには合うと感じている」
米国では牛乳離れが進む中、「牛乳は健康に良い」だけでは消費を促進できなくなっていました。そこで、カリフォルニア乳業協会は、「甘いお菓子に牛乳がほしくなる」という日常の文脈に着目。「Got Milk?」という短い問いかけを広告コピーに用い、生活者の無意識の習慣に訴求。牛乳の購買理由を“理屈”ではなく“感覚”にすり替えたことで、アイコニックな広告キャンペーンとして長年にわたり成功を収めました。
4. マクドナルド「クォーターパウンダー」
インサイト:「体には悪そうだが、ジャンクフードの背徳感がたまらなく好き」
健康志向の高まりとは裏腹に、消費者の中には“たまにはガッツリ食べたい”という衝動が存在します。マクドナルドはこの「罪悪感も含めて楽しみたい」という本音に注目。高カロリー・高ボリュームの「クォーターパウンダー」を投入し、あえて“背徳感”を訴求するメッセージ戦略を展開。コア層に強く響き、ブランドの独自性を際立たせました。
5. NewsPicksの有料会員戦略
インサイト:「ただニュースを読むだけでなく、自分の知見を表現したい」
一般的なニュースメディアと異なり、NewsPicksは「読者は情報を受け取るだけではなく、語りたい」「情報感度の高い人間として認識されたい」という承認欲求に着目。コメント機能や専門家によるピックアップ機能を強化し、“読むメディア”から“語るメディア”へと進化。知的なアイデンティティを表現する場として、熱量の高いファンコミュニティを形成しています。
これらの事例に共通しているのは、消費者の“問題”ではなく、“感情”にフォーカスしていることです。表面的なニーズに応えるのではなく、その背後にある欲求や葛藤を見抜き、それに対してまっすぐ応答している点が、成功の鍵となっています。
インサイトとは、顧客の「理屈」ではなく「気持ち」に耳を澄ませること。それができたとき、商品やブランドは人の心に深く刺さり、“選ばれる理由”を手に入れるのです。
第5章:インサイトはどうやって見つける?発掘のための5つの方法
「インサイトが重要なのはわかった。でも、どうやって見つければいいのか?」これは、多くのマーケターが直面するリアルな疑問です。実際、インサイトはアンケートや定量データだけではなかなか見えてきません。
なぜなら、インサイトとは顧客の“無意識の本音”であり、本人すら気づいていないことが多いからです。では、どうやってその深層心理を見つけ出せばよいのでしょうか。以下に、実際のマーケティング現場で広く使われている代表的なインサイト発掘手法を4つご紹介します。
実践的なインサイト発見の4手法
1. デプスインタビュー(深層インタビュー)
一対一でじっくりと行うインタビュー手法です。
顧客の「なぜそう思うのか?」「どうしてそう感じたのか?」という問いを重ね、表面的な回答の奥にある感情や価値観を引き出します。安心感のある環境づくりや、誘導しすぎない質問設計がポイントです。
2. エスノグラフィー(行動観察)
観察を通じて顧客の無意識な行動を捉える手法です。たとえば、店舗での動線や商品の手に取り方、自宅での使い方など、「本人も気づいていない行動」を丁寧に観察します。発話よりもむしろ無言の動作や表情の変化に注目することで、インサイトのヒントが浮かび上がります。
3. ソーシャルリスニング
SNSやレビューサイト、掲示板など、生活者が自由に発言している場をモニタリングし、共通する言葉や感情を抽出します。口コミやタグ付けされた投稿から、企業が聞き取れないリアルな声=インサイトの兆候を見つけることができます。特に“ネガティブなつぶやき”の中に本音が隠れていることが多く、重要な気づきの宝庫です。
4. ペルソナ・共感マップ・5 Whys
顧客像や生活文脈を可視化する「ペルソナ」や、「見ているもの」「感じていること」「痛みや願望」などを整理する「共感マップ」、そして「なぜ?」を5回繰り返して本質を深掘る「5 Whys」など、洞察を構造的に導き出すフレームワークも有効です。これらを組み合わせることで、個別の声から本質的なパターンや矛盾、欲求の構造が見えてきます。
これらのアプローチに共通しているのは、「インサイトは顧客の中にあるが、ストレートには出てこない」という前提です。
だからこそ重要なのは、「問いの立て方」「観察の視点」「仮説の組み立てと検証フレーム」の精度です。インサイトとは“発見する”というより、“丁寧に掘り起こし、つないでいく”プロセス。その地道な工程の中にこそ、他社には見えない、顧客との強い結びつきのヒントが潜んでいるのです。
関連記事「顧客インサイトとは?見つけ方・成功事例まとめ」
第6章:インサイト活用のメリットと注意点
インサイトを活用することで、マーケティング施策に多くの恩恵をもたらすことができます。しかし一方で、誤った使い方をすると逆効果になる可能性もあります。戦略に組み込む前に、インサイト活用のメリットと注意点をしっかり理解しておきましょう。
インサイト活用の主なメリット
①:商品・サービスの差別化が可能になる
競合が容易に模倣できない、顧客の深層心理に基づく価値提供が可能になります。
結果として、価格や機能以外の“意味づけ”によって選ばれるブランドになります。
②:ブランドへの共感と好感度が高まる
「このブランドは自分のことを理解してくれている」と感じた顧客は、強いロイヤルティを持ちます。
感情レベルでの共鳴が生まれることで、長期的なファンの獲得にもつながります。
活用時の注意点・落とし穴
①:インサイトの見誤りが施策のズレを生む
インサイトとはあくまで仮説です。仮説がズレていれば、いくら施策を精緻に設計しても、顧客の心には響きません。
だからこそ、チーム内での多角的な視点からの検証と、実行前の小規模テストが重要です。
②:発見に時間とコストがかかる
インサイトはアンケートや数値データからは見えにくいため、インタビューや観察といった定性調査が欠かせません。
これらの調査には、計画・実行・分析に一定のリソースと時間を要します。片手間では得られないという点を、組織内で共有しておく必要があります。
特に気をつけたいのは、「インサイトが一人歩きする」ことです。
インサイトとは“答え”ではなく、“気づき”の出発点にすぎません。にもかかわらず、インサイトを発見した瞬間に「これでいける!」と施策を走らせてしまうと、的外れなマーケティングにつながる恐れがあります。
だからこそ重要なのが、「調査 → 仮説 → 検証 → 改善」というPDCAの徹底です。インサイトは一度見つけたら終わりではなく、繰り返しの検証と改善によって磨き上げていくべき“仮説ベースのナビゲーション”と捉えるのが正しい姿勢です。
マーケティングにインサイトを取り入れることは、企業にとって“感覚的”なことではなく、“戦略的”な判断です。
だからこそ、メリットとリスクを冷静に捉えながら、組織としての検証力・解釈力・実行力を磨いていくことが求められます。
“ユーザー視点での改善”について詳しく知りたい方はこちら:
第7章:これからのマーケターが持つべき「インサイト視点」とは?
インサイトを語るのは簡単です。しかし、それを本当にマーケティングに活かすためには、単なる知識の習得ではなく、“ものの見方”そのものを変えることが求められます。
インサイト視点の4つの心得
1. 「問題」ではなく「感情」に注目する
不便さや不満といった機能的な問題の背後にある、「なぜそう感じたのか」という感情の動きを見逃さないこと。
感情を深掘りすることで、顧客の選択の理由や動機の本質が見えてきます。
2. 「事実」と「真実」は違うと理解する
数値データが示すのは、あくまで行動の“結果”です。
その行動を引き起こした“動機”や“意味”――すなわち真実――は、観察や対話、共感を通じてしか見えてきません。インサイトとは、定量データでは測れない深層に潜んでいるものです。
3. 「顧客の代弁者」ではなく「共感者」になる
顧客の気持ちを“代弁”するのではなく、その隣に立ち、一緒に感じる姿勢を持つことが、真に刺さるマーケティングへの第一歩です。インサイトは「代わりに考えてあげる」ことでなく、「寄り添い、感じ取り、翻訳する」プロセスから生まれます。
4. 「インサイトは見つけるもの」ではなく「創り出すもの」だと気づく
インサイトは、観察と分析、仮説と検証を繰り返す中で、初めてかたちになる“創造的な気づき”です。偶然の発見ではなく、意図とプロセスの中から掘り起こすべきものとして向き合いましょう。
変化の激しい市場において、顧客との“ズレ”は避けられません。だからこそ、インサイトを捉え続けることは一過性のプロジェクトではなく、マーケティング活動の根幹に組み込まれるべき継続的な営みです。
「インサイトとは何か?」という問いは、単なる用語の理解にとどまらず、「あなたは顧客の感情にどれだけ本気で向き合っているか?」という視点の質を問う問いでもあります。
この記事が、言葉の定義をなぞるだけでは終わらず、御社のマーケティングのあり方を見つめ直すヒントとなれば幸いです。
“心理的安全性”や組織文化を通じた顧客理解へのアプローチは、こちらの記事も参考になります:
インサイト、“数字だけ”で見抜けますか?
インサイト、“数字だけ”で見抜けますか?
- アンケートや行動データはあるのに、「本音」が見えにくい
- 定性インタビューは一度きり、継続的なインサイトが蓄積されない
- “生の声”を拾いたいが、どこから手をつければいいか分からない
- 現場の気づきやUGCが、社内共有されず埋もれてしまっている
Commune は、コミュニティを起点に顧客のつぶやき・投稿・レビューといった“生の声”を継続的に集め、インサイトとして可視化・活用できるプラットフォームです。
Commune は、コミュニティを起点に顧客のつぶやき・投稿・レビューといった“生の声”を継続的に集め、インサイトとして可視化・活用できるプラットフォームです。
