コラム
マーケティング
リピーターを増やすには?安定収益とブランド力を高める戦略
2025/06/20
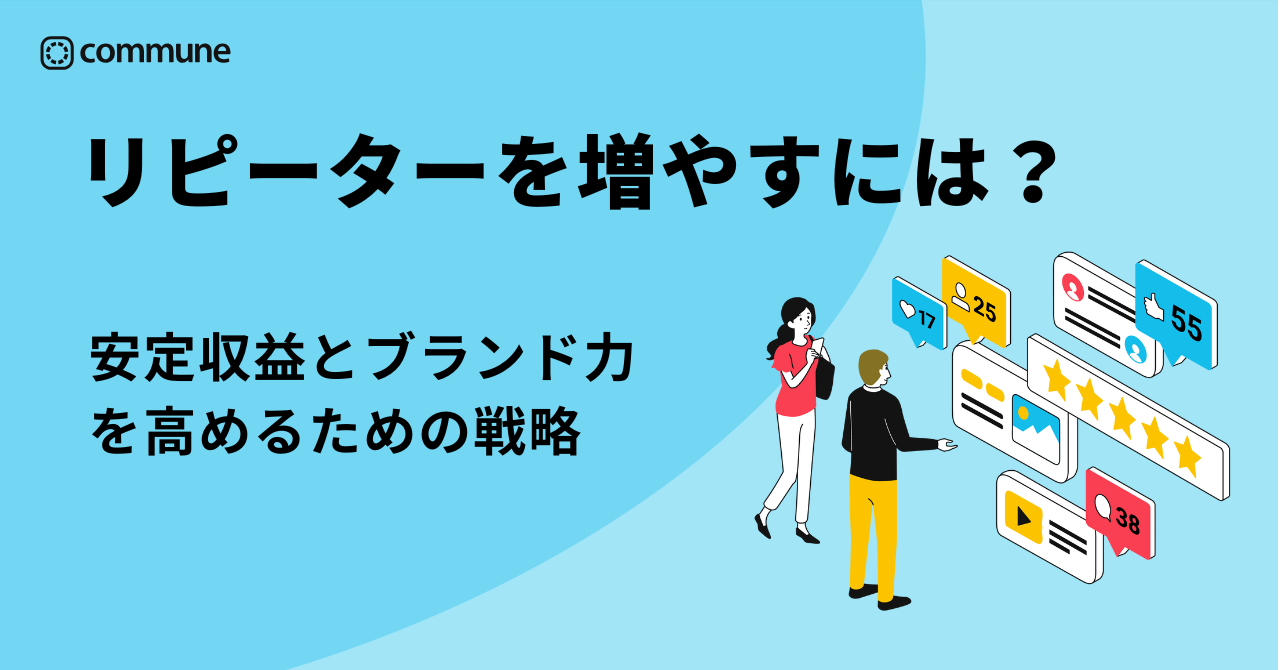
一度購入や利用をしてくれたお客様に、何度も繰り返し選んでもらうためにはどうすればよいのでしょうか。「リピーターを増やす」という問いは、新規顧客の獲得コストが高騰する現在、あらゆる業種で注目されています。
実際のところ、どんな施策を打てばリピーターが定着し、さらには周囲へのポジティブな口コミも広げてくれるファンに育っていくのでしょう。本記事では、リピーターが増えない根本的な原因から成功事例までを掘り下げ、長期的に成果をもたらす戦略を解説します。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
第1章:リピーターの重要性
リピーターとは、一度商品やサービスを体験した上で再び購入・来店を継続する顧客を指します。単に「もう一度買う人」ではなく、企業の財務的・戦略的な基盤を支えるキープレイヤーです。
近年はデジタル広告費の高騰やプラットフォーム依存による集客リスクの増大により、新規獲得偏重のビジネスモデルが揺らぎつつあります。その結果、マーケティング担当者は「いかにリピーターを増やすか」を最優先課題として捉え始めました。
ある調査によると「リピート率を5%向上させるだけで利益が25〜95%伸びる業界も」とされるなど、リピーターがもたらす収益インパクトは小さくありません。
収益の安定化
リピーターは過去に購買経験を持つため、商品やサービスへの期待値と満足度がすでに醸成されています。この信頼関係があるからこそ、購買頻度や平均客単価が自然と上昇しやすく、売上予測の精度も高まります。
特にサブスクリプションでは、解約率(チャーンレート)の低下がそのまま月次MRRの増加につながります。結果、金融機関からの評価も向上し、資金調達の面で有利に働くことがあります。安定的なキャッシュフローは新規事業やR&Dへの投資余力を生み、長期的な企業価値の向上にも直結すると言えるでしょう。
新規顧客獲得コストの削減
米国のダイレクトマーケティング協会(DMA)は、「新規獲得コストは既存顧客維持コストの平均5倍」と報告しています。デジタル広告のCPAが年々高騰する現在、限られたマーケティング予算をリピーター醸成に振り向けることは、投資効率の面で極めて合理的です。
たとえば、メールマーケティングやロイヤルティプログラムの実装は、1ユーザーあたり数十円規模のコストで実行できるのに対し、新規リード獲得のための検索連動型広告は1クリック数百円に達するケースもあります。費用差の大きさは、顧客維持戦略の優位性を示す明確な根拠と言えるでしょう。
既存顧客維持コストを1とした時、新規顧客獲得コストは5という「1:5の法則」についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
口コミ波及効果
リピーターはブランド体験を自発的に語る最良の広告塔でもあります。SNSやレビューサイト、オフラインの友人ネットワークで発生する好意的なクチコミは、広告よりも高い説得力を持ち、意思決定の最終局面で大きく影響を与えます。
とりわけZ世代やミレニアル世代は「他者の実体験」を購入判断の有力情報源として重視するため、リピーター由来のUGC(ユーザー生成コンテンツ)が新規顧客の信頼獲得に寄与します。結果として広告依存度が軽減され、顧客獲得チャネルが多様化・自走化する好循環が生まれるのです。
■関連記事:
UGCとは何か?メリット・生成促進4ステップと成功事例
ブランド力の向上
リピーターの存在はブランドが提供する価値の「実証データ」として機能します。価格競争や模倣品が蔓延する市場であっても、実利用者が継続的に支持しているという事実は差別化の強力な裏づけとなり、競合の参入障壁を高めます。
さらに、リピーターがブランドストーリーへの共感やライフスタイルへの適合性を理由に選択を続ける場合、ブランドは単なるベンダーではなく「共感を媒介するコミュニティ」として位置づけられます。このフェーズに達すると、値引きやクーポンといった価格インセンティブに頼らずともロイヤルティを維持・向上させることが可能です。
リピーターは短期的な売上拡大を支えるだけでなく、顧客ライフサイクル全体の価値を最大化し、中長期的なブランド資産を築く推進力となります。続く章では、リピーターが増えない原因の深掘りと打ち手の全体設計、さらに実践的な施策や効果測定の方法まで詳しく解説します。
■関連リンク:
ロイヤルティとは?向上させる方法や成功事例を紹介
第2章:リピーターが増えない主な原因
「新規顧客が定着しない」「2回目の購入に結びつかない」、多くの事業者が抱えるこの悩みは複合的な要因が絡み合っている場合がほとんどです。まずは代表的な原因を丁寧に整理し、なぜ顧客が“もう一度選ぶ理由”を見いだせないのかを深掘りしてみましょう。
印象に残らない(接点の不足)
購入直後は高まっていた期待値も、時間の経過とともに急速に薄れていきます。大手化粧品ECサイトの調査によれば、購入後48時間以内にサンクスメールや利用ヒントを送った顧客の再購入率は、フォローがない場合の2.7倍に達したと報告されています。
多くの人は日常生活において洪水のような情報にさらされています。よほど強く記憶に残る体験でなければ、忘却してしまうものです。接点の不足は「買ったときは良かったけれど、次の機会に思い出せなかった」状態を生み、再訪のトリガーが立ち上がらないまま競合へ流出する温床となります。
顧客の満足度不足
購入時点での期待値と実際の体験にギャップがあると、たとえ大きなクレームがなくても“静かな不満”が蓄積します。飲食業のリピート調査では、料理の味よりも「待ち時間へのストレス」や「接客の態度」が再来店意向に強く影響することが分かっています。
つまり商品そのものと同じくらい、環境やスタッフの対応、アフターサービスが満足度を左右するのです。特にオンライン購入では、配送のスピードや梱包の丁寧さといった周辺体験が記憶に残りやすく、ここでつまづくとブランド全体の印象が毀損されてしまいます。
再来店・再購入の動機づけ不足
「また選ぶとお得だ」という具体的メリットが提示されなければ、価格や体験価値で上回る競合が現れた瞬間に顧客は離脱します。ポイントやクーポンといった金銭的インセンティブも一定の効果があるものの、近年は体験価値を高めるリワードの重要性が増しています。
ホテル業界では、滞在回数に応じて部屋のアップグレード権やウェルカムドリンクを提供したところ、年間平均宿泊数が30%以上伸びたケースがあります。金額的な割引だけでなく、VIP体験のような“名誉的リワード”が動機づけとして強く機能する好例です。
差別化が曖昧
似た商品・サービスが飽和する市場では、「値段」「立地」「納期」といった分かりやすい指標だけで競うと、必ず上位互換が現れます。顧客が「ここでなければならない理由」を語れない限り、選択の軸は容易に切り替わってしまいます。
家電量販店を例に取ると、同じ最新モデルでも「専門スタッフによる設置サポートが無料」「リサイクル回収を付加」「購入後90日間は無償で設定サポート」といった独自の付加価値がある店舗は、オンライン最安値より高価格でもリピーターを確保しています。機能や価格ではなく、体験価値や世界観で差別化する姿勢が不可欠です。
顧客データ活用不足
顧客属性や購入履歴を十分に活用できていない企業は、パーソナライズされた提案やタイミング最適化が行えず、均質なコミュニケーションに終始しがちです。結果として、顧客が「自分向け」の提案ではないと感じ、エンゲージメントが低下します。
CRMを導入していても入力の統一ルールが曖昧だったり、担当者任せで情報が分散していると、データは宝の持ち腐れになりかねません。精緻なセグメンテーションと分析プロセスを整備してこそ、顧客の期待値を超える提案が可能になります。
購入体験における障壁
ECならカート画面の複雑さ、実店舗ならレジ待ち時間の長さといった“摩擦”は、再購入のハードルを高める目に見えない壁です。米国の調査会社Baymard Instituteのレポートでは、カゴ落ち要因の第一位が「会員登録プロセスの煩雑さ」であると結論づけられています。購入体験にかかるストレスや不安を徹底的に解消することで、リピーターの離脱を防げるのみならず、初回から高評価を獲得してポジティブな口コミが広がる好循環が生まれます。
以上のように、リピーターが定着しない背景には接点の希薄化、満足度ギャップ、動機づけ不足、差別化不在、データ活用遅れ、体験の摩擦といった多面的な課題が存在します。自社がどの領域で課題を抱えているかを可視化し、優先順位を付けて改善を進めることが、長期的なリピーター育成の第一歩となるでしょう。
関連記事:UGCとは何か?メリット・生成促進4ステップと成功事例
┗口コミ波及効果に直結する、“ユーザー生成コンテンツ”の具体解説です。
第3章:リピーターを増やす全体戦略
リピーター獲得は「一度きりの値引きキャンペーン」や「豪華ノベルティ」だけでは持続しません。顧客がブランドを“再び選ぶ必然性”を感じるには、商品開発からアフターフォローまで一貫した体験設計が求められます。本章では、その核となる四つの戦略と、組織的に実行力を高めるための視点を立体的に整理します。
顧客満足度の最大化
まず土台となるのが顧客満足度の最大化です。リピーター戦略においては、顧客が商品やサービスの価値を体感した瞬間から、継続的な支持を得るまでの全プロセスを最適化することが第一歩となります。
製品の基本品質や機能性を磨くのはもちろん、購入前の情報提供のわかりやすさ、決済・受け取りまでのスムーズさ、購入後の問い合わせ対応や保証内容までが総合的に評価されます。特にオンラインとオフラインが交錯するオムニチャネル環境では、チャットボット・対面スタッフ・FAQページなど接点ごとの“トーン&マナー”を統一し、どこで接してもブランドらしい安心感を得られる仕組みが欠かせません。
顧客データの活用
次に欠かせないのが顧客データの活用です。顧客が何を買い、いつ使い、どんな感情を抱いたかという行動・感情データを統合することで、真に価値ある提案が可能になります。たとえば、購買履歴と閲覧ログを掛け合わせると「頻繁に閲覧しているが購入していないカテゴリー」が浮かび上がり、そこに限定オファーを提示すると購入転換率が大きく跳ね上がります。
また、チャットサポートの会話内容をテキストマイニングすると、FAQには表れない潜在的な不満を検知でき、プロダクト改善サイクルを一段と高速化できます。こうしたデータドリブン運用を支えるのはCRMやCDPですが、ツール導入そのものより、部門を横断して顧客情報が循環する“組織文化”の醸成こそが成功の鍵となります。
ブランドストーリーやコアコンセプトの打ち立て
三つ目の柱はブランドストーリーやコアコンセプトの打ち立てです。どれほど利便性や価格競争力を訴えても、似たような製品が市場に溢れる現在ではすぐにコピーされてしまいます。そこで重要になるのが、企業の思想やプロダクトが生まれた背景、社会課題への貢献など、機能価値を超えた情緒的・文化的な価値を物語として提示することです。
たとえば、環境配慮のポリシーを徹底し、そのプロセスを動画やSNSライブで透明性高く共有すると、消費者は購入行為そのものを“社会的な良い行い”と認識し、再購入意欲が高まる傾向があります。ブランドの世界観を体現するポップアップイベントやオンラインコミュニティを運営すれば、顧客同士の共感が強まり、企業が介在しなくてもUGCが自然発生する状態へと発展します。
関連記事:パーセプションとは?「認識」の本質と実践
┗ブランドストーリー設計や顧客認識改善に向けた“パーセプションフロー”視点を提供。
長期的な視点でのPDCA運用
最後に、長期的な視点でのPDCA運用が不可欠です。一度実行した施策は、必ず具体的なKPI設定と効果測定を行い、成功要因と改善点を明確にする必要があります。
例えばメルマガなら開封率とクリック率だけでなく、開封後のサイト滞在時間や購買転換まで追跡して初めて全体のROIが見えます。クーポン施策も使用率の高低だけでなく、クーポン利用者のLTV(ライフタイムバリュー)が非利用者より長期的に伸びているかをウォッチしなければ、本当の意味でのリピーター育成とは言えません。
サーベイによるNPS(ネットプロモータースコア)計測や、コホート分析によるチャーン兆候検知と組み合わせれば、戦略の改善サイクルを高速で回す体制が整います。中長期的には、これらのデータをベースにA/Bテストを継続し、アルゴリズムによるレコメンド精度を高めるなど、テクノロジー活用を深化させることで競争優位を持続できます。
この4つの戦略をバラバラにやるのではなく、うまく連携させるには、会社全体でのルール作りや調整が欠かせません。たとえばマーケティングやカスタマーサクセス、商品開発、店舗運営など、それぞれの部署が自分たちの目標だけを追いかけていると、顧客体験はバラバラになってしまいます。
経営陣が「お客様を一番大事にする」という考え方をはっきり示し、全ての部署で共通の目標(たとえば「1年後にどれだけお客様がリピートしてくれているか」など)を決めることで、みんなが同じ方向を向いて動けるようになります。こうすることで、お客様が「いつでも、どこでも、何度でもこのブランドを選びたい」と思えるような体験を作ることができるのです。
第4章:有効な施策の具体例
リピーター(何度も買ってくれるお客様)を増やすには、1回きりのキャンペーンだけでは足りません。お客様が商品を買う前から買った後まで、ずっと良い体験をしてもらうことが大切です。ここでは、リピーターを増やすために効果的な4つの方法を、できるだけわかりやすく説明します。
1. 定期的な情報発信とフォローアップ
商品を買ってくれた直後にサンクスメールやLINEなどで伝えるのはもちろん、その後も役立つ情報を届けましょう。たとえば商品の使い方を説明した動画や、よくある質問への答え、他のお客様の体験談などを送ると、「このお店は親切だな」「また買いたいな」と思ってもらえます。
また、お客様が次に買いそうなタイミングを予測してお知らせやクーポンを送るのも効果的です。さらに、過去に見た商品や買った商品に合わせて「こんな商品もおすすめです」と紹介すれば、ついで買いや新しい商品の購入につながります。
2. 会員ランクやポイント制度
リピーターを「特別なお客様」として扱う仕組みも大切です。たとえば、買い物の回数や金額に応じて「シルバー」「ゴールド」などのランクをつけ、ランクが上がるごとに割引や限定イベントへの招待、特別なサポートなどの特典を用意します。
さらに、「あと○円でゴールドに昇格!」など、次のランクまでの目標をわかりやすく見せると、「もう少し買ってみようかな」と思ってもらいやすくなります。上位ランクのお客様には、専任のスタッフが相談に乗るなど、特別感を演出するのもおすすめです。
3. お客様の声を活かした商品・サービス改善
リピーターが増えない原因には、ちょっとした不満や使いづらさが隠れていることも。そこで、購入後のアンケートやレビューを簡単に答えられるようにして、お客様の本音を集めましょう。
集まった声は、すぐに社内で共有し、商品やサービスの改善につなげます。改善したら「皆さまのご意見をもとに、ここを直しました」とお知らせすると、「自分の声が届いた」と感じてもらえ、信頼感がアップします。SNSでの口コミにも素早く返信し、感謝や改善策を伝えることも大切です。
4. 限定イベントやコミュニティづくり
「ここでしか体験できない」イベントを用意すると、お客様との絆が深まります。たとえば、新商品の試食会や、特別なディナーイベントなど、特別感のある企画は思い出に残りやすく、SNSでの話題作りにもなります。
また、招待制のオンラインコミュニティを作り、商品開発の裏話を共有したり、お客様同士で使い方を教え合う場を作るのも効果的です。イベント後には参加者の感想や写真を発信し、次回の案内をすると「また参加したい」と思ってもらえます。
これら4つの方法は、1つだけでも効果がありますが、組み合わせるとさらに効果を増します。たとえば、コミュニティの参加者に特別なクーポンを配ったり、その情報を会員データと連携して、よりピッタリな情報を届けるなどです。お客様が「面倒だな」「迷うな」と感じる場面を減らし、自然とまた買いたくなる仕組みを作ることが、リピーターを増やす一番の近道です。
第5章:リピーター育成の成功事例
理論やノウハウを学んでも、「本当に効果があるの?」「自分の会社でも使えるの?」と不安になることは多いですよね。ここでは、さまざまな業界・規模の企業がリピーターを増やすために実際に行った施策と、その結果どうなったのかを、できるだけ分かりやすく紹介します。自社で応用できそうなヒントを見つけてみてください。
【事例1】居酒屋チェーン:アプリで再来店が大幅アップ
全国に200店舗以上ある居酒屋チェーンは、スタンプ機能とプッシュ通知がついたスマホアプリを導入しました。スタンプを5個集めると人気メニューが1品無料、10個でグループ全員のドリンクが半額になるなど、ゲーム感覚で楽しめる仕組みです。席にあるQRコードを読み込むだけでスタンプがもらえるので、手間もかかりません。
その結果、アプリ導入から半年で月の再来店率が30%アップ、客単価も10%上がりました。さらに、友達を招待できる機能で、新規のお客さんの3人に1人が既存のお客さんの紹介で来店するようになり、リピーターが新規集客にもつながる好循環が生まれました。
【事例2】化粧品EC:AIメールでLTVが1.5倍に
スキンケアのD2Cブランドでは、会員登録時に肌の悩みや年齢、生活習慣を聞き取り、AIがその人に合った商品を自動で提案する仕組みを作りました。さらに、購入サイクルをAIで予測し、商品がなくなりそうな7日前に「リフィル特典」メール、3日前に「まとめ買い割引」メールを送信。メールの開封率は通常の2.2倍、リピート購入率も40%から63%に急増。1年後には顧客のLTV(生涯価値)が1.5倍になり、広告費が上がっても十分に利益が出るようになりました。
【事例3】SaaS企業:オンボーディングと特典で解約率が半分に
プロジェクト管理ツールを提供するSaaS企業は、契約後90日以内に使いこなせず離脱するお客さんが多いことに注目。そこで、最初の3か月間は専任スタッフが週1回オンラインで短いワークショップを開き、実際の業務に役立つテンプレートを一緒に作成しました。
さらに、6か月継続したユーザーには上位機能を無料で使える特典も用意。その結果、ツールの利用率が大きく上がり、1年以内の解約率は16%から7%に半減。解約が減ったことでアップセルのチャンスも増え、契約単価も年18%伸びました。
これらの事例に共通しているのは、
- お客様の行動データや声をもとに施策を考えている
- 「特別感」や「自分向け」の体験をタイミングよく提供している
- 成果をしっかり測定し、改善を続けている
という点です。業種が違っても、「特別な体験」「一人ひとりに合わせた対応」「継続的なコミュニケーション」を組み合わせれば、リピーターは確実に増やせることが分かります。次の章では、こうした施策を進めるうえで大切な評価指標や測定方法について、分かりやすく解説します。
第6章:効果測定のポイントと指標
リピーター施策が本当に利益につながっているかどうかを判断するには、「なんとなく良さそう」という感覚ではなく、数字でしっかり検証する仕組みが大切です。見るべき指標は「1回きりの取引」ではなく、「お客様がどれくらいブランドと長く深く関わってくれているか」を表すものを選びましょう。
ここでは、特に重要な4つの指標について、計算方法や使い方、読み解き方をわかりやすく説明します。
まず「リピート率(再購入率)」は、ある期間に買ってくれたお客様のうち、もう一度買ってくれた人の割合です。たとえば「今月買った人が、来月も買ってくれたか?」というように、月ごとや四半期ごとに区切って変化を見ていくと、キャンペーンやサービス改善の効果が分かりやすくなります。
ECサイトなら「初回購入から30日以内」「60日以内」「90日以内」など、期間ごとに追いかけると、短期的な人気と中期的な定着の両方をチェックできます。ただし、消耗品や季節商品など、もともと買い替えサイクルが長い商品はリピート率が低く見えがちなので、「想定される再購入周期に対して、どれくらいリピートされているか」といった補助的な指標も使うと良いでしょう。
次に「LTV(顧客生涯価値)」は、1人のお客様が生涯でどれくらい利益をもたらしてくれるかを表します。計算は「平均購入金額 × 購入頻度 × 継続期間」で出します。リピーター施策の最終的な目標は、このLTVを上げることです。
LTVは「粗利ベース(売上から原価を引いた利益)」や「純利益ベース(さらに広告費や人件費も引いた利益)」など、どこまでコストを含めるかで見方が変わるので、社内で基準を揃えておくと議論がスムーズです。また、「12か月LTV」「24か月LTV」など期間を決めて、チャネル別やキャンペーン別に分けて分析すると、どこに力を入れるべきか判断しやすくなります。
「NPS(ネットプロモータースコア)」は、「あなたはこの会社(商品)を友人や同僚にどれくらい勧めたいですか?」と0〜10点で聞き、「勧めたい」と答えた人の割合から「勧めたくない」と答えた人の割合を引いて算出します。NPSは直接売上を示すものではありませんが、ファンの多さや口コミで新規顧客が増える可能性を測る大事な指標です。定期的にNPSを調べて推移を見れば、顧客の満足度やロイヤルティの変化が分かります。また、NPS調査の自由記述欄にはお客様の本音が集まりやすいので、よく出るキーワードや感情を分析して、商品やサービス改善に活かすのもおすすめです。
「休眠客割合」は、しばらく購入や来店がないお客様が全体の中でどれくらいいるかを示します。たとえばSaaSなら「30日間ログインがなければ休眠」と定義し、メールやカスタマーサクセス担当が段階的にフォローすることで解約を防げます。小売業なら「普段90日ごとに買うお客様が120日以上来店しなければ休眠」といった具合に、業種や商品ごとに基準を調整しましょう。休眠客をグループ分けして、復帰キャンペーンの効果を比べると、どんな施策が効率的かも見えてきます。
この4つの指標だけでは分からない部分を補うために、「チャーン率(解約率)」「AOV(平均注文額)」「セッションごとの売上」「CSAT(顧客満足度スコア)」「DAU/WAU/MAU(アクティブユーザー数)」など、必要に応じて他の指標も組み合わせると、より細かく状況を把握できます。
特に「コホート分析」は、獲得月やキャンペーンごとにお客様をグループ分けし、時間が経つごとのリピート率やLTVを比較できるので、施策ごとの効果が一目で分かります。また、「CAC(顧客獲得コスト)」とLTVの比率が3:1を超えているかどうかをチェックすれば、投資判断にも役立ちます。こうした数字を使って、経営層にも納得してもらえる説明ができるようになります。
第7章:まとめと今後の展望
本記事では「リピーターを増やすには?」というテーマで、リピーターの価値や増やし方について分かりやすくまとめてきました。ここでは、企業がこれからもリピーターを増やし続けるために大切なポイントと、今後の変化について簡単に整理します。
まず、リピーターは「売上を安定させる」「ブランドを強くする」ためにとても重要です。新規のお客さんを集めるコストがどんどん上がっている今、リピーターがいることで広告に頼りすぎずにすみます。リピーターは何度も買ってくれるだけでなく、SNSで口コミを書いたり、友達に紹介してくれたりと、広がりの効果も大きいです。こうした価値を数字で見える化し、会社の大事な戦略として位置づけることが、これからの競争で勝つカギになります。
次に、リピーターが増えない原因をしっかり見つけて、常にお客さんの立場で考え直すことが大切です。たとえば「印象が薄い」「満足できなかった」「また買う理由がない」「他と違いが分からない」など、よくある原因を自社のお客さんの流れに当てはめて整理しましょう。社内のいろんな部署で優先的に直すべきことを共有できる仕組みも必要です。特に今はネットとリアル店舗の両方で買い物する人が増えているので、どこで買っても同じように気持ちよく体験できるようにすることが急務です。
また、リピーターを増やす施策は「単発」ではなく「長く続く仕組み」にすることが成功のポイントです。会員ランクやクーポンなどお得な特典だけでなく、ブランドのストーリーに共感してもらう、ユーザー同士がつながるコミュニティを作る、初めての人をしっかりサポートするなど、いろいろな価値を重ねて「このブランドと長く付き合いたい」と思ってもらうことが大切です。
さらに、リピーター施策の効果をしっかり測り、改善を続けることも重要です。リピート率やLTV(顧客生涯価値)、NPS(おすすめ度)、休眠客の割合などを一つの画面で見えるようにし、どの施策がどれだけ効果があったかすぐに分かる仕組みを作りましょう。最近はAIの進化で、お客さんの声をリアルタイムで分析し、商品開発や個別対応にすぐ活かせるようになっています。こうした新しい技術を早く取り入れた企業ほど、変化に強くなります。
これからは、プライバシー保護の強化やCookie(ネットの追跡技術)の廃止が進むことで、自社で集めたお客さんのデータやコミュニティの価値がますます高まります。また、AIとリアルタイムのパーソナライズが進み、「一人ひとりに合った体験」を提供する時代が本格的にやってきます。さらに、環境や社会貢献への関心が高まる中で、ロイヤルティプログラムに社会貢献の要素を組み込む動きも増え、「買うこと自体が社会への投票になる」という新しいリピートの理由も生まれています。
こうした流れをふまえると、企業は短期的なセールだけでなく、お客さんと長く信頼関係を築く「共感資本」を作ることが大切です。自社の強みを活かしつつ、テクノロジーやデザイン、コミュニティ運営を組み合わせて、「ここで買い続けることが自分らしい」と思ってもらえる体験を磨いていきましょう。リピーターは単なる売上源ではなく、時代の変化に強いブランドを作る最大の資産です。これからもお客さん目線を忘れず、データと心の両方からアプローチを進化させて、リピーターを育てていきましょう。
あわせて読みたい
- ロイヤルティプログラムとは?顧客をファン化する施策の基本と成功のカギ
┗リピーターがブランドに戻る理由となる“信頼・愛着”強化のメカニズムが理解できます。 - UGCとは何か?メリット・生成促進4ステップと成功事例
┗「口コミ波及」章とつながるUGC活用の具体策と実例がわかります。 - パーセプションとは?「認識」の本質と実践
┗ブランドストーリーの効果を高めるための、顧客認知設計の視点を補います。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
