コラム
マーケティング
ポジショニング戦略とは?市場で選ばれる「唯一の存在」になる
2025/08/01
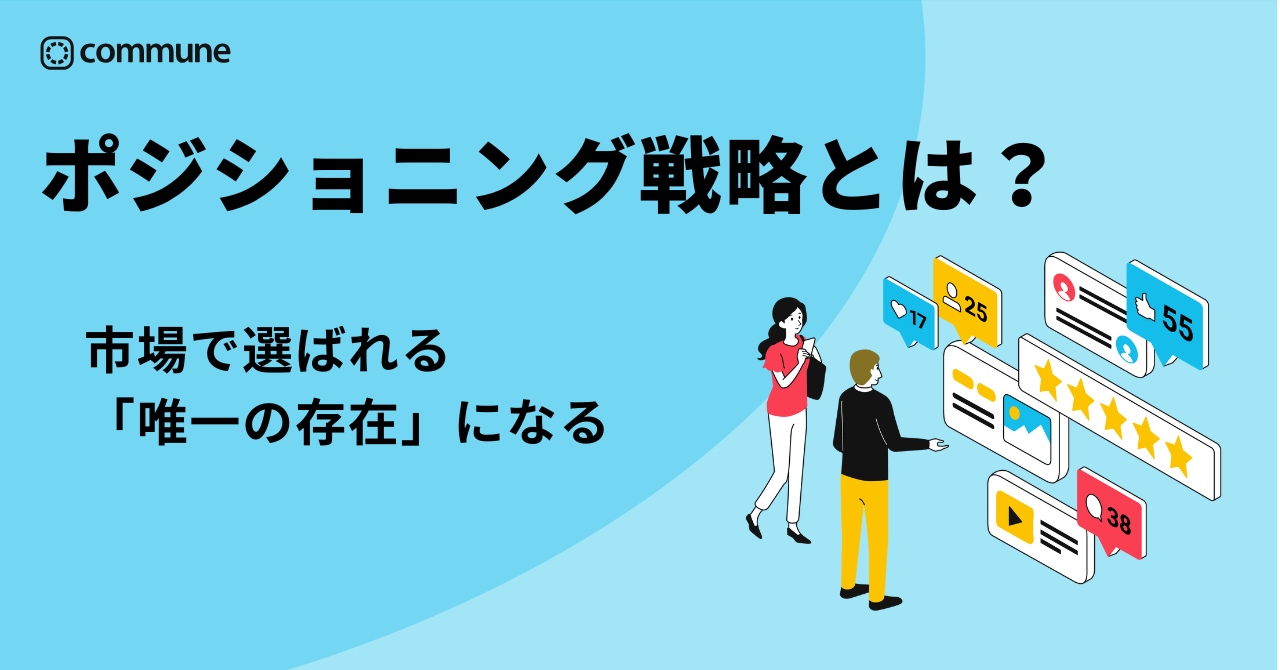
「自社の強みが顧客にうまく伝わらない」「気づけば競合との価格競争に陥っている」——。 この記事に辿り着いたあなたは、こうした課題を前に、自社製品やサービスが市場で確固たる地位を築くための本質的な方法を模索されているのではないでしょうか。
その問題意識は、現代のビジネス環境において極めて重要です。情報爆発時代の到来により、消費者が1日に触れる情報量は10年前の約530倍に達したとも言われています(総務省情報通信白書)。また、BtoBの領域では、購買担当者の約7割が営業担当者に会う前にオンラインでの情報収集を終えているとも言われます。これは、企業が「売り込む」前に、顧客の中で「選ばれる」ための理由が確立されていなければ、そもそも検討の土俵にすら上がれない時代の到来を意味します。
本稿は、こうした熾烈な市場競争を勝ち抜き、「自社ならではの価値」を顧客の心に深く刻み込みたいと考えるすべてのビジネスパーソンのために構成しました。ポジショニング戦略とは何か、その本質から具体的な策定手順、そして国内外の成功事例までを網羅的に解説します。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
- 第2章 なぜ今、ポジショニング戦略が不可欠なのか?データで見る市場の変化
- 情報爆発と「選ばれない」リスクの増大
- 顧客主導の購買プロセスへの移行
- 「体験価値」への期待の高まり
- 第3章 ポジショニング戦略の4つの基本形 - 自社に合う型を見つける
- ✅ 自社のポジショニング診断チェックリスト
- 第5章 陥りがちな3つの罠と回避策 - ポジショニング戦略のリスク管理
- ① 曖昧なポジショニングの罠:「万人受け」を狙い、誰にも響かない
- ② 現実と乖離したポジショニングの罠:「宣言」と「実態」が伴わない
- ③ 硬直化したポジショニングの罠:市場の変化に気づかず「過去の成功」に固執する
第1章 ポジショニング戦略とは?その定義と「選ばれる理由」の本質
ポジショニング戦略とは、「ターゲット顧客の心の中に、競合とは異なる明確で価値ある独自の地位(ポジション)を築くための活動」と定義されます。提唱者である経営学者のフィリップ・コトラーは、この活動をマーケティング戦略の核に据えました。
重要なのは、これが単なる「製品の差別化」ではないという点です。自社が「うちはここが優れています」と主張するだけでなく、その価値が顧客の頭の中で「確かにこの製品は、〇〇という点で他とは違う特別な存在だ」と認識されて初めて、ポジショニングは成功したと言えます。
つまり、ポジショニングの戦場は市場ではなく、顧客の「頭の中」なのです。
よくある誤解:「差別化」や「ターゲティング」との違い
ポジショニングは、しばしば他のマーケティング用語と混同されがちです。特に「差別化」や「ターゲティング」との違いを理解することが、戦略の精度を高める第一歩となります。
| 項目 | ポジショニング (Positioning) | ターゲティング (Targeting) | 差別化 (Differentiation) |
| 目的 | 顧客の心の中に独自の地位を築く | どの市場・顧客層を狙うか決定する | 競合との違いを創り出す |
| 焦点 | 顧客の「認識」 | 狙うべき「市場」 | 製品やサービスの「機能・特徴」 |
| 問い | 「顧客にどう思われたいか?」 | 「誰を顧客にするか?」 | 「競合と何が違うか?」 |
| 関係性 | ターゲティングと差別化の結果を統合し、顧客への提供価値を定義する活動 | ポジショニング戦略の前提となる活動 | ポジショニングを支える具体的な要素 |
このように、ターゲティングで「誰に」を定め、差別化で「何を」を明確にし、それらを統合して「どう思われるか」を設計するのがポジショニング戦略です。これらは独立した活動ではなく、一連の流れとして捉える必要があります。
なぜ「価格」で戦ってはいけないのか?
多くの企業が陥りがちなのが、安易な価格競争です。しかし、ポジショニング戦略が不在のまま価格だけで勝負しようとすると、利益率の低下を招き、ブランド価値を毀損し、結果的に企業の体力を奪う消耗戦に突入します。
優れたポジショニング戦略は、顧客に「価格が高くても、この価値のためなら支払う価値がある」と感じさせます。これにより、企業は価格競争から一線を画し、持続的な成長の基盤を築くことができるのです。
第2章 なぜ今、ポジショニング戦略が不可欠なのか?データで見る市場の変化
ポジショニング戦略の重要性は、年々高まっています。その背景には、無視できない3つの市場変化が存在します。
情報爆発と「選ばれない」リスクの増大
現代人は、1日に平均して34GBもの情報に接していると言われます(カリフォルニア大学サンディエゴ校調査)。これは、新聞10万ワード分に相当する量です。この情報洪水の中で、特徴のない製品やサービスは、顧客の記憶に残ることなく、あっという間に忘れ去られてしまいます。明確なポジショニングがなければ、存在しないのも同然なのです。
顧客主導の購買プロセスへの移行
Gartner社の調査によると、B2Bの購買担当者は、購買プロセス全体のわずか17%しか営業担当者との対話に費やしていません。残りの時間は、オンラインでのリサーチや社内での議論に使われています。これは、企業が顧客と接触する以前に、Webサイトや第三者の評価によって「どのような企業か」というポジションがほぼ決定づけられていることを示唆しています。
「体験価値」への期待の高まり
PwCの調査では、消費者の86%が「優れた顧客体験」のためなら、より多くのお金を支払ってもよいと回答しています。製品の機能や価格だけでなく、「この企業から買うこと」自体に価値を感じる時代へとシフトしているのです。この「体験価値」こそが、ポジショニングを形成する上で極めて重要な要素となっています。
これらのデータが示すのは、「特徴のないその他大勢」は淘汰され、「明確な価値を持つ唯一の存在」だけが生き残るという厳しい現実です。だからこそ今、自社のポジションを戦略的に設計し、顧客の心に刻み込む努力が、企業の生死を分けるのです。
第3章 ポジショニング戦略の4つの基本形 - 自社に合う型を見つける
ポジショニングを確立するための切り口は無数にありますが、代表的な戦略は主に4つの型に分類できます。自社の強みや市場環境と照らし合わせ、どの型を目指すかを考えることが重要です。
| 戦略タイプ | 特徴 | メリット | デメリット | 代表例 |
| ① 品質リーダー型 | 圧倒的な品質、性能、技術力で市場を牽引する。 | 高いブランドイメージと利益率を確保できる。価格競争に巻き込まれにくい。 | 開発コストが高く、模倣リスクがある。市場が成熟すると価値が伝わりにくくなる。 | ダイソン、メルセデス・ベンツ |
| ② 価格リーダー型 | 徹底したコスト削減により、競合よりも低い価格で提供する。 | 大量の市場シェアを迅速に獲得できる。規模の経済が働きやすい。 | 利益率が低い。常にコスト削減のプレッシャーに晒される。ブランドイメージが安っぽくなるリスク。 | ユニクロ、マクドナルド |
| ③ ニッチ特化型 | 特定の顧客セグメントやニーズに特化し、その領域で圧倒的なNo.1を目指す。 | 競合が少なく、顧客ロイヤルティを高めやすい。高い専門性を武器にできる。 | 市場規模が限定される。市場の嗜好が変化するとリスクが大きい。 | スバル(AWD技術)、ガリバー(中古車買取) |
| ④ 顧客体験・ソリューション型 | 製品だけでなく、コンサルティングやサポート、コミュニティなどを通じて包括的な解決策を提供する。 | 顧客との関係性が深まり、LTVが向上する。スイッチングコストが高くなる。 | 高度な組織力と人材が必要。成果が出るまでに時間がかかる。 | Salesforce、リッツ・カールトン |
✅ 自社のポジショニング診断チェックリスト
自社がどの型を目指すべきか、以下の質問に答えてみましょう。
- 自社の技術力や製品品質は、客観的に見て業界トップクラスと言えるか? (Yesなら①)
- 業界で最も効率的な生産・供給体制を構築できるか? (Yesなら②)
- 大企業が見過ごしている、特定の深い悩みを持つ顧客層は存在するか? (Yesなら③)
- 顧客の成功を支援するための手厚いサポート体制やノウハウがあるか? (Yesなら④)
- 顧客が自社製品を選ぶ最大の理由は「価格の安さ」か? (Yesなら価格競争の危険信号)
これらの問いを通じて、自社の進むべき方向性が見えてくるはずです。重要なのは、複数の型を中途半端に追うのではなく、一つの型に集中投資することです。
第4章 成功事例に学ぶ「勝ち筋」- BtoBとBtoCのケーススタディ
理論だけでなく、実際の企業がどのようにポジショニングを確立したかを見ていきましょう。
✅ BtoC事例:ワークマン(アパレル)
かつてのワークマンは「プロ職人向けの作業服専門店」という明確なポジションを持っていました。しかし、その市場は限定的でした。同社は、自社の強みである「高機能・低価格」という価値を維持したまま、ターゲットを一般消費者に広げるという大胆な再ポジショニングに挑戦します。
- 戦略:
「アウトドアウェア市場」という新たな戦場において、「高機能・低価格」という空白のポジションを狙う。 - 実行:
SNSでインフルエンサーを巻き込み、「#ワークマン女子」という言葉を生み出すことで、ファッション性をアピール。製品の機能性の高さを一般消費者にも分かりやすく伝えました。 - 成果:
この戦略転換により、既存のプロ職人層を維持しつつ、女性やファミリー層という新たな顧客を獲得。2024年3月期の営業総収入は1,333億円に達し、12期連続で過去最高を更新しました。これは、自社のコアな強みを再定義し、新たな市場で独自のポジションを築いた典型的な成功例です。
✅ BtoB事例:Slack(ビジネスコミュニケーション)
Slackが登場する前、ビジネスコミュニケーションの主役は「メール」でした。Slackは、この巨大な既存市場に対して「メールを置き換える、より速く、整理されたコミュニケーションツール」という明確なポジションを打ち出しました。
- 戦略:
単なるチャットツールではなく、「仕事のハブ(Hub)」としてのポジションを確立。あらゆる業務アプリケーションと連携できるプラットフォームを目指す。 - 実行:
直感的で楽しいUI/UXを提供し、開発者向けのAPIを早期に公開。ユーザーが自発的に連携アプリを開発するエコシステムを構築しました。これにより、単なるコミュニケーションツールを超え、「Slackさえ開けば仕事が進む」という独自の価値を生み出しました。 - 成果:
2021年にSalesforceに約277億ドルで買収され、BtoB SaaS史上最大級の成功事例となりました。これは、競合(メール)の弱点を突き、新たなカテゴリーを創造することで圧倒的なポジションを築いた好例です。
これらの事例から学べるのは、自社の揺るぎない強み(コア・コンピタンス)を基軸に、市場の空白地帯(ブルー・オーシャン)を見つけ出し、そこに旗を立てることの重要性です。
第5章 陥りがちな3つの罠と回避策 - ポジショニング戦略のリスク管理
輝かしい成功事例の裏には、数多くの失敗があります。ポジショニング戦略を推進する上で、多くの企業が陥る典型的な3つの罠と、その回避策を理解しておきましょう。
① 曖昧なポジショニングの罠:「万人受け」を狙い、誰にも響かない
「高機能でありながら、価格も手頃で、デザインもおしゃれ」といったように、あらゆる面で優位に立とうとすると、結局特徴がぼやけてしまい、顧客の記憶に残りません。
- 回避策: 「何をやらないか」を決める勇気を持つこと。 ポジショニングとは、選択と集中です。自社が最も価値を提供できる顧客と提供価値を一つに絞り込み、それ以外の要素は思い切って捨てる覚悟が必要です。
② 現実と乖離したポジショニングの罠:「宣言」と「実態」が伴わない
マーケティング部門が「我々は業界最高品質です」と宣言しても、実際の製品やサポート体制がそれに伴っていなければ、顧客の信頼を失うだけです。
- 回避策: 組織全体でポジショニングを共有し、体現すること。 策定したポジショニングは、製品開発、営業、カスタマーサポートなど、すべての顧客接点で一貫して表現されなければなりません。全社を巻き込んだプロジェクトとして推進することが不可欠です。
③ 硬直化したポジショニングの罠:市場の変化に気づかず「過去の成功」に固執する
一度成功したポジショニングも、市場環境や顧客ニーズの変化によって陳腐化します。かつての巨人コダックがデジタル化の波に乗り遅れたように、過去の成功体験が足かせになるケースは少なくありません。
- 回避策: 定期的にポジショニングを見直す仕組みを構築すること。 最低でも年に一度は、市場調査や顧客インタビューを通じて、自社のポジションが今も有効かを確認しましょう。ポジショニングは彫刻ではなく、生き物のように変化し続けるものと捉えるべきです。
第6章 実践ロードマップ - 5ステップで構築する自社のポジショニング
では、具体的にどのようにポジショニング戦略を構築すればよいのでしょうか。ここでは、明日から着手できる5つのステップからなる実践的なロードマップを紹介します。
ステップ1:戦場の定義(市場・顧客の理解)
まず、自社が誰のために、どの市場で戦うのかを明確にします。ここでは3C分析(Customer:顧客, Competitor:競合, Company:自社)が有効です。顧客インタビューやアンケートを通じて、顧客が本当に求めている価値(インサイト)を深く掘り下げます。
ステップ2:競合の配置図作成(ポジショニングマップ)
次に、競合他社が顧客からどのように認識されているかを可視化します。縦軸と横軸に「価格(高/低)」「品質(高/低)」「ターゲット層(プロ/一般)」などの重要な購買決定要因を置き、競合をマッピングします。これにより、競合がひしめく「激戦区」と、まだ誰もいない「空白地帯」が一目瞭然となります。
ステップ3:自社のユニークな強みの発見(USPの定義)
ステップ1と2の結果を踏まえ、自社だけが提供できる独自の価値提案(USP: Unique Selling Proposition)を定義します。「(ターゲット顧客)向けの、(競合製品)とは違う、〇〇という価値を提供する」という形で言語化してみましょう。
ステップ4:ポジションの宣言(ポジショニング・ステートメントの策定)ステップ4:ポジションの宣言(ポジショニング・ステートメントの策定)
定義したUSPを、社内外に示す簡潔な宣言文にまとめます。これがポジショニング・ステートメントです。このステートメントが、今後のあらゆるマーケティング活動の判断基準となります。 例:「(ブランド名)は、(ターゲット顧客)にとって、(競合)とは異なり、(独自の価値)を提供する唯一の(製品カテゴリー)である。」
ステップ5:戦略の実行と浸透(マーケティングミックスへの展開)
最後に、策定したポジショニングを具体的なアクションに落とし込みます。製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4Pすべてにおいて、ポジショニング・ステートメントとの一貫性を持たせます。例えば、高品質ポジションなら価格は高く設定し、プロモーションも高級感のある媒体を選ぶ、といった具合です。
この5つのステップを組織的に実行し、PDCAサイクルを回し続けることで、ポジショニングは徐々に、しかし確実に顧客の心に浸透していきます。
第7章 まとめと行動プラン:あなたの次の一手は?
情報が溢れ、顧客が主導権を握る現代において、ポジショニング戦略はもはや単なるマーケティング手法の一つではありません。それは、企業が市場で「選ばれる理由」そのものを創造する、経営の中核をなす活動です。
本記事で解説したように、優れたポジショニングは、
- 価格競争からの脱却
- 高い利益率とブランド価値の確立
- 顧客ロイヤルティの向上 といった、持続的な成長に不可欠な果実をもたらします。
✅ 今日からできる!ポジショニング戦略の3ステップ
この記事を読み終えた今、まずは次の3つのアクションから始めてみてください。
① 顧客が「競合に感じる不満」を3つ書き出す
自社の顧客は、競合製品や既存の解決策のどこに不満や不便を感じているでしょうか? 営業担当者やカスタマーサポートへのヒアリングが有効です。ここに、あなたの会社が狙うべきチャンスが眠っています。
② 自社の「これだけは絶対に負けない」という点を言語化する
技術、ノウハウ、サポート体制、企業文化など、客観的に見て競合他社に勝る点は何でしょうか? 感覚ではなく、事実ベースで書き出してみましょう。それがあなたのポジショニングの核となります。
③ 30秒で自社を説明する「エレベーターピッチ」を作成する
「私たちは、〇〇(ターゲット顧客)に対して、△△(競合)とは違う□□(独自の価値)を提供しています。」この文章を、誰にでも伝わるように30秒で話せるように練習してみてください。これができれば、あなたの頭の中ではポジショニングの輪郭が見え始めている証拠です。
確立したポジショニングを顧客に伝え、ファンになってもらうためには、継続的なコミュニケーションが不可欠です。特にBtoBビジネスや高関与商材においては、顧客同士が価値を共有し、成功体験を語り合う「コミュニティ」が、そのポジショニングを盤石なものへと昇華させます。顧客の声こそが、最も強力なブランドの証明となるからです。
Commune(コミューン)は、そうした顧客との強い絆を育むためのコミュニティサクセスプラットフォームです。ノーコードでコミュニティサイトを構築し、顧客エンゲージメントを高める多様な機能を提供。顧客の成功を支援することで、LTV向上や解約率低減に貢献します。
自社のポジショニングをさらに強固なものにしたいとお考えの方は、ぜひ以下のフォームから詳しい資料をダウンロードしてください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
