コラム
マーケティング
MRR(月次経常収益)とは何か?定義・計算方法から伸ばし方まで
2025/06/26
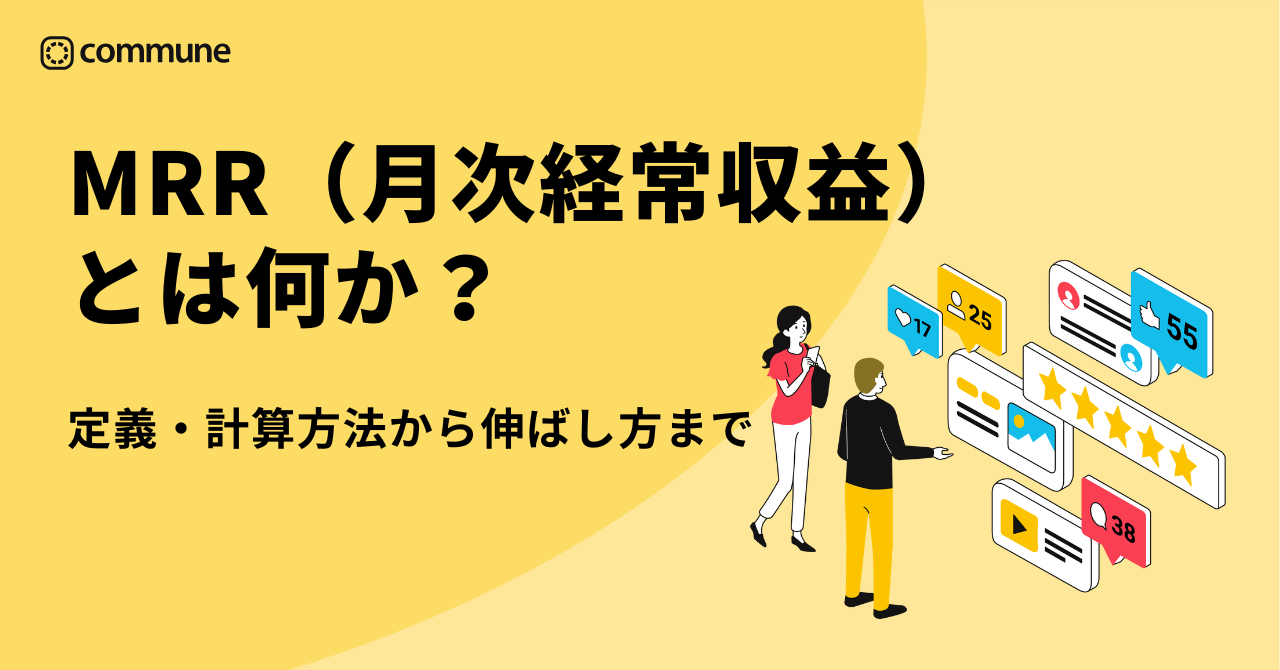
サブスクリプション型ビジネスの拡大により、MRR(月次経常収益/Monthly Recurring Revenue)は、もはや経営者だけでなくマーケターにとっても不可欠なKPIとなりました。
本記事ではMRRの定義・重要性・関連指標から計算方法・要因分析・改善施策までを一気通貫で理解できるように構成しています。マーケティング施策がどのようにMRRに貢献するのか、また投資家や経営陣がMRRをどのように評価しているのか──その全体像を、具体的かつ実践的に解説します。
これからSaaSやサブスク型モデルに取り組む方、既存事業をグロースさせたい方は、ぜひ本記事を“収益の羅針盤”としてご活用ください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
第1章 MRRとは何か?──毎月の“安定収入”を測る体温計
MRR(Monthly Recurring Revenue)は、月額課金などで毎月繰り返し発生する売上を金額で表す指標です。SaaSやサブスクリプション型ビジネスでは、この数値が事業の“体温”とも言えるほど重要です。増えれば成長、減れば危機と、健康状態を映し出します。
その変動に応じて、営業やプロダクトのリソース配分が見直されるため、MRRは単なる売上の記録ではなく戦略判断の軸として経営と直結する存在です。なお、初期費用や単発の売上は含めず、月額換算で安定して入る金額だけを集計するのが基本ルールです。
なぜMRRを把握するのか?
まず、MRRを見れば「今月・来月の売上」がかなりの精度で予測できます。これはキャッシュフローの安定管理に直結し、特に資金繰りに敏感なスタートアップにとっては命綱のような役割を果たします。
また、MRRを年間ベースに換算すればARR(年間経常収益)が見え、これが投資判断や事業計画の土台になります。数字の裏にある持続性や拡張性が可視化されるため、投資家も事業価値を測る上で注視するポイントです。
マーケティング視点でのMRRの価値
MRRは経営陣だけが見る数字ではありません。マーケターにとっても、自らの成果を“経営に効く形”で証明できる重要な指標です。
たとえば新規顧客による売上(New MRR)、既存顧客の追加購入(Expansion MRR)、解約による減収(Churn MRR)などは、すべてマーケティング活動の延長線上にあります。広告やキャンペーンの効果をコンバージョン数で終わらせず、「どれだけMRRを押し上げたか」という視点で語れると、施策のインパクトがより説得力を持ちます。
MRRに含めるもの・含めないもの
含めるのは、月額課金や年払いなどを月換算した「毎月繰り返し発生する収益」のみ。逆に、初期費用・単発案件・返金分などは除外します。無料トライアル中の顧客もカウントしません。
計算は、「各プランの月額 × 契約数」を合計するシンプルな方式。ただし、割引がある場合は適用後の金額で計算し、支払い遅延があっても契約が続いていればカウントします。
MRRを正しく理解し、改善の指針にできるかどうかは、マーケターが単なる施策担当に留まるか、“売上創出部門”として信頼されるかの分かれ道です。数字の先にある経営との接点を意識することで、あなたのマーケティングが一段上の説得力を持ち始めます。
関連記事:
➤ 「LTVとは?重要視される背景や計算方法、向上のための施策例を解説」
→ LTVとMRRとの関係を理解するのにおすすめします。
第2章 なぜMRRが“最重要KPI”になったのか
かつて、サブスクリプションビジネスで最も重視されたのは「登録者数」や「契約ID数」のような規模を示す指標でした。
しかし今では、SaaSやD2Cのような継続課金ビジネスでは、MRR(月次経常収益)が、事業が市場に受け入れられているか(PMF)を判断する最も重要な指標となっています。これは単なる流行ではなく、MRRが持つ3つの本質的な特徴に基づいています。
再現性のある売上を把握できる
MRRは、広告やキャンペーンによる一時的な売上ではなく、契約が続くことで積み上がる「持続的な収益」を可視化します。これにより、将来の売上の安定性や予測性がわかり、経営者が中長期戦略を立てる上で信頼できる数字となります。
投資家の評価指標として世界的に標準
SaaS専門ファンドやVCなどが企業を評価する際、MRRの成長率と解約率は、投資の収益性(IRR)を測る上で重要な要素となります。
ARRやLTV/CACも大切ですが、投資家は「毎月どれだけ確実に稼げていて、それがどれくらいの速さで伸びているか」を重視します。実際の交渉では、「MRR × 成長率 × マルチプル」という計算式で企業価値の最低ラインが算出されることもあり、MRRは「企業価値の入り口」とも言えます。
全社的な「共通言語」となる
MRRは単なる財務指標にとどまらず、マーケティング、営業、カスタマーサクセス、そして経営陣が、それぞれの貢献を同じ尺度で語る土台を提供します。
各部門の活動がMRRにどう影響したかが明確になることで、マーケターは「ブランド認知」や「クリック率」といった中間指標ではなく、「この施策でどれだけMRRが増えたか」を語れるようになり、マーケティング自体が経営の「収益ドライバー」として機能するようになります。
このように、MRRは単なる収益の一部ではなく、ビジネスの信頼性と将来性を映し出す鏡であり、同時に社内のコミュニケーションを円滑にする共通のツールでもあります。この構造的な強さこそが、MRRが「最重要KPI」である最大の理由です。
関連記事:
➤ 「リレーションシップマーケティングとは?メリットと活用事例を徹底解説」
→ 解約率やNRR、LTV/CACなどMRR指標との関連性も含め解説。
第3章 ARR・NRR・LTV──MRRを中心に据えた指標体系
ARR(年間経常収益)
MRR(月次経常収益)は、サブスクリプション型ビジネスの健全性を測るための基礎的かつ最重要な指標のひとつです。しかし、MRRだけでは長期的な事業の見通しを語るには不十分です。
そこで登場するのがARR(年間経常収益)です。ARRは通常、MRRに12を掛けて算出しますが、年契約の一括前払いや割引を含む場合には、まず月額ベースに換算してから12倍することが求められます。これにより、売上の過大評価や誤解を防ぎ、より正確なストック収益を把握できます。
MRRとARRは短期と中長期の売上動向をそれぞれ表しており、いずれもマーケティング戦略に不可欠な視座を提供します。MRRは、新しい施策や広告キャンペーンの即時的な影響を測るのに適しており、施策の立ち上がりの勢いを可視化します。一方、ARRは予算策定や広告投資、営業人員計画の裏付けとなり、投資家との対話やIR資料においてはサマリー指標として重宝されます。
NRR(Net Revenue Retention)
次に注目すべきは、NRR(Net Revenue Retention)です。これは既存顧客からの収益に絞ってその純増減を示す指標であり、アップセルやクロスセルによる拡張分を、解約やダウングレードによる減少分と相殺した上で計算されます。
NRRが110%を超えていれば、既存顧客群の中だけで売上が自己拡張している、いわゆる「ランド&エクスパンド」が機能していると判断されます。これは、広告費が高騰して新規顧客の獲得コストが増大している状況においても、既存基盤の中から収益を回収できる強さを意味します。
LTVとCAC
さらに、LTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得単価)という2つの指標の関係も無視できません。LTVは顧客の生涯価値を、CACは顧客を獲得するためのコストを示します。この比率が適切であれば、マーケティング投資は回収可能なものとみなされます。
逆に獲得コストが膨らんでも、NRRが高く保たれていれば、そのコストを既存顧客のアップセルで回収できるという説明が成り立ちます。こうした関係性があるからこそ、マーケティング部門は単発の成果ではなく、指標間の構造的つながりをもって施策の妥当性を語るべきなのです。
一方で、NRRが100%を切っている局面では、施策の優先順位も変わります。このような状態でブランド認知やイメージ広告にリソースを投じるよりも、まずはチャーンの原因を解明し、オンボーディング体験やカスタマーサクセスの改善に注力すべきだという判断が導かれます。つまり、指標同士の因果関係を理解することで、マーケティングの方向性はより精緻に制御されていくのです。
MRR、ARR、NRR、そしてLTVとCAC。この4つの指標は、順番に並ぶ階層構造ではなく、互いに影響を及ぼし合う立体的なネットワークとして捉えるべきです。その中心にあるのがMRRです。ここを基点として、各指標の動きを連動させながら施策と成果を結びつけていくことで、マーケティングは単なる集客部門ではなく、経営に資する戦略機能としての存在感を強めていくことができるのです。
第4章 MRRの計算方法──“迷いどころ”を潰す実務ルール
MRRの計算式はシンプルですが、実際のビジネスでは様々な契約形態があるため、計上方法に迷うことがあります。ここでは、代表的な契約タイプごとにMRRへの反映方法を解説します。
まず、年払い契約の場合。例えば12万円(税抜)の一括払い契約があれば、これを12で割り、毎月1万円をMRRに加えます。これは、実際にお金が入ったタイミングではなく、サービスが提供される期間に基づいて売上を計上する「発生主義」の考え方です。キャッシュフローの管理とは分けて考える必要があります。
次に、従量課金を含むハイブリッド型契約では、毎月の基本料金に加えて、従量分の金額が確定次第MRRに上乗せします。従量分が翌月にならないと確定しない場合は、会計処理の都合上、当月に見込み額を計上することもありますが、その際は翌月以降に実際の金額との差額を調整し、常に正確な累計額を保つ必要があります。
割引やクーポンが適用される場合は、顧客が実際に請求された金額に基づいてMRRを計算するのが基本です。割引前の定価で計算すると、MRRが実態よりも大きく見えてしまい、社内外で誤解を招く可能性があります。
無料トライアル中のユーザーは、原則としてMRRには含めません。ただし、トライアルから本契約への転換率は「New MRRの先行指標」として重要なので、別途KPIとして管理することをお勧めします。
これらの算出ルールを明確に定義する目的は、単に計算できることよりも「チーム内で解釈を統一し、毎月スムーズに更新できる体制を整えること」にあります。契約社数がまだ数十社から百社規模であれば、Excelと自動化テンプレートで十分対応できます。しかし、200社を超えると、BIツールとの連携やSaaSデータ基盤との統合が現実的な選択肢となります。
API連携が可能なSaaS製品を選べば、CRM、MA、会計ソフトなどとのデータ統合がスムーズになり、エンジニアでなくてもダッシュボードの構築・運用が可能になるメリットがあります。特に、月次でMRRを経営会議や施策判断に活用する体制を整える上では、「算出できること」だけでなく「共有・運用できること」がより重要になります。
関連記事
➤ 「DAU・WAU・MAUの計算方法とは?定義や使い分け・活用方法を解説」
→ データ設計や集計ルールの整備に関心を持つ方におすすめです。
第5章 4つのMRR内訳──New / Expansion / Downgrade / Churn を読み解く
MRR(月次経常収益)を増やすには、その内訳を詳しく見て、どの要素がどれくらい影響しているかを知る必要があります。MRRは、前の月のMRRを基準に、以下の4つの要素を足し引きして計算されます。
New MRR(新規契約による増加):
新しいお客様との契約で増える収益です。マーケターが直接的に影響を与えやすく、広告やコンテンツ施策の効果が分かりやすく現れます。獲得したリードがどれくらいの収益を生んでいるかを見ることで、マーケティング活動が会社の経営にどう貢献しているかを把握できます。
Expansion MRR(既存顧客からの増加):
既存のお客様が上位プランに移行したり、追加機能を契約したりすることで増える収益です。カスタマーサクセスや製品開発部門と協力し、お客様の利用状況に合わせた情報提供や、上位プランのメリットを伝えるコンテンツなどを通じて、この収益を伸ばすことができます。
Downgrade MRR(プラン縮小による減少):
お客様がプランをダウングレード(下のプランに変更)することで減る収益です。これは、お客様が現在のプランの機能を使いこなせなかったり、料金が高いと感じたりした場合に起こります。丁寧な導入サポートや日常的な活用支援、また、必要な機能だけを選べるようなプラン構成にすることで、プラン縮小を防ぐことができます。
Churn MRR(解約による減少)
お客様がサービスを解約することで失われる収益です。価格への不満、使い勝手の悪さ、サポート不足など、様々な原因が考えられます。解約時に理由を詳しく聞き、その情報を製品開発やカスタマーサクセス部門と共有して改善に活かすことが重要です。マーケターも、お客様からのネガティブな意見や声を常にチェックし、社内で共有する仕組みを作る必要があります。
これらの指標をバランスよく見るために、「Quick Ratio」という指標も有効です。これは、New MRRとExpansion MRRの合計を、Churn MRRとDowngrade MRRの合計で割った値で、企業の成長性を示します。この比率が4を超えていると、高い成長が見込めると判断されます。マーケティング部門は、新規顧客獲得と既存顧客からの収益増加に貢献しつつ、解約やプラン縮小を防ぐために他の部門と連携して取り組む必要があります。
第6章 MRRを伸ばすマーケティング施策──4象限別アプローチ
MRR(月次経常収益)を本質的に伸ばすには、4つの構成要素――New MRR(新規契約)、Expansion MRR(追加契約)、Downgrade MRR(プラン縮小)、Churn MRR(解約)――を正確に理解し、それぞれに合わせた、再現性のある具体的な施策を実行することが欠かせません。
New MRR:新規契約を増やすために
新規契約による収益を最大化するためには、まず「理想の顧客像(ICP)」を再定義することが出発点です。LTV(生涯顧客価値)とCAC(顧客獲得コスト)のバランスが良いターゲット層に広告費を集中させることで、費用対効果が大きく改善します。
そのうえで、ホワイトペーパー、ウェビナー、比較記事といった資料やコンテンツを活用し、リード(見込み客)を獲得。CPL(リード獲得単価)を下げながら、質の高い顧客接点を増やします。さらに「無料で始められるけど、期間終了後は自動課金」というトライアルモデルを導入することで、無料ユーザーの有料化率も高まります。
また、商談化を担うインサイドセールスでは、問い合わせからのレスポンス時間を2時間から15分以内に短縮しただけで、商談化率が15%から28%へとほぼ倍増した事例もあります。
Expansion MRR:既存顧客からの収益を伸ばす
アップセル(上位プランの提案)やクロスセル(追加オプションの購入)による収益拡大は、既存顧客の活用レベルを把握し、適切なタイミングで価値を提案することがカギとなります。
たとえば、利用状況に応じて「次に使うべき機能」や「おすすめのアドオン」を紹介するステップメールを設計すれば、顧客の自然な成長に沿って無理のないアップセルが可能になります。加えて、NPS(顧客満足度スコア)で評価の高い顧客に紹介キャンペーンを案内すれば、新たな契約を獲得しながら、平均売上単価(ARPA)も引き上げられます。
料金を改定する際は、単なる値上げではなく「機能追加やサポート改善による価値向上」として説明し、90日前には通知することで、価格への抵抗も最小限に抑えることができます。
Downgrade MRR:プラン縮小を防ぐ
顧客が上位プランをやめて安価なプランに切り替える背景には、「あまり使っていない」「使いこなせていない」といった不満があることが多いです。これを防ぐには、利用頻度が落ちたアカウントをいち早く察知し、冷めきる前にカスタマーサクセスが対応する仕組みが必要です。
たとえば、AIを使って利用低下の兆候を検出し、30日以内にCSチームがフォローできる体制を整えるのが理想です。さらに、機能の使いづらさや迷いやすい箇所をダッシュボードで可視化し、プロダクトチームと連携してすぐに改善できるようにすることで、離脱リスクを未然に減らせます。
顧客の規模や重要度に応じて、手厚い支援(ハイタッチ)と効率重視の支援(ロータッチ)を使い分けることも、コミュニケーションのすれ違いによるプラン縮小を防ぐポイントです。
Churn MRR:解約を防ぐために
解約による収益の喪失は、もっとも避けたい損失です。これに対しては、事前の対策と継続的なケアが求められます。
たとえば、解約直前に簡単なアンケートを行い、その結果を受けて24時間以内にCS担当者が電話フォローする。さらに3カ月後に再び連絡を入れる「三段階対応」を徹底することで、離脱率が下がります。
よくある解約理由である「機能不足」については、競合との比較で劣っている点を隠さず示し、ロードマップ上に「改善予定」として明記することで、顧客が離れそうになるのを引き止める効果も期待できます。
また、すでに解約した顧客に対しても、90日間は継続的にメールでユースケースや改善情報を発信することで、「もう一度使いたい」と思わせる“復活チャーン”の機会を作ることができます。
このように、MRRを構成する4つの要素それぞれに対して、具体的なアプローチと改善策を持ち、それらを数値で管理・最適化する体制を整えることが、継続的な売上の積み上げを支える基盤となります。短期的な施策と、長期的な戦略がうまく接続されることで、MRRは単なる“数字”ではなく、事業の健全性を示すコンパスとして機能するようになるのです。
第7章 実務運用とまとめ──MRRを“チームKPI”に昇華させる
MRRは本来、財務の数字として捉えられることが多いですが、実際には全社で取り組むべき横断的な指標です。マーケティング、営業、カスタマーサクセス、プロダクト開発といったすべての部門が、何らかの形でMRRの増減に関わっています。だからこそ、MRRは“全社KPI”として組織に根づかせることが大切なのです。
そのためには、MRRの動きをリアルタイムで把握し、迅速にアクションを取れる仕組みを整える必要があります。たとえば、Slackでの週次レポートや、月次レビューで詳細な分析をチーム全体で共有するなど、MRRを日常の“共通言語”として使う文化が欠かせません。KPIは眺めるだけの数字ではなく、組織を動かす会話の起点として機能することで初めて力を発揮します。
とりわけマーケティング部門には、MRRの文脈で担うべき明確な役割があります。
まず1つ目は、施策の効果を数値で示す役割です。広告やキャンペーンが実際にどれだけNew MRRを生んだのか、ROI(投資対効果)を定量的に説明できれば、マーケ施策の正当性が経営レベルで認められるようになります。
2つ目は、顧客の声を翻訳して伝える役割です。VOC(顧客の声)やNPS、さらには競合比較などの情報を整理し、プロダクト開発やCSと共有することで、解約やダウングレードを防ぐための改善につなげます。
3つ目は、KPI間の関係性をつなぐファシリテーターの役割です。ARR(年間経常収益)やNRR(売上継続率)、LTV/CAC(顧客価値と獲得コストの比率)といった周辺指標とMRRを関連づけて、「なぜ今MRRを見るべきか」を経営の視点で整理・説明できる存在になることが求められます。
運用面では、最初はスプレッドシートなどで十分ですが、契約社数が100を超える頃にはCRMや会計、MA(マーケティングオートメーション)などのデータを一元化し、BIダッシュボードで可視化する仕組みに移行すべきです。Looker、Tableau、Power BIなどを使い、APIで自動連携すれば、煩雑な手作業から解放され、より重要な分析と判断に時間を使えるようになります。さらに、定義や集計のルールを統一することで、組織全体の“数字の質”も格段に上がります。
最後に:この記事で伝えたい4つのポイント
- MRRは「毎月繰り返し得られる売上」だけを対象とし、初期費用などは含まれない
- 重要な理由は、将来の売上予測ができること、投資家からの評価指標になること、社内の共通言語になること
- MRRを中心にしつつ、ARR・NRR・LTV/CACと組み合わせてKPIの全体像を構築すること
- MRRの構成要素(New/Expansion/Downgrade/Churn)を追い、Quick Ratio(増加と減少の比率)が4以上を目指すこと
マーケターにとって、MRRは単なる数字ではありません。自分の施策がどれだけ収益を押し上げたかを語れる「MRR純増ストーリー」を描くことが求められます。MRRは、経営を動かす言語であり、事業の未来を先読みするための羅針盤です。
ぜひ今日から自社のダッシュボードを開いて、New・Expansion・Downgrade・Churnの各項目をチェックしてみてください。そこにあるわずかな変化が、数カ月後のARRや企業価値に大きな影響を与えるかもしれません。未来の成長は、今の数字の中にすでに芽吹いているのです。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
