コラム
社内コミュニティ
双方向コミュニケーションとは?メリットや促進するためのコツをわかりやすく解説
2024/03/27
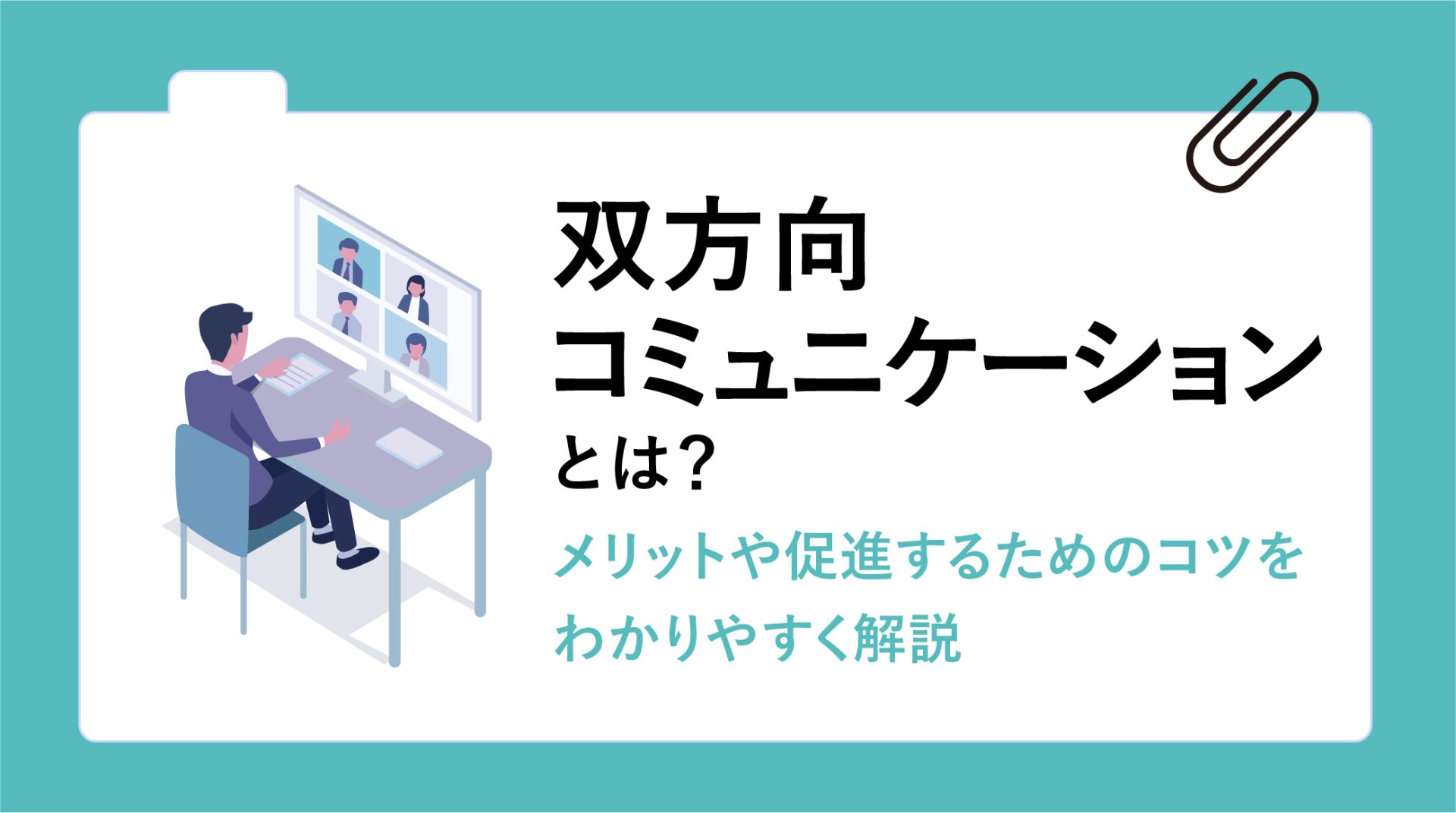
双方向コミュニケーション(Two-way Communication)は、発信者と受信者のあいだで情報が行き来し、互いの理解を深めながら意思決定や行動につなげる対話スタイルを指します。一方的に伝達して終わる“送りっぱなし型”と異なり、相手からの質問・意見・感情のフィードバックを常に受け取り、それを次の発信に反映させる循環構造が特徴です。
この記事では、双方向コミュニケーションの考え方やメリット、実践のコツを解説します。「社内での意思疎通をスムーズにしたい」「会議で現場の担当者にもっと率直な意見を出してほしい」などの悩みを抱える方は、普段のコミュニケーションに積極的に取り入れていくと良いでしょう。
「伝えたつもり」が積み重なってませんか?
「伝えたつもり」が積み重なってませんか?
- 会議後に「で、結局どうするんだっけ?」が発生する
- 上からの発信だけ多くて、現場の本音が見えない
- チャットやメールが散らかり、情報を追いきれない
- アンケートを取っても、率直なコメントが集まらない
双方向コミュニケーションを根づかせるには、
「声が集まり、見え、ちゃんと次のアクションにつながる場」 が必要です。
Commune For Work は、社内コミュニティを軸に情報発信・フィードバック・ナレッジ共有を一つに集約し、“伝わらない会議だらけの職場”からの卒業を後押しします。
双方向コミュニケーションを根づかせるには、
「声が集まり、見え、ちゃんと次のアクションにつながる場」 が必要です。
Commune For Work は、社内コミュニティを軸に情報発信・フィードバック・ナレッジ共有を一つに集約し、“伝わらない会議だらけの職場”からの卒業を後押しします。
目次
双方向コミュニケーションとは
双方向コミュニケーションとは、必要な情報を伝達し合うコミュニケーション手法です。ビジネスやマーケティングの文脈においては、様々なチャネルを使って顧客の感情を確認する施策を指す場合もあります。双方向コミュニケーションは、相互理解を深めるために行うコミュニケーションであり、一方通行の指示や伝達とは異なります。
相手の意見や思考、感情などを吸い上げながらコミュニケーションを行うため、細部のニュアンスまで共有し合えるのがポイントです。一方的ではなく、相手の声にも耳を傾けるコミュニケーションが双方向コミュニケーションだと言えます。
双方向コミュニケーションとインタラクティブ(対話型)の違い
双方向コミュニケーションと似た言葉に「インタラクティブ」があります。インタラクティブとは、「相互に作用する」などの意味を持つ用語です。英語では “interactive” と表記され、特にIT業界でよく使われています。
インタラクティブは、ビジネスやマーケティングの現場でも定着している用語です。「相互の」「双方向の」という意味合いで、双方向性のやり取りがある状態を指すのが一般的です。自由に発言できるミーティングや顧客とのコミュニケーションはインタラクティブだと言えます。
インタラクティブは相互のやり取りがある状態、双方向コミュニケーションは相互に伝達し合うコミュニケーション手法として押さえておきましょう。
ビジネスで双方向コミュニケーションを心がけるメリット

ビジネスシーンで双方向コミュニケーションを実践するメリットには、次のようなものがあります。
・ミスコミュニケーションの防止
・組織エンゲージメントの向上
・信頼関係の構築
一つずつ見ていきましょう。
ミスコミュニケーションの防止
双方向コミュニケーションでアクションとリアクションが繰り返されることで、必要な情報を円滑にシェアしやすくなります。一方的なコミュニケーションだと、話者の意図通りに相手に伝わっているとは限りません。
理想的な双方向コミュニケーションにより相互の認識齟齬が減るため、ミスコミュニケーションの防止・減少につながります。「すり合わせ不足のまま業務を進めてしまい、二度手間が生じた」「意図していた内容と異なる納品物が上がってきた」などのトラブルが減り、仕事の生産性を上げられるメリットがあります。
組織エンゲージメントの向上
双方向コミュニケーションは、組織にポジティブな変化をもたらします。双方向コミュニケーションによって、適切なフィードバックが得られたり率直な意見交換ができたりすると、従業員のモチベーションが上がります。
また、双方向コミュニケーションが浸透した風通しの良い環境下では、情報交換が活発に行われるようになり、結果として組織エンゲージメントの向上につながります。コミュニケーションを取りやすい風土は、組織への思い入れや前向きな気持ちを育みやすいものです。
組織エンゲージメントの向上によって、一体感のある空気が生まれるだけでなく、人材流出のリスクを下げられるのもポイントです。
信頼関係の構築
双方向コミュニケーションの成立によって、職場の居心地が良くなるのもメリットです。フランクなやり取りや業務の域を超えた会話からアイデアが生まれることもあるでしょう。また、双方向コミュニケーションによって業務連携がうまくいくと、効率の良い働き方が叶います。
一方的なコミュニケーションではなく、コミュニケーションのやり取りを重ねることで、信頼関係が構築されます。ポジティブな人間関係は、様々な相乗効果を生み出し、プラスの影響をもたらします。
双方向コミュニケーションを高めるための強力な手段が、コミュニティ活用です。
双方向コミュニケーションを高める方法【伝え方】
ここからは、双方向コミュニケーションの質を高める方法を紹介します。まずは伝え方編です。自分の意図や意思をきちんと相手に届けるコツを解説します。
相手の立場を理解する
意見を伝える前に、相手の立場や状況を想像することは欠かせません。話し手と聞き手の前提が食い違っていると、どれほど論理的な説明でも噛み合わなくなるからです。
まずは相手が「どれだけの情報を持っているか」「どんな成果をゴールに置いているか」を把握し、その前提を共有したうえで自分の主張を組み立てましょう。このひと手間が、対話をスムーズにし、誤解やすれ違いを未然に防ぎます。
結論から話す
要点を確実に届けるには、最初に結論を示すのが鉄則です。そこで役立つのが「PREP法」という枠組みです。
Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(再結論)の順に話を展開することで、聞き手は冒頭で全体像をつかみ、続く理由と具体例で理解を深め、最後に再度結論を確認できます。
結論から入ることで相手の認知負荷が下がり、コミュニケーションの所要時間も短縮。相手の時間を無駄にせず、ストレスのない対話を実現できます。
伝えたい内容をコンパクトにする
情報を伝える前に要点を絞り込み、メッセージをコンパクトに設計しましょう。理想は、一度のコミュニケーションにつきテーマを一つに限定することです。複数のトピックを詰め込むと受け手の認知負荷が高まり、理解が散漫になりがちです。話し手と聞き手の思考をクリアに保つためにも、優先順位をつけて「何を伝えないか」を決めておくことが肝要です。
さらに、曖昧な表現はミスコミュニケーションの温床です。解釈に幅が出る抽象語やあいまいな比喩は避け、具体的な数値や事例、根拠を示しながら筋道立てて説明しましょう。そうすることで、相手の理解を深めるだけでなく、議論のズレや誤解も未然に防げます。
■関連リンク:
ミスコミュニケーションとは?原因・影響・防ぎ方を徹底解説
双方向コミュニケーションを高める方法【聞き方】
次に、聞き方のコツを紹介します。聞き方を意識するだけでも双方向コミュニケーションの質は高まります。相手とのスムーズなやり取りを実現するために、以下のポイントを意識してみましょう。
聞く姿勢を意識する
基本的なことと思われがちですが、話を真剣に聞くことは重要なコツと言えます。話し手が「話をきちんと聞いてもらえている」と感じる場を作ることで、より深いコミュニケーションが可能になります。
聞いている姿勢を見せるためには、目線を合わせることが有効です。他にも、相槌を打ったりメモを取ったりするのも良いでしょう。聞いている姿勢を見せるためにできるアクションは様々なので、大袈裟にならない程度に、相手に合わせて実行するのがおすすめです。
話の内容によっては、場所を変えて聞いたほうが良いケースも存在します。相手への配慮を持って柔軟に対応するのがポイントです。
最後まで話を聞く
話し手の話には、最後までしっかりと耳を傾けることが大切です。共感や反論など、途中で言いたいことが出てくる場合があるかもしれませんが、まずは最後まで聞く側に徹しましょう。話を遮ったり、相手のタイミングを奪ってしまったりすると、話し手の伝える機会を損失させてしまいます。
理想通りの双方向コミュニケーションを実現するためにも、相手のペースを乱さない配慮が必要です。
質問は最後にまとめて行う
質問や疑問は、話を聞いてしまった後にまとめて投げかけるのがおすすめです。質問事項が多い場合は、メモにまとめておくと質問時に役立ちます。
「最後まで話を聞く」のと通じますが、相手のタイミングを遮らないことが重要です。「今自分は伝える側と聞く側のどっちのターンなのか?」を意識してコミュニケーションを行うことで、両者にとって気持ちの良いやり取りが実現します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 双方向コミュニケーションと「インタラクティブ」の違いは何ですか?
双方向コミュニケーションは“相手の反応を受け取り、それを次の発信に反映させる”という循環型のコミュニケーション手法を指します。一方、インタラクティブは「相互作用がある状態」を指す概念であり、必ずしも対話の改善サイクルまで含むわけではありません。つまり、インタラクティブは状態、双方向コミュニケーションはプロセス(手法)だと覚えておくと整理しやすいでしょう。
Q2. 双方向コミュニケーションを導入すると、具体的にどのようなメリットがありますか?
主なメリットは「ミスコミュニケーションの防止」「組織エンゲージメントの向上」「信頼関係の構築」の三つです。発信とフィードバックを往復させることで認識齟齬が減り、従業員の意見が反映されやすくなるため、モチベーションと一体感が高まります。結果として業務効率の改善や離職率の低減も期待できます。
Q3. 社内に浸透させるための最初の一手は何でしょうか?
「結論ファーストで伝え、最後まで聞く」という基本動作を徹底することが第一歩です。具体的には、会議の冒頭で目的とゴールを明示し、発言ルール(例:被せず最後まで聞く、質問は最後にまとめる)を設定すると、双方向のやり取りがスムーズになります。小さな成功体験を積み重ねると浸透が早まります。
Q4. 遠隔・リモートワーク環境でも効果的に実践できますか?
はい、オンラインこそ双方向コミュニケーションの重要性が高まります。Web会議ツールのチャット・挙手機能や、スレッド型チャット(Slack など)を活用し、発言しやすい設計にするのがポイントです。リアクションアイコン・ポーリング機能で即時フィードバックを可視化すると、対面時と遜色ないインタラクティブな環境を構築できます。
Q5. 効果測定はどう行えばよいですか?
定量面では「発言数/参加率」「質問・回答までの平均時間」「アンケートによる認識齟齬の件数」などをトラッキングします。定性面では1on1やパルスサーベイで「心理的安全性」「エンゲージメント」のスコアを確認し、数値変化と業務成果の相関を分析すると改善点が見えやすくなります。
Q6. 部門間で温度差がある場合、どうやって巻き込みを図ればいいですか?
“自部署に関係する具体的な課題”をテーマにした小規模ワークショップから始めると効果的です。早期に成果(例:リードタイム短縮、顧客満足度向上)が出た事例を社内報や全社ミーティングで共有し、メリットを可視化することで徐々に他部門を巻き込みやすくなります。
Q7. ツール選定のポイントは何ですか?
必須条件は「リアルタイム性」「記録性」「アクセスのしやすさ」です。具体的には (1) Web会議ツール+チャットツールの組み合わせ、(2) スレッドで議論が追えるUI、(3) モバイルでも快適に使えること、が鍵になります。さらにコミュニティ機能を持つプラットフォーム(例:Commune)は部門横断の情報共有とロイヤリティ向上に寄与するため、双方向コミュニケーションの基盤づくりに適しています。
双方向コミュニケーションを高めるための強力な手段が、コミュニティ活用です。
双方向コミュニケーションの活性化にはツールの利用がおすすめ
ビジネスにおける双方向コミュニケーションを活性化させるには、ツールの活用が有効です。Web会議ツールとしては、「Google meet」や「Zoom」が有名です。チャットツールである「Chatwork」や「Slack」は、テキストコミュニケーションの枠組みを超えた機能が充実しています。
上で挙げたものの他にも、社内外でのコミュニケーションを活性化させるためのツールは多数存在します。
✨双方向コミュニケーションなら Commune for Work
Commune for Work は、双方向コミュニケーションを起点に“組織が変わり続ける仕組み” をつくる社内コミュニケーションプラットフォームです。
一方通行の社内発信では届かなかった、従業員の声(VoE)・部署横断のつながり・日々のリアクション を引き出し、エンゲージメント向上やカルチャー浸透を後押しします。
社内SNS、社内報、社内アプリ、社内ポータルなど、組織課題に応じた使い方を All-in-One で実現できるのが特徴です。
投稿・コメント・リアクション、アンケート、社内報、リンク集、Eラーニング、ゲーミフィケーション、クエスト機能 などをすべてノーコードで構築でき、日常的に声が集まり、循環する状態をつくれます。
組織内でよくある課題──「現場の声が見えない」「トップメッセージが浸透しない」「情報が散乱している」といった状態から、“声が見える・つながる・行動が変わる組織” への転換を支援します。
「伝えたつもり」が積み重なってませんか?
「伝えたつもり」が積み重なってませんか?
- 会議後に「で、結局どうするんだっけ?」が発生する
- 上からの発信だけ多くて、現場の本音が見えない
- チャットやメールが散らかり、情報を追いきれない
- アンケートを取っても、率直なコメントが集まらない
双方向コミュニケーションを根づかせるには、
「声が集まり、見え、ちゃんと次のアクションにつながる場」 が必要です。
Commune For Work は、社内コミュニティを軸に情報発信・フィードバック・ナレッジ共有を一つに集約し、“伝わらない会議だらけの職場”からの卒業を後押しします。
双方向コミュニケーションを根づかせるには、
「声が集まり、見え、ちゃんと次のアクションにつながる場」 が必要です。
Commune For Work は、社内コミュニティを軸に情報発信・フィードバック・ナレッジ共有を一つに集約し、“伝わらない会議だらけの職場”からの卒業を後押しします。
