コラム
マーケティング
ヒートマップとは何か?仕組みやメリット、活用方法を解説
2024/07/10

「ヒートマップとは何なのか。」
「ヒートマップを導入するメリットは?」
「ヒートマップから読み取れることは?」」
など、初めてヒートマップの利用を検討している場合、これらの疑問が浮かぶのではないでしょうか。
ヒートマップは、ユーザーの行動や興味を可視化できる、マーケティング戦略を立てるうえで重要なツールです。CVRが低い、ユーザーの滞在時間が短いなど、Webページに課題を感じているのであれば、ヒートマップの知識を深めて、導入を検討しましょう。
今回は、ヒートマップについて解説します。ヒートマップを導入するメリットや、ヒートマップが生まれた背景についても解説しています。
この記事を読めばヒートマップの具体的な活用方法がわかりますので、ぜひ参考にしてみてください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
ヒートマップとは?

ヒートマップは、ウェブサイト上のユーザーの行動を視覚的に表現したものです。色の濃淡を使って表現することから「ヒートマップ」と名付けられました。ヒートマップツールでは、ページのスクロールやマウスの動き、ページの滞在時間などがわかります。
これらを分析することにより、ユーザーがウェブサイト上でどのエリアに興味を示しいているのか、どこで離脱しているのか、視覚的に情報を得られます。ヒートマップは、主に以下の3つのエリアからWebページを解析できます。
- 熟読エリア
- 終了エリア
- クリックエリア
それぞれについて詳しく解説します。
1. 熟読エリア
熟読エリアはユーザーによく読まれているエリアです。最もよく読まれている段落や文章は赤色で表示されます。一番読んでほしい箇所が赤い色で表示されていない場合は、ユーザーのニーズと異なる内容を掲載している可能性があります。
2. 終了エリア
終了エリアは、ページのどの部分まで読まれているか、どこで離脱したかがわかります。サイトに訪れたユーザーが、その箇所までどのくらい残っているかの割合も確認できます。
購入ボタンや誘導したいリンクよりも上部で多くの離脱が発生している場合、ボタンやリンクの位置の変更などの改善が必要となります。
3. クリックエリア
クリックエリアは、ユーザーがWebサイト上でクリックした場所を示すエリアのことを指します。購入ボタンや申し込みボタンなどが、クリックされているか確認できます。
リンク先がない画像がクリックされている場合は、ユーザーを迷わせている可能性があるので、改善が必要となります。
ヒートマップの熟読エリアから読み取れること

ヒートマップの熟読エリアでは、ユーザーのマウスの動きや滞在時間から、よく読まれているエリアを分析できます。
熟読エリアはユーザーの行動を客観的に把握できるため、必要な改善をすることで、離脱率の低下につなげられます。
ここからは、熟読エリアから読み取れることについて解説します。
読まれていない原因と対処法
熟読エリアを読まれていない原因として以下の3つが考えられます。
- コンテンツの質が低い。
- ページのレイアウトに問題がある。
- ニーズと異なる情報を掲載している。
熟読エリアが読まれていない原因として最初に考えられるのが、コンテンツの質の低さです。文章が長すぎたり、分かりにくかったりする場合はユーザーが離脱する原因となります。
レイアウトに問題がある場合も、改善が必要です。フォントサイズが小さかったり行間が狭かったりする場合は、ページレイアウトを改善して視認性を高めましょう。
ニーズと異なる情報を掲載している場合も読まれない原因となります。コンテンツの内容がニーズとマッチするようにコンテンツの入れ替えをしたり、デザインを改修したりすることで、熟読エリアの拡大に繋げていけるでしょう。
読まれている理由は?
一方、想定外によく読まれている理由としては以下の3点が考えられます。
- ユーザーのニーズに応えられている。
- 読みやすいレイアウト。
- 内容の理解に時間がかかっている。
読者の興味を惹く内容だったり、情報量が豊富であったりする場合、熟読される可能性が高まります。
また、読みやすいレイアウトに設定することも、熟読エリアの拡大につながります。文字だけのコンテンツよりも、画像や表を取り入れた方が、離脱率を軽減できるでしょう。
ただし、コンテンツの内容が難しく、読むことに時間がかかっている可能性も考えられます。想定よりも熟読エリアが広い場合には、内容がわかりにくくなっていないか、もう一度コンテンツの内容を見直すことも大切になります。
コンバージョン地点の調整も有効
ヒートマップでは、コンバージョン地点の内容やリンクが、どのくらいのユーザーに表示されたのか確認できます。
コンバージョン地点よりも上部で大幅に離脱している場合は、コンバージョン地点の調整が有効です。コンバージョン地点を上部に位置変更したり、目立つデザインに変えたりすることで、コンバージョンが増える可能性があります。
ヒートマップのクリックエリアから読み取れること

クリックエリアから読み取れることは、ユーザーが興味を持つ箇所やユーザーの行動です。このクリックエリアを分析することで、ページ全体の改善すべき箇所がわかります。
注目すべきポイントは、リンクがない場所にクリックする「空クリック」が起きている箇所です。
空クリックが起きている原因としてボタンやリンクが見つけにくいことが考えられます。ユーザーのニーズにあった適切な場所にリンクを貼るなど、周囲のコンテンツを変更することで、空クリックを減らすことに繋がります。
空クリックは、コンバージョンの機会損失につながるため、早急に対処することが大切です。
ヒートマップの活用事例
パナソニック株式会社は、日本の総合エレクトロニクスメーカーで、家電製品、空調設備、店舗・オフィス向け商品・サービスなどを提供しています。
パナソニック株式会社の個人向け家電商品関連Webサイトは、かつてインデックスページからの直帰や離脱が多いことが課題でした。
ヒートマップを導入し、クリックエリアを確認してみると、製品ページがほとんどクリックされていないことがわかりました。
加えて、熟読エリアを見るとページの下部にあるスペック表が熟読されていることが把握できました。ヒートマップを分析すると、製品の紹介ページに誘導ができておらず、スペック表などのユーザーのニーズに応える情報が適切な位置にありませんでした。
以上のことから、クリック率の高いものを上部へ移動し、スペック表はファーストビューへ移動しました。そうすることで、インデックスページの離脱率が18.4%→14.4%に改善され、インデックスページの熟読エリアが広がりを見せました。
さらに、リニューアル前後の比較画像がヒートマップで一目瞭然で伝わるので、資料制作の時間短縮につながり、スムーズな社内の情報共有に役立っています。
ヒートマップを導入したことにより、WebサイトのUI改善に非常に高い効果が現れました。加えて、社内のコミュニケーションツールとしても活用されています。
ヒートマップが生まれた背景
ヒートマップという用語は、1991年にデザイナーのCormac Kinneyにより作られ、商標登録されています。ヒートマップは元々、ゲノム/遺伝子解析や統計学の分野で利用されていた手法です。色付けし可視化することで、視覚的にデータの理解を深めるために使用されてきました。ヒートマップは、現在では様々な分野にも広がりをみせています。大量のデータを視覚的に表現し、パターンや傾向を明らかにする重要なツールとして、多くの人がヒートマップを活用しています。
近年のヒートマップの動向
近年、ヒートマップの技術は進化し続けています。ユーザーのスクロール速度やクリック間隔の分析も可能となり、Web上でのユーザーの行動がより詳細に把握できるようになりました。
加えて、AIや機械学習技術の進化により、大量のデータを高速に処理し、複雑なパターンを見つけ出せるようになっています。それにより、ユーザーの行動予測や改善策の提案が自動化され、これまでよりも効率的なサイト運営が可能となってきています。
ヒートマップは今後さらなる進化が見込まれ、VRやARなどのテクノロジーと組み合わせることで、さらに深いユーザー心理の理解が可能となる見込みです。
ヒートマップは、今後のビジネスにおいても、マーケティング戦略を立てる上で重要なツールとして位置付けられていくでしょう。
近年のヒートマップの仕組み
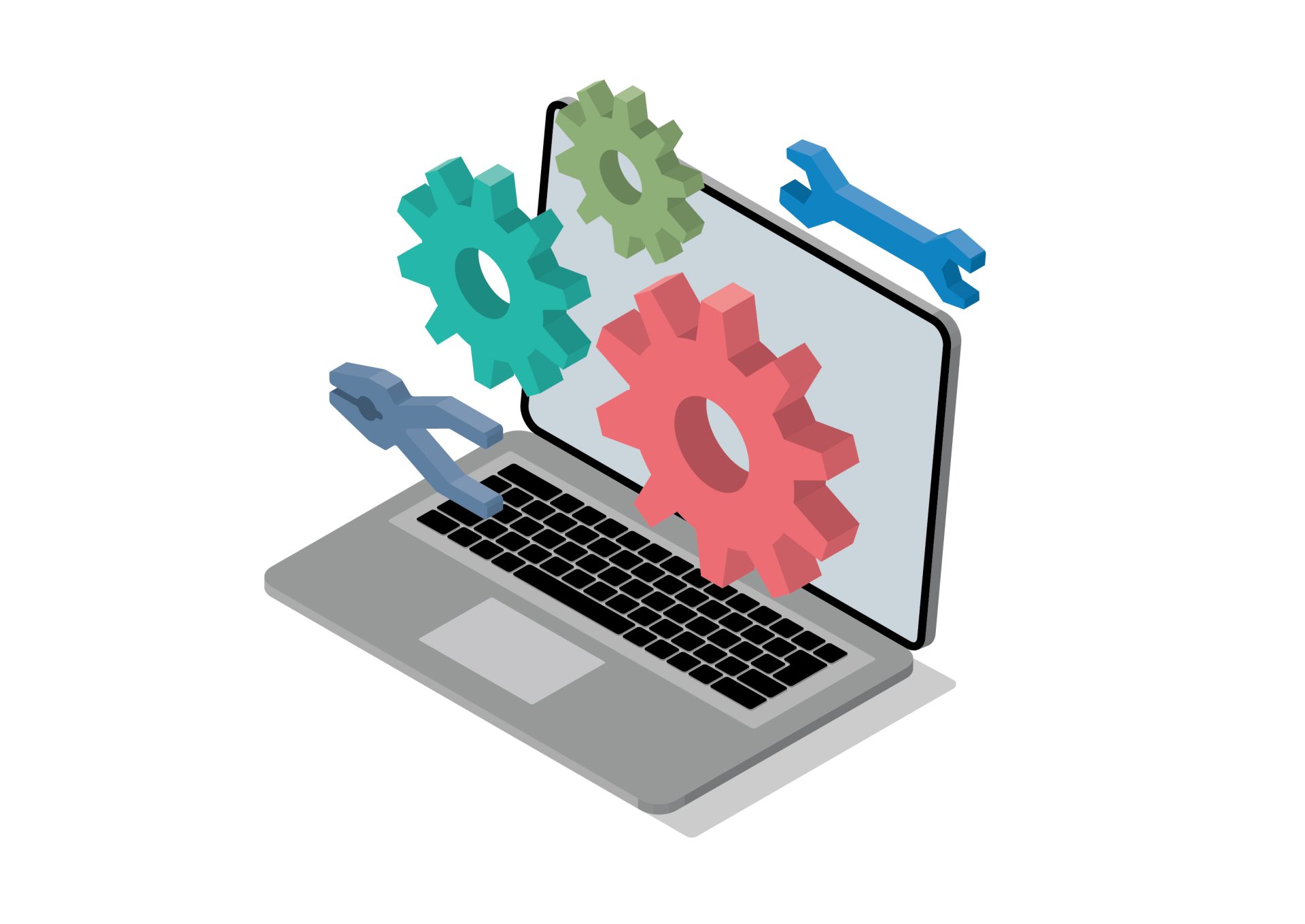
ヒートマップでクリックされた回数を計測する際、分割したエリアごとに数値化します。最もクリックされているエリアは赤く、最もクリックが少ないエリアを青色とし、グラデーションにしていきます。
また、ユーザーがWebページに滞在している時間を計測するアテンションヒートマップでは、ページを横に分割します。エリアごとにスクロールが留まった時間を計測します。長い時間留まった部分は赤い色がつけられ、短い時間しか見られていない部分は、青い色がつけられます。
このように、ヒートマップは種類によって、エリアの分割の仕方や、計測方法が異なるため、目的に合わせて種類を選択する必要があります。
ユーザー行動の分析ならCommune(コミューン)
Commune(コミューン)は、コミューン株式会社が運営する顧客コミュニティツールです。自社に最適なコミュニティをノーコードで簡単に構築・運用でき、顧客・ユーザーコミュニケーションのワンストップ化を可能にします。
分析画面では、タグの埋め込みは必要ありません。データを分析するダッシュボードの操作性も直感的に利用できます。また、顧客のデータを蓄積し、CRMやSFAなどの外部ツールに蓄積しているデータとも連携可能です。顧客のデータを集約することで精度の高い分析が可能となります。
「3分で分かるCommune」には、より詳細な情報が記載されています。気になる方はぜひ以下のフォームからダウンロードしてみてください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
