コラム
マーケティング
ファンマーケティングを仕組み化する戦略と手法
2025/07/15
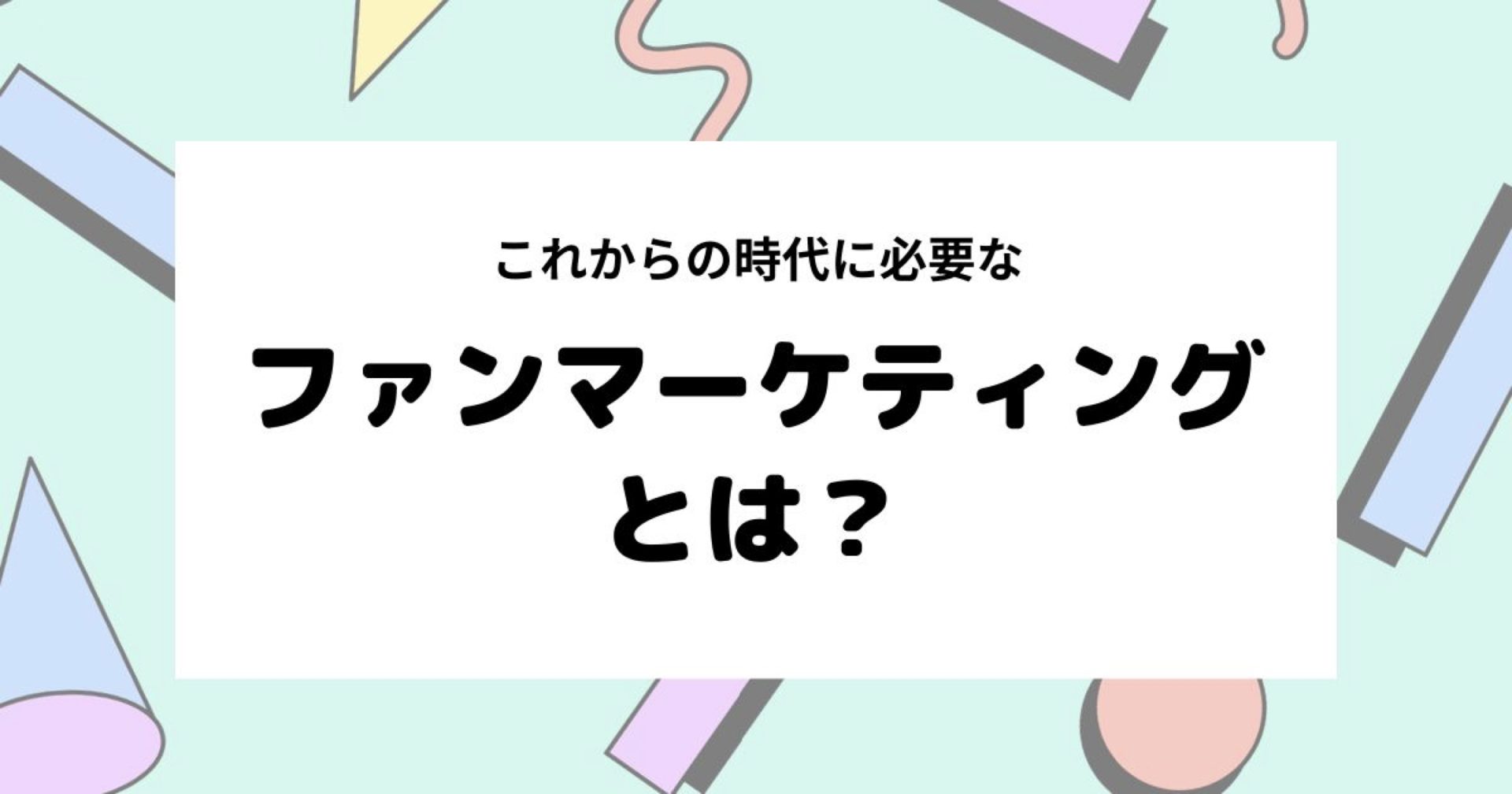
ファンマーケティングは、ブランドの世界観に共感してくれるファンとの継続的な関係構築を通じて、売上やブランド価値の工場を目指すマーケティング手法です。
現代のBtoCマーケティングでは、単なる商品の訴求ではなく「共感」や「つながり」が消費行動の鍵となっています。ファンとの関係性を強化することで、ロイヤルティ向上やUGC(ユーザー生成コンテンツ)による自然な拡散が期待できます。
従来のファネル型施策(広告→認知→購入)ではなく、ファンがブランドの伝達者として活動する循環型のマーケティングがファンマーケティングであり、一過性のトレンドではなく、選ばれ続けるブランド・サービスになるための中長期的なマーケティング手法と言えます。
今回の記事では、ファンマーケティングの戦略設計や手法、導入事例を紹介します。
ファンマーケティングの定義や基礎については「ファンマーケティングとは?意味・効果・実践方法までわかりやすく解説!」をご覧ください。https://commune.co.jp/magazine/fan_marketing_fundamentals/
<記事監修:黒田悠介(コミューンコミュニティラボ所長)>
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
■記事監修:黒田悠介(くろだ・ゆうすけ)
コミューンコミュニティラボ所長。2008年に東京大学卒業後、マーケティング企業2社と起業(売却済み)を経て2013年にスローガン株式会社へ入社。2015年にはフリーランスとしてディスカッションパートナーを生業とし、スタートアップから大企業の新規事業まで、主に1on1の議論を通じて立ち上げを支援。
その傍ら2017年2月に日本最大級のフリーランスコミュニティ「FreelanceNow」や、同年11月に問いでつながるコミュニティ「議論メシ」を創立。2024年3月よりコミューンコミュニティラボ所長としてコミューン株式会社に参画しコミュニティ研究家として活動。著書にコミュニティ論『コミュニティ経営の教科書』『コミュニティシフト』及びキャリア論『ライフピボット』がある。Xアカウント
1. ファンマーケティングの設計ステップ
ファンマーケティングを成功させるためには、手法を選ぶ前に「誰に・どのような体験を提供するか」を明確に設計する必要があります。
ターゲット像や体験設計、成果の指標が曖昧なまま施策を始めてしまうと、施策がバラバラになり、継続的な関係構築が困難になるためです。
以下のようなステップを踏んでファンマーケティングの設計を進めていきましょう。
1-1. 理想のファン像を定義する
ファンマーケティングにおける”ファン”とは、単に商品を購入する顧客ではなく、ブランドの価値観に共感し、自発的に応援・発信してくれる存在を指します。
そのため、一般的なターゲット設定(年齢や性別、エリアなど)ではなく、「どのような価値観を持ち、どうブランドに関わってほしいか」という視点でファン像を定義することが重要です。
たとえば、ブランドのストーリーを好んで共有してくれる人や、口コミ投稿を自然に実施してくれる人、イベントに継続的に参加してくれる人など、熱量や関与度を基準に設計を行うことで、施策とのつながりが強まります。
1-2.カスタマージャーニーと体験設計
ファンとの関係を深めていくには、「出会い」から「共感」「参加」「継続」へと進む流れを描き、各フェーズにおける接点や体験を設計することが求められます。
たとえば、
出会い・・・SNS広告でブランドの価値観に触れる
共感・・・ストーリー性のあるコンテンツに惹かれる
参加・・・アンケートやプレゼントキャンペーンに参加
継続・・・クローズドなコミュニティに加入し、意見を発信する
といったように、「感情の動き」と「体験の流れ」を連動させる設計が理想です。
どの段階で、どんな体験を提供すればファン化が進むのかを可視化し、計画的に施策を組み立てていきましょう。
1-3.KPIを設計する
ファンマーケティングの効果は、フォロワー数やPV数などの表層的な指標だけでは測れません。ファンとの関係の深さや、行動の質を表す指標を設けることが重要です。
代表的なKPIには以下のようなものがあります。
- コミュニティ参加率(参加者数/対象ユーザー数)
- 投稿数・UGC数(ユーザー発信のコンテンツ量)
- アンバサダーの紹介件数
- イベント参加率、再参加率
- 顧客満足度(NPS)やロイヤリティ指標
KPIは戦略のゴールとリンクしているかを意識し、運用フェーズで継続的に見直していく設計が求められます。
KPIの立て方については「ファンマーケティングを成功させるKPIの立て方」も併せてご確認ください。
1-4.運用体制を構築する
どんなに設計や施策が良くても、運用体制が機能していなければ継続的なファンマーケティングは成立しません。
施策の実行やモニタリング、ファンとのコミュニケーションを担う役割を明確にし、部署横断で連携できる体制を整えましょう。
特に重要なのは、ファンの声を拾い、社内にフィードバックできる仕組みです。
コミュニケーションツールなどを活用した情報共有、定例ミーティングでの施策レビューなど、継続的にPDCAを回せるチームづくりがファンマーケティングの成功を左右します。
2. 主なファンマーケティング手法
ファンマーケティングでは、ファンの「共感」「参加」「拡散」「継続」など各フェーズに合わせた手法を組み合わせることが重要です。
ファンとの関係構築は一段階ではなく、体験や関与度の蓄積によって深まります。目的に応じた手法を使い分けることで、自然な行動変容を促すことが期待できます。
ここでは、代表的な手法を紹介しますが、手法は目的に応じて選び、ファンの心理フェーズに寄り添った設計を行うことが鍵です。単発ではなく、点と点をつなぐストーリー性あるファン体験を意識しましょう。
2-1.共感を生む手法:ブランドの世界観を届ける
ファンとの最初の接点では、ブランドの想いや背景に共感してもらうことがポイントです。この段階では、企業側からの一方的な発信ではなく、ストーリー性や感情に訴えるコンテンツが効果的です。
- SNSのストーリー投稿(創業秘話、想い)
- ブランドムービーやインタビュー記事
- 世界観が伝わるパッケージデザインやキャッチコピー など
自分もこのブランドの考え方が好き」と思ってもらえることがファン化の第一歩です。
2-2.参加を促す手法:行動へのきっかけを提供する
共感の次は、「自分も関わっていいんだ」という心理的ハードルを下げる仕掛けが必要です。
- SNSキャンペーン(投稿・投票・クイズ)
- オンラインイベントやライブ配信
- フィードバック募集、ユーザーアンケート
- コミュニティ招待
重要なのは、「発信の上手さ」よりも「気軽さ」や「楽しさ」です。ファンが主役になれる場を設けましょう。
2-3.拡散を促す手法:自発的な紹介を促進する
ある程度関係性が深まったファンには、“応援したい”という気持ちを行動に変える仕組みが有効です。
- アンバサダー・紹介制度
- リポストキャンペーン
- UGCコンテンツの紹介・フィードバック
- ファン同士の交流機会(オフ会など)
この段階では、ファンがブランドの“伝道師”となってくれるような構造を意識すると、自然なクチコミが広がります。
2-4.共創を促す手法:ブランドの一部になってもらう
さらに熱量の高いファンには、「一緒にブランドを育てる」体験を提供します。
- 商品開発への意見募集
- キャッチコピーやネーミングの投票
- ファン発案の企画を採用
- ユーザーとの対談・共同記事
このように、“参加”から“共創”へ昇華させることで、ブランドへの愛着は格段に高まります。
2-5.継続を促す手法:関係性を維持する仕組みづくり
ファンマーケティングのゴールは、「好きでいてくれる状態をいかに長く保つか」です。
- 専用コミュニティ(Slack・LINE・独自アプリなど)
- 限定コンテンツ・ニュースレター
- ファン感謝イベント
- ステージ制やバッジなどの“育成”要素
「応援し続ける理由」を感じられる設計が、長期的なLTV最大化につながります。
3. 活用パターンと導入事例
ファンマーケティングは、業種や事業フェーズに応じて最適な導入方法が異なります。自社の状況に合った施策を選ぶことが、成果を最大化するポイントです。
「どの施策が有効か」は、ブランドの認知度・ユーザーとの関係性・扱う商材の特徴によって変わるからです。万能な“型”は存在しないため、目的と状況に合わせた設計が不可欠です。
誰に、どのフェーズで、何を届けるかを設計し、施策そのものの正しさではなく、自社との相性の良さが成果を分けるポイントとなります。
より具体的な成功事例は 「ファンマーケティングの成功事例10選!成功のコツやメリット・デメリットを解説」をご覧ください。https://commune.co.jp/magazine/fan_marketing_success_examples/
3-1.新規獲得フェーズ:まずはブランドに出会ってもらう
認知拡大や接点づくりが必要なフェーズでは、共感を引き出すコンテンツや、参加しやすいキャンペーン施策が効果的です。
- SNSを活用したハッシュタグキャンペーン
- ブランドムービーの拡散
- プレゼント企画、アンケート参加型施策
- インフルエンサーとのコラボ
「このブランド、ちょっと気になるかも」という“きっかけ”を広く届ける段階です。
3-2.関係性深化フェーズ:体験を通じてブランドとつながる
接点を持った顧客との継続的な接触と信頼構築を目的に、参加型の施策やコミュニティ形成が有効です。
- オンラインイベントやオフライン交流会の実施
- ファンコミュニティへの招待
- コミュニティ内での対話・コンテンツ提供
- ファン限定情報・企画の提供
このフェーズでは「自分ごと化」を促進することが重要で、双方向のコミュニケーションが鍵になります。
3-3.熱量の高いファンフェーズ:共創・紹介で輪を広げる
ファンの中でも熱量が高い層には、ブランドと一緒に何かを創る・伝える立場になってもらう施策が適しています。
- アンバサダープログラムの導入
- 商品開発・企画への巻き込み
- UGCの紹介・感謝企画
- ファン同士のネットワーク形成(サークル化)
ここでは「私はこのブランドの仲間である」という当事者意識がファンのロイヤルティを加速させます。
4. ファンマーケティングの導入事例
ベースフード
ベースフードでは、ファンコミュニティを通じて得られたお客様の声を商品開発・改良に役立てています。
コミュニティ内では、社員×ユーザー×ユーザーのコミュニケーションが活発に行われています。ユーザーからのオリジナル商品の提案、ベースフードの新しい食べ方の紹介などアイディアがたくさんあり、ユーザー・企業双方にとって価値のあるコミュニティです。
ベースフードの事例について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
・ベースフード株式会社 vol.1 「ユーザーコミュニティで継続率の向上とお客様からの紹介数増加を実現」
・ベースフード株式会社 vol.2 「ユーザーがユーザーに働きかける好循環。コミュニティ内の投稿が商品理解の促進と新商品アイデアの源泉に」
ヤッホーブルーイング
ヤッホーブルーイングは、熱狂的なファンにより19年連続で増収、常に過去最高益を更新しています。企業の価値観に共感/支持してくれるファンをターゲットにしたイベントの開催や、自社レストランでの交流会を行っています。5,000人規模のファンイベントのほか、ファン主催のイベントなど、ファン同士での交流が活発に行われ、心に秘めている「好き」という思いを共有する場です。
*出典:
【ヤッホーブルーイング2021年業績】売上高は前期比3割増 19期連続増収・過去最高益を記録
日経XTREND 大手では真似できないライトユーザーを”伝道師”に導くヤッホーブルーイング流”ファンづくり”
カゴメ
カゴメは「ファンを知る」「ファンに伝える」「ファンと一緒に体験する」を目的としてコミュニティ「&KAGOME」を運営しています。カゴメの商品の売上の30%を2.5%のヘビーユーザーが占めており、ヘビーユーザーの離脱が売り上げの伸び悩みの原因となっていました。そこで、ファンを増やして継続的にユーザーとつながるためにコミュニティを立ち上げました。
このコミュニティのアクション率は10%を維持しており、活発なコミュニケーションが行われています。
コミュニティ運営のほかにも、座談会を開き、会員の意見を取り入れた商品の改良や”カゴメらしさ”について語るファンミーティングを開催しています。
このように多様な顧客接点を持つことで、ファンのブランドや商品への愛着を育んでいます。
*出典:
ITmedia ビジネスオンライン カゴメが築く「ファンを夢中にさせる」戦略 わずか2.5%のユーザーに注目したワケ
mineo
mineoは、愛着や共感を抱いてくれているファンとの共創を重視しています。機能やサービスで差別化するのが難しいモバイル通信市場では、安いプランを提供できる企業が有利です。
その中でmineoは、mineoでしか得られない機能・価格以外の価値体験を提供することで、顧客にとってのオンリーワンになれるのではないかと考えました。
コミュニティサイトでの社員とファン・ファン同士の交流のほか、ファンの集いやオフラインイベントを通じてファンとの共創を体現しています。
実際に、新規契約の3〜4割が既存ユーザーからの紹介となっているとともに、解約率もそれまでの2.0%前後から約1.0%まで改善しており、ファンとの共創が長期的な売り上げに貢献しています。
*出典:
KARTE CX Clip “オンリーワン”の体験価値はファンとの共創から生まれる。mineoの実践するコミュニティづくり
まとめ
ファンマーケティングは、「戦略なき手法の乱用」ではなく、設計と継続運用を前提としたマーケティング戦略です。単発のキャンペーンやバズ狙いの施策では、関係性の継続は難しく、ブランドへの信頼や愛着を育むことはできません。一貫したビジョンと構造的な仕組みがあるからこそ、ファンは共に歩む存在となります。
今回ご紹介した通り、ファンマーケティングを成功させるには、ファン像や体験設計を描く「戦略設計」、各フェーズで最適化された「手法選定」、成果を可視化する「KPI設計」、
継続的に取り組める「運用体制の構築」など、要素を一つずつ丁寧に組み立てていくことで、ファンと共にブランドを育て、選ばれ続ける存在になることができます。
ファンマーケティングの導入や改善を検討している方は、まずは社内で以下のような問いから始めてみてください。
- 自社の“理想のファン像”はどんな人たちか?
- その人たちと、どんな体験を共有したいか?
- 今ある施策は、ファンとの関係を深めているか?
さらに詳しいノウハウや社内提案に使える資料はこちらから
【資料ダウンロード】3分でわかるCommune
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
