コラム
マーケティング
DXコミュニティとは何か?成功事例と実践ポイントを徹底解説
2025/05/17
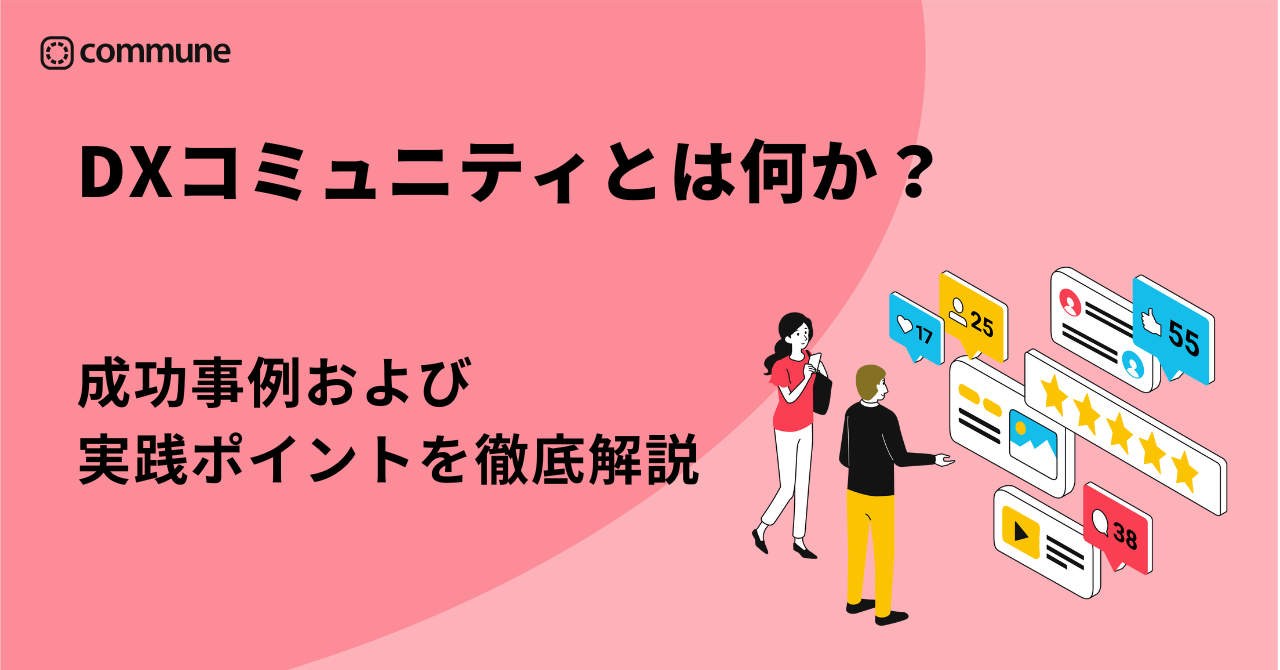
DXコミュニティとは、 DXを単なるIT導入にとどめず、組織の文化や働き方まで変革へ導く“共創の場”を指します。最先端ツールを導入しても、現場が活用しなければ価値は生まれません。変革を浸透させるにはDX推進担当者だけでなく、社員一人ひとり、さらには外部パートナーや他社プレイヤーとのネットワークが不可欠です。
本記事では、DXコミュニティの定義と役割から立ち上げ・運営のポイント、自治体や大企業での成功事例までをわかりやすく解説します。組織が直面する「変革の壁」を突破する具体策を手に取り、小さな一歩を積み重ねてコミュニティの力を最大化し、DXを加速させていきましょう。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
- 第3章 DXコミュニティは、社内外の壁を乗り越える
- 3-1. DX担当者の孤立を解消する
- 3-2. 組織文化の慣性を打破する
- 3-3. ノウハウやスキル不足を補う
- 3-4. 人材育成とモチベーション維持につなげる
- 第4章 DXコミュニティの具体的な運営メソッド
- 4-1. 目的とビジョンを全員で共有する
- 4-2. 使いやすいコミュニケーション基盤を整える
- 4-3. 学びと実践を回す仕組みをつくる
- 4-4. 成果を可視化してモチベーションを高める
第1章 なぜ「DXコミュニティ」が注目されるのか
企業がデジタル技術を活用してビジネス変革を図る DX(デジタルトランスフォーメーション) は、すでに多くの現場で当たり前のテーマとなりました。
しかし、導入したITツールが使われずに終わったり、現場の多忙さやリテラシー不足が原因で変革が進まなかったりする事例は少なくありません。どれほど高度なソリューションを用意しても、それを活かす「人」と「組織」のマインドセットが変わらなければ成果は生まれないためです。
実際には「DX担当者が孤立しがち」「経営層の理解が乏しい」「部門間サイロや旧来の慣例が根強い」など、多くの企業が共通する壁に直面します。こうした課題を乗り越える切り口として、注目を集めているのが DXコミュニティです。社内外のメンバーがゆるやかにつながり、試行錯誤や情報共有を重ねることで、変革を受け入れる土壌を育むという発想が広がっています。
DXコミュニティは単なる勉強会やSNSグループではなく、合意形成と行動促進を同時に生み出す「場」 として機能します。技術ノウハウの交換にとどまらず、組織横断的な協力体制やメンバー同士のモチベーションを高め合う仕組みまで包含する点が特徴です。
本記事では、コミュニティがDX推進に有効な理由を深掘りしながら、具体的な運営方法と成功事例をわかりやすくご紹介します。
第2章 DXコミュニティとは何か
2-1. DXコミュニティの定義
DXコミュニティとは、デジタル技術やデータ活用を軸に業務改革・新規価値創出をめざす人々が、自発的に集まり学び合う“成果志向型のネットワーク”です。ただ情報を共有するだけでなく、試行錯誤を通じて実践知を蓄積し、組織や地域の変革を加速させる「学習と実践の場」である点が大きな特徴です。
参加メンバーは社内DX推進担当者に限られず、エンジニアやマーケター、他部門の管理職、さらには外部ITベンダーや自治体の支援機関など多様です。多角的な視点が交わることで、思いも寄らない連携やアイデアが生まれやすくなります。
2-2. 主な類型
-
社内コミュニティ
企業内の有志が立ち上げる小規模なネットワークです。現場主導で業務改善や意識改革を進めるための情報交換・共助の場として機能します。 -
社外コミュニティ
異業種・異企業の担当者や専門家が参加し、ノウハウや事例を相互に提供し合います。他社の成功・失敗から学べるため、自社のDX戦略を俯瞰的に見直すきっかけになります。 -
地域コミュニティ
自治体や支援機関が主導し、中小企業やスタートアップを広く巻き込む形態です。補助金・助成情報の共有や共同実証実験の場として機能し、リソース不足を補完しながら地域全体のDXを底上げします。
2-3 DXコミュニティが注目される背景
DXが停滞する現場では、「推進担当者の孤立」「経営層・他部門の理解不足」「旧来文化による抵抗」といった壁が共通して見られます。トップダウンの研修やツール導入だけでは現場が動かず、改革が絵に描いた餅に終わるケースが後を絶ちません。
こうした課題を乗り越えるために、多様な人材が主体的に学び合い、成功・失敗を共有しながら小さく素早く実践を回す「コミュニティ型アプローチ」への期待が高まっています。コミュニティは自発的な行動と横の連携を育むことで、変革を根付かせる土壌をつくり、成功事例が連鎖的に広がる拡張性の高さも魅力です。
DXコミュニティを活用すれば、組織のサイロを越えて知見を結集し、“人” と “組織” の変革を同時に進めることができます。次章では、その立ち上げ方と運営ノウハウを具体例とともに解説します。
第3章 DXコミュニティは、社内外の壁を乗り越える
3-1. DX担当者の孤立を解消する
DX推進プロジェクトが発足しても、担当者が部署内で孤軍奮闘しがちな状況はよくあります。「自分ひとりで何とかしないと」と思うあまり、気軽に相談できなかったり、周りの忙しさに遠慮してサポートを得にくかったりするのです。
そこで、社内外のコミュニティを活用すれば、他の担当者や先進事例とつながるきっかけが生まれます。孤立状態を脱し、同じ悩みを共有し合う仲間がいるという安心感は、DXを続ける上で大きな支えとなります。
3-2. 組織文化の慣性を打破する
DXは最新技術の導入だけでなく、旧来の業務慣習や組織構造にメスを入れる必要があります。ここで大きな壁となるのは、過去から続く根強い「現状維持バイアス」です。
コミュニティが社内各部署のメンバーを巻き込む形で広がれば、抵抗感を持つ層にも「周囲が変わり始めている」という刺激が伝わりやすくなります。少しずつでも成功事例や改善効果が共有されることで、自然と組織文化そのものが変わっていく流れを作り出せます。
3-3. ノウハウやスキル不足を補う
DX推進に求められるのはIT系の技術力だけでなく、プロジェクトマネジメントやデータ分析、組織改革のノウハウなど幅広い領域です。社内だけで完結しようとすると限界がありますが、社外コミュニティや地域コミュニティなら、他社の事例や専門家からのアドバイスを直接得ることができます。現場レベルでリアルな成功・失敗談を聞けるのは、書籍やネット記事からは得られない学びが多いはずです。
3-4. 人材育成とモチベーション維持につなげる
DXに興味を持つ社員が増えても、業務で忙しい中で自主的に学習を続けるのは簡単ではありません。コミュニティが機能していると、勉強会やツール共有が定期的に行われ、学ぶ機会が自然と増えます。仲間が頑張っている様子を見て刺激を受けるため、モチベーションを保ちやすくなる点も大きいでしょう。さらに、小さな成功事例が表彰されたり、社内SNSで称賛されたりする仕組みがあれば、「自分もチャレンジしてみよう」と思う社員が続々と出てくる可能性があります。
第4章 DXコミュニティの具体的な運営メソッド
4-1. 目的とビジョンを全員で共有する
コミュニティ立ち上げの第一歩は、「DXを通じて何を達成したいのか」を言語化し、メンバー全員と合意することです。既存業務の効率化、新規ビジネス創出、地域連携の強化――狙いがはっきりしていれば、開催すべき勉強会のテーマや招くべき専門家、優先導入するツールが自ずと定まります。
4-2. 使いやすいコミュニケーション基盤を整える
コミュニティ活性の鍵は、ストレスのない情報交換です。社内向けには Microsoft Teams や Slack、社外メンバーを含む場合は Facebook グループや LINE 公式アカウントなど、参加者が日常的に使い慣れたプラットフォームを選びましょう。通知ルールやチャンネル設計を整えておけば、質問・回答が自然に循環する文化が根づきます。
4-3. 学びと実践を回す仕組みをつくる
形骸化を防ぐには、学習→実践→共有のサイクルを意図的に設計することが重要です。ハンズオンやライトニングトークで得た知見を、ナレッジベースや GitHub/Notion に公開し合うと学びが資産化します。初心者歓迎セッションやペアメンタリングを組み込めば、参加ハードルが下がり、新規メンバーの定着率も向上します。
4-4. 成果を可視化してモチベーションを高める
通常業務と並行する活動は、成果が見えにくいと頓挫しがちです。月次の成果発表会や社内報で、「RPA導入により年間○時間削減」「新ツール活用で商談成約率+△%」といった数値を共有しましょう。上司・経営層が効果を即座に理解できるため支援が得やすくなり、メンバーの達成感と次のチャレンジ意欲も高まります。
第5章 成功事例から学ぶ:社内・社外コミュニティのリアルな取り組み
草の根DXコミュニティで現場を変革――ヤンマーグループのボトムアップ×トップダウン戦略
ヤンマーホールディングスは2022年度、中期戦略で「DXに対応する次世代経営基盤」を掲げ、全社横断のデジタル戦略推進部を新設しました。同部は現場発のデジタル活用を後押しする「草の根DX活動」を展開し、社内チャット上にDXコミュニティ(参加1,100人超)とローコードコミュニティ(同530人)を立ち上げています。
アーリーアダプター社員がノーコード/RPAで業務改善事例を共有し、月例の発表会や勉強会で知識を水平展開。中間層の意識変革を狙い、CDOが事業部長会議で成功事例を紹介し、国内外の現場報告会も実施してトップダウンで後押ししています。コミュニティ起点の査定アプリなど成果が相次ぎ、海外拠点へも活動が拡大中です。
全社教育ではUdemy Businessを導入し、①全社員向けリテラシー動画、②必修+選択ラーニングパス、③Power Platform実践研修の三段構えで800人が受講。修了者にはオープンバッジを発行し、自己評価ではDX理解度が平均1ポイント向上しました。アンケートでも85%が「役立つ」と回答し、データ分析・自動化プロジェクトが加速。2025年度までにコミュニティ参加率を10〜20%へ高め、草の根成功事例を倍増させることで、「誰もがデジタルで価値を創る」企業文化の定着を目指しています。
■関連記事
現場主導でデジタル改革!積極的な社員のコミュニティを軸に成功事例を増やす(リンク)
DX初心者と上級者が助け合うエコシステム――福岡市DX推進ラボの相互扶助モデル
公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)が事務局を務める「福岡市DX推進ラボ」は、DXコミュニティ「福岡DXコミュニティ」と地域DX促進事業「One Kyushu DX」を束ね、2023年度から地域DX推進ラボとして再始動しました。
同ラボは2016年度に地方版IoT推進ラボとして発足し、当初はオンライン中心でしたが、コロナ禍収束後に対面イベントへ転換しリアルとオンラインを融合しています。参加費無料のコミュニティには経営者、会社員、学生など多様な立場・スキルの参加者が集まり、製造業を中心にDX推進の悩みを共有しています。
主軸イベント『DX推進「実行力」の勉強会』は月1回19時開始。アジャイル開発をベースにした座学+ワークショップを1回完結型で提供し、混成チームで「わかる人が教える」状況を自然発生させています。終了後の懇親会とSlack交流が相互扶助を加速し、参加企業のオートシステムでは社内DX大学「ASC」が誕生するなど波及効果も顕著です。
今年度はテーマを「データドリブン」など3本に拡大しつつ年12回開催を維持。参加ハードルを下げた設計と学び合いの仕組みで、地域全体のDX人材育成を加速しています。
■関連記事:
DX初心者と上級者が助け合う相互扶助の輪、広がれ!――福岡市DX推進ラボ(リンク)
マンションSNS「GOKINJO」――リアルとデジタルの融合でご近所づきあいを再設計
株式会社コネプラは旭化成発のベンチャーとして、マンション居住者限定SNS「GOKINJO」を開発しました。登録コードによる認証で居住者だけが安心して参加でき、情報交換・不要品の「お譲り」・相互支援の「お助け」という三機能を提供しています。
アプリとリアルイベントを組み合わせ、顔見知りになるきっかけを用意することで継続利用を促しています。UI/UXはシニアにも直感的に使えるよう自社で設計し、導入9物件で月間アクティブ率79%、ユーザー満足度89%を達成しました。収益は新築マンション開発業者からの初期導入費と管理組合からの維持費の二本柱で、創業初年度から黒字化を実現しています。
現在のユーザーは約2,600名で、その24%が60代以上と高齢層にも浸透しており、年間1万人ユーザー獲得を目指して拡大中です。今後はコミュニティ活動データの蓄積とビッグデータ分析を進め、戸建て分譲地や自治体へも展開し、地域DXと資産価値向上に貢献する計画です。
大企業の信頼性とスタートアップの機動力を両立したモデルは高く評価され、日本DX大賞2023 UX部門ファイナリストにも選出されました。
関連記事:
地域コミュニティのDX事例:「GOKINJO」が示す新たなつながりの創出|日本DX大賞2023(リンク)
地域コミュニティの事例と連携の可能性
6-1. 地域コミュニティのメリット
地方の中小企業などはIT人材の不足やノウハウ不足が深刻化しがちで、新たにDXへ踏み出すハードルが高いという現実があります。地域コミュニティに参画すれば、地元ベンダーや支援機関、金融機関とつながることで補助金情報をいち早く入手したり、専門家派遣を受けたりすることが可能です。さらには同じ地域の企業同士でネットワークを作れば、共同プロジェクトの形で一緒にツール導入や実証実験を行い、単独では難しい大きな課題にも挑戦しやすくなります。
6-2. 他地域や他コミュニティとの連携
地域コミュニティが成功すると、その事例を他地域が学習し合う動きが出てきます。たとえば福岡DXコミュニティの成果やノウハウが大分や山口へ伝わり、隣県間で補助金制度の比較検討を行うといった形です。また、トヨタのような大企業が社外に向けてオープンなコミュニティ活動を行う例もあり、それを地方のコミュニティが取り入れることでさらに発展するケースもあります。コミュニティ同士がゆるやかにつながることで、広域的なDXネットワークが形成される可能性を秘めているのです。
7. まとめと次のアクション
本記事では、DXコミュニティという視点からDX推進の課題と解決策を探りました。新しいツールや仕組みを導入しても、人と組織が変わらなければ真のDXは実現できません。そこで、同じ目的を持つ人々が集まり、学びと実践を積み重ねる「コミュニティ」の役割が非常に重要だといえます。大企業の社内コミュニティから地域コミュニティまで、成功事例はすでに数多く登場しており、小さく始めながら成果を積み重ね、拡大していくプロセスが各所で見られています。
コミュニティを活用したDX推進は、スタートアップ企業に限らず多くの組織が実践可能です。たとえば、「まず社内のSlackにDX専用チャンネルを作る」「地域の勉強会やセミナーを探して参加してみる」「簡単なツール紹介会を社内で開く」など、小さな一歩から進めてみてください。少人数でも成功体験を共有できれば、「自分たちにもできるかも」という意欲が高まり、協力者が増えていきやすくなります。
DXは1回のプロジェクトで完結するものではなく、絶えず進化する連続的な取り組みです。コミュニティが有効に機能し始めれば、メンバー同士でスキルや情報が循環し、成果が生まれやすくなるでしょう。ただし、盛り上がりにムラが出たり、マンネリ化したりする可能性はゼロではありません。定期的な目標設定と成果の見える化、外部との連携によって刺激を与え続けることで、変革を続ける組織風土を育むことができます。
DX担当者が孤立しがちな環境でも、コミュニティを活用すれば仲間や専門家、成功事例と結びつきやすくなります。企業規模や業種を問わず、そして地域でも全国でも、コミュニティがDXのエンジンとなる可能性は大いにあるでしょう。小さなアクションを積み重ね、ぜひあなたの組織や地域に合ったコミュニティを育てていってください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
