コラム
マーケティング
DAU・WAU・MAUの計算方法とは?定義や使い分け・活用方法を解説
2025/05/26
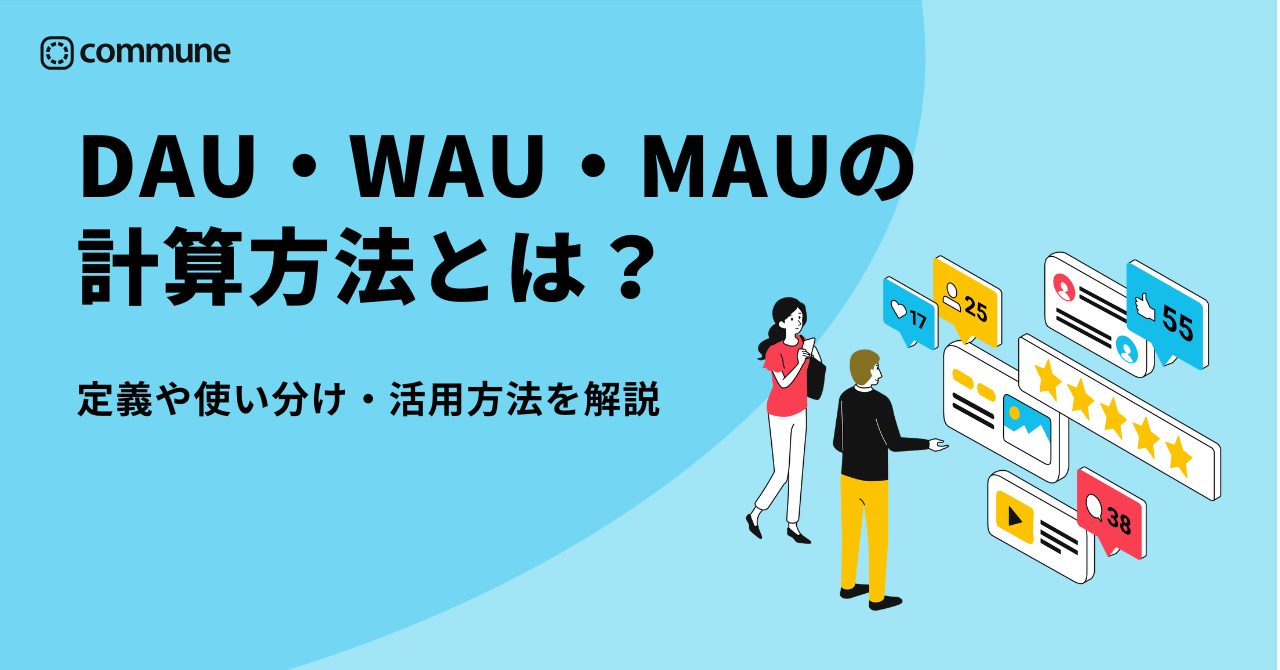
Webサイトや顧客コミュニティを運営する際は、さまざまな指標がKPIとして活用されています。そのなかでも「MAU」「WAU」「DAU」は、顧客の熱量やエンゲージメントを測る指標として特に重要です。
これらの指標を活用することで、より適切な戦略・施策を実行しやすくなります。そこで本記事では、MAU・WAU・DAUの計算方法や活用法について詳しく解説します。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
そもそも「AU(アクティブユーザー)」とは

詳細は後述していますが「MAU・WAU・DAU」は、いずれも「AU(アクティブユーザー)」に関する指標です。そこで、まずはAUについて次のポイントから見ていきましょう。
- 一定期間内にアクセスしたユーザーのこと
- 成果の向上にはAUを増やす施策が重要
一定期間内にアクセスしたユーザーのこと
「AU(アクティブユーザー)」とは、自社のWebサイトやコミュニティの利用者のうち、一定期間内に1回以上アクセスしたユーザーを指します。
ただし、ユーザー個人が複数回アクセスしたとしても1人としてカウントし、期間外に訪問したユーザーはカウントしません。この「一定期間」と関係するのが後述するMAU・WAU・DAUです。
成果の向上にはAUを増やす施策が重要
一方で、自社のWebサイトやコミュニティを積極的に利用していないユーザーは、「非アクティブユーザー」と呼ばれます。非アクティブユーザーが増えると、自社の施策に対して反応するユーザーの割合が低下するため、サービスの運用成果が出づらくなります。そのため、AUをいかに増やすかが重要です。
DAU・WAU・MAUとは
前述したAU(アクティブユーザー)を踏まえたうえで、DAU・WAU・MAUについて次のポイントから見ていきましょう。
- 期間内のアクティブユーザー数を示す指標
- DAU・WAU・MAUそれぞれの計算方法
- 「DAU/MAU比率」も重要な指標となる
期間内のアクティブユーザー数を示す指標
DAU・WAU・MAUは、いずれの一定期間内に自社のWebサイトやコミュニティを利用したユーザーを示すための指標です。3つの指標は次のように期間設定に応じて使い分けられます。
| DAU(Daily Active User) | 1日あたりのアクティブユーザー |
| WAU(Weekly Active User) | 1週間あたりのアクティブユーザー |
| MAU(Monthly Active User) | 1か月あたりのアクティブユーザー |
これらの指標を活用して一定期間ごとのアクティブユーザーを把握することで、自社サービスの顧客エンゲージメントを測ったり、運営の課題を把握したりすることができます。
DAU・WAU・MAU率で施策の効果を測定
それぞれの指標の変動を測定することで、短期的な施策の効果や季節要因や週末の影響など、異なる時間軸での施策の効果分析に役立てることができます。
計算式は以下となります。
| DAU | 1日あたりのアクティブユーザー ÷ サービス登録者数 × 100 |
| WAU | 1週間あたりのアクティブユーザー ÷ サービス登録者数 × 100 |
| MAU | 1か月あたりのアクティブユーザー ÷ サービス登録者数 × 100 |
例えば、10万人が登録している顧客コミュニティで、1か月あたりのアクティブユーザーが3万人である場合は、MAU率は「3万 ÷ 10万 × 100」で、30%となります。
DAU/MAU比率」も重要な指標となる
DAUとMAUは、前述したように1日と1か月のアクティブユーザーを示します。このDAUをMAUで割った指標を「DAU/MAU比率」と呼び、ユーザーの「スティッキネス(粘着性)」を測る指標として活用されています。スティッキネスは、サービスに熱中して頻繁に利用する状態のことです。
DAU/MAU比率は、1か月のうちユーザーがどれくらいの頻度でサービスを利用しているかの指標となります。
例えば、DAU/MAU比率が70%の場合、ユーザーは毎月平均で21日利用しているということです。この数値が高いほど、ユーザーは自社サービスへの熱量が高い状態にあります。
関連記事:
カスタマーサクセスのKPI、何を設定すべき?主要な10種を解説
┗ AU/DAUなど“利用度指標”の基本がわかる記事です。
スティッキネスが高いコミュニティの共通点
前述したように、スティッキネスはメンバーがどれだけ頻繁かつ継続的に、コミュニティに関与しているかを示す指標です。スティッキネスが高いコミュニティの特徴として、次のようなものが挙げられます。
- UGC比率が高い
- オフライン連動性が高い
- コンテンツが定期的に更新される
- テーマ設定の共感性が高い
- 可視化された成長体験がある
UGC比率が高い
コミュニティの主要コンテンツが運営側ではなく、メンバー側が発信するUGC(ユーザー生成コンテンツ)で成り立っている傾向があります。基本的には、投稿数や返信数の7割以上がUGCで構成されている場合、スティッキネスが高いコミュニティであるといえるでしょう。ユーザー同士のやり取りは常に新しいものがあるため、継続的に訪問したくなるのです。
オフライン連動性が高い
コミュニティの内容が現実の顧客体験や人間関係と連動、つまりオフライン連動性があるコミュニティは、スティッキネスも高くなりやすいです。例えば、オフラインの交流会・勉強会・商品体験イベントをコミュニティ上で募集しているなどです。メンバー同士のつながりがリアルになることで離脱心理が低下し、アクセス数も自然と増えるでしょう。
コンテンツが定期的に更新される
コミュニティ内のコンテンツが毎日・毎週など定期的に更新されていると、「コンテンツ消費」という行動がメンバーの行動に組み込まれて、コミュニティ訪問が習慣化します。また、投稿しやすいテーマやテンプレートが用意されていれば、メンバーが気軽に投稿しやすいためUGCも増えて、そのチェックやコメントのための再訪も増えるでしょう。
テーマ設定の共感性が高い
コミュニティのコンテンツやスレッドなどのテーマが、「自分ごと化」しやすい設定になっていると、メンバーの共感や承認が得やすい雰囲気が醸成されます。「理解し合える」「認め合える」関係を築ける環境は、メンバーの精神的な充足感につながるため、継続利用の明確な動機となるでしょう。
可視化された成長体験がある
ゲーミフィケーションに代表される「可視化された成長体験」が提供されているコミュニティは、スティッキネスが高まりやすいと考えられます。例えば、投稿やリアクションなどによって、ポイント・バッジ・ランキングなどの報酬に反映されるなどです。こうした施策により、メンバーがコミュニティへの所属意識や自己効力感が得られるため、コミュニティに関与し続ける動機となります。
関連記事:
スーパーユーザーとは何か?どうやって育成するのか?
┗ 粘着度を高める鍵=“コアユーザー”育成ノウハウを解説した記事です。
DAU・WAU・MAUを測定するメリット
DAU・WAU・MAUを測定することで、Webサイトやコミュニティ運用において次のようなメリットが得られます。
- ユーザーのエンゲージメントを把握できる
- 適切なマーケティング戦略を実行しやすくなる
- 競合他社のサービスと定量的な比較ができる
ユーザーのエンゲージメントを把握できる
アクティブユーザー数はいわば自社のサービスを繰り返し利用する「リピーター」でもあります。リピーターの多さは、自社サービスに対するユーザーのエンゲージメントの高さを意味するため、DAU・WAU・MAUを計算することでユーザー心理を把握できます。
適切なマーケティング戦略を実行しやすくなる
自社のWebサービスの運用において何らかの施策を実行する場合、DAU・WAU・MAUはその効果をダイレクトに反映します。施策の実行前と実行後にDAU・WAU・MAUを計算して比較することで、その施策の有効性を判断できます。適切な戦略を実行するためにも、DAU・WAU・MAUの数値が重要です。
競合他社のサービスと定量的な比較ができる
自社のWebサービスの運営状況を把握するうえで、競合他社との比較が役立つ場合があります。DAU・WAU・MAUを計算し、その数値を競合他社や業界平均値と比較することで、自社サービスの魅力を判断可能です。例えば顧客コミュニティの場合は、一般的にアクティブ率30%以上が理想値であるといわれています。
関連記事:
心理ロイヤルティとは?測定指標・高める4施策・成功事例を5分で解説
┗ 数値に表れにくい“気持ちのロイヤルティ”を把握する視点が得られる記事です。
DAU・WAU・MAUの指標を改善するための手法・施策
DAU・WAU・MAUの指標を改善するためには、次のような施策が効果的だと考えられます。自社の状況に合わせた施策を検討してみましょう。
- 限定コンテンツを配信する
- オンボーディングを工夫する
- プッシュ通知でアプローチする
- インセンティブ制度を整備する
- コミュニティ内の人間関係を強化する
- コンテンツの発見性を高める
- 外部の事業者に相談してみる
限定コンテンツを配信する
コミュニティのメンバーだけ閲覧できるコンテンツを、例えば「1日だけ」「1週間だけ」など期間限定で配信することで、コミュニティ訪問の動機を強化できます。
例えば、ヘルスケアコミュニティの限定コンテンツとして、5分程度で読める健康コラムを日替わりで配信するなどです。「今日だけ得られる情報がある」と示すことで、FOMO(Fear Of Missing Out)である「取り逃しへの不安」を刺激できます。
オンボーディングを工夫する
Webサービスをユーザーが初めて利用する導入段階である「オンボーディング」を充実させることが重要です。ユーザーが利用するハードルを低くすることで、継続利用への意欲を高めることができます。例えば顧客コミュニティの場合は、ウェルカムメッセージを送付したり、新規登録者用のチャネルを用意したりすることで、ユーザーがスムーズに慣れることができるでしょう。
プッシュ通知でアプローチする
タイムリーな通知やリマインドを送信することで、即時的な行動をユーザーに促すことができます。例えば、「機能の投稿に新しいコメントが付きました」「本日限定のコンテンツ配信中」などの通知です。特に自身の投稿に関するメンションは、承認欲求の観点から心理的な影響が強いため、再来訪の強いきっかけとなるでしょう。
インセンティブ制度を整備する
コミュニティへのアクセスや投稿に対してインセンティブを与えるようにすることで、メンバーの達成感を刺激し、コミュニティへのアクセスを習慣化できます。例えば、1週間連続でアクセスしたメンバーに限定スタンプや称号を与えたり、投稿やコメントをするごとにポイントを付与したりするなどです。また、ポイントランキングなどを公開して競争要素を設けることで、継続利用のための強い動機となるでしょう。
コミュニティ内の人間関係を強化する
顧客コミュニティのDAU・WAU・MAUを改善するためには、メンバー同士の「人間関係」の強化も欠かせません。コミュニティの居心地の良さは、再訪のための強力な動機となるからです。コメント・いいね・メンションなど、相互作用を活用してみましょう。例えば、ほかのユーザーからのメンションや、投稿へのリアクションがあったときにプッシュ通知を送信するなどです。通知経由のアクセスが増えるため、DAUの向上に特に効果的です。
コンテンツの発見性を高める
新しい投稿や人気の高いスレッドを発見しやすい設計にすることで、投稿が埋もれることなくユーザーの目に触れやすくなります。例えば、「本日の注目投稿セクション」を設けたり、「あなたにおすすめの投稿」を表示したりするなどです。魅力的なコンテンツが多い印象を与えることができれば、再訪率や滞在時間が向上するでしょう。
外部の事業者に相談してみる
DAU・WAU・MAUを計算すること自体は容易ですが、指標の管理や向上施策の実行には専門的な知見が必要なため、自社リソースでさまざまな施策を実行しながら効果検証を行うのが難しいこともあります。そこで外部事業者にサービス運用を依頼したり、コンサルティングを受けたりすることで運用成果が高まるでしょう。
顧客コミュニティの場合は、メンバーの熱量を高めるための適切な戦略設計やKPI設定が必須です。コミュニティ運用サービスを利用することで、専門家の知見を得ながらコミュニティの運用成果を高めることができるでしょう。
関連記事:
リピーターを増やすには?安定収益とブランド力を高める戦略
┗ 継続利用を促す具体策が網羅され、DAU/WAU向上に直結することを示した記事です。
DAU・WAU・MAUの向上施策の成功事例
顧客コミュニティの運営では、コミュニティアクティブ率を高めることが重要です。ここでは、メンバー同士が語り合える場所をコミュニティで提供したことで、コミュニティアクティブ率(MAU)が飛躍的に向上した事例をご紹介します。
株式会社タンガロイは、切削工具をはじめとした超硬工具や摩擦材料・耐摩耗工具の製造販売を行う、創業90年を超える歴史をもつ企業です。同社のYouTubeチャンネルのコメント欄にて、顧客同士が工具の使い方について議論している様子から、双方向のコミュニケーションが取れるコミュニティの必要性を感じました。
そこで同社が導入したコミュニティ運用サービスが「Commune」です。ローンチから年度末までにコミュニティ登録者500人という目標を掲げ、事前にSNSでの反応が良好なフォロワーを積極的にコミュニティに招待しました。その結果ローンチ初日に400名を、わずか1か月で500名を達成できたのです。
同社のコミュニティ運営施策の特徴は、SNSを活用した認知の拡大です。過去にSNSで投稿した内容をコミュニティで発信したり、コミュニティ内部の有益な情報をSNSに投稿することで、顧客体験を最大化しています。さらに「切削工具のコミュニティ」として、参加者を自社製品のユーザーに絞り込まないことで間口が広く、さまざまなメンバーにとって有益なコミュニティとなっています。
こうした取り組みにより、メンバーの約75%が定期的にログインし、4人に1人は投稿やコメントなどのアクションも行うなど、MAUやエンゲージメントも高い水準にあります。同社の導入事例の詳細については、こちらの記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:
コミュニティサイトツールとは?おすすめのクラウド型サービス10選を徹底解説!
┗ 成功事例を再現するためのツール選定ポイントを比較しながら理解できる
コミュニティ運営の成果向上には「Commune」がおすすめ!
DAU・WAU・MAUを計算することで、ユーザーのエンゲージメントを把握し、適切な戦略を実行しやすくなります。コミュニティ運用においてDAU・WAU・MAUなどのアクティブ率の向上を目指す場合は、専門的な知識や経験が必要なため、社内リソースでは対応しきれないこともあるでしょう。顧客コミュニティ構築サービスの活用がおすすめです。
「Commune」には、ユーザー同士の交流や企業とユーザーとの共創を実現するための機能が備わっています。顧客の熱量を上げ、双方向の関係を築く仕組みにより、優れた成果を得られるカスタマーリレーションズやファンマーケティングが実現できます。
こちらのリンクで、資料「3分でわかるCommune」を無料でダウンロードできます。この機会にぜひ、導入をご検討いただければ幸いです。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
