コラム
マーケティング
カスタマーサクセスとカスタマーサポートの違いとは?LTV最大化を実現する「攻め」と「守り」の役割分担
2025/08/01
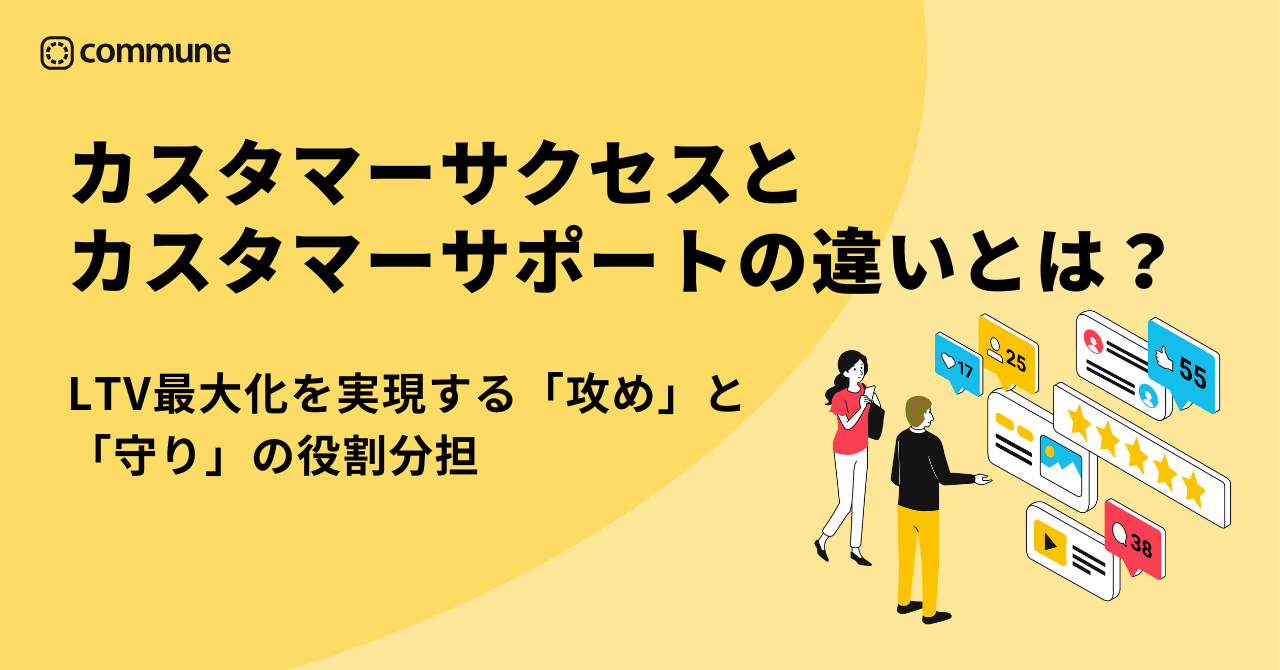
「顧客からの問い合わせには丁寧に対応しているはずなのに、なぜか解約が減らない」「最近よく聞く『カスタマーサクセス』。うちのカスタマーサポートと、一体何が違うのだろうか?」ーーこうした問いを抱く方は多いのではないでしょうか。
サブスクリプションモデルが主流となり、新規顧客の獲得コストは年々上昇。企業の持続的な成長は、いかに既存顧客との関係を深め、長期的な価値(LTV)を生み出せるかにかかっています。
事実、世界のカスタマーサクセスマネジメント市場は年平均22.18%という驚異的な成長率で拡大しており、2029年には55億米ドルを超える規模に達すると予測されています(Mordor Intelligence調べ)。これは、もはや「顧客対応」という言葉だけでは捉えきれない、戦略的な顧客エンゲージメントの時代が到来したことを意味します。
本稿では、「カスタマーサクセス」と「カスタマーサポート」という、似て非なる2つの概念の本質的な違いを解き明かします。両者の役割を「攻め」と「守り」の観点から整理し、国内外の最新データと成功事例をもとに、あなたの会社が顧客から選ばれ続けるための具体的な組織設計とアクションプランを提示します。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
第1章 なぜ今、「違い」の理解が不可欠なのか?市場の変化と経営インパクト
なぜ今、これほどまでにカスタマーサクセスとカスタマーサポートの違いを明確にすることが求められているのでしょうか。その背景には、無視できない市場構造の変化があります。
「所有」から「利用」へ――サブスクリプション経済の到来
かつての「売り切り型」ビジネスでは、契約成立がゴールでした。しかし、SaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプションモデルでは、契約はスタートラインに過ぎません。顧客はいつでもサービスを「解約」できるため、企業は継続的に価値を提供し続けなければ、収益を維持・拡大することができません。
この環境下で、顧客からの問い合わせを待つだけの受動的な姿勢は、致命的なリスクとなり得ます。顧客が不満や疑問を口にする前に、その兆候を察知し、先回りして成功体験へと導く「能動的な働きかけ」が不可欠なのです。
よくある誤解――「サポート担当にサクセスも任せればいい」は危険
「カスタマーサクセスも、結局は顧客対応だろう。今のサポートチームに兼務させれば十分ではないか?」――これは、多くの企業が陥る最初の誤解です。
しかし、両者は目的も、求められるスキルも、評価される指標(KPI)も全く異なります。受動的な問題解決(守り)と、能動的な価値提供(攻め)を同じ担当者に担わせると、日々の緊急対応に追われ、長期的な関係構築という重要なミッションが後回しになります。結果として、チームは疲弊し、静かに解約していく「サイレントカスタマー」を増やすことになりかねません。
この違いを理解し、組織として明確に役割を分担することこそが、LTV(顧客生涯価値)を最大化し、持続的な成長を実現するための第一歩なのです。
第3章 経営指標で見る両者の価値――ROIとLTVへの貢献
「攻め」と「守り」の役割は、最終的に企業の経営指標にどのようなインパクトを与えるのでしょうか。それぞれの価値を、投資対効果(ROI)の観点から見ていきましょう。
① カスタマーサポートがもたらす「コスト削減」と「ブランド毀損の防止」
優れたカスタマーサポートは、企業のコスト構造を大きく改善します。
- 問題解決の効率化: FAQやチャットボットを整備し、簡単な問い合わせを自動化することで、サポート担当者はより複雑な問題に集中できます。これにより、1件あたりの対応コストは劇的に下がります。
- ブランドイメージの維持: 不満を持った顧客の91%は、二度とその企業から購入しないと言われています(Bain & Company調べ)。迅速で丁寧なサポートは、こうしたネガティブな口コミの発生を防ぎ、ブランド毀損のリスクを最小限に抑えるのです。
サポートは直接的な売上を生む部門ではありませんが、その活動は確実に企業の利益を守っています。
② カスタマーサクセスがもたらす「LTV向上」と「持続的成長」
カスタマーサクセスへの投資は、未来の売上を創出する直接的なドライバーとなります。
- 解約率の劇的な改善:
米国の著名なコンサルタントであるフレデリック・ライクヘルドが提唱した「5:25の法則」によれば、顧客離れを5%改善すれば、利益が最低でも25%改善されるとされています。カスタマーサクセスは、顧客の成功を支援することで解約率を直接的に引き下げ、収益基盤を安定させます。 - アップセル・クロスセルの促進:
既存顧客への販売成功率は60〜70%である一方、新規顧客への販売成功率は5〜20%に過ぎません(Marketing Metrics)。顧客との信頼関係を築いたカスタマーサクセス担当者からの提案は受け入れられやすく、顧客単価(ARPU)とLTVの向上に直結します。 - NPS®(ネットプロモータースコア)の向上:
顧客の成功体験は、ロイヤルティを高め、「このサービスを友人や同僚に勧めたい」という推奨意向に繋がります。NPS®の向上は、新たな顧客を呼び込む強力なマーケティングエンジンとなるのです。
このように、サポートが「損失の最小化」に貢献するのに対し、サクセスは「利益の最大化」を担います。両者は、企業の財務健全性を支える上で不可分な存在なのです。
第4章 陥りがちな3つの罠と、その克服戦略
カスタマーサクセスの重要性を理解し、いざ導入しようとしても、多くの企業が同じような壁にぶつかります。ここでは、代表的な3つの「罠」とその克服法を紹介します。
① 役割の混同による「サクセス業務の形骸化」
最も多い失敗が、カスタマーサポートチームに「今日からサクセスもやって」と丸投げしてしまうケースです。日々の問い合わせ対応に追われる中で、能動的なアプローチや長期的な戦略立案は後回しになりがち。結果、「カスタマーサクセス担当」という肩書だけが存在し、実態は従来のサポート業務と変わらない、という事態に陥ります。
克服戦略: まずは組織として「サポート」と「サクセス」の役割とKPIを明確に分離しましょう。たとえ最初は一人が兼務するとしても、業務時間を明確に分け(例:午前はサポート、午後はサクセス)、それぞれの活動を評価する仕組みを作ることが重要です。
② KPIの形骸化による「自己満足な活動」
「オンボーディングの実施回数」「定期ミーティングの開催数」といった活動量(Activity)だけをKPIに設定してしまう罠です。担当者はKPI達成のために活動しますが、それが本当に顧客の成功や解約率低下に繋がっているかが見えません。
克服戦略: 活動量KPIと並行して、必ず「解約率」「LTV」「NPS®」といった成果(Outcome)に紐づくKPIを設定します。そして、活動と成果の相関関係を常に分析し、「どの活動が最も成果に繋がったか」を検証する文化を醸成することが不可欠です。
③ ツール導入だけで満足してしまう「テクノロジー依存」
「高機能なカスタマーサクセスツールを導入すれば、すべて解決するはずだ」という期待も危険です。ツールはあくまで活動を効率化する手段であり、戦略や目的がなければ宝の持ち腐れになります。
克服戦略: ツール導入の前に、「誰に(顧客セグメント)」「何を(提供価値)」「どのように届けるか(コミュニケーションプラン)」という戦略を徹底的に議論しましょう。戦略というOSがあって初めて、ツールというアプリケーションが真価を発揮するのです。
第5章 成功事例に学ぶ「攻め」と「守り」の連携プレイ
理論だけでなく、実際の企業がどのように「攻め」と「守り」を連携させているのかを見ていきましょう。
✅ 事例1:Salesforce(BtoB SaaS)
世界的なCRM/SaaS企業であるSalesforceは、カスタマーサクセスの概念をいち早く確立し、実践してきたパイオニアです。同社では、顧客を成功に導くための役割が明確に分担されています。
- 攻め(カスタマーサクセスマネージャー): 契約後の顧客に対し、専任のマネージャーが伴走。顧客のビジネス目標をヒアリングし、Salesforceを活用した目標達成プランを共に策定。定期的なミーティングを通じて進捗を確認し、新たな活用法を提案することで、アップセルや契約更新に繋げます。
- 守り(テクニカルサポート): 技術的な問題や仕様に関する問い合わせには、専門のサポートチームが迅速に対応。これにより、サクセスマネージャーは戦略的な対話に集中できます。
この明確な役割分担と、CRM上に蓄積された顧客情報のスムーズな連携が、同社の驚異的な顧客定着率と成長を支えています。
✅ 事例2:アドビ株式会社(BtoC/BtoB クリエイティブツール)
クリエイター向けソフトウェアで圧倒的なシェアを誇るアドビもまた、巧みな顧客エンゲージメント戦略を実践しています。
- 攻め(コミュニティとコンテンツ): 「Adobe Creative Cloud」のユーザー向けに、豊富なチュートリアル動画や、ユーザー同士が質問し合えるオンラインコミュニティ「Adobe Support Community」を提供。ユーザーが自ら学び、問題を解決し、新たな表現方法を発見できる「成功体験」を能動的に創出しています。これにより、ユーザーはツールの価値を最大限に引き出し、ファン化していきます。
- 守り(専門サポート): アカウント情報や決済、複雑な技術トラブルといった個別対応が必要なケースでは、チャットや電話による専門のサポート窓口が対応。コミュニティで解決できない問題を確実に受け止めます。
アドビの事例は、1対1の対応だけでなく、コミュニティのような「1対多」のアプローチを組み合わせることで、効率的かつ効果的にカスタマーサクセスを実現できることを示しています。
第6章 自社に最適な顧客体制を築くための導入ロードマップ
では、あなたの会社では、明日から何を始めるべきでしょうか。ここでは、顧客中心の体制を組織に定着させるための4段階の実行ステップを紹介します。
ステップ1:現状分析と目的設定
まずは、自社の顧客接点が今どのような状態にあるかを客観的に把握することから始めます。以下のチェックリストで、自社の課題を洗い出してみましょう。
✅ 直近3ヶ月の解約理由で、最も多かったものは何か? ✅ 顧客からの問い合わせ内容を分析し、分類できているか? ✅ サポートチームは、問い合わせ対応以外の活動に時間を使えているか? ✅ 顧客のサービス利用状況(ログイン頻度、機能利用率など)をデータで把握できているか? ✅ 「理想的な顧客」とは、どのような状態の顧客かを言語化できるか?
これらの問いを通じて、「守りが手薄なのか」「攻めの機会を逃しているのか」を明確にし、「カスタマーサクセス/サポートを通じて、何を達成したいのか(例:解約率を半年でX%改善する)」という具体的な目標を設定します。
ステップ2:役割定義とKPI設計
次に、分析結果と目標に基づき、「誰が」「何を」「どの指標で」担うのかを定義します。最初は少人数でも構いません。サポート担当者の中からサクセス兼任者を任命し、「週に1日はサクセス活動に充てる」といったルールから始めるのが現実的です。それぞれの役割に対し、第2章で紹介したような明確なKPI(CSAT、解約率など)を設定し、評価の軸を定めます。
ステップ3:プロセスとツールの整備
役割が決まったら、チームがスムーズに連携するためのプロセスを設計します。例えば、「サポートチームが受けた製品改善要望を、週次でサクセスチームと開発チームに共有する」「利用率が低下している顧客リストをツールで自動抽出し、サクセス担当者がアプローチする」といった具体的なルールです。この段階で初めて、情報共有を円滑にするためのCRMやカスタマーサクセスツールなどの導入検討が有効になります。
ステップ4:小さな成功からの全社展開
最初から完璧な体制を目指す必要はありません。まずは特定の顧客セグメントに絞ってスモールスタートし、「このアプローチで解約率が下がった」「この提案でアップセルに繋がった」という小さな成功事例(Quick Win)を積み重ねましょう。その成功体験とデータを社内で共有することで、経営層や他部門の理解と協力を得やすくなり、取り組みを全社へとスケールさせていくことができます。
第7章 まとめと行動プラン:あなたの次の一手は?
本記事で見てきたように、「カスタマーサポート」と「カスタマーサクセス」は、どちらが優れているという話ではなく、企業の持続的な成長に不可欠な両輪です。
- カスタマーサポート(守り): 顧客の「不満」を解消し、信頼の土台を築く。
- カスタマーサクセス(攻め): 顧客の「成功」を創出し、LTVを最大化する。
この2つの機能を戦略的に連携させ、顧客データを組織の資産として活用できる企業だけが、これからの競争を勝ち抜いていくことができます。
✅ 今日からできる!顧客エンゲージメント改革の3ステップ
この長い記事を読み終えた今、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。
① 直近1ヶ月の問い合わせ内容を分析する
まずはExcelでも構いません。「操作方法の質問」「不具合報告」「機能要望」など、問い合わせ内容を分類してみましょう。そこから、「FAQで解決できたはずの問題」や「製品改善のヒント」といった、次の一手に繋がる宝の山が見つかるはずです。
② あなたの会社の「サクセス」を1文で定義する
「顧客が、我々のサービスを通じて〇〇という状態になること」。この〇〇を、あなたのチームで議論してみてください。この一文が、今後のすべての活動の北極星となります。
③ サポートと営業/マーケで「顧客共有会」を30分だけ開く
サポートが聞いている「顧客の生の声」と、営業/マーケが描いている「ペルソナ像」のギャップを共有する場を設けてみましょう。この小さな対話が、部門の壁を越えた顧客中心の文化を育む第一歩となります。
顧客の成功を能動的に支援し、LTVを最大化する上で、顧客同士が繋がり、学び合う「オンラインコミュニティ」は極めて強力な武器となります。アドビの事例のように、コミュニティは顧客の自己解決を促し(守り)、新たな活用法や成功事例の発見を促進する(攻め)、まさにカスタマーサクセスとサポートを融合した場となり得るのです。
私たちコミューン株式会社が提供する「Commune」は、こうした戦略的な顧客コミュニティをノーコードで、かつスピーディーに立ち上げ、成功へと導くプラットフォームです。顧客エンゲージメントを次のレベルへ引き上げ、持続的な事業成長を実現したいとお考えなら、ぜひ一度、下記の資料をご覧ください。
Commune (コミューン) の詳しい情報が気になる方は、以下のフォームから資料をダウンロードしてください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
