コラム
マーケティング
顧客インサイトとは?見つけ方・分析手法・成功事例までわかる完全ガイド
2024/07/19
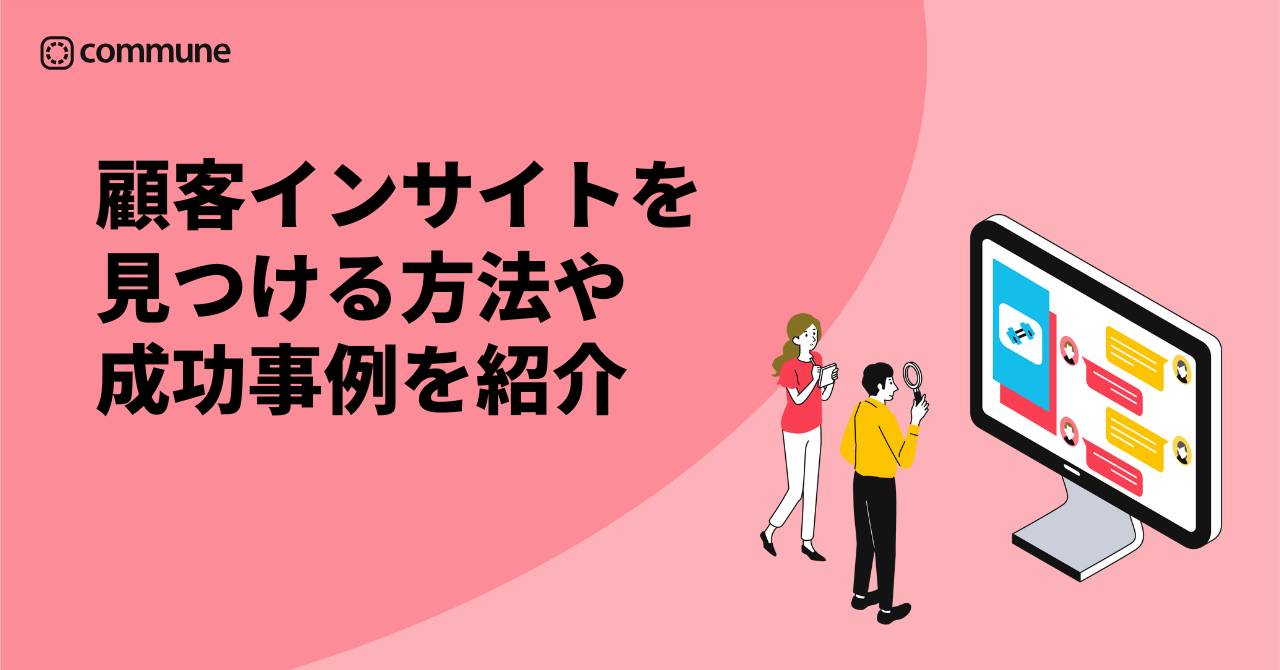
顧客インサイトとは、顧客自身もまだ言語化できていない「隠れた本音(深層動機)」のことです。これを捉えられれば、商品設計や訴求が“刺さる理由”が明確になり、価格や機能の差以上に強い購買動機をつくれます。
一方で、インサイトは待っていても見つかりません。仮説を立て、観察と検証を繰り返しながら、定性・定量データをつないで掘り起こす必要があります。
本記事では、顧客インサイトの定義から、発掘に使えるフレームワーク/手法、実務での落とし込み方、成功事例までを体系的に整理し、明日から再現できる手順として解説します。
顧客インサイト、事業成果につながってますか?
顧客インサイト、事業成果につながってますか?
- インサイトが施策単発で終わる
- 商品開発や改善の優先順位に使えない
- 部門間で顧客理解が共有されない
- LTV向上に結びつかない
Commune Voiceは、顧客の声を事業横断で共有できる分析基盤です。
インサイトをプロダクト改善、マーケティング、CSの判断に接続し、
売上・LTV向上につながるアクションを後押しします。
Commune Voiceは、顧客の声を事業横断で共有できる分析基盤です。
インサイトをプロダクト改善、マーケティング、CSの判断に接続し、
売上・LTV向上につながるアクションを後押しします。
目次
顧客インサイトとは
顧客インサイトの概要
「インサイト(Insight)」とは、文字どおり洞察を意味します。なかでも顧客インサイトは、顧客自身がまだ言語化できていない、つまり無自覚・潜在的な動機や心理を指します。
たとえば自社商品を購入した理由を尋ねても「たまたま目に入ったから」「なんとなく」 といった曖昧な答えしか返ってこないことがあります。これは表層的なニーズにすぎず、その背後には別の感情や行動原理が潜んでいるかもしれません。実際には「クッキーやパンを食べるとき、牛乳で喉を潤したい」という無意識の習慣が購入を後押ししていた――そんなケースも想定できます。
もしこのインサイトを掘り当てられれば、マーケティング施策は一段と鋭くなります。たとえば パン売り場に牛乳を並べる、あるいは 牛乳の広告に“相性の良い食べ物”の写真を添える といった展開が考えられるでしょう。こうした仕掛けは、顧客の潜在欲求をダイレクトに刺激し、購買行動を自然と導く強力なドライバーとなります。
顧客インサイトとニーズとの違い
-
ニーズ
顧客が自覚し、言語化できる「表層的な要望」。
例)「夜遅くまで開いているカフェが欲しい」 -
顧客インサイト
そのニーズを生み出す、無意識下の深層動機や心理。
例)「仕事終わりに、自分だけの時間と空間でリラックスしたい」
顧客はニーズを口にできますが、インサイトは自分でも気づいていないことが多く、丁寧な観察やデータ分析、インタビューを通して初めて浮かび上がります。インサイトを捉えれば、単なる要望への対応を超え、顧客の本質的価値を満たす提案が可能になります。
顧客インサイトが注目される理由
選択肢があふれる今、品質や価格だけでは競合と差がつきにくいのが現実です。そこで鍵になるのが、顧客自身がまだ気づいていない潜在ニーズを満たす体験づくり。インサイトを掘り起こし、商品開発やプロモーションに落とし込めば――
- 差別化の源泉になる
価格競争に巻き込まれず、独自価値で指名買いを促進。 - 感情に響く訴求ができる
顧客の“本音”に沿ったメッセージは、記憶に残り共感を生む。 - LTV(顧客生涯価値)が伸びる
隠れた欲求を継続的に満たせるブランドは、リピートと推奨を生みやすい。
このように、顧客インサイトの発見は売上・ブランドロイヤルティ双方のドライバーとなるため、マーケティングの最前線で注目を集めています。
顧客インサイトを活用するメリット
顧客インサイトを活用することができれば、集客力や売上の向上、新規需要の把握など、さまざまなメリットがあります。以下では、顧客インサイト活用のメリットを解説します。
集客力を高める
顧客の潜在欲求を捉え、それを製品設計やマーケティングに反映できれば、ブランドの認知度は自然と拡大します。インサイトにぴたりと響く商品・サービスは共感を呼びやすく、これまで届かなかった層にもリーチ可能です。その結果、流入チャネルが増え、集客力全体を底上げできます。
売上の向上
インサイトを起点にすれば、クロスセルやアップセルなど“顧客単価を高める施策”の設計精度が一気に向上します。顧客の深層動機に沿った提案は受け入れられやすく、追加購入や上位プランへの移行を自然に後押しできるからです。
近年は新規獲得コストの高騰を背景に、既存顧客からの売上比重が増大し、LTV(顧客生涯価値)の最大化がマーケティングの最優先テーマとなっています。インサイトドリブンの単価向上施策は、この潮流で最も強力なレバーと言えるでしょう。
新しい需要の把握
顧客インサイトを掘り当てれば、顧客自身も気づいていなかった欲求を満たす商品・サービスを創出できます。既存プロダクトのリニューアルやマーケティング施策の再設計にも活かせる上、競合のいない“ブルーオーシャン”を切り拓くことさえ可能です。
競合他社との差別化
顧客インサイトは表層ニーズとは違い、企業にとっても容易に掴めません。だからこそ、その深層心理を突き止めて潜在需要を満たす新商品・新サービスを創出できれば、競合が追随しにくい明確な差別化を築けます。
顧客との関係性構築
顧客の潜在ニーズを把握しておけば、一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションが取りやすくなります。インサイトに基づくメッセージは従来よりも的確に響き、より効果的なアプローチが可能です。その結果、顧客との関係性は一層深まり、長期的なロイヤルティの向上につながります。
顧客インサイトを見つける方法

顧客インサイトを発見するためには、データ収集・分析を行うことが必要です。こちらでは、顧客インサイトを見つける方法をステップ別にご紹介します。
データを収集する
顧客インサイトを掘り当てる第一歩は、綿密なデータ収集計画を立てることです。
表面的な要望を把握するだけであれば、オンラインアンケートで十分に対応できます。しかし、顧客自身も気づいていない深層心理を探るとなると、数値化しやすいアンケートだけでは力不足です。そのため、インタビューやソーシャルリスニングといった定性調査を組み合わせることが重要になります。
インタビューには複数人で意見を交わすグループインタビューと、一対一でじっくり深掘りするデプスインタビューがあります。前者は参加者同士の相互作用から思わぬ本音がこぼれ出ることが多く、後者は安心できる環境で個人の深い動機を詳しく語ってもらえる点が魅力です。いずれの手法でも、誘導質問を避けながら流れに応じて掘り下げられるように、質問項目を綿密に設計しておくことが欠かせません。
一方、SNSやレビューサイトの投稿を横断的に収集・分析するソーシャルリスニングは、ポジティブな賞賛だけでなくネガティブな本音も大量に集められるのが強みです。ただし、得られるデータが膨大になるため、テキストマイニングやキーワードフィルターを用いてノイズを適切に除外し、洞察につながる発言を抽出する工程が不可欠です。
このように、定量調査で仮説を立て、定性調査で裏付けを取るサイクルを回すことで、顧客の無意識下に隠れていた本当のニーズがようやく輪郭を現します。両者を組み合わせたデータ収集と分析を行うことで、インサイトに基づいた商品開発やマーケティング施策を実現し、競合に差をつけられるでしょう。
データを分析する
顧客インサイトを的確に抽出するには、インタビューやソーシャルリスニングで得た定性データと、アンケートや購買ログなどの定量データを組み合わせて分析することが欠かせません。
たとえば、インタビューで浮かび上がった自由回答を「年齢」「職業」「使用シーン」などの属性情報でグルーピングすれば、どの層に特有の深層欲求なのかを立体的に把握できます。両データを往復しながら仮説を磨き込むことで、表層の声だけでは見えなかった因果関係やトリガーが鮮明になります。
分析から得た示唆は、まずペルソナとして言語化すると効果的です。名前やライフスタイル、価値観まで踏み込んだ一人の「象徴的な顧客像」をチーム全員で共有すれば、施策立案の際に常に顧客視点へ立ち戻る指針になります。
さらに、ペルソナを補完する形で共感マップを作成すると、ターゲットが置かれた環境、日々見聞きしている情報、抱えている感情や思考プロセスが一枚のシートに整理され、深層心理のイメージがいっそう具体的になります。共感マップを見ながら議論すると、機能訴求だけでは届かなかった「感情的ベネフィット」や「潜在的な不安の払拭策」が自然と発想しやすくなるでしょう。
このように、定量データで傾向を捉え、定性データで解像度を高め、ペルソナと共感マップで共有する――という一連のプロセスを踏むことで、チーム全体が同じ顧客像を描きながら、インサイトドリブンの施策を一貫して推進できます。
発見した顧客インサイトを活用する
データの収集と分析を終えたら、次に取り組むべきは「顧客はなぜその行動を選んだのか」という動機の深掘りです。
分析結果と実際の行動が食い違う場面に出会うことも珍しくありませんが、まさにその矛盾こそがインサイトの手がかりになります。表面的な説明で済ませず、「どうしてアンケートではAと答えたのに、購入時にはBを選んだのか」と因果関係を突き詰めることで、顧客自身も気づいていない本質的な欲求が姿を現します。
インサイト活用の成功事例としては、ベースフード株式会社が運営するオンラインコミュニティ「BASE FOOD Labo」が挙げられます。同コミュニティではユーザーからの意見募集を常設し、寄せられた声をもとに新商品の開発や既存サービスの改良をスピーディーに実行しています。
顧客インサイトの事例2選
日本ケロッグ合同会社
日本ケロッグ合同会社はロングセラー商品「オールブラン」の顧客インサイトを獲得し、ロイヤルカスタマーを育成するためにオンラインコミュニティ「オールブラン腸活部」を開設しました。まずは約70名の限定メンバーだけでクローズドに運営を始め、商品への愛着が強いコアファン同士の質の高い投稿と活発な交流を促進することで、コミュニティの土台を築きました。その後、人気企画「オールブランすっきりチャレンジ」を実施したことで会員数は一気に500名へと拡大しました。
コミュニティ内ではメンバーが独自のレシピや食べ方の工夫を自然に共有し合い、企業側では想像できなかった活用アイデアが次々に誕生しています。たとえば「オールブランを生地に混ぜ込んだお好み焼き」など、ユニークなアレンジが顧客インサイトとして蓄積され、商品開発やマーケティングに生かされています。
その結果、メンバーの平均喫食回数は1.6倍に伸び、全5種類のうち3種類以上を購入する会員が44%に達するなど、買い回り率も大幅に向上しました。現在では会員数が約700名にまで増え、コミュニティを通じた継続的な対話が新たな商品価値の発見とロイヤルカスタマー化に確かな効果をもたらしていることが示されています。

*日本ケロッグ合同会社の事例インタビューをみる
喫食回数1.6倍!ロングセラー商品のコミュニティで実現する顧客インサイトの獲得とロイヤルカスタマー化
カルビー株式会社
カルビー株式会社は、認知度99%を誇る「かっぱえびせん」の新商品開発に向け、これまでの調査では捉えきれなかった顧客インサイトを探るためにオンラインコミュニティ「絶品部」を開設しました。
転機となったのは発売後に観測された“箱買い”や“30店を巡る品探し”といった予想外の購買行動です。この熱狂的なファンの存在が「より深い顧客理解が必要だ」という気づきを生み、コミュニティの本格運営へとつながりました。
「絶品部」では晩酌シーンを中心に活発な対話が行われ、社員と顧客がオンライン飲み会で打ち解けながら意見交換することで、通常の調査では得がたい率直なインサイトを継続的に収集できました。こうした対話の中から、商品の食べ方やアルコールとの組み合わせなど、多様な消費パターンが次々と明らかになっています。
2023年12月には、コミュニティメンバーから寄せられた50件を超える味のアイデアをもとに新商品を開発し、潜在ニーズを的確に捉えたラインアップの拡充に成功しました。さらに、このプロセスで得た深い顧客インサイトは既存の「かっぱえびせん」にも波及し、ブランド全体の魅力向上に寄与しています。継続的な対話でインサイトを掘り下げ、それを即座に商品に反映する取り組みが、熱狂的ファンの育成と市場での差別化を同時に実現した好例と言えるでしょう。

*カルビー株式会社の事例インタビューをみる
熱狂的なファンとオンラインで直接繋がる。商品の共創も実現した絶品かっぱえびせんのファンコミュニティ
顧客インサイトを活用して売上向上へつなげましょう
本記事では、顧客インサイトの基礎知識から活用メリット、具体的な発見手法までを解説してまいりました。顧客インサイトを的確に捉えれば、自社の強みを最大限に引き出したサービス設計やマーケティング施策が実現し、競合が追随しにくい独自価値を築けます。
そのためにはまず適切なデータを収集・分析し、顧客自身もまだ気づいていない隠れたニーズを掘り起こす姿勢が欠かせません。特にオンラインコミュニティを運営すると、日常の投稿や対話を通じて定性・定量の両面から豊富な洞察が得られ、インサイト発見のスピードと精度を大幅に高められます。
もしコミュニティ運営をご検討中でしたら、コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune(コミューン)」をご活用ください。下記フォームより、サービスの特徴を3分で把握できる資料を無料でダウンロードいただけますので、ぜひお気軽にお役立てください。
顧客インサイト、事業成果につながってますか?
顧客インサイト、事業成果につながってますか?
- インサイトが施策単発で終わる
- 商品開発や改善の優先順位に使えない
- 部門間で顧客理解が共有されない
- LTV向上に結びつかない
Commune Voiceは、顧客の声を事業横断で共有できる分析基盤です。
インサイトをプロダクト改善、マーケティング、CSの判断に接続し、
売上・LTV向上につながるアクションを後押しします。
Commune Voiceは、顧客の声を事業横断で共有できる分析基盤です。
インサイトをプロダクト改善、マーケティング、CSの判断に接続し、
売上・LTV向上につながるアクションを後押しします。
