コラム
マーケティング
カスタマーセントリックとは?あらゆる局面で「顧客を中心にする」戦略
2025/06/26
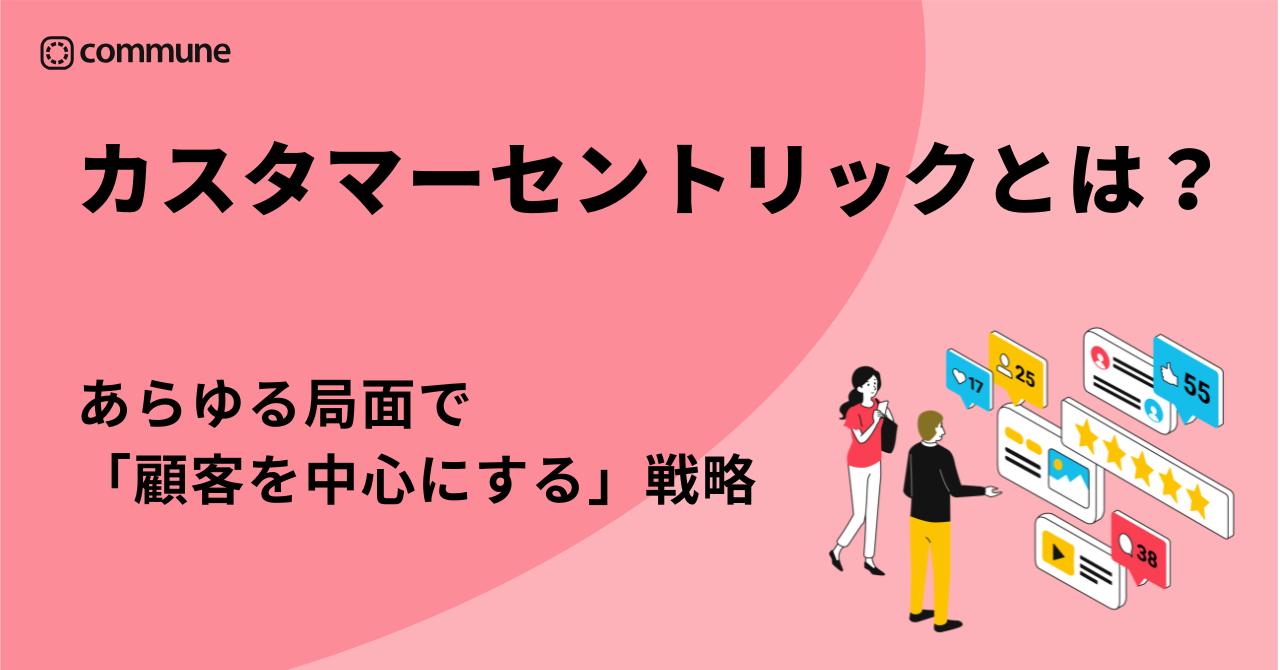
「良いものを作れば売れる」時代は終わりました。多くの企業が一定以上の高品質なプロダクト・サービスを出せる中、顧客から選ばれる企業はほんの一握り、という状況が生まれつつあります。顧客に選ばれるポイントとなる考え方の一つが、「カスタマーセントリック(顧客中心主義)」です。
顧客の声に耳を傾け、行動データを読み解き、企業の判断や施策をすべて顧客視点で構築していく。そうした姿勢が、選ばれ続けるブランドを育てます。本記事では、カスタマーセントリックの本質から導入ステップ、成功事例、運用のポイントまでをコンパクトに解説します。顧客中心文化を組織に根づかせるための実践的ガイドです。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
- 第4章 顧客中心経営を実現するための4ステップ・ロードマップ
- ステップ1:顧客理解の徹底
- ステップ2:価値仮説の設計とパーソナライズ施策
- ステップ3:全社連携と“瞬発力のある”組織づくり
- ステップ4:成果の可視化とPDCAの高速回転
- 実装時の注意点(2つの落とし穴を避ける)
第1章 カスタマーセントリックとは?
カスタマーセントリックとは、ひと言でいうと「お客様のことを一番に考えて、すべての判断を行う経営の考え方」です。
もちろん「お客様の言うことを何でも聞く」とか「丁寧な接客をすること」ではありません。本当に大切なのは、「お客様が成功することが、会社の成功につながる」と考える視点です。お客様の目標達成を最大限にサポートできれば、契約更新や追加購入、良い口コミなど、会社の売上も自然に増えていきます。
例えばAmazonはプライム会員の便利さをとことん追求することで、お客様からの信頼を得て、結果として顧客生涯価値(LTV)を大きく伸ばしました。Netflixは視聴データをAIで分析し、「次に見たい作品」をおすすめする機能で、お客様の継続利用率を劇的に高めました。
この2社に共通しているのは、「お客様が何を求めているかを先読みして、困りごとを解決する」というアプローチです。表面的な「お客様第一」ではなく、お客様の時間やお金、心理的な負担を減らすための工夫が、会社全体に深く根付いている点が重要です。
知っておきたい3つの考え方
- プロダクトセントリック:
良い商品を作ることに力を入れる考え方。昔はこれでうまくいきましたが、今は似たような商品が多く、差別化が難しくなっています。 - マーケットセントリック:
市場の大きさや競合の状況から戦略を考える考え方。お客様“全体”を見るので、一人ひとりのお客様の視点が薄くなりがちです。 - カスタマーセントリック:
特定のお客様を深く理解し、そのお客様の体験を常に良くしていく考え方。お客様の成功を会社の目標(KPI)に直接つなげる点が大きく違います。
カスタマーセントリックは、マーケティング部門だけのものではありません。開発、営業、サポート、事務など、すべての部署の人が「お客様の一日」を想像し、お客様の満足度を高めるために自分の役割を見直すこと。ここから会社の改革が始まります。
第2章 “いま”不可欠な3つの環境変化
カスタマーセントリックがなぜ今必要とされているのか。それは、テクノロジーと社会の大きな変化が背景にあります。
①情報の非対称性が崩壊したこと
インターネットやSNS、レビューサイトの普及により、顧客は商品やサービスを「買う前に使った人」の体験談を簡単に知ることができるようになりました。企業が発信する情報だけでなく、利用者のリアルな声(UGC)が重視されるため、良いものでなければすぐに淘汰されてしまいます。
②サブスクリプション経済の台頭
SaaS(ソフトウェアの月額利用)やD2C(メーカー直販)のようなサブスクリプションモデルでは、一度売って終わりではありません。顧客に長く使い続けてもらうことが利益の源泉です。そのため契約後の顧客体験が非常に重要で、解約率が少し変わるだけで会社の収益に大きな影響が出ます。顧客中心の経営は、サブスク企業にとって「やらない選択肢はない」前提条件なのです。
③人口減少と成熟市場
日本では少子高齢化が進み、新しい顧客の獲得が難しくなっています。既存の顧客との関係を深め、生涯にわたって利用してもらう「LTV(顧客生涯価値)の最大化」が不可欠です。また、デジタル化が進み、製品や価格、販売方法で差別化がしにくい時代では、「体験そのものの価値」が他社との違いを生み出す重要な要素になります。
顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じた瞬間に、そのブランドに強い愛着を抱きます。逆に、少しでも不満があると、企業に伝えることなく「静かに去っていく」ことも少なくありません。不満をX(旧Twitter)に投稿され、それが炎上して顧客離れが加速するケースも後を絶ちません。企業の評判を守るためにも、顧客と継続的に対話する「顧客中心」の姿勢は避けて通れないものとなりました。
マーケティング担当者が直面する課題
- 短期的な売上(ROI)を求められる一方で、顧客体験(CX)は中長期で効果が出るため、投資の必要性を説明しにくい。
- 部署ごとに顧客データがバラバラに管理され、顧客全体の姿が見えにくい。
- 顧客一人ひとりに合わせた施策(パーソナライズ)を行うためのデータ基盤や専門知識を持った人材が足りないことが多い。
- 「顧客の声(Voice of customer)」は集まるものの、それを実際の現場の業務に活かす仕組みが弱い。
これらの課題を乗り越えるには、経営層の強いコミットメントと、成果を測るための明確な指標(KPI)、そして部署間での一貫した情報共有が不可欠です。次章からは、具体的なメリットと対策について詳しく見ていきます。
第3章 顧客と企業が共に伸びる4つの成果指標
カスタマーセントリックを単なる「考え方」で終わらせず、実際のビジネス成果につなげるには、具体的な数字で測ることが大切です。主なメリットは、以下の4つにまとめることができます。
- 解約率(チャーンレート)の低下
SaaS企業Gainsightの調査によると、カスタマーセントリックを導入した企業では、年間の解約率が平均15%改善したと報告されています。例えば、毎月1,000万円の売上がある企業なら、年間で1,800万円もの売上損失を削減できる計算になります。 - LTV(顧客生涯価値)の向上
顧客一人ひとりに合わせた施策(パーソナライズ)により、より高い商品やサービスを購入してもらう(アップセル・クロスセル)確率が上がります。これにより、顧客一人あたりの購入単価が向上します。Shopify Plusの事例では、顧客中心のリテンション施策によって、平均注文額が14%増加したとされています。 - NPS(顧客推奨度)の向上と口コミの拡散
Retail Diveの分析によると、NPSが10ポイント上がると、Google検索などからの自然なアクセスが平均20%増加すると言われています。顧客が自ら商品やサービスを広めてくれる(UGC:ユーザー生成コンテンツ)ことで、広告費を大幅に削減できる良い循環が生まれます。 - 開発期間の短縮と無駄なコストの削減
顧客からのフィードバックがすぐに製品の改善に活かされるため、必要のない機能開発に時間や資源を浪費することがありません。結果として、製品を市場に出すまでの期間が短くなり、競合よりも早く「顧客が本当に求めているもの」を提供できるようになります。
これらの成果は、それぞれがバラバラに現れるのではなく、互いに影響し合いながら会社の利益率を底上げします。解約率が下がれば固定費の割合も下がり、そこで生まれた余裕をさらに顧客体験の改善に再投資する――この好循環が、企業の持続的な成長を支える原動力となるのです。
第4章 顧客中心経営を実現するための4ステップ・ロードマップ
「顧客中心でいこう!」というスローガンは多くの企業で掲げられますが、実際にはデータ基盤や現場の意思決定権限が整わず、形骸化してしまうケースが少なくありません。ここでは、顧客中心の取り組みを組織にしっかりと定着させるための4段階の実行ステップを紹介します。
ステップ1:顧客理解の徹底
まずは、顧客の「声」と「行動」の両方をしっかり捉えることから始めます。定量的なデータとしては、NPSやCSAT(顧客満足度スコア)といった顧客満足度を測る指標や、購買履歴、サイトでの行動履歴を継続的に観察し、傾向を分析します。定性的なデータとしては、ユーザーインタビューやアンケート調査を通じて、顧客がどのような気持ちでサービスを利用しているかをジャーニーマップなどで分かりやすく示します。
こうした両方のデータを使うことで、感覚的な印象ではなく、根拠に基づいた洞察として顧客の課題を深く理解できます。
ステップ2:価値仮説の設計とパーソナライズ施策
次に、理解した顧客像ごとに「この顧客層にはどんな価値を提供できるか(UVP:独自の価値提案)」を明確に設計します。
その上で、MA(マーケティングオートメーション)やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)といったツールを活用し、一人ひとりに合わせた最適なメッセージ、特別なオファー、使いやすい画面表示を自動的に届けます。
この段階で特に重要なのが、ABテストを当たり前に行う文化を根付かせることです。仮説を素早く試し、結果から学び、改善するという高速な検証サイクルを回せるかどうかが、成果を大きく左右します。
ステップ3:全社連携と“瞬発力のある”組織づくり
本格的な運用に向けては、部署を横断したCX(カスタマーエクスペリエンス)委員会を設置し、目標達成度を示すKPIや顧客の声を組織全体でオープンに共有します。
また、特に重要なのは現場の従業員に即座に判断・実行できる権限を与えることです。たとえばリッツ・カールトンでは、従業員一人ひとりに顧客の問題解決のために使える一定額の予算が与えられており、顧客を「あっ」と驚かせるような体験をその場で提供できる仕組みになっています。こうした文化があるかどうかで、顧客体験の質は大きく変わってきます。
ステップ4:成果の可視化とPDCAの高速回転
最後に、実行した施策の効果をきちんと測定し、継続的に改善していく文化を根付かせます。ダッシュボードを使って目標と現在の実績をチーム全体で共有し、毎週のように改善のためのアイデアを話し合う場を設けましょう。
具体的には、「顧客がなぜ解約したのかをヒアリングする → 必要な機能を追加する → もう一度アプローチする」という流れを素早く繰り返すことで、製品やサービス、そして顧客体験が常に進化し続ける状態を作り出すことができます。
実装時の注意点(2つの落とし穴を避ける)
- 「何を知りたいか」を先に決め、データ収集はその後にする:
「どんな情報が欲しいのか」を明確にすることで、不要なデータの収集や分析に時間を費やすのを避けられます。 - 小さな成功を、素早く共有する:
社内で「こんなにうまくいったよ!」という小さな成功事例を積極的に共有し、仲間を巻き込むことで、変革への動きが会社全体に広がっていきます。
この4段階の実行ロードマップを、感覚に頼るのではなく仕組みとして回せるようになったとき、企業は初めて“顧客中心”という目標を、具体的な行動と確かな成果に結びつけることができるのです。
第5章 カルチャーを変える──トップの覚悟と現場のエンパワーメント
●カスタマーセントリックは「文化」である
「カスタマーセントリック(顧客中心主義)」は、単にツールや施策を入れるだけでは実現できません。それは、会社に深く根付いた文化そのものです。
導入を成功させている企業には、共通点があります。それは、社長をはじめとする経営層が、自ら“顧客の代弁者”として行動していることです。
たとえば、スターバックスの元CEOであるハワード・シュルツは、店舗に行くたびに顧客の行動を細かく観察し、店員と直接話していたことで知られています。彼の「見る」「聞く」「語る」という行動は、言葉以上に強い影響力を持ち、現場に「自分の判断で顧客を笑顔にしていいんだ」という安心感を生みました。こうして、文化としての顧客中心主義が育っていくのです。
●ストーリーが文化をつくる
文化を変える上で、特に効果的なのがストーリーテリング(物語を語ること)の活用です。たとえば、顧客との感動的なやり取りを社内SNSや会議で共有し、「なぜそれが会社の価値につながったのか」をみんなで話し合い、明確にする。こうした体験の共有が、会社全体の価値観を広げるきっかけになります。
さらに、成功事例を褒め合う文化を社内に定着させれば、“良い行動”が広がる速度も上がります。
●評価制度で文化を補強する
加えて、人事評価の仕組みもカスタマーセントリックを支える重要な要素です。たとえば米国のオンライン小売企業Zapposでは、カスタマーサポート担当者の評価基準を「通話時間」ではなく、「問題解決率」や「顧客からの満足コメント」に置いています。長い時間の通話でも、顧客が喜べば評価が高まる仕組みです。
このように、どの数字を目標にするかによって、会社の行動原理そのものが変わるのです。つまり、「文化はKPI(重要業績評価指標)がつくる」と言っても良いでしょう。
●失敗に寛容な環境が、CXを進化させる
そして最後に重要なのは、失敗を許容する会社の雰囲気作りです。顧客体験の改善は、試行錯誤の繰り返しです。全ての施策がうまくいくわけではありません。しかし、心理的な安心感がなければ、従業員は“失敗しないこと”ばかりを優先し、平均的なサービスにとどまってしまいます。
Googleの「プロジェクト・アリストテレス」でも明らかになったように、チームの創造性と成果を高める鍵は、心理的な安心感にあります。失敗談も成功と同じくらい価値ある学びとして受け止める雰囲気が、顧客体験の革新を生み出すのです。
カスタマーセントリックを実現するためには、「顧客第一」というスローガンだけでなく、経営者の行動・ストーリーの共有・評価制度・失敗への寛容さといった“文化を支える仕組み”のすべてが必要です。
それらが重なり合ってはじめて、従業員は自ら「どうすれば顧客が喜ぶか」を考え、行動し、会社全体が顧客のために動くエンジンへと変わっていくのです。
第6章 国内外の先進事例──成功パターンと学びの抽出
マクドナルド:データ×現場オペレーションで“待ち時間ゼロ”へ
マクドナルドでは、モバイルオーダーを利用するお客様の最大の不満が「商品受け取りまでの待機時間」でした。この課題を解決するため、店舗アプリに「受取予定時刻の選択機能」を導入。さらに、店頭に設置されたキオスク端末をセンサーと連携させることで、注文から商品提供までのプロセスを飛躍的に効率化しました。
お客様の「時間価値」に焦点を当てたこの取り組みにより、NPS(顧客推奨度)はグローバル平均を8ポイントも上回る結果となりました。
Spotify:文脈に入り込むパーソナライズ
音楽ストリーミングサービスSpotifyの楽曲レコメンド機能の精度向上は、今や広く知られています。しかし、Spotifyの顧客理解は単なる音楽の嗜好に留まりません。
「雨の日に聴きたいプレイリスト」や「集中して作業できるBPM(拍子)の楽曲」など、ユーザーの具体的な生活シーンや気分に合わせた提案を行うことで、利用者の「自分の気分をわかってくれる」という感覚を醸成しました。これにより、1人あたりの聴取時間が増加し、広告接触機会の最大化とサブスクリプション継続率の向上に繋がっています。
Sansan:名刺データから“顧客を連れてくる”プロダクトアウトカム
法人向けクラウド名刺管理サービスを提供するSansanは、「人脈を活かした営業活動を効率化したい」という顧客からの声を出発点に、接点レコメンド機能を開発しました。
この機能は、顧客が具体的な商談を獲得できるという「成果」に直接貢献することを目指して設計されています。その結果、Sansanは単なる業務効率化のためのSaaSという位置付けから、「売上創出ソリューション」へとそのポジショニングを進化させ、顧客のビジネス成果に直結する価値を提供しています。
帝国ホテル:権限移譲で“一期一会の感動”を創出
帝国ホテルでは、お客様に忘れられない感動体験を提供するため、従業員一人ひとりに「2万円までの決裁権」を与えています。これにより、お客様の誕生日や記念日といった特別な日には、サプライズ演出などをその場で即座に決定・実行することが可能です。
現場の裁量を大幅に高めた結果、宿泊予約サイトでの「また来たい」という意向率は、業界平均を大きく上回る数値を記録しており、きめ細やかな顧客サービスがリピート率向上に貢献しています。
成功企業に共通するポイント
- 顧客の“時間”を削減し、体験を軽量化している:
顧客の待ち時間をなくしたり、操作の手間を省いたりすることで、よりスムーズでストレスフリーな顧客体験を提供しています。 - データ→洞察→即実装のサイクルが高速:
顧客の行動データを分析し、そこから得られた洞察に基づき、迅速にサービスや機能を改善・導入することで、常に顧客ニーズに対応しています。 - 現場に裁量と失敗許容の文化がある:
顧客と直接接する現場の従業員に適切な権限を与え、たとえ小さな失敗があってもそれを許容する文化があることで、主体的な顧客サービスや改善提案が生まれています。 - 成果を顧客のKPIで語れる(例:商談獲得数、作業効率 etc.):
自社の製品やサービスが、顧客のビジネス目標(KPI)に具体的にどのように貢献しているかを明確に示せることで、顧客からの信頼と継続的な利用に繋がっています。
これらの事例は業界を問わず応用可能です。成功のポイントは「顧客の生活や業務プロセスをどこまで深く理解し、自社のサービスに内面化できるか」に尽きます。自社でこれらの成功モデルを再現する際は、机上の空論で終わらせず、顧客調査と小規模な実証実験を並行して進める「ラーニングループ」の設計が、成功の鍵を握るでしょう。
第7章 効果測定と継続改善──数字で語り、体験を磨き続ける
カスタマーセントリックの醍醐味は、顧客価値と企業価値が同時に成長する点にあります。ただし「やりっぱなし」では成果が可視化されず、社内投資が続きません。本章では計測フレームと長期PDCAの回し方を整理します。
まずKPI設計は「顧客の成功指標」と「企業の収益指標」をワンセットで並べるのが鉄則です。例えばBtoCサブスクなら「平均連続視聴時間」「解約率」、BtoB SaaSなら「機能利用率」「契約更新率」など、顧客の成果が数字に現れるメトリクスを選定します。その上で次の4種はほぼ全業態に有効です。
- NPS(ネットプロモータースコア):
推奨意向を-100〜+100で測定。顧客エンゲージメントの総合指標。 - CSAT(顧客満足度):
タッチポイントごとの体験を10点満点などで評価。局所改善に最適。 - チャーンレート/リテンションレート:
継続率の推移をウォッチし、施策と因果関係を確認。 - LTV(顧客生涯価値):
購入頻度×平均単価×継続期間で算出。経営インパクトを株主へ示す際に必須。
数値化したら、データドリブンなアクションに即つなげるフローが重要です。たとえばSlack連携でNPS低評価コメントが投稿された瞬間に担当者とプロダクトマネージャーへアラートを飛ばし、48時間以内にフォローアップを実施。改善内容と効果をノーションなどで共有し、ナレッジ資産化します。
さらに、OKRやノーススター指標と統合することで全社が同じ旗を見て走れる状態を作ります。Airbnbは「予約完了率」をノーススターと定め、部門横断で体験改善に集中した結果、わずか1年で取扱額を2倍に伸ばしました。
改善を持続させるヒント
- KPIは“減点方式”ではなく“成長指標”として共有し、挑戦を促す
- ダッシュボードは誰でもアクセス可能にし、透明性を担保
- 四半期単位で“顧客ストーリー”を経営会議に持ち込み、数字と感情の両面で議論
最後に強調したいのは、カスタマーセントリックが「終わりなき旅」であることです。顧客の期待値は常に上書きされるため、昨日のベストプラクティスが明日の当たり前になります。数字で現状を照らし、学習を止めない限り、貴社は顧客と共に成長し続ける企業へと確実に進化できるでしょう。
終わりに
本ガイドでは、カスタマーセントリックに真摯に向き合い、その裏に潜む「課題を解決したい」という切実な願いに応えるべく、カスタマーセントリックの概念、その重要性が高まる背景、具体的なメリットから、実践に向けたステップ、企業文化の変革の重要性、成功事例、そして効果測定のためのKPI運用に至るまで、多角的に解説しました。
ぜひ、本日より「顧客の真の代理人」として、カスタマーセントリックへの第一歩を踏み出してください。
あわせて読みたい
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
