コラム
マーケティング
カスタマージャーニーの作り方|7つのステップで顧客理解を深め、成果を最大化する完全ガイド
2025/07/29
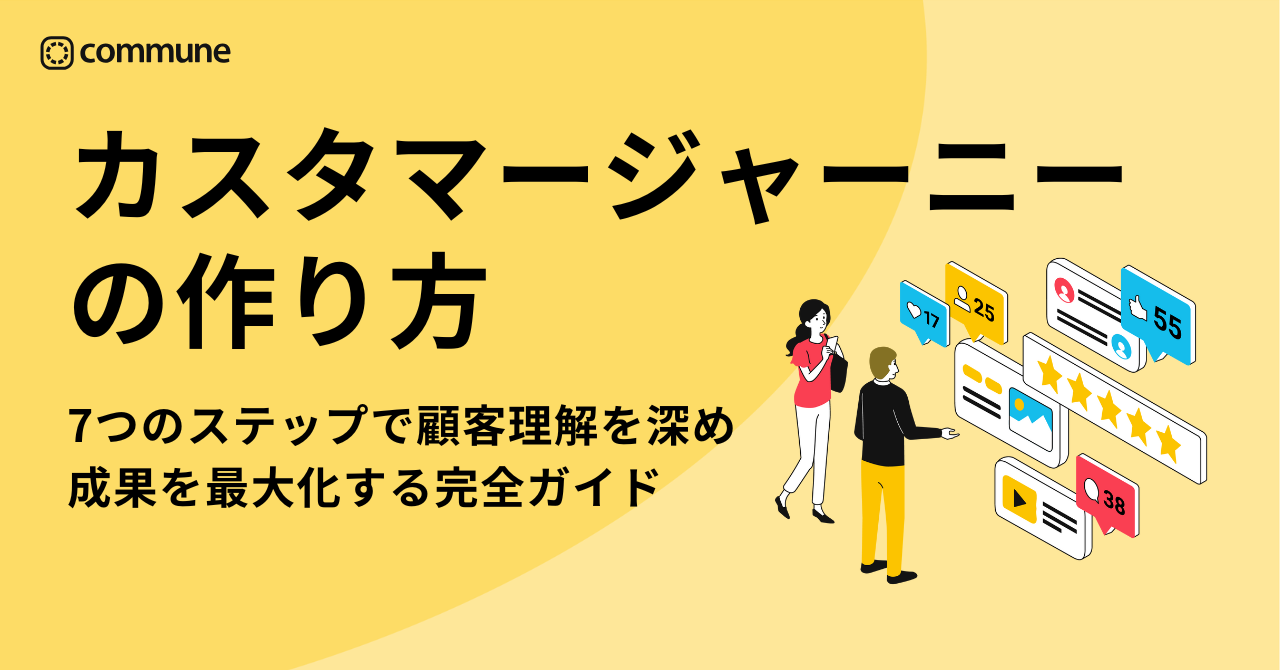
「顧客の行動が多様化し、従来のマーケティング施策が効きづらくなった」「データは集めているが、どう顧客理解に繋げればいいか分からない」といった課題に直面しているマーケターの方は、多いのではないでしょうか。
世界のカスタマージャーニー分析市場は、2033年までに年平均14.8%で成長すると予測されており(imarcgroup.com)、これは多くの企業が「顧客を点ではなく線で捉える」ことの重要性に気づき、投資を本格化している証拠です。顧客の購買プロセスの約70%が、営業担当者と接触する前にオンラインで完了しているというデータ(openpage.jp)も、この潮流を裏付けています。
つまり、企業が顧客に選ばれるためには、「売り込む」前に「理解し、寄り添う」ことが不可欠な時代なのです。本稿は、そうした変化に対応し、顧客中心のマーケティングを実践したい方のために構成された網羅的なガイドです。カスタマージャーニーとは何か、という本質的な問いから、具体的な作り方、BtoB・BtoCの成功事例、そして「作っただけ」で終わらせないための注意点までを、国内外の最新データと事例をもとに解説します。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
- 第2章 なぜ今、カスタマージャーニーが必要なのか?―顧客主導時代への転換
- ① 購買行動のデジタルシフトと複雑化
- ② 「所有」から「利用」へ―サブスクリプションモデルの浸透
- ③ パーソナライゼーションへの期待の高まり
- 第3章 経営指標で語るメリット―LTV向上とCAC削減の科学
- ① 顧客LTV(生涯顧客価値):最大25%向上
- ② 顧客獲得コスト(CAC):平均15-20%削減
- ③ 顧客満足度とNPS®(推奨度):10ポイント以上改善
- 第4章 潜むリスクと克服戦略―「作っただけ」で終わらせないために
- ① リスク:社内の思い込みだけで作ってしまう
- ② リスク:ペルソナが曖昧で、誰の旅か分からない
- ③ リスク:一度作って満足し、更新されない
- ④ リスク:部門間の連携がなく、施策が分断される
第1章 カスタマージャーニーとは?その定義と本質
カスタマージャーニーとは、顧客が商品を認知し、興味を持ち、購入し、最終的にファンになるまでの一連の「体験の旅」を指します。そして、この旅を可視化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。最大の特徴は、企業目線の「売り方」ではなく、顧客目線の「購買プロセス」に焦点を当てる点にあります。
このアプローチの目的は、顧客が各段階で何を考え、何を感じ、どのような行動を取るかを深く理解し、それぞれの接点(タッチポイント)で最適な体験を提供することです。
顧客体験を「点」ではなく「線」で捉える
従来のマーケティングは、広告、営業、サポートといった各接点を個別に最適化する「点」のアプローチが主流でした。しかし、顧客にとってはそれらすべてが、その企業との一連の体験、つまり「線」です。例えば、魅力的な広告を見てサイトを訪れても、情報が分かりにくければ離脱します。素晴らしい製品を購入しても、サポートの対応が悪ければ二度と買わないでしょう。
カスタマージャーニーは、こうした分断された顧客体験を統合し、一貫した価値提供を目指すための思考フレームワークなのです。
よくある誤解:「セールスファネル」との違い
カスタマージャーニーは、しばしば「セールスファネル」と混同されますが、両者は視点が根本的に異なります。
| 項目 | カスタマージャーニー | セールスファネル |
| 視点 | 顧客視点(顧客の感情や思考が中心) | 企業視点(いかに購入に導くかが中心) |
| 形状 | 複雑なループ型(行ったり来たりする) | 線形(上から下への一方通行) |
| 焦点 | 顧客体験の全体最適化 | コンバージョン率の最大化 |
| 目的 | 顧客との長期的な関係構築(LTV向上) | 短期的な売上獲得 |
ファネルが「いかに顧客を絞り込むか」を考えるのに対し、ジャーニーは「いかに顧客の旅を快適にし、ファンになってもらうか」を考えるアプローチであり、現代のLTV(顧客生涯価値)を重視するビジネスモデルに不可欠な考え方と言えます。
第2章 なぜ今、カスタマージャーニーが必要なのか?―顧客主導時代への転換
多くの先進的な企業がカスタマージャーニーの作成に取り組む背景には、無視できない3つの市場環境の変化があります。
① 購買行動のデジタルシフトと複雑化
スマートフォンの普及により、顧客はいつでもどこでも情報を収集し、比較検討できるようになりました。BtoBの購買担当者の70%以上が営業担当者に会う前にリサーチを終えている(Forrester調査)という事実は、もはや「営業が会ってからが勝負」ではないことを示しています。
SNS、レビューサイト、ブログ、動画など、顧客が触れる情報は爆発的に増加し、その購買プロセスは直線的ではなく、行ったり来たりを繰り返す複雑なものになっています。この複雑な「旅」を理解せずして、適切なアプローチは不可能です。
② 「所有」から「利用」へ―サブスクリプションモデルの浸透
SaaSビジネスに代表されるサブスクリプションモデルの普及は、「一度売って終わり」のビジネスを過去のものにしました。重要なのは、契約後の顧客体験を向上させ、継続的に利用してもらうことです。
実際、既存顧客の維持コストは新規顧客の獲得コストの5分の1で済む(Bain & Company調査)とされており、解約率(チャーンレート)の抑制が事業成長の生命線となります。カスタマージャーニーを通じて契約後の顧客体験を丹念に分析し、改善し続けることが、LTVを最大化する上で不可欠なのです。
③ パーソナライゼーションへの期待の高まり
顧客は、自分を一人の個人として認識し、最適化された体験を提供してくれる企業を好みます。Salesforceの調査によれば、消費者の73%が、企業が自分のニーズや期待を理解してくれることを期待しています。画一的なメッセージングはもはや響かず、顧客がジャーニーのどの段階にいるのかを正確に把握し、「あなたにぴったりの情報はこれです」と提示できる企業だけが、顧客の信頼を勝ち取ることができるのです。
これらの変化は、企業に対して「顧客を深く、正しく理解すること」をこれまで以上に強く要求しています。カスタマージャーニーの作成は、この要求に応えるための最も効果的な手段の一つなのです。
第3章 経営指標で語るメリット―LTV向上とCAC削減の科学
カスタマージャーニーの作成は、単なる「顧客理解のための活動」ではありません。LTV(顧客生涯価値)やCAC(顧客獲得コスト)といった経営指標に直接的なインパクトを与える、極めてROIの高い投資です。
① 顧客LTV(生涯顧客価値):最大25%向上
Aberdeen Groupの調査によると、カスタマージャーニー戦略を実践している企業は、そうでない企業に比べ、顧客からの平均収益が年間で25%も高いという結果が出ています。これは、ジャーニーの各段階で顧客の課題を先回りして解決し、満足度を高めることで、アップセルやクロスセル、そして長期的な契約継続に繋がるためです。顧客の成功を支援することが、自社の収益に直結するのです。
② 顧客獲得コスト(CAC):平均15-20%削減
顧客がどのような情報を求めて購買に至るのかを正確に把握できれば、マーケティングや広告の費用を最適化できます。例えば、「導入事例」を求めている検討後期の顧客に、認知拡大目的の広告を打つのは非効率です。ジャーニーに基づいて適切なコンテンツを適切なタイミングで提供することで、無駄な広告費を削減し、より質の高いリードを効率的に獲得できます。結果として、CACを平均で15〜20%削減できる可能性があります。
③ 顧客満足度とNPS®(推奨度):10ポイント以上改善
顧客の感情やペインポイント(不満・悩み)を可視化し、それを取り除く施策を実行することで、顧客満足度は劇的に向上します。McKinseyのレポートでは、カスタマージャーニーを最適化した企業は、顧客満足度を20%向上させ、従業員のエンゲージメントも30%高めたと報告されています。満足した顧客は、知人や同僚にサービスを推奨する「推奨者」となり、NPS®(ネット・プロモーター・スコア)の向上にも大きく貢献します。
第4章 潜むリスクと克服戦略―「作っただけ」で終わらせないために
多くの企業がカスタマージャーニーの重要性を認識しつつも、その活用に失敗しています。ここでは、よくある4つの落とし穴と、それを乗り越えるための戦略を解説します。
① リスク:社内の思い込みだけで作ってしまう
課題: 顧客へのヒアリングやデータ分析を怠り、担当者の「きっとこうだろう」という憶測だけでマップを作成してしまうケース。これは最も多い失敗パターンであり、現実の顧客像とかけ離れた、役に立たない地図が出来上がってしまいます。
✅ 克服戦略:
- 定性・定量データの両方を活用する: 顧客アンケート、インタビュー、NPS調査などの「声(定性)」と、Webサイトのアクセス解析、購買データ、CRMの活動履歴などの「行動(定量)」を必ず組み合わせます。
- 顧客接点を持つ全部門を巻き込む: マーケティングだけでなく、営業、カスタマーサポート、開発など、実際に顧客と接する部門の担当者を集めたワークショップ形式で作成し、多角的な視点を取り入れます。
② リスク:ペルソナが曖昧で、誰の旅か分からない
課題: ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)が曖昧なままジャーニーを描こうとすると、感情や思考に具体性がなく、当たり障りのない内容になってしまいます。
✅ 克服戦略:
- 実在の顧客をベースにペルソナを作成する: 理想的な優良顧客や、典型的な問い合わせをくれる顧客など、実在の人物をモデルにペルソナを詳細に設定します。詳細は関連記事「ペルソナ設定の具体的な方法」もご参照ください。
- ジャーニーはペルソナごとに作成する: 新規顧客と既存顧客、情報システム部門の担当者と経営者では、旅の道のりは全く異なります。主要なペルソナごとに別のジャーニーマップを作成することが重要です。
③ リスク:一度作って満足し、更新されない
課題: 時間をかけて立派なマップを作成し、壁に貼って満足してしまうケース。市場や顧客の行動は常に変化するため、マップもまた「生き物」として捉え、定期的に見直す必要があります。
✅ 克服戦略:
- KPIと連動させ、定期的な見直し会議を設定する: 四半期に一度など、マップ上の各ステージに対応するKPI(例:認知段階のWebサイト流入数、検討段階の資料DL数)の進捗を確認し、マップを更新する会議を定例化します。
- マップを「業務のOS」として活用する: 新規施策を企画する際は、「この施策はジャーニーのどの段階の、誰の、どんな課題を解決するものか?」を必ず問う文化を醸成します。
④ リスク:部門間の連携がなく、施策が分断される
課題: マーケティング部が作ったマップを営業部やサポート部が知らないため、結局は各部門がバラバラの顧客対応をしてしまい、一貫した体験を提供できないケース。
✅ 克服戦略:
- 全社でアクセスできる場所にマップを保管・共有する: クラウドストレージや社内Wikiなど、誰もがいつでも参照できる場所にマップを保管します。
- ジャーニーに基づいた部門横断プロジェクトを立ち上げる: 例えば「検討段階の顧客体験向上プロジェクト」といったテーマで、マーケ、営業、CSが連携するチームを組成し、共通の目標に向かって施策を実行します。
第5章 国内外の成功事例と数字―BtoB・BtoCに学ぶ「勝ち筋」
理論だけでなく、実際にカスタマージャーニーを活用して成果を上げている企業の事例を見ていきましょう。BtoCとBtoB、それぞれの領域で成功している企業の「勝ち筋」を分析します。
✅ 事例1:スターバックス(BtoC・飲食)
スターバックスは、単にコーヒーを売るのではなく、「サードプレイス(家庭でも職場でもない、第3の心地よい場所)」という体験を提供することに長けています。同社は顧客のジャーニーを「来店前」「来店中」「退店後」に分け、それぞれの体験を緻密に設計しています。
- 来店前: モバイルアプリで新商品の情報を届け、事前注文・決済を可能にすることで、行列に並ぶストレスをなくす。
- 来店中: Wi-Fiや電源を完備し、居心地の良い空間を演出。バリスタが顧客の名前を呼んで商品を渡すなど、パーソナルな接客を徹底。
- 退店後: アプリを通じてリワード(ポイント)を付与し、アンケートでフィードバックを収集。次の来店動機を創出する。
成果: この一貫した体験設計により、スターバックスはロイヤルティの高い顧客層を確立。モバイルアプリ経由の売上は、米国全体の売上の25%以上を占めるまでに成長し、顧客との継続的な関係構築に成功しています。(出典: Starbucks 公式発表)
✅ 事例2:Salesforce(BtoB・SaaS)
世界的なCRM/SaaS企業であるSalesforceは、BtoBにおけるカスタマージャーニー活用の模範例です。彼らは見込み客のジャーニーを詳細に分析し、各段階に合わせた膨大なコンテンツを用意しています。
- 認知・学習段階: 「CRMとは何か?」といった基本的な知識を提供するブログ記事やeBook。
- 比較・検討段階: 競合製品との比較資料、導入企業の成功事例(ケーススタディ)、無料トライアル。
- 導入・活用段階: 使い方を解説するオンラインヘルプ「Trailhead」、ユーザー同士が交流するコミュニティ、定期的な活用ウェビナー。
成果: このコンテンツ戦略により、営業担当者が接触する前段階で、見込み客は自ら課題を認識し、解決策としてのSalesforceへの理解を深めています。これにより、商談化率が大幅に向上し、営業効率が劇的に改善。同社が業界のリーダーであり続ける大きな要因となっています。
第6章 導入ロードマップと組織デザイン―顧客中心経営を実現する4ステップ
「顧客中心」というスローガンを形骸化させず、組織に根付かせるためには、体系的なロードマップが必要です。ここでは、カスタマージャーニー作成を軸とした顧客中心経営への変革を、4つのステップで解説します。
ステップ1:目的定義とスコープ設定
まず、「何のためにカスタマージャーニーマップを作るのか」という目的を明確にします。「新規顧客獲得プロセスの改善」「既存顧客の解約率低下」など、具体的なビジネス課題と結びつけることが重要です。次に、どのペルソナの、どの期間(例:認知から初回購入まで)のジャーニーを描くのか、スコープ(対象範囲)を定めます。最初から完璧な全体像を目指すのではなく、最も課題の大きい部分から着手するのが成功の鍵です。
ステップ2:情報収集とペルソナ・ジャーニー骨子作成
次に、定義したスコープに基づき、顧客に関する情報を徹底的に収集します。アクセス解析、CRMデータ、アンケート、顧客インタビューなど、定量的・定性的なデータを集め、分析します。この情報をもとに、具体的なペルソナ像を確立し、ジャーニーの各ステージ(認知、興味・関心、比較・検討、購入、利用、ファン化など)と、各ステージでの顧客の行動・思考・感情・タッチポイントの骨子を洗い出します。
ステップ3:ワークショップによるマップ作成と可視化
ステップ2で作成した骨子をもとに、部門横断のワークショップを開催します。付箋やホワイトボードを使い、参加者全員で顧客の行動や感情をマッピングしていきます。この共同作業を通じて、部門間の顧客理解のズレが明らかになり、組織としての一体感が生まれます。完成したマップは、MiroやCanvaといったツールを使ってデジタル化し、誰もがいつでも参照できる形に整えます。
ステップ4:課題発見と施策実行、そして改善サイクルへ
完成したマップは、ゴールではなくスタートラインです。マップを俯瞰し、「顧客の感情がネガティブになっている箇所」や「企業との接点が途切れている箇所」など、改善すべき課題(ボトルネック)を特定します。そして、その課題を解決するための具体的なアクションプランを立て、優先順位をつけて実行します。施策の効果はKPIで測定し、その結果をマップにフィードバックして更新する。このPDCAサイクルを回し続けることで、顧客体験は継続的に向上していくのです。
第7章 まとめと行動プラン:あなたの次の一手は?
本記事で見てきたように、カスタマージャーニーの作成と活用は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。顧客の行動が複雑化し、企業との関係性が問われる現代において、すべての企業にとって不可欠な経営戦略です。
その本質は、顧客を「正しく理解」し、「一貫した体験」を提供し、「長期的な関係」を築くことにあります。これを実践することで、以下のような具体的な成果が期待できます。
- ROI効果: LTV最大25%向上、CAC平均15-20%削減
- 顧客満足度: NPS®10ポイント以上改善、解約率の低下
- 組織変革: 部門間の連携強化と、顧客中心文化の醸成
✅ 今日からできる!カスタマージャーニー実践の3ステップ
この記事を読んで「何から始めればいいか」と感じた方は、まず以下の3つのアクションから着手してみてください。
① チームで「目的」を言語化する 「なぜ、我々はカスタマージャーニーを作るのか?」を関係者と議論し、A4一枚に書き出してみましょう。「新規リードの質を上げたい」「既存顧客の満足度を高めたい」など、目的が明確になるだけで、その後のプロセスが格段にスムーズになります。
② 既存の「顧客データ」を棚卸しする 顧客アンケート、Webサイトのアクセスログ、営業日報、サポートへの問い合わせ履歴など、社内に散らばっている顧客データをリストアップしてみましょう。「意外とこんなデータがあったのか」という発見が、顧客理解の第一歩になります。
③ 最もシンプルな「ミニジャーニー」を描いてみる 完璧なマップを目指す必要はありません。まずは一人の優良顧客を思い浮かべ、その人が自社を認知してから購入するまでの大まかな流れを、数個のステージに分けて書き出してみましょう。この小さな成功体験が、本格的な取り組みへの推進力となります。
たったこれだけのステップでも、あなたのチームの視点は確実に顧客側へとシフトし始めるはずです。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
