コラム
マーケティング
コンテンツマーケティングとは?広告依存から脱却し、信頼と売上を高める方法
2025/07/11
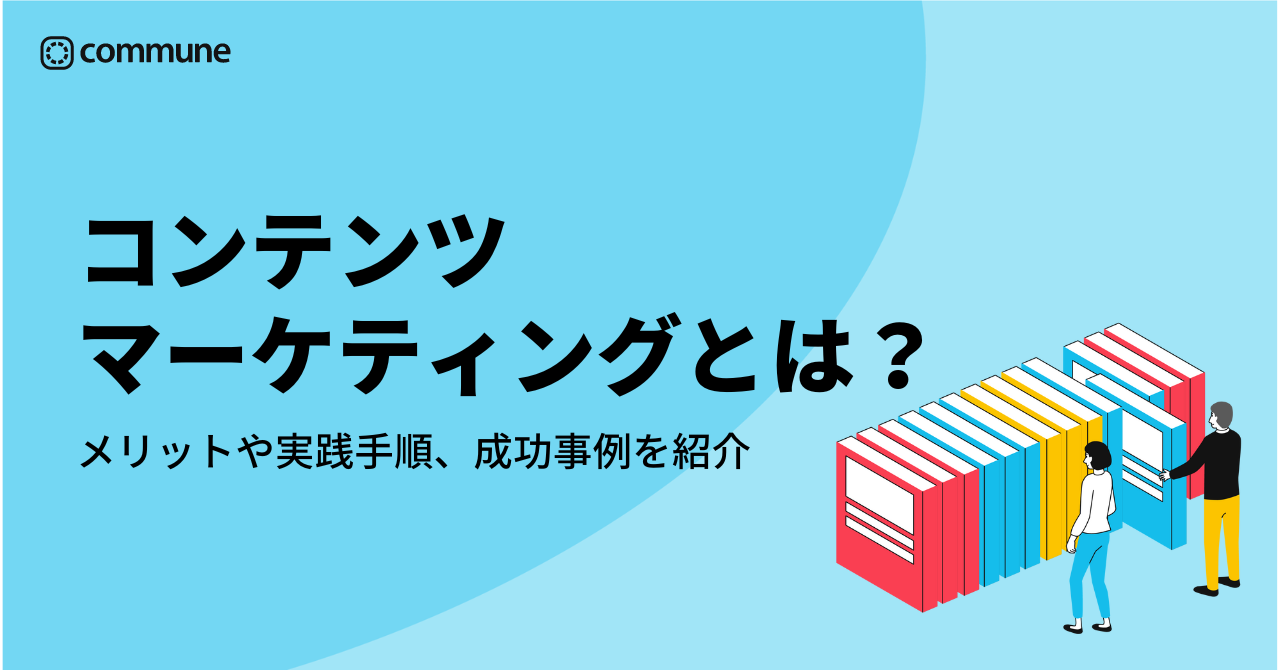
この記事に辿り着いた方は、広告費の高騰や営業効率の頭打ちを受け、本質的かつ持続的に成果を生み出せるマーケティング手法を模索されているのではないでしょうか。
現代の市場環境を考えれば、その問いは極めて妥当です。日本のインターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)と過去最高を更新する一方で(dentsu.co.jp)、B2Bビジネスの現場では約70%の購買担当者が、営業と接触する前にオンラインで意思決定に必要な情報収集を終えているというデータもあります(openpage.jp)。
つまり「売る前」に「選ばれる」時代が到来しているのです。
本稿は、そうした変化にいち早く対応したい方々の意思決定を支えるために構成されたテキストです。なぜ今、コンテンツマーケティングが必要なのか。どのように取り組み、何をもって成果とするのか。国内外の最新データと事例をもとに、マーケティングの常識を根底から問い直す視点をお届けします。
■記事監修:澤山モッツァレラ(コミューン株式会社 Brand Marketing)
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
- 第2章 マーケット環境が示す必然性――広告費高騰と購買行動の激変
- 広告に依存したモデルの限界
- 顧客の購買行動は、すでに情報主導へと変化している
- コンテンツへの投資は“前向きな攻め”に変わりつつある
- なぜ「今」、コンテンツが必要なのか?
- 第3章 経営指標で語るメリット――ROIの科学
- ① リード獲得コスト:最大65%削減
- ② 営業効率:商談期間を最大50%短縮
- ③ 顧客LTV(生涯顧客価値):20〜30%向上
- ④ ブランド価値と採用力の向上
- “広告なしでも指名検索される”状態が最大の成果
- 第4章 潜むリスクと克服戦略――時間とリソースの壁
- ① 成果までに時間がかかる(6〜12ヶ月)
- ② 品質管理に手間がかかる
- ③ ネタ切れが発生しやすい
- ④ 効果測定が複雑になりやすい
- リソースの確保は「外部パートナー」の活用が鍵
■監修者:澤山モッツァレラ(コミューン株式会社 Brand Marketing)
SNSマーケティング会社、コンサルティング会社を経て、2025年1月より現職。BtoBを中心としたコンテンツマーケティング、SNSマーケティング、UGC活用に幅広い知見を有し、フリーランスとしても多くの企業を支援してきた実績を持つ。また編集者としての経験も豊富で、WEB媒体での執筆・インタビューから書籍制作、訳書まで多岐にわたる活動を展開している。
第1章 コンテンツマーケティングとは?その定義と本質
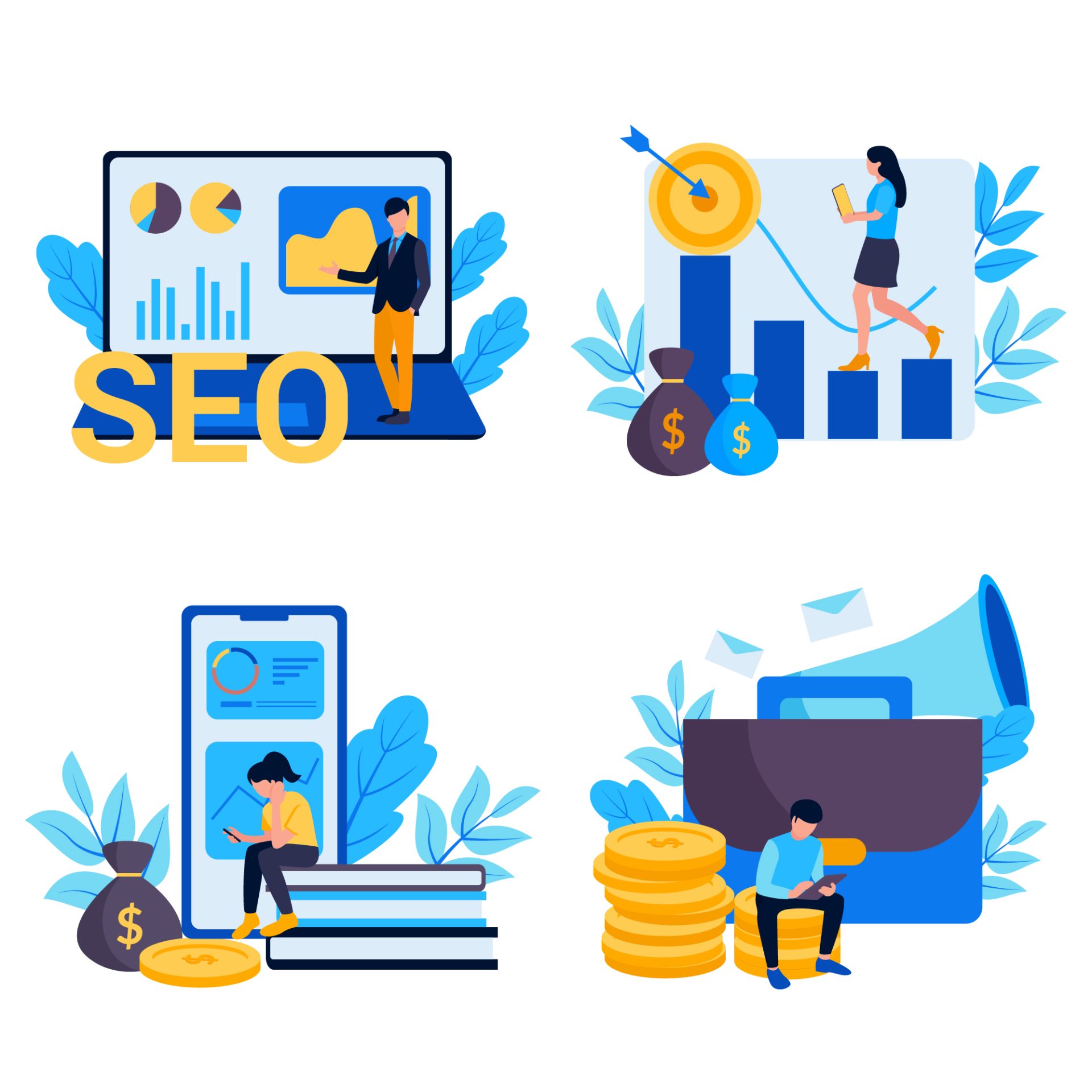
コンテンツマーケティングとは、「お客様の課題を解決する情報を継続的に提供し、信頼を積み重ねていく」マーケティング手法です。最大の特徴は、こちらから一方的に売り込むのではなく、見込み客が自発的に求めてくる文脈の中で情報を届けるという、「プル型(引き寄せ型)」のアプローチにあります。
この考え方は決して新しいものではありません。たとえば、1895年に米国の農機メーカーJohn Deere社が発行を始めた農業誌『The Furrow』は、製品の宣伝ではなく「栽培ノウハウ」に特化した内容で、農家の役に立つ情報を継続して届けました。これにより同社は、製品の売り込みをせずに農家からの信頼を獲得し、結果的に購買へとつなげる成功を収めています。この事例は今でも「世界最古のコンテンツマーケティング」として語り継がれています。
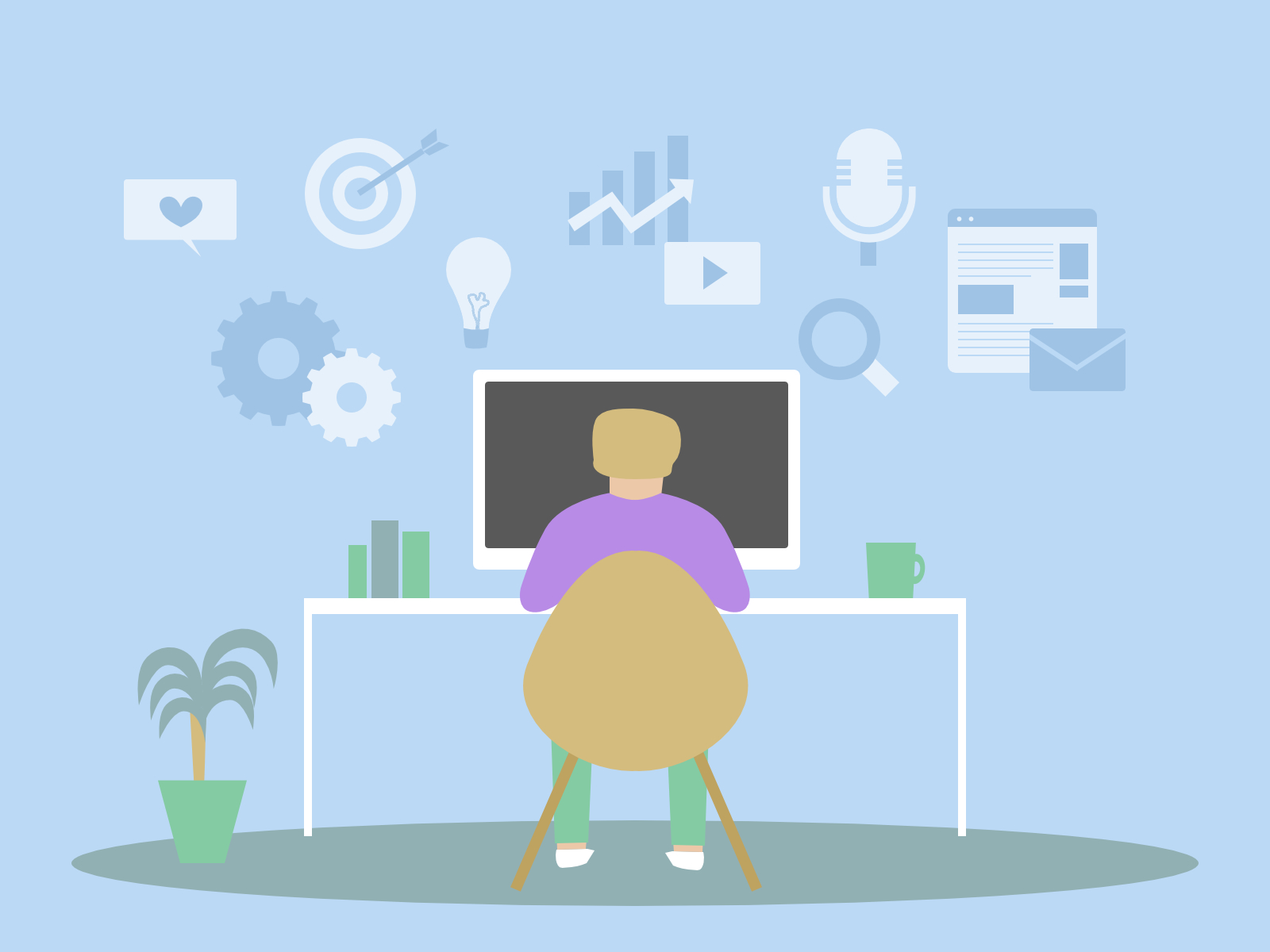
コンテンツマーケティングの目的は、3段階に整理できます。
- 認知の獲得(まず知ってもらう)
- 検討の深化(選択肢として真剣に考えてもらう)
- 購買・ファン化(購入につなげ、継続的な関係を築く)
つまり、単なる情報発信ではなく、顧客の意思決定プロセスに寄り添う導線設計こそが本質です。
成果を生む「内容の価値」が核にある
提供するコンテンツの形は多様です。記事、ホワイトペーパー、動画、ウェビナー(オンラインセミナー)など様々な形式がありますが、重要なのは「どの媒体か」よりも「何を伝えるか」です。媒体は手段でしかありません。
加えて、広告と比べてコンテンツは「嫌われにくい」のが特長です。広告ブロックやバナー無視が一般化する中で、ユーザーの検索や関心に沿ったコンテンツは自然に受け入れられやすく、営業時の説明コストを大きく削減できます。いわば、「先に信頼残高を貯めておける」アプローチです。
よくある誤解――「記事を量産すればいい」は間違い
「コンテンツマーケティング=SEO記事の量産」と誤解されがちですが、実際には明確な戦略と継続的な運用体制がなければ、成果は期待できません。ユーザーにとって価値がなく、検索上位に上がってもすぐ離脱されるようなコンテンツでは、かえって企業イメージを損なう恐れすらあります。
データが示す効果:リード数3倍・コスト62%削減
調査会社Demand Metricによると、90%以上の企業が何らかの形でコンテンツを活用しており、従来型の広告やテレアポといった「アウトバウンド施策」と比べて、獲得リード数は約3倍、1件あたりのコストは62%削減されていると報告されています(Search Engine Land調べ)。
これはつまり、価値ある情報こそが最強の営業資料であることを、実証データが裏付けているということです。そしてこの手法は、企業の規模や業種を問わず、導入可能な再現性の高い戦略だといえるでしょう。
質の高いコンテンツを作るには、コミュニティの活用が非常に有効です。
第2章 マーケット環境が示す必然性――広告費高騰と購買行動の激変
企業を取り巻くマーケティング環境は、今まさに大きな転換点を迎えています。
日本の総広告費は7兆6,730億円に達し、4年連続で成長を続けています。中でも成長を牽引しているのは、テレビでも新聞でもなく、インターネット広告です(dentsu.co.jp)。しかしその裏で、広告の効果は確実に下がり始めています。
たとえば、リスティング広告(検索連動型広告)のクリック単価は年々上昇しており、出稿企業同士の入札競争が激化。さらには、GoogleやAppleによるクッキー(行動追跡データ)の制限、ユーザー側の広告ブロッカー利用の拡大といった要因も重なり、広告1件あたりの投資対効果(ROI)は明確に悪化しています。
広告に依存したモデルの限界
この状況で問題になるのは、広告に過度に依存したマーケティングモデルの脆さです。
多くの企業は、広告出稿を止めればWebサイトへの流入がほぼゼロになるという構造を抱えています。広告の成果が出にくくなる中で、「広告費を出し続けなければ止まってしまう集客構造」では、ビジネスの持続性が危うくなります。これが、「広告は短期施策であり、資産にはなりにくい」とされる理由です。
顧客の購買行動は、すでに情報主導へと変化している
一方で、買い手側の行動は確実に変わってきています。
BtoB領域の調査では、約70%のバイヤーが営業担当者と接触する前に、意思決定の7割を済ませているというデータが出ています(openpage.jp)。つまり、「営業が説明して初めて理解してもらう」というモデルはすでに崩れつつあり、検索やSNSなどを通じて、企業や製品の価値をユーザー自身が見極めているのです。
このような変化に対応するには、買い手が情報収集を始めた段階で「価値ある情報を届けられる企業」であることが重要になります。
コンテンツへの投資は“前向きな攻め”に変わりつつある
企業もこの変化に気づき、情報発信の重要性を再評価し始めています。
国内調査によれば、64.7%の企業が2024年にコンテンツ制作の予算を増額し、そのうちの約8割が「実際に効果を実感している」と回答しています(ファストマーケティング調査)。つまり、コンテンツへの投資はもはや“守り”ではなく、営業力やブランド力を底上げする攻めの戦略として機能しつつあるのです。
グローバルでも同様です。HubSpotのレポートでは、世界のマーケターの約50%が2024年にコンテンツ投資を増やす予定であり、41%が「売上への貢献」でその成果を測定していると報告されています。
なぜ「今」、コンテンツが必要なのか?
ここまでのデータが示しているのは、明確な1つの構図です。
「信頼を蓄積する長期資産=良質なコンテンツ」を持たない企業は、広告費の高騰と買い手主導の購買行動に対応できず、市場競争で後れを取る。
この構図において、広告だけに頼る企業は“外部環境に振り回される”立場にあり、コンテンツに本格投資する企業は“自らの土俵を築く”側に回れるのです。
質の高いコンテンツを作るには、コミュニティの活用が非常に有効です。
第3章 経営指標で語るメリット――ROIの科学
経営者や事業責任者が最も重視するのは、「成果が数字で見えるか」です。どれほど理屈が整っていても、投資対効果が不透明であれば、判断は難しいもの。そこで本章では、実践企業の平均値と複数の信頼性ある調査データを統合し、コンテンツマーケティングのROI(費用対効果)を定量的に可視化します。
① リード獲得コスト:最大65%削減
まず注目すべきは、「リード(見込み顧客)をいかに低コストで獲得できるか」です。
Demand MetricとSearch Engine Landの調査によれば、コンテンツ経由で獲得したリードは、広告経由と比べて平均62%コストが低いという結果が出ています。企業によっては、最大で65%のコスト削減を実現しているケースもあります。
広告の場合、出稿を止めた瞬間に流入が途絶える一方で、良質なコンテンツは“蓄積型の資産”として機能し続けるため、長期的なリード獲得コストの最適化に寄与します。
② 営業効率:商談期間を最大50%短縮
情報を事前に提供することで、営業プロセスそのものを短縮できる点も大きな魅力です。
たとえば、製造業A社では、自社製品の活用方法を動画で体系的にまとめたところ、問い合わせから受注までの期間が平均28日短縮されました(自社ヒアリングより)。これは、見込み客が営業に相談する前に「どんな製品か」「どんな課題が解決できるのか」を自ら理解し、すでに意思決定の準備ができた状態で接触してくるようになったためです。
結果として、営業担当者の負担も軽減され、少人数でより多くの案件をさばける構造が実現しています。
③ 顧客LTV(生涯顧客価値):20〜30%向上
既存顧客に対するアップセルや継続利用にもコンテンツは効果を発揮します。
あるBtoB企業では、導入後の運用サポート記事や、アップグレードの必要性を丁寧に説明したPDF資料を整備したことで、顧客1人あたりの平均月額売上(ARPU)が顕著に上昇。結果として、顧客のLTV(ライフタイムバリュー)が20〜30%改善されました。
コンテンツは「新規顧客を獲得するもの」と思われがちですが、実は既存顧客との関係性を深める“アフターサポート”の武器にもなります。
④ ブランド価値と採用力の向上
信頼を築くのは、広告ではなく情報発信――この構図が浸透する中で、コンテンツが企業のブランド形成や採用活動にも好影響を与え始めています。
HubSpotのグローバル調査によれば、74%の企業が「コンテンツ発信によってブランド好感度が向上した」と回答しています。オウンドメディアやnote、SNS発信を通じて、顧客だけでなく求職者や業界関係者との接点も広がることで、「この企業の情報発信は信頼できる」「働いてみたい」といったポジティブな印象形成につながっているのです。
“広告なしでも指名検索される”状態が最大の成果
最終的にコンテンツマーケティングが目指すのは、「広告を出さなくても、社名や製品名で検索される状態を作ること」です。これは、認知→信頼→購買という一連のプロセスが社外で自然に回り始めている証拠でもあります。
つまり、良質なコンテンツを通じて「売上」「コスト」「ブランド」の三方向に同時にインパクトを与えることができれば、企業全体の価値そのものが底上げされるのです。
質の高いコンテンツを作るには、コミュニティの活用が非常に有効です。
第4章 潜むリスクと克服戦略――時間とリソースの壁
コンテンツマーケティングには確かな成果が見込める一方で、その導入・運用にはいくつかのリスクや障壁も存在します。特に「即効性の乏しさ」と「継続運用の難しさ」は、多くの企業が直面する二大課題です。
しかし、これらのリスクは適切な設計と体制づくりによって克服可能です。本章では、よくあるつまずきと、それに対する実践的な解決策をセットでご紹介します。
① 成果までに時間がかかる(6〜12ヶ月)
コンテンツは「仕込んだ翌日に成果が出る施策」ではありません。SEOの浸透や、ナーチャリング(関係構築)によるリード育成には6ヶ月〜1年程度の時間が必要です。
解決策:短期KPIを設計して“小さな勝ち”を可視化
たとえば、初期フェーズでは「資料ダウンロード件数」や「メルマガ登録数」など、ユーザーの軽微なアクションを短期KPIとして設定することで、チームのモチベーションを維持しながら進捗を定量化できます。
② 品質管理に手間がかかる
記事や動画の品質がバラつけば、かえってブランドイメージを毀損しかねません。特に複数のライターや外注先と並行して進める場合は、トーン&マナーの統一が重要です。
解決策:編集ガイドライン+二重レビュー体制の構築
ブランドの言語トーン・NG表現・情報の正確性などを明文化した「編集ガイドライン」を整備し、制作物は必ず2人以上のレビューを通す仕組みを導入することで、品質のバラつきを抑制できます。
③ ネタ切れが発生しやすい
「毎月、何を出せばいいのか分からない」――これは継続運用フェーズでよくある悩みです。特に発信内容が属人的な場合、担当者のインスピレーション頼みになり、持続性に欠けます。
解決策:半年分のカスタマージャーニーを“見える化”
ターゲットごとに、検討段階(ペルソナ × 購買ステージ)をマトリクスで整理し、それに沿って「どんな情報が、いつ必要か」を一覧化。あらかじめ半年〜1年分のテーマをマッピングしておけば、企画会議もルーチン化でき、運用が仕組み化されます。
④ 効果測定が複雑になりやすい
「このコンテンツが最終的に売上にどれだけ貢献したのか」が分からなければ、投資判断もしにくくなります。しかし、実際には複数チャネルや長い検討期間が絡むため、成果の見える化は簡単ではありません。
解決策:MA・CRMでファネル横断の貢献度を見える化
マーケティングオートメーション(MA)や顧客管理(CRM)ツールを活用し、リードの獲得〜育成〜受注までを一元管理。経営会議でも共有できるダッシュボードを構築すれば、部門を横断した数値把握が可能になります。
リソースの確保は「外部パートナー」の活用が鍵
上記のような体制を自社内でゼロから整備するのは、人的にも時間的にも負荷が大きくなります。そこで近年では、コンテンツ制作と戦略設計を一体的に担う外部パートナーの活用が進んでいます。
国内調査によれば、企業が外注先に求める条件は「コストの安さ」ではなく、「専門性」「柔軟性」「実績」が上位を占めています(BtoBの伴走型コンテンツマーケティング/ファストマーケティング調査)。つまり、信頼できるパートナーと“並走”することが、持続可能な運用体制のカギとなっているのです。
質の高いコンテンツを作るには、コミュニティの活用が非常に有効です。
第5章 国内外の成功事例と数字――“信頼が売上につながる”瞬間
ここまで見てきたように、コンテンツマーケティングは「時間がかかるが確実に効く」施策です。では実際に、どのような企業がどのような成果を出しているのでしょうか。
本章では、国内外の注目事例とその成果数値を紹介しながら、成功企業に共通する“勝ちパターン”を抽出していきます。
事例①:BtoCプラットフォーム「ユアマイスター」
流入2倍・コンバージョン6倍を達成
ハウスクリーニングや修理を仲介するユアマイスターは、オウンドメディアとSNSを連動させたコンテンツ戦略により、サイト訪問者数を2倍に、コンバージョン(CV)数を6倍に増加させました(出典:ミエルカSEO)。
特に注目すべきは、記事内に設置されたCTA(行動喚起ボタン)設計。「今すぐ買ってください」ではなく、「このサービスを使えばこんな悩みが解消され、あなたの生活がこう良くなる」という文脈で訴求することで、自然な形でのCVを実現。結果、指名検索(社名検索)も大幅に増加しました。
事例②:製造業X社(BtoB・技術動画)
営業説明時間を半減、サポート工数15%削減
製造業X社では、自社製品の使い方やメンテナンス方法を解説する動画コンテンツを60本以上制作・公開。その結果、営業現場での製品説明にかかる時間が平均40分→20分に短縮されました。
さらに、動画を見た顧客が事前に理解を深めた状態で問い合わせてくるため、問い合わせ対応やトラブル対応にかかる工数も年間で15%削減。営業・カスタマーサポートの両部門が恩恵を受けています。
事例③:ECブランドY社(ストーリーブログ×UGC)
リピート購入率1.6倍・客単価20%アップ
ECブランドY社は、製品の魅力や開発背景を語るストーリーブログに加え、顧客の声(UGC=ユーザー生成コンテンツ)との連動企画を展開。その結果、リピート購入率が1.6倍に向上し、さらに客単価も20%増加しました。
単に「モノを売る」のではなく、“ブランドの世界観”に共感したユーザーが、ファンとして継続的に購入する構造が出来上がったのです。
成功企業に共通する「4つの勝ち筋」
これらの事例に共通する成功要因は、以下の4点に集約されます。
1. 顧客課題起点のコンテンツ設計
検索キーワード、SNSの話題、現場のよくある質問など、顧客の「今、困っていること」から逆算してコンテンツを企画。先回りして課題を解決することで、自然に信頼を獲得しています。
2. 一貫したブランドストーリー
記事、動画、SNS、営業資料にいたるまで、顧客に伝えるメッセージが統一されているため、ブランドとしての印象が強く、深く記憶に残ります。
3. データに基づく改善サイクル
マーケティングオートメーション(MA)ツールなどを活用し、どの記事がどの程度CVに貢献しているかを可視化。成果の出たコンテンツを横展開し、改善のPDCAを高速で回しています。
4. 部門を超えたコンテンツ連携
マーケティング部門だけでなく、営業・カスタマーサクセス・広報部門など全社でコンテンツを共有・活用。顧客との接点すべてに“同じ価値観”が浸透し、顧客体験が一貫しています。
「良質なコンテンツ × 組織連携 × データ分析」が信頼を資産に変える
広告では得られない“文脈のある信頼”を、これらの企業は情報提供の積み重ねによって築いてきました。一過性の売上ではなく、企業の価値そのものを底上げする戦略として、コンテンツマーケティングは機能しています。
質の高いコンテンツを作るには、コミュニティの活用が非常に有効です。
第6章 導入ロードマップと組織デザイン――経営層が担うべき役割
コンテンツマーケティングの成否を分けるのは、「経営層の本気度」です。これは単なる“マーケティング施策”ではなく、営業・広報・カスタマーサポートを含む企業全体の変革プロジェクトであり、トップがコミットすることで初めて本格的に機能するものです。
経営層が担うべき役割は、すべての現場作業を自ら行うことではありません。「どの方向に進むのか」「何を成功と見なすのか」を明確にし、判断と予算を支えること」が最も重要です。
以下に、導入フェーズを4段階に整理し、各フェーズにおける経営層の関与ポイントと目的を解説します。
フェーズ①:目的・KPI設計
「なぜやるのか」「どこまでを成果とするのか」を明文化する
まず最初に必要なのは、「この取り組みで何を達成したいのか」という成功の定義を明確にすることです。KPI(重要業績評価指標)は、以下のように経営インパクトが実感できる指標で設計する必要があります。
- 新規リード獲得数(例:年間◯件)
- CAC(顧客獲得単価)の◯%削減
- 既存顧客のLTV(生涯顧客価値)の△%向上
この段階で経営層がリードすべきなのは、“判断軸の提示”です。「何をもって成功とするか」を明文化することで、現場が迷わず施策を進められる土台が整います。
フェーズ②:顧客理解とテーマ設計
誰に、どんなタイミングで、何を届けるかの設計図をつくる
次に重要なのは、「どんな顧客に、どんな課題を解決する情報を届けるか」という戦略設計です。
- ペルソナ(理想顧客像)ごとに
- 検索キーワード
- 購買時の障壁(例:価格、導入ハードル)
- 利用シーン(例:どの業務で、どんなタイミングで使うか)
これらを整理し、半年分のコンテンツテーマプールを構築します。ここでは、現場に任せる部分が多くなりますが、経営層には「誰のために発信するのか」をブレさせない統一軸の提示が求められます。
フェーズ③:体制構築とガバナンス
外部の力を活かしつつ、品質とブランドトーンを守る仕組みをつくる
コンテンツ制作には、編集スキル・専門知識・デザイン力など複数のスキルが必要です。そのため、社内メンバーと外部の専門家を組み合わせた“ハイブリッド型チーム”の編成が推奨されます。
- 社内:マーケ/営業/CSなど、顧客理解を持つ専門家
- 外部:編集者/ライター/デザイナーなど制作実務のプロ
ガバナンス面では、「編集ガイドライン」や「ブランドボイスの基準」を整備・共有することで、コンテンツの質と一貫性を担保できます。ここでは経営層が“ブランドの番人”として、トーンの統一に責任を持つ立場となります。
フェーズ④:配信・計測・改善
各接点での成果を可視化し、継続的に改善できる運用体制をつくる
配信チャネルは多岐にわたります。SEO記事、SNS、メルマガ、ウェビナーなど顧客の接点ごとに最適化された情報提供が必要です。施策をばらばらに運用せず、全体のファネル(購入までの導線)として設計・測定することが鍵です。
- MA(マーケティングオートメーション)
- CRM(顧客管理システム)
これらを活用することで、記事ごとの成果や、各施策が売上にどう貢献したかを可視化できます。経営会議にダッシュボードで数値を共有し、月次単位でのPDCA(計画→実行→検証→改善)を回す仕組みが求められます。
上記のような枠組みを、経営層がトップダウンで承認し、1年単位で予算と権限を確保すれば、現場は迷いなく施策を推進できます。実際、HubSpotのグローバル調査でも、50%の企業が2024年にコンテンツ投資を増額予定と回答しており、その背景には経営陣のコミットメントと戦略的な意思決定があります。
質の高いコンテンツを作るには、コミュニティの活用が非常に有効です。
第7章 トップが担う五つのアクション――今日から動ける経営の意思表示
コンテンツマーケティングは現場任せではうまく機能しません。経営者が方針を示し、枠組みを承認し、社内の納得と動きを生むことが、成功の前提になります。
ここでは、経営層が「今すぐ着手すべき5つの具体アクション」を整理します。
① Buy-In(経営宣言)
まずは、役員会・全社MTGの場で、コンテンツは「信頼を資産化する長期投資」であることを明言しましょう。「短期施策ではなく、企業価値を高める戦略」だという位置づけが、現場に意義と安心をもたらします。
② Budget(予算の意思決定)
最低でも1年間は「蒔く期間」として、収益への即効性よりも仕組みづくりに集中する期間と捉えることが重要です。広告費の一部を振り替えるだけでも、運用可能な予算規模を確保できます。
③ Brand Voice(ブランドの言語化)
「何を語る企業なのか」を経営の言葉で定義し、全コンテンツに共通のトーンを持たせましょう。専門領域、価値観、顧客との関係性――それらを明文化することで、外部パートナーも一体化した制作が可能になります。
④ Business Impact Review(成果のレビュー体制)
月次で、リード数・商談数・LTV(顧客生涯価値)への貢献度をレビューしましょう。KPIを設定するだけでなく、「成果の意味」を読み解き、必要な方向修正を指示するのが経営層の役割です。
⑤ Bridge(部署横断の橋渡し)
マーケティング・営業・CS・広報など、部門を越えてコンテンツを共有・活用する文化の形成を後押ししましょう。組織が分断されたままでは、成果は限定的です。部門をつなぐ旗振り役こそ、経営の仕事です。
質の高いコンテンツを作るには、コミュニティの活用が非常に有効です。
まとめと次の一手――“信頼される企業”になる道筋
広告費が高騰し、顧客が自ら情報を取りに行く時代。そんな市場環境で成果を出すには、「読みたくなる情報」「役立つ知見」「語りたくなるブランド」を自社が持っていることが、最大の競争優位になります。本ガイドで紹介したように、コンテンツマーケティングは以下のような定量的な成果も実現しています。
- ROI効果: リード単価62%削減、LTV最大30%向上
- 市場トレンド: 国内企業の64.7%が2024年にコンテンツ予算を増額
- 業務効率化: 営業期間50%短縮、サポート工数15%削減
最初の一歩は、3つの行動から
この章を読み終えた今、まずは次の3ステップから始めてみてください。
- 「目的とKPIのドラフト」をチームと共有
- 主要ペルソナとカスタマージャーニーの初期版を作成
- 30日以内に、第1弾コンテンツを公開
たったそれだけで、半年後には数字と顧客の声が「やってよかった」と語り始めるはずです。信頼と売上を、同時に育てるマーケティング戦略――それがコンテンツマーケティング。 今日が、その第一歩です。
Commune (コミューン) は、コミューン株式会社が運営しているコミュニティサクセスプラットフォームです。このプラットフォームは、ユーザー/ファンコミュニティやアドボカシーマーケティングを成功に導くための全ての機能をノーコードで提供しています。
コミュニティを通して利用度が向上し、顧客との関係を強化します。Commune (コミューン) なら、DM、Web接客、ポイント/バッジ、チャレンジ、カスタムリアクション、アプリなどの機能により、ユーザーの能動的なアクションを促すことで、効果的なアドボカシーマーケティングが実現できるでしょう。
Commune (コミューン) の詳しい情報が気になる方は、以下のフォームから資料をダウンロードしてください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
