コラム
マーケティング
アカウントベースドマーケティング(ABM)とは?ROIをぐっと上げるBtoB必勝ガイド
2025/06/17
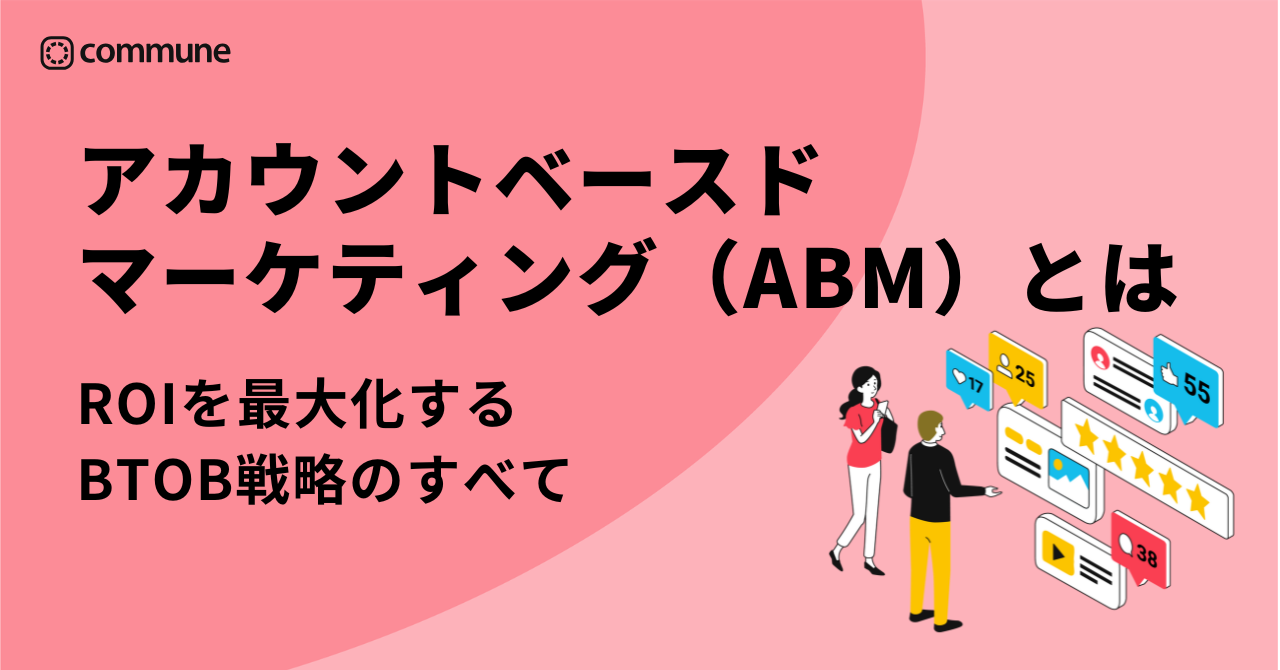
ABM(アカウントベースドマーケティング)とは、狙う企業を先に決めて営業とマーケが一体で攻略するBtoB戦略です。展示会や広告で大量リードを集めても商談にならない、営業とマーケがかみ合わない――そんな悩みを抱える企業ほど導入効果が大きいと言われています。
Forresterの 2024年調査ではABMを実践する23%の企業が「ROIが従来施策の1.5~3倍になった」と回答し、北米・欧州・APACすべての地域で優位性が確認されています。ABM支援ツール市場は年平均12%以上で拡大し、2024年の1.5 Bドル規模から2031年に2.4 Bドルへ成長する見込みです。日本国内でもSaaS・製造・ITサービス各社がこぞってABM専任チームを設置し、「見込み客の数より受注額・継続率を重視する」潮流へ舵を切り始めました。
本稿は専門用語を極力かみ砕きつつ「ABMの基礎、導入ステップ、KPI、ツール選定、最新事例、よくある失敗パターン」まで徹底的に解説します。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
第1章 ABMの基本概念と“銛型マーケティング”3つの特徴
ABM(アカウントベーストマーケティング)をひとことで言えば、「狙った企業と、その中の意思決定に関わるすべての関係者を動かすマーケティング戦略」です。
これまで主流だったリードベースドマーケティング(LBM)では、まず広く個人の問い合わせを集め、その後じっくり育てていくという“網を張る”スタイルが一般的でした。これに対してABMでは、最初から「理想的な顧客企業」を選定し、その企業のキーパーソン、予算を握っている人、導入のタイミング、抱えているであろう課題などを徹底的に調査したうえで、ピンポイントで突破していく手法をとります。
ABMが特に効果を発揮するのは、1件の契約あたりの売上が大きく、導入にあたって社内の複数の関係者が関与するような商材です。例えば、SaaSのエンタープライズプラン、AIやIoTを活用した設備投資、大規模な業務ソフトウェアの導入、グローバルな物流体制の構築などが典型です。
こうしたBtoBの取引では、担当者個人は導入に前向きでも、財務部門や情報システム部門が反対したりと、社内の事情が複雑に絡み合っていることがよくあります。このような場面では、従来のように個人リードを育てるアプローチでは限界があり、意思決定者全体に影響を及ぼすABMの方が適しています。
ABMの特徴
ABMにはいくつかの特徴があります。まず、成果指標(KPI)を企業単位で設計する点です。個人リードの数を追うのではなく、「狙った企業がどれだけ商談化したか」「受注につながったか」「平均的にどれほどの金額になったか」といった、アカウント単位での成果を測ることで、少ない指標でもぶれのない戦略設計が可能になります。
また、アプローチのスタイルも柔軟に変えるのがABMの特徴です。完全に1社だけに特化して施策を組み立てる「One-to-One型」、共通の業界や課題を持つ企業をまとめて狙う「One-to-Few型」、より広範囲に広告やコンテンツを展開する「One-to-Many型」と、目的や規模に応じて使い分けることで、限られたリソースを効率よく活用できます。
さらに、ABMでは受注前後を分けず、長期的な関係を前提に設計します。つまり、受注して終わりではなく、その後のオンボーディング、利用拡大、クロスセル(関連製品の提案)、契約更新に至るまで、ひとつのシナリオとして一貫して描くことで、顧客から得られる総収益(LTV)を最大化する設計思想になっています。これにより、営業活動も単発で終わらず、中長期的な関係構築の中で価値提供が続いていくのです。
また、ABMを成功させるには、マーケティング部門と営業部門の連携が不可欠です。これまでのようにマーケティングがリードを獲得し、それを営業に渡した時点で役割を終えるような縦割りのやり方では、ABMは機能しません。むしろ、両者が同じ目標やKPIを共有し、データを連携し、必要であればコンテンツも共同で制作していくという、一体的なチーム運営が求められます。こうした体制が整えば、アカウント単位での深い関係構築がスムーズに進むだけでなく、社内のノウハウや成果も蓄積されやすくなります。
最後に、ABMを導入する企業が次に目指すべきステージとして、「ABX(アカウントベースド・エブリシング)」という考え方があります。これは、営業やマーケティングだけでなく、カスタマーサクセス、サポート部門、さらには経営層に至るまで、全社が「アカウント=顧客企業単位」で連携して動くというアプローチです。ABXでは、企業内のすべての顧客接点がつながっている状態が理想とされます。そのため、ABMを始める際には、将来的にABXへと発展させられるように、データ設計や業務プロセスをあらかじめ視野に入れておくことが、無駄な再構築を避けるポイントになります。
第2章 なぜ今ABMなのか――4つの市場・組織変化を読み解く
ABM(アカウントベーストマーケティング)がここまで世界的に注目されるようになった背景には、大きく分けて「外部環境の変化」と「企業内における構造的な課題」という、ふたつの視点があります。順を追って見ていきましょう。
まず外部環境の変化として顕著なのは、BtoBの購買プロセスが以前よりも格段に複雑化しているという現実です。Gartnerの調査によれば、たとえばITツールや業務システムの導入を決める際、その意思決定に関わる社内の関係者は平均で9.6人にのぼるとされています。
これだけ多くの人が関与するということは、役職や部門ごとに異なる関心や評価軸が存在することを意味します。つまり、特定の一人にだけ働きかけていても商談は前に進まず、全体の情報設計やコミュニケーション設計を緻密に構築する必要がある、という状況が常態化しているのです。
また、テクノロジー面でも大きな変化がありました。近年では、マーケティングオートメーション(MA)ツールと営業支援(SFA)ツールがSaaSとして普及し、APIを通じてシームレスに連携できるようになりました。これにより、たとえばWebサイト上でのクリックや資料ダウンロードといった行動履歴と、実際の商談金額や受注状況を、「企業単位」でひとつなぎにして把握することが可能になっています。こうした技術基盤の進化が、ABMの中核である“アカウント単位での分析とアクション設計”を、現実的なコストで実行できる環境を整えてきたのです。
さらに無視できないのが、企業の投資判断に影響する経済的プレッシャーの高まりです。たとえばデジタル広告の費用、特に表示あたりの単価(CPM)は2019年と比較して約26%も上昇しており、同じ成果を得るために必要な予算が確実に増えています。こうした状況の中で、経営層は「できるだけ高い確率で成果が出る投資先」を選ばざるを得なくなっており、まさにABMのような“狙いを絞ったアプローチ”が強く支持される理由になっています。
実際、Forresterの2024年調査によれば、ABMを導入している企業の99%が「従来のマーケティング施策と比べて高いROI(投資対効果)を得られている」と回答しており、すでにその有効性は経営の意思決定を支える根拠として定着しつつあるのが現実です。
ABMの急速な広がりを支えているもう一つの要素が、専用ツールの普及と価格低下です。以前はABMに取り組むには高額な海外製ツールを導入する必要があり、言語やコストの面でハードルが高いものでした。しかし現在では、ABM専用のプラットフォームの価格帯は2018年と比べて約3割下がり、市場全体の成長率も年平均12%と堅調です。2032年には約40億ドル規模に達するとも予測されており、特に国内市場では日本語対応の広告配信サービスや企業データベースが次々と登場してきたことで、以前のように英語UIが壁になることはほとんどなくなっています。これにより、日本企業でもABMに取り組みやすい土壌が整ったと言えるでしょう。
一方で、ABMが必要とされる背景には、企業内部の課題も密接に関係しています。たとえば、長年にわたって分業化が進んできた営業とマーケティングのあいだには、しばしば“連携の壁”が生まれています。マーケティング部門はリード(見込み顧客)を集めることが目的になりがちで、その後の商談化や受注には関与しない。営業側は、マーケティングが送ってくるリードの質に不満を持つ。こうした分業疲れは、多くの企業で慢性的な問題となってきました。
また、せっかく集めた顧客データが部門ごとに分断され、統合的に活用できない「サイロ化」も深刻です。その結果として、営業パイプライン(商談の見込み数や質)そのものが年々劣化している、という現象も多くの現場で起きています。
ABMは、これらの内部課題を「アカウント単位での一貫した戦略」という形で一気に解決し得る手段として注目されています。営業とマーケティングの連携を前提にし、企業全体の意志を統一しながら狙い撃ちで成果を上げていく。その明快な設計思想が、現在の混沌としたマーケティング環境のなかで、数少ない“希望の処方箋”として広く受け入れられつつあるのです。
・関連記事:カスタマーセントリックとは?あらゆる局面で「顧客を中心にする」戦略
┗ ABM成功の下地となる「顧客中心文化」の具体策を解説します。
・関連記事:【2025年最新】オンラインサロンとオンラインコミュニティ、何が違う?徹底比較ガイド
┗ キーパーソンとの関係を深める“コミュニティ型タッチポイント”設計のヒントがわかる記事です。
第3章 ABMの5大メリット
ABM(アカウントベーストマーケティング)が注目される最大の理由は、その明確な投資対効果の高さにあります。実際、ABMに取り組むことで、マーケティング予算の使い方そのものが変わり、少ない打数で大きな成果を狙う戦略が可能になります。ここでは、ABMが企業にもたらす代表的な5つのメリットと、あわせて注意すべきリスクについて整理しておきましょう。
第一に、大型案件の獲得における勝率が大きく向上する点です。Forresterの報告によれば、ABMを導入している企業では、そうでない企業に比べて平均契約額が33%も大きいというデータがあります。これは、意思決定に関わる複数の関係者に対して適切にアプローチするABMの特性が、大きな商談の成立に直結していることを示しています。つまり、一件あたりの成果が大きくなる分、限られた営業リソースでも十分に成果を出せるようになるのです。
第二に、全体としてのROI(投資対効果)の改善が挙げられます。ABMを実践した企業では、同じマーケティング予算でも、成果が1.5倍から最大で3倍にまで拡大したというケースが報告されています。これにより、経営層にとっても「確度の高い投資先」として認知されやすくなり、マーケティング部門に対する信頼性も向上するという好循環が生まれます。
第三に、営業部門とマーケティング部門の連携によるシナジー効果の最大化が挙げられます。ABMでは、両部門が同じKPIを共有しながらリアルタイムで情報を連携するため、従来のような「営業への引き継ぎ待ち」や「案件進捗の不透明さ」といったタイムロスが大幅に削減されます。こうした体制は、単に効率化にとどまらず、顧客に対する対応スピードや提案精度の向上にも直結します。
第四に、顧客一人ひとりとの関係性が深まり、結果としてLTV(顧客生涯価値)の向上につながる点です。ITSMAの調査によると、ABMを実践している企業の87%が「他の施策よりもROIが高い」と回答しており、特に既存顧客とのアップセルや契約更新といった領域において、安定した成果を生み出しています。こうした成果は、単なる新規顧客の獲得ではなく、長期的な顧客関係の中で得られる利益の最大化という観点からも、ABMが有効であることを示しています。
第五に、顧客体験そのものの質を高めることができます。ABMでは、対象企業ごとにパーソナライズされた情報提供やコミュニケーションが行われるため、顧客は「自分たちの課題に本気で向き合ってくれている」と感じやすくなります。こうした信頼感の蓄積は、商談段階から導入、さらには活用フェーズに至るまで、一貫性のある良質な体験を提供するベースとなり、差別化の要素としても機能します。
第4章 ABMの3大デメリット
もっとも、ABMにもリスクがないわけではありません。まずひとつ目のリスクは、ターゲット企業の選定ミスです。ABMは少数の企業に集中して施策を行うため、最初のターゲット選びがズレてしまうと、その分の工数やコストがすべて無駄になってしまう可能性があります。広く薄く展開する従来のマーケティングと違い、“外れ”が許されにくい構造なのです。
二つ目のリスクは、データの質が施策の成果を大きく左右する点です。たとえば、MA(マーケティングオートメーション)やSFA(営業支援)、CRM(顧客管理)といった各システム間で、フィールドの定義や管理ルールがバラバラだった場合、企業単位での情報統合が困難になり、ABMが求める「統合された顧客像」が描けなくなってしまいます。つまり、ツールが揃っていても、それを使いこなす基盤が整っていないと意味をなさないのです。
三つ目の注意点は、ABMがすべての商材に向いているわけではないということです。特に、アップセルの余地が少なく、一度の取引で関係が終わってしまうような単発完結型のビジネスモデルでは、ABMの初期投資を回収するまでに時間がかかりすぎてしまう可能性があります。したがって、ABMを導入する際は、自社の提供する商材やサービスが「長期的に価値を提供できるかどうか」を見極める必要があります。
こうしたリスクを回避するためには、いくつかの原則を押さえることが重要です。
まず第一に、理想的な顧客像(ICP:Ideal Customer Profile)を感覚ではなく、データに基づいて設計すること。過去の受注データや利用履歴から、成果につながった顧客の共通点を抽出するプロセスが不可欠です。
次に、小規模なパイロット導入によって、実際の施策が有効かどうかを検証しながら段階的に展開すること。いきなり全社導入を目指すのではなく、仮説を検証する柔軟さが求められます。そして最後に、MAやSFAといった基幹システムの連携体制をあらかじめ整備し、情報が部門をまたいで正確に共有される仕組みを確立すること。これら3つの原則を丁寧に実行することで、ABM導入に伴う失敗コストを最小限に抑えることができるのです。
・関連記事:MRR(月次経常収益)とは何か?定義・計算方法から伸ばし方まで
┗ ABM投資の回収指標となるMRR/ARRの基礎と伸ばし方を網羅した記事です。
・関連記事:リピーターを増やすには?安定収益とブランド力を高める戦略
┗ 受注後のアップセル・継続率最大化でABM効果を長期化する方法を解説します。
第5章 実務で使えるABM5ステップ
ABM(アカウントベーストマーケティング)の実行プロセスは、設計から運用、そして最適化までを一貫して戦略的に進める必要があります。その全体像をフェーズごとに整理すると、実務の輪郭がより明確になります。以下は、ABMの代表的なワークフローの流れを、実務に即した形で解説したものです。
まず、最初に行うのはターゲットアカウントの選定、いわば設計フェーズです。ここでは、自社の売上上位顧客をもとにRFM分析(Recency:購買の新しさ、Frequency:購買頻度、Monetary:購買金額)を行い、その結果を3×3のマトリクスに落とし込むことで、顧客を優先度に応じて分類していきます。
この作業により、既存顧客のなかでも重点的にアプローチすべき企業が明確になります。そのうえで、外部の企業データベースと連携し、上位顧客と類似した特性を持つ企業を自動的に抽出することで、いわゆる“ホワイトスペース”──まだ接点のないが潜在的に高い成果が見込める企業群──を特定します。
次に進むのは構想フェーズで、キーパーソンの特定とカスタマージャーニーの設計を行います。まず、各アカウントにおける意思決定関与者の職種や役職に応じて、抱えている課題や重視するポイントをまとめた「役職別インサイトマップ」を作成します。
たとえば、DX推進担当部長であれば「業務全体の効率化」、情報システム部門の管理者であれば「既存システムとの整合性や安定稼働」といった視点が重視される傾向があります。さらに、実際に商談が成立するまでにどの役職の誰が、どのタイミングで、何を決めているのか──これを「決裁プロセス逆算表」という形で見える化することで、適切なタイミングに適切な情報を届けられるようになります。
構想が固まったら、次は制作フェーズに入り、具体的なコンテンツとチャネルの設計を行います。ここではトピッククラスタという考え方を活用し、「関連テーマごとに記事、ホワイトペーパー、セミナーなどを体系的に配置する」ことがポイントになります。これにより、顧客の関心に応じたナレッジ提供が可能となり、認知から比較検討、意思決定に至るまでの情報接点を段階的に築くことができます。
推奨されるチャネルの組み合わせ例としては、メールを起点にLinkedIn広告やミニウェビナー、さらには紙のDM(ダイレクトメール)など複数の接点を連動させることで、個別最適ではなく全体最適な訴求が可能になります。
実行フェーズでは、実際のキャンペーンを展開しつつ、取得したデータに基づいて顧客の状態を把握していきます。マーケティングオートメーション(MA)ツールを用いれば、顧客の「行動スコア(Web閲覧、資料DLなど)」と「属性スコア(企業規模、業種など)」をリアルタイムで加算していくことができ、あらかじめ設定した閾値──たとえば75点──に達したタイミングで、インサイドセールスチームに自動で通知が飛ぶような仕組みを作ることが可能です。
その後、SFA(営業支援ツール)を活用して、案件化、提案書作成、受注に至るまでのプロセスを一連のタイムラインとして管理していきます。こうすることで、施策と成果が一対一でひも付けられ、次の施策へのフィードバックもスムーズになります。
最後は、効果測定とスケール拡大のフェーズです。この段階では、アカウント単位のエンゲージメントスコア、商談の平均規模、アップセルの金額など、複数の観点から成果をダッシュボードで可視化し、どの要素が成功に寄与しているかを評価します。定められた基準値をクリアした時点で、対象アカウント数をたとえば+50%に拡大し、同じプロセスを適用していくことで、再現性のある成長が可能になります。
なお、ABMを組織的に運用するうえでは、各種テンプレートの整備も不可欠です。たとえば、理想顧客像を定義する「ICPシート」、キーパーソンの行動を整理する「ジャーニーマップ」、セールスメールの文面を記載した「メール台本」、週ごとの進捗管理に使える「週次KPIレポート雛形」など、こうした資料を全社で共有することで、属人的な判断や個人依存のリスクを最小限に抑えることができます。ABMは仕組みの勝負です。再現性ある型を作れるかどうかが、成果を左右する最大のポイントとなるのです。
第6章 ABM専用KPIとROI計算モデル
ABM(アカウントベーストマーケティング)を実務で運用していく上では、成果の測定とそのフィードバックが戦略の軸となります。
とりわけ重要なのが、「何をKPIとして追うか」をあらかじめ明確に定義し、施策ごとにぶれのない評価軸を持つことです。ABMでは、KPIを「早期成果」「中間成果」「最終成果」という3つの階層に分けて設計することで、短期的な手応えから中長期的な成果までを一貫してモニタリングできます。
最初の「早期成果」は、施策が動き始めてすぐに表れる変化、いわゆる先行指標にあたります。代表的なのが「アカウントエンゲージメントスコア」で、特定アカウントがWebサイトや資料にどれほど関与しているかをスコアリングで把握します。たとえば、資料を開封した回数、社内での共有(転送)頻度、資料ページへの再訪率といった数値は、キーパーソンや関係部署が内容に関心を持っている兆しを示す重要なヒントになります。これらは受注には直結しないものの、「関心が熱を帯びているかどうか」を判断する材料として、早い段階での評価に活用されます。
次に「中間成果」では、アカウントが実際に商談のステージに入ったかどうか、つまりプロセスの進行状況を示す指標を追います。ここで代表的なのが「QACR(Qualified Account Conversion Rate)」という数値で、これは接点を持ったアカウントのうち、どれだけが“商談化に足る質”を持っていたかを示す比率です。あわせて「パイプライン速度」、つまり商談開始から受注に至るまでの日数の平均を測定することで、プロセスの詰まりやすい箇所を特定することもできます。中間成果は、ABM施策が“ちゃんと案件を前に進めているか”をチェックするための客観的なバロメーターです。
そして最終的に重視されるのが「最終成果」、すなわち財務的インパクトです。これはマーケティング施策が実際に会社の売上や利益にどれだけ貢献したかを評価するフェーズで、具体的には受注額や受注率、さらにアップセルにより増加した年間収益(ARR)や契約の継続率といった指標が含まれます。これらは経営層や財務部門がもっとも重視する評価項目であり、ここでの成果が次期予算の説得材料にもなります。
ABMのROI(投資対効果)を定量的に示す際には、シンプルな算出式が有効です。基本形は「(受注額 - マーケティング+営業コスト) ÷(マーケティング+営業コスト)」という式で、投入したリソースに対してどれだけ利益が生まれたかを示します。このとき、経営層に対しては「従来型の施策」と「ABMパイロット施策」の結果を横並びで比較し、その差分をグラフや数値で明示することで、施策の優位性に説得力が増します。
さらに、リアルタイムで進捗を管理するためのダッシュボードには工夫が必要です。たとえば、「施策ごとの受注への貢献額」「アカウント単位でのLTV(顧客生涯価値)」「営業がどの程度関与して受注に至ったか=営業介在コスト」といった視点を並べて表示することで、何が成果につながり、どこに改善余地があるのかを直感的に把握しやすくなります。ABMは精密さが求められる施策だからこそ、KPIの設計と可視化の質が、最終的な成果を大きく左右するのです。
第7章 国内外の成功事例
ABM(アカウントベーストマーケティング)の有効性を示す上で、具体的な成功事例は非常に重要です。ここでは、国内外の代表的な事例を2つ紹介します。それぞれ異なる規模・フェーズにある企業ながら、ABMの導入により目に見える成果を短期間で獲得しています。
まず、国内のSaaS企業B社では、ABM導入にあたって最初から全社展開せず、選定した50社に対してパイロット的に施策を実施する方式を採用しました。導入から3か月後には、そのうち40%という非常に高い割合で商談化に成功し、短期間での手応えを得ることに成功しています。さらに1年後の段階では、既存顧客とのアップセルによる年間収益(ARR)が140%増加しており、ABMの狙いでもある“LTVの最大化”を見事に実現した形です。この事例は、特に中堅〜成長段階にあるSaaS企業にとって、リスクを抑えながら確実にABMの成果を得るための参考モデルになるでしょう。
一方、より大規模な事例としては、売上10億ドル規模の米国SaaS企業による取り組みがあります。この企業は、ABM支援企業であるInsights ABMのサポートを受けながら、より精緻なアカウント設計とパーソナライズ施策の高度化に取り組みました。その結果、従来のマーケティング施策と比較してリードの質が125%向上し、全体の営業パイプラインも20%拡大したと報告されています(出典:insightsabm.com)。
この事例が示すのは、規模が大きくなってもABMの原則──すなわち、選定、設計、連携──を徹底することで、成果の天井を押し上げることが可能であるという点です。特に、グローバルで多拠点を持つ企業においては、ABMのもつ“組織横断型アプローチ”がより効果を発揮しやすい環境が整っていると言えるでしょう。
これらの事例は、ABMが決して理論だけの話ではなく、現場で実際に成果を生み出している具体的な手法であることを示しています。規模や業種を問わず、明確な戦略と実行体制さえ整えば、ABMはその期待に応えるだけのポテンシャルを備えているのです。
・関連記事:単純接触効果(ザイオンス効果)とは?広告・営業への活用法と注意点
┗ キーパーソンへの“適切な回数アプローチ”を設計する心理学の応用。
・関連記事:ロイヤルティとは?向上させる方法や成功事例を紹介
┗ 受注後フェーズでLTVを伸ばすロイヤルティ施策を体系的に学べる。
まとめと実践チェックリスト
ABM(アカウントベーストマーケティング)を実行に移す際、まず必要なのは「大がかりな体制づくり」ではなく、明確な狙いと小さな一歩です。最初から完璧な仕組みを構築しようとするのではなく、少数のターゲットアカウントに集中し、仮説検証を通じて学びを重ねていく姿勢こそが、成果を最速で引き寄せる鍵になります。
まず取り組みたいのは、上位20社程度の有望顧客を対象に、それぞれが抱えていそうな課題や意思決定構造を言語化し、共通点と個別差異を見極めることです。そのうえで、特に施策適合度が高そうな3社を選び、PoC(概念実証)という形でABMを実践してみる。この段階では、完璧な運用体制よりも、「試しながら学ぶ」ことに重点を置くべきです。
施策を始める前には、MA(マーケティングオートメーション)とSFA(営業支援ツール)のID連携を済ませておくと、行動ログと商談進捗が一気通貫で把握でき、データ分析や成果測定が圧倒的にスムーズになります。あわせて、営業チームと共通のダッシュボードを構築し、商談の温度感やアカウントの反応をリアルタイムに共有できる仕組みを整えておくと、部門間の連携が自然と強化されます。
また、ABMはその性質上、経営陣からの理解と支援が不可欠です。そのためにも、週次で「現在の成果」「学び」「次に取るべきアクション」の3点を簡潔にまとめて経営層に報告するサイクルを設けておくと、戦略的なバックアップが得やすくなり、スピード感のある改善が可能になります。
さらに、PoCの段階で得られた成功パターンは、必ずテンプレート化して社内にナレッジとして蓄積しておきましょう。具体的にはターゲット選定フロー、キーパーソンマップの書き方、メール台本、コンテンツ設計、成果のKPI指標などをドキュメントに落とし込み、再現性のある「型」として共有できるようにしておくことが重要です。これにより、将来的にスケール拡大を図る際の教育コストや立ち上げ工数を大幅に削減することができます。
ABMはその本質において、「狙いを絞って、深く寄り添う」マーケティングです。言い換えれば、少数の顧客に対して深く理解を重ね、組織全体で寄り添う姿勢を貫くことが、成果に直結するということです。完璧を求めて動き出せないよりも、小さくても確実なアクションを積み重ねるほうが、ROI最大化への道を早く切り開くことができます。
本記事で紹介したフレームワークを参考に、まずは貴社の最重要顧客3社に絞った“ミニABM”からスタートしてみてください。その最初の一歩が、売上成長と顧客体験の両立という、BtoBマーケティングの本質的な変革へとつながっていくはずです。
あわせて読みたい
・関連記事:カスタマーセントリックとは?あらゆる局面で「顧客を中心にする」戦略
┗ ABMでも欠かせない「顧客中心」の思考を組織に根付かせる方法を詳述。
・関連記事:リピーターを増やすには?安定収益とブランド力を高める戦略
┗ 受注後のアップセル・継続率を高めてABMのROIをさらに伸ばすヒント。
・関連記事:単純接触効果(ザイオンス効果)とは?広告・営業への活用法と注意点
┗ キーパーソンに“最適回数”で接触し、商談化率を上げる心理学テクニック。
・関連記事:パーセプションとは?「認識」の本質と実践
┗ アカウント内の意思決定者全員に“望ましい認識”を醸成するための基礎知識。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
