コラム
マーケティング
クロスセルとは?取り組むメリット・デメリットや具体的な施策・事例を解説
2025/03/04
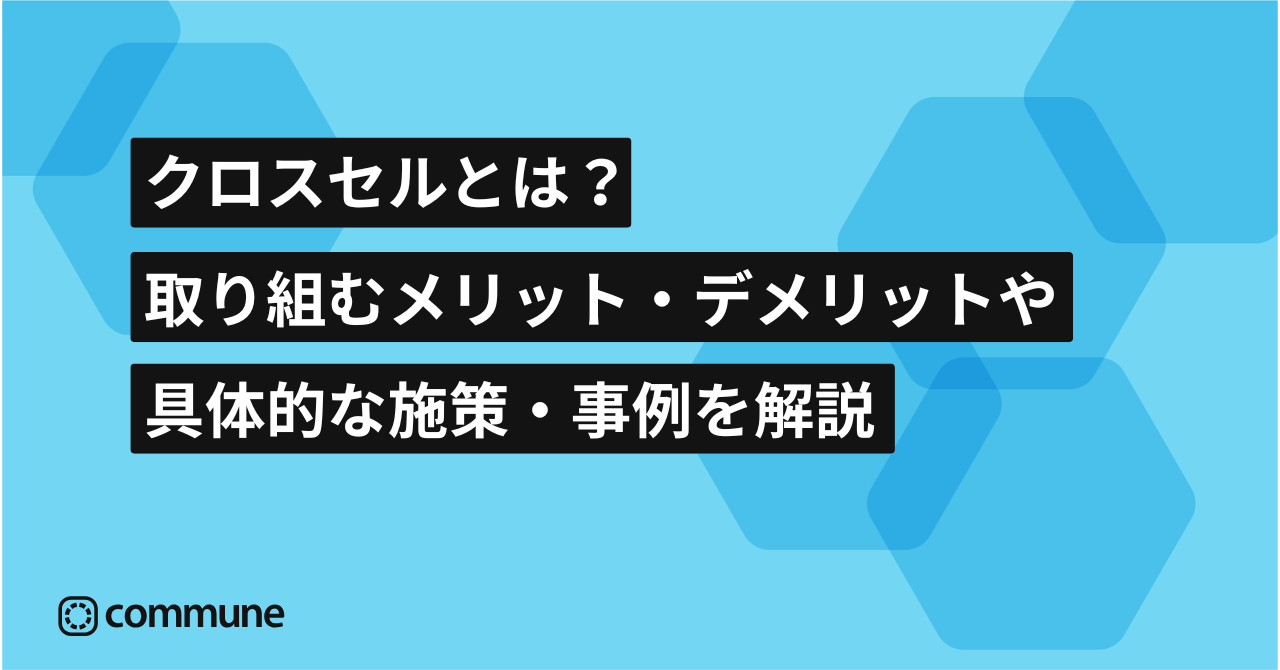
「クロスセル」とは、商材購入を検討中の顧客に関連商材を提案し、売上向上を目指す営業手法です。クロスセルの活用で顧客単価が向上しますが、使い方を誤れば顧客離れにつながるリスクがあります。そこで本記事では、クロスセルのメリット・デメリット、具体的な施策や事例について詳しく解説します。
目次
クロスセルとは

まずはクロスセルの概要について、次のポイントから見ていきましょう。
- 顧客に関連商材を購入してもらうための手法
- より上位の商材を提案するのが「アップセル」
顧客に関連商材を購入してもらうための手法
「クロスセル」とは、自社の製品・サービスの購入を検討している顧客に対し、関連する別の商材も購入してもらうセールス手法です。例えば、パソコンを購入しようとしている顧客に、キーボードやマウスも勧めるなどです。このように、いわば「セット販売」のような形で提案することで、顧客単価を引き上げることができます。
より上位の商材を提案するのが「アップセル」
クロスセルと似たような用語に「アップセル」がありますが、こちらは顧客が検討しているより、上位の商材を購入してもらうための手法です。例えば、あるサービスのスタンダードプランを利用中の顧客に対し、より内容が充実したプレミアムプランを勧めるなどです。
このように、関連商品をセット販売するクロスセルに対し、アップセルでは商材そのものをアップグレードして顧客単価を引き上げます。
クロスセルを実施するメリット

クロスセルを実施することで、企業は次のようなメリットが得られます。
- 顧客単価を改善できる
- ファンの育成でLTVも向上する
- 関連商品が訴求しやすくなる
顧客単価を改善できる
クロスセルにより関連商材をセット購入してもらえるため、顧客単価を引き上げることができます。また、すでに購買を検討中の顧客に対して行うため、低コストで利益率を向上させやすいことが魅力です。
ファンの育成でLTVも向上する
クロスセルは、顧客ニーズに合わせて関連商材を提案する手法なので、顧客体験の向上にもつながります。自社サービスに好印象を抱いた顧客は、次回以降も自社との取引を継続する「ファン」となります。その結果、顧客から最終的に得られる収益である「LTV(顧客生涯価値)」の向上も期待できるのです。
関連商品が訴求しやすくなる
単体では訴求が難しい商材であっても、クロスセルなら顧客の購買意欲を刺激できる可能性があります。例えば、単体では販売が見込めないネクタイを、ワイシャツの関連商品として提案するなどです。また、クロスセルは一度の販売機会で複数の商材をセットで訴求できるため、営業の効率化も見込めるでしょう。
クロスセルを実施するデメリット
クロスセルには次のようなデメリットが生じる恐れがあります。
- 「押し売り」と感じて不信感を抱くことがある
- 提案した商材の質が低いと顧客離れにつながる
「押し売り」と感じて不信感を抱くことがある
顧客に対する関連商材の訴求方法によっては、「押し売り」だと思われて不信感を招いてしまうことがあります。近年では、顧客はインターネットで自ら情報を収集するため、押し売りに対する忌避感が強くなっています。クロスセルを行うときは、目先の売上目標ではなく「顧客ニーズ」を意識して、顧客の立場に立った訴求を行うことが大切です。
提案した商材の質が低いと顧客離れにつながる
顧客ニーズを満たせない提案をすると、自社ブランドに不信感を抱いた顧客が、競合他社に流出してしまう可能性があります。また近年では、企業やブランドに対する悪いクチコミが、SNSやブログなどで拡散されるケースが珍しくありません。つまり、不適切なクロスセルは「企業イメージ」の低下につながりかねないということです。
クロスセルを実施する際の注意点
クロスセルを実施する際は、次のポイントに注意しましょう。
- 商材を強くプッシュしすぎない
- アフターフォローを丁寧に行う
商材を強くプッシュしすぎない
前述したような「顧客の不信感」を避けるためには、商材を強くプッシュしすぎないように注意しましょう。そもそもクロスセルは、顧客が購入を予定していない製品・サービスを提案する手法なので、顧客ニーズに適合していなければ「押し売り」だと感じられてしまいます。
そのため、まずは顧客との対話を通じて、顧客が潜在的に必要としている商材を検討してみることが大切です。クロスセルの提案内容と結果をまとめて、社内でパターンを共有しておくのも効果的です。適切な提案ができれば、顧客はむしろ自社に対する信頼感を深めて、リピート購入してもらえるかもしれません。
アフターフォローを丁寧に行う
クロスセルによる顧客満足度を高めるためには、「アフターフォロー」を丁寧に行うことが大切です。「売って終わり」というのでは、顧客は「企業から軽く扱われている」と感じ、顧客満足度が低い状態になります。購入後のカスタマーサポートや情報提供を顧客目線で行えば、自社に対する信頼度が高まるでしょう。
クロスセルを成功させるためのポイント

クロスセルを成功させるために、次のポイントを意識しましょう。
- 事前に顧客情報を収集しておく
- 購入を決めた直後のタイミングで実施する
- 顧客ニーズに沿った商材を提案する
- 顧客のベネフィットを明示する
事前に顧客情報を収集しておく
クロスセルに限らず、マーケティングや営業を成功させるために欠かせないのが「顧客情報」です。顧客情報が不十分であれば、顧客の属性や課題が分からないため、的外れな提案をしてしまうことがあります。例えば、「購入履歴」や「問い合わせ履歴」は、顧客ニーズを把握するために特に重要な要素なので、全社的に共有して活用できるようにしておきましょう。
購入を決めた直後のタイミングで実施する
クロスセルは適切なタイミングで行わなければ、顧客を購買に誘導できません。例えば、まだ購入を検討している段階でクロスセルを仕掛けると、「押し売り」の印象が強くなって不信感につながってしまいます。
クロスセルの最適なタイミングは、顧客が購買を決定した直後です。この段階では顧客の意欲が高いため、関連商材を購入するハードルも低くなります。ただし、タイミングを逃すと提案後に迷いが生じてしまうため、購買決定のタイミングで速やかにクロスセルに移行することが大切です。
顧客ニーズに沿った商材を提案する
前述したように、クロスセルで重要なポイントは「顧客ニーズ」を踏まえた提案を行うことです。そのためには、購入履歴や閲覧履歴などの顧客情報を踏まえて、顧客が必要とするものを把握する必要があります。例えば、画像編集作業のためにパソコンを購入しようとした顧客には、キーボードよりも画像編集ソフトを提案することで、クロスセルが成功しやすくなるでしょう。
顧客のベネフィットを明示する
クロスセルでは、そのまま商材を提案するよりも、顧客が得られるベネフィットを明示することで成功率が高まります。例えば、関連商品を購入した場合に、一定の割引が受けられるなどです。価格面でのベネフィットがあることで、顧客は「せっかくだから購入しよう」という心理が働いて購買へ進みやすくなります。
クロスセルの代表的な成功事例・施策を紹介

クロスセルの代表的な成功事例や具体的な施策をご紹介します。
- ECサイトで「関連商品」を紹介
- セットメニューの提示で割安感を演出
- サービス利用状況を踏まえた機能の提案
- 相性の良いサービスの提案で売上を拡大
ECサイトで「関連商品」を紹介
インターネット通販サイト大手のA社は、ECサイトの商品説明や購入画面などで、「関連する商品」「一緒に購入されている商品」という項目で、関連商材を顧客に紹介しています。また、顧客が「押し売り」だと感じてしまうのを防ぐため、邪魔にならないように画面下部に表示されることもポイントです。
セットメニューの提示で割安感を演出
ファーストフードのチェーン店を世界中に展開しているB社では、「セットメニュー」でクロスセルを行っています。例えば、ハンバーガーを注文した顧客には、ポテトやドリンクなどを提案するなどです。さらに、セットにした場合は割引が受けられるため、お得感から多くの顧客がセットメニューを購入しています。
サービス利用状況を踏まえた機能の提案
ソフトウェア開発会社のC社では、ひとつのサービスを導入した顧客に対し、課題解決につながるほかの機能も提案しています。ただし、顧客のサービス利用状況を確認し、課題を見極めて適切なものをプッシュしていることが特徴です。本事例のように、ひとつのサービスから関係が始まった顧客であっても、信頼関係を丁寧に構築することで、将来的により多くのサービスを導入してもらえるようになります。
相性の良いサービスの提案で売上を拡大
携帯電話の販売代理店を展開しているD社では、機種変更時にクロスセルを実施しています。その際に追加オプションとして、動画ストリーミングサービスや電気・ガスなどの割引契約を提案していることがポイントです。生活に関連する携帯電話と相性が良い商材を提案することで、顧客の忌避感を招かずに売上拡大が目指せます。
クロスセルを実施する流れをステップごとに解説

クロスセルを実施する流れを次の4つのステップに分けて解説します。
- ステップ1:顧客を分析する
- ステップ2:戦略を設計する
- ステップ3:顧客に提案する
- ステップ4:効果を検証する
ステップ1:顧客を分析する
クロスセルを実施する際は、まず対象となる顧客を分析しましょう。すべての顧客を対象とするのではなく、自社商材への関心度が高い顧客を選定することが大切です。そのために、顧客情報や購買履歴などから、ターゲットを絞り込みます。顧客管理のシステム化や顧客コミュニティの運用などを行っている場合は、顧客情報をより活用しやすくなるでしょう。
ステップ2:戦略を設計する
分析した顧客情報をもとに、対象となる顧客に「どの商材をどのように提案するか」を検討しましょう。前述したように、適切なタイミングで顧客に刺さる訴求をする必要があるため、顧客への理解が欠かせません。
またクロスセルの手法はさまざまなので、例えばECサイトが販売チャネルである場合は「おすすめ」や「関連商品」の表示、訪問営業・テレアポがメインの場合は営業担当者への教育など、自社に合う戦略設計が必要です。
ステップ3:顧客に提案する
戦略設計ができたら、実際に顧客への提案を行います。成約率を高めるためには、必ず顧客が得られるベネフィットを明示することが大切です。顧客目線の提案を戦略どおりに行うことで、顧客をスムーズに購買へ誘導できるでしょう。
ステップ4:効果を検証する
クロスセルはすべてが成功するわけではないため、提案の効果を検証して改善を重ねる必要があります。提案が顧客に刺さらなかった場合、顧客分析や戦略設計などいずれかの段階での不備が考えられます。改善点を次回以降に活かすことで、クロスセルの効果がさらに高まるでしょう。
クロスセルの最適化には顧客コミュニティ「Commune」がおすすめ

クロスセルは顧客単価の向上に有効な施策であり、さまざまな業界で展開されています。しかし、クロスセルを成功させるためには、綿密な顧客情報の収集と分析をあらかじめ行っておく必要があります。そこで「顧客コミュニティ」を構成し、顧客と双方向のコミュニケーションを行うなかで、顧客管理やクロスセルを行ってみてはいかがでしょうか。
顧客コミュニティ構築サービス「Commune」には、ユーザー同士の交流や企業とユーザーとの共創を実現するための機能が備わっています。顧客の熱量を上げ、双方向の関係を築く仕組みにより、優れた成果を得られるカスタマーリレーションズやファンマーケティングが実現できます。この機会にぜひ、Communeの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
以下のフォームから「3分でわかるCommune」資料を無料でダウンロードできます。気になる方は、ぜひご確認ください。
