コラム
マーケティング
口コミマーケティングとは?効果測定・成功事例から失敗回避策まで
2025/04/14
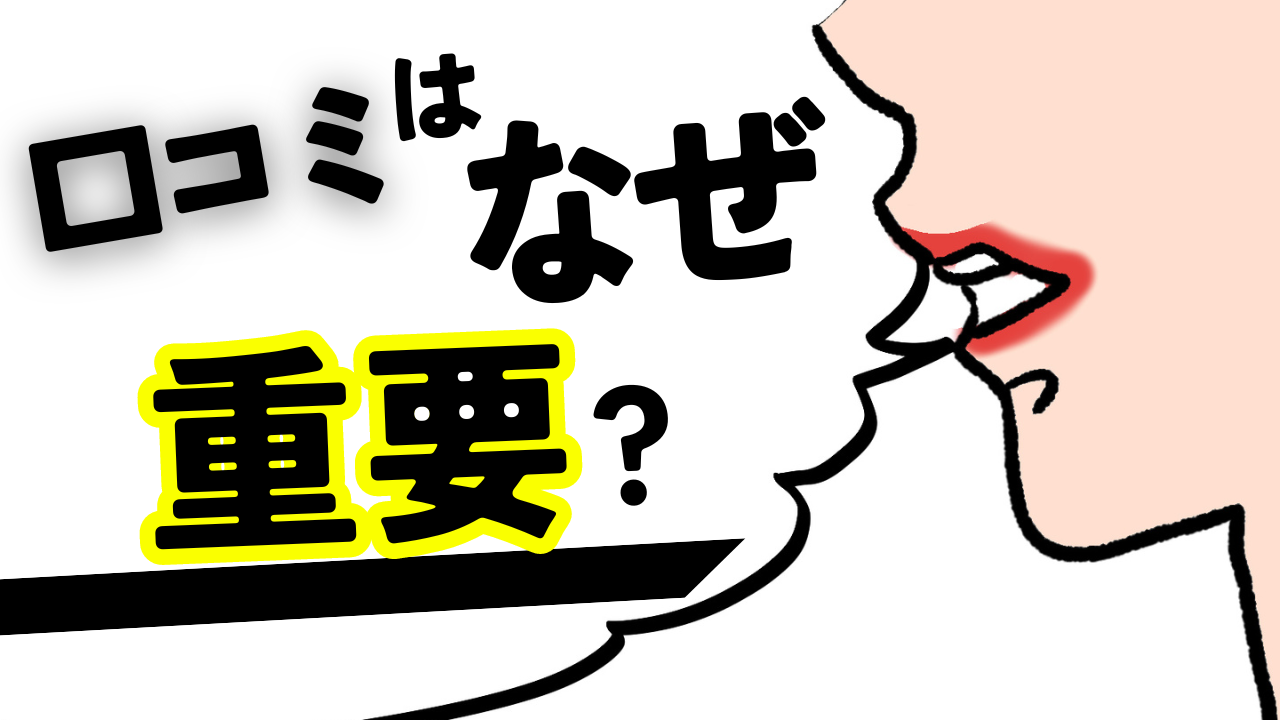
今や口コミは、商品やサービスの評価を左右する重要な要素となりました。
現在の消費者は、企業が直接発信する広告よりも「第三者のリアルな声」を信頼する傾向が強まっています。特にインターネットで購入を検討する際、多くの人がSNSやECサイトの口コミを事前に確認する習慣が定着しています。
本記事では、口コミをマーケティングに活用するための基本知識からメリットとデメリット、主な活用手法、成功事例と失敗事例、さらには口コミ効果の測定方法やネガティブな意見への対応ポイントまでわかりやすく解説します。
うまく口コミを創出できれば、低コストで高いマーケティング効果を得ることが可能です。しかし、口コミは企業が完全にコントロールすることが難しく、手法を誤れば「ステマ」として批判を受けたり、悪評が拡散するリスクも伴います。正しい知識を持つこと、慎重かつ戦略的な運用をしていくことが不可欠です。
口コミマーケティングをこれから始めたい方、すでに導入しているものの成果をさらに改善したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
監修:澤山モッツァレラ(コミューン株式会社)
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
口コミマーケティングとは?
口コミマーケティングとは消費者同士の“口コミ”を活用し、商品・サービスの認知拡大や購入を促進するマーケティング手法です。広告や公式アカウントからの情報ではなく、実際に体験した第三者のリアルな声が広まることによって、企業やブランドに対する信頼を高める効果が期待できます。
「口コミ」という言葉から、家族や友人間の口コミだけを想像するかもしれません。しかしインターネットが浸透した現代では、SNS・ブログ・レビューサイト・オンラインコミュニティなど、多様なチャネルで口コミが生まれるようになりました。
そのため企業が広告費を大きくかけずとも、魅力ある商品・サービスがあり、プロモーションをうまく仕掛ければ正しい認知を広げられる可能性があるのです。
なぜ今、口コミが注目されるのか?
簡単にいえば「人は、広告よりも口コミの方を信じるから」に尽きます。実は、こうした傾向は1955年に発表された論文でもすでに言及されています。
ラザースフェルド/エリフ・カッツと同僚による1955年刊行の『Personal Influence(個人的影響)』では、イリノイ州デケーターでの調査結果が報告されています。それによれば日用品や食品の購入に関しては、家族・友人・同僚といった対人ネットワーク上の発言者が最も重要な影響源となっており、広告などマス媒体の影響力は限定的だったといいます。
「対人影響(後に1960年代にマーケティングの文脈で“クチコミ”と呼ばれる)は新聞・雑誌広告の7倍、ラジオ広告の2倍、販売員からの直接セールストークの4倍もブランド変更を促す効果があった」と報告されています。この研究は、当時盛んになりつつあった大量広告の熱狂に冷や水を浴びせ「人は人によって動かされる」というメッセージをマーケティング関係者に突き付けました。
■関連論文:
Personal Influence The Part Played by People in the Flow of Mass Communication By Elihu Katz and Paul F. Lazarsfeld(The Free Press, 1955)(リンク)
SNSの普及と第三者情報への信頼
ひるがえって、現代はどうでしょうか。テレビCMや新聞広告といったマス広告が主流の時代は終わり、SNSを中心に個人が手軽に情報発信できる時代になりました。上記したように人間の認知傾向として「広告よりクチコミを信用する」がある以上、SNSを起点としたクチコミによるマーケティングが注目を集めるようになったのは必然と言えるでしょう。
「商品やサービスの存在を知らせる」という点で、広告の重要性が無くなることはありません。しかし「信用してもらう」「好きになってもらう」「継続して使用してもらう」という観点からいうと、広告だけでは難しいのが実情です。
大企業の一方的な宣伝より、同じ消費者の「使ってみた正直な感想」のほうが信用されやすい──この現象は、ウィンザー効果と呼ばれる心理的メカニズムでも説明できます。実際に「口コミを見て購入を決めたことがある」という消費者は9割以上ともいわれ、いまや企業発信<第三者発信が当たり前となっているのです。
■関連リンク:
ウィンザー効果とは(一般社団法人日本経営心理士協会 リンク)
口コミマーケティングのメリット・利点
信頼性が高い
さまざまな利点がありますが、まず「信頼性が高い」ことが挙げられます。「利害関係のない第三者が発信していることで、信頼されやすい」ことが口コミの最大の利点です。消費者目線の口コミは親近感や共感を生み、「本当に良い製品・サービスだからこそ紹介している」という印象を与えます。特に「使ってみた感想」「ビフォーアフター写真」といった“体験談”は購買意欲を強力に後押しします。
低コストで高い費用対効果
次に、機能すれば低コストで高い費用対効果が得られる点が挙げられます。紙媒体やテレビCMのように多額の広告費を出さなくても、SNSやレビューサイトにおけるポジティブなクチコミが生まれれば、それが勝手に広がり続けます。もちろん一定の施策コストは必要ですが、成功すれば広告以上のリーチや売上効果を得られる可能性があります。特に規模の小さい企業にとっては、口コミの力は大きな武器になり得ます。
質の高い口コミの蓄積は「資産」となる
さらに、蓄積された質の高い口コミは資産になることが挙げられます。多くの口コミが投稿され、検索結果やSNS上に残ることは、見込み客が購買を検討する際のサポートコンテンツとして機能します。例えばECサイトでやや高めの商品購入を検討する際は、念入りに商品レビューをチェックした経験があなたにもあるはずです。その際に、質の高い口コミが蓄積していれば、それだけ購入検討者の判断材料になります。
新規層へのリーチが期待できる
最後に、新規層へのリーチが期待できることです。口コミが自然発生的に広がる過程で、企業が想定していなかった層にまで情報が届く場合があります。既存顧客が自発的に共有してくれるおかげで、広告ターゲット外のユーザーへも認知が広がり、思わぬ市場を開拓するきっかけになり得ます。
■関連リンク:
UGC活用ガイド|メリット・生成促進4ステップと成功事例
口コミマーケティングのデメリット・注意点
口コミマーケティングには多くのメリットがありますが、同時に以下のようなデメリットや注意点も存在します。
コントロールが難しく、炎上リスクがある
口コミはユーザーが主体的に発信するものであり、企業側が内容や拡散を完全に制御することは困難です。意図しないネガティブな情報や、誤解を招く情報が拡散されるリスクがあります。また、企業が口コミを意図的に操作しようとすると「ステルスマーケティング(ステマ)」とみなされ、場合によっては炎上を引き起こす恐れがあります。近年はPR表記の義務化が進み、透明性が求められているため、細心の注意が必要です。
法規制への理解が必要になる
口コミの内容によっては、薬機法や景品表示法などの法規制に抵触する可能性があります。例えば、医薬品や健康食品に関する口コミで「この商品で10キロ痩せました」といった表現は、事実であっても薬機法違反となる恐れがあります。企業がこれらの口コミを二次利用する際には、法規制の理解とそれに応じた対応が必要です。
しっかりとした設計が求められる
口コミは広告とは異なり、クリック数やコンバージョンなどの明確な数値目標を計測することが難しいケースがあります。またユーザーが独自のハッシュタグを使用したり、企業名を明記せず口コミを投稿したりするケースもあります。口コミ効果を正確に把握するためには、キャンペーンにおける事前の数値設計をしっかり行なう工夫が求められます。
これらのデメリットや注意点を踏まえ、口コミマーケティングを活用するには慎重かつ戦略的な取り組みが必要です。
質の高い口コミを生む上で、顧客むけコミュニティの活用は非常に有効です。

口コミマーケティングの主要な手法
ここでは代表的な手法をいくつかご紹介します。それぞれの長所・短所や予算感を考慮しながら、自社に合った組み合わせを検討することが大切です。
SNSキャンペーン
InstagramやTwitter(X)などでハッシュタグや写真投稿を条件にプレゼント企画を行い、ユーザー参加型で認知拡大を狙う手法です。「指定ハッシュタグをつけて商品写真を投稿すると抽選で景品が当たる」など、参加しやすいインセンティブを用意すれば、短期間で大量のUGC(ユーザー生成コンテンツ)が発生します。
- メリット:拡散力が高く、面白い企画なら一気にバズる可能性がある。
- デメリット:一過性になりやすく、キャンペーン終了後に継続的な投稿が減ってしまう可能性がある。企画立案や景品を用意するコストが必要。
インフルエンサーマーケティング
フォロワー数や視聴者数の多い、いわゆるインフルエンサーに商品の魅力を発信してもらう方法です。美容・ファッション・飲食など、ジャンルごとに得意なインフルエンサーと契約するのが一般的です。近年はPR表記を明確にしつつ、自然な体験談として紹介するスタイルが主流です。
- メリット:インフルエンサーのファンコミュニティに深く刺さり、口コミの二次拡散も見込める。
- デメリット:PR表記をきちんと行わないなど、法的対応を失敗すると「ステマ」に該当する危険がある。施策と相性の悪いインフルエンサーを起用すると、費用対効果に見合わないケースも。
モニター募集・サンプリング
新商品を無料または割引価格で試してもらい、感想投稿やレビュー作成を条件とする施策です。アンケートやSNS投稿をセットにすれば、使った実体験をより詳しく共有してもらえます。商品にある程度自信がないと、ネガティブな口コミを増やしてしまうリスクがある点に注意が必要です。
- メリット:クチコミを一定数獲得しやすい。リアルな体験談が集まるので二次利用できる。
- デメリット:大量サンプルの配布費用や、レビュー収集・管理の運用コストがかかる。サンプルを事前に受け取っている旨明記しない場合、ステマに該当する可能性も
ファンコミュニティの運営
企業公式のオンラインコミュニティやファンサイトを作り、ロイヤル顧客同士の交流をサポートする手法です。定期的にイベントや限定情報を提供することで、ファンをブランドの“応援団”に育てられます。ファンが自主的にSNSへ投稿してくれれば、自然な口コミ拡大が期待できます。
- メリット:長期的にファンと関係を築き、継続的な口コミを生みやすい。
- デメリット:コミュニティ運営の手間や継続コストがかかり、活性化しない場合は効果薄。
ファンコミュニティ運営には、質の高いノウハウが必要です。弊社コミューンにお任せください。
成功事例
はなまるうどん様「まるごとダイオウイカ天」
はなまるうどん様が2013年に実施したエイプリルフール企画「まるごとダイオウイカ天」は、ちょうど当時話題になっていたダイオウイカをフィーチャーしたユニークな企画でした。発表後すぐにSNSで話題となり、公式サイトのアクセス数が通常の24倍に増加。話題性のあるコンテンツが口コミを促進した好例です。
思わずシェアしたくなる“ネタ”要素と、ユーザー参加型の企画を掛け合わせたこと。短期的ながら認知が急速に広がった例です。(参照)
フリスク様「さわやかすぎる通勤」
2011年、新商品「フリスク マスカットミント」のプロモーションとして、フリスクはTwitterで「フリスク(FRISK)」と投稿した方を対象に、抽選で豪華な通勤体験をプレゼントするキャンペーンを実施しました。
キャンペーン期間は2月28日から4月20日までで、抽選で選ばれた5名のビジネスパーソンは、運転手付きのリムジンで優雅な通勤を体験。車内では朝食のサービスやバイオリンの生演奏を楽しむことができました。
窮屈でストレスの多い朝の通勤を、非日常的で爽やかな体験に変えたこのユニークな企画はSNSで大きな話題となり、フリスクに関するポジティブなツイート数がキャンペーン期間中に15%増加するなど、ブランドの認知度向上に成功しました。(参照)
江崎グリコ様「ポッキー&プリッツの日」
2013年11月11日、江崎グリコは「ポッキー&プリッツの日」を記念して、Twitterで「ポッキー」を含むツイートを投稿するキャンペーンを展開しました。
このキャンペーンは、24時間で371万回を超えるツイート数を記録し、大きな注目を集めました。特にTwitterユーザーにおいて、キャンペーン当日のポッキー購入者数(1万人あたり)は140人に達し、前週の約4倍に急増。一方で、非Twitterユーザーの購入者数はほぼ横ばいであったことから、キャンペーンがTwitter上での購買意欲を強く喚起したことがわかります。
具体的な影響を見ると、「ポッキー」と実際にツイートした人はキャンペーン前の購入率が26%でしたが、キャンペーン後は44%に上昇しました。また、自らツイートはしなかったものの、他人のツイートを見たユーザーでも購入率は7%から14%へと倍増しました。
Twitterを活用したユーザー参加型のユニークなキャンペーンが、多くの消費者の関心を引きつけ、実際の購買行動にも大きく影響を与えた成功事例となりました。(参照)
ソフトバンクグループ様「一生分の携帯料金プレゼント」
2013年4月18日、ソフトバンクグループは「ソフトバンクFacebookページ」の開設1周年を記念して、Facebookを活用した特別なキャンペーンを開催しました。
このキャンペーンでは、「ソフトバンクFacebookページ」に「いいね!」を押して専用サイトから応募した方を対象に、抽選で1名に携帯電話料金の一生分に相当する518万8,000円の商品券をプレゼントしました。また、さらに抽選で1,000名に1,000円分の商品券も贈呈されました。
「携帯電話料金一生無料」という大胆かつ魅力的な企画が注目され、ソフトバンクユーザーだけでなく、広く一般の方々からも多くの応募を集めました。キャンペーン期間は2013年4月18日から5月17日までの約1か月間で、このユニークなプロモーションはブランドの認知度向上やFacebookページへのユーザー参加を促進し、大きな成功を収めました。(参照)
失敗例:注意すべき落とし穴
某社が運営する低価格ジムチェーンの事例
2024年、某社が運営する低価格ジムにおいて、インフルエンサー10数名に対価を支払い、Instagramでの宣伝投稿を依頼しました。しかし、これらの投稿を自社ウェブサイトに転載する際、「広告」や「PR」などの表記をせず、あたかも一般消費者の体験談であるかのように掲載していました。
さらに、「全サービス24時間使い放題」と謳っていたにもかかわらず、実際にはサービスごとに利用可能時間が限定されており、消費者庁はこれらの行為が景品表示法違反に該当するとして、同社に対し措置命令を出しました。
教訓:広告表記の欠如や誇大表現は短期的な注目を集めることがありますが、法的リスクや消費者の不信感につながりやすく、結果的にはブランドの持続的な成長を妨げます。
東京・大田区のクリニックにおける事例
2024年6月、東京・大田区のクリニックが、インフルエンザワクチン接種費用の割引と引き換えにGoogleマップで高評価の口コミ投稿を促していたことが判明しました。消費者庁は、この行為が景品表示法に違反するステルスマーケティングであるとして行政処分を行いました。
クリニックは、患者に対して「☆4以上の評価を投稿すればワクチン接種代金を割引する」と依頼し、実際に45件以上のステマ投稿が確認されました。口コミには「ワクチンが他より安い」「お得な価格」などの投稿が並び、評価が意図的に操作されていました。この事案は2023年10月のステマ規制施行後、初の措置命令事例となり大きな注目を集めました。
教訓:評価の操作を金銭的報酬と引き換えに行うと、消費者だけでなく業界全体からの信頼を失います。特に医療や健康分野でその影響は甚大であり、信用回復は困難です。
某人気映画のPR漫画にステマ疑惑
2019年12月、某人気映画のレビュー漫画が、複数の人気漫画家のTwitterアカウントで一斉に投稿され、ステルスマーケティング(ステマ)ではないかという疑惑が浮上しました。漫画は好意的な内容ばかりで、同時刻に集中して投稿されたため、「広告会社による指示があったのでは」とネット上で批判が殺到しました。
騒動を受け、一部の漫画家は後日、試写会に招待された上でPRとして描いたものだったと認め、謝罪しましたが、この謝罪も広告会社からの指示によるものではないかとの疑念をさらに強める結果となりました。
教訓:透明性を欠くプロモーションは疑念を招きやすく、消費者からの信頼回復は容易ではありません。企業は明確なPR表記と適切な情報開示により、消費者との誠実な関係を築くべきです。
効果測定とネガティブ対応のポイント
効果測定(KPI設定)
口コミ施策は、広告のクリック数やCV数ほど明確な数値で測りにくい面があります。そこで、以下のようなKPI(重要業績評価指標)を設計するとよいでしょう。
- UGC投稿数:指定ハッシュタグ投稿が何件あったか。
- リーチ数・エンゲージメント率:SNS上のインプレッションやいいね数、シェア数。
- サイト流入やコンバージョン数:紹介リンクやクーポンを経由した流入・購入数。
- NPS(Net Promoter Score):顧客がどれほど商品を他人に勧めたいかを測る指標。
SNSキャンペーンなら、専用ハッシュタグの検索数や投稿数をモニタリングし、Googleアナリティクスなどで流入経路を追跡する方法が一般的です。インフルエンサー施策の場合は、インフルエンサー個別に提供したURLのクリック数やクーポン使用回数などを測定します。
ネガティブ対応の基本姿勢
悪い口コミが出ること自体は避けられません。むしろ、全肯定レビューだけだと“サクラ臭”が強まり逆効果になることも。大切なのは、不満の声を放置せず誠実に対処することです。具体的には、以下のようなポイントを押さえましょう。
- 速やかに対応する:クレームや批判を見つけたら時間を空けすぎずに反応。
- ユーザーの感情を尊重する:「ご指摘ありがとうございます」など丁寧な言葉づかいで返答。
- 事実関係の説明、改善策の提示:誤解があれば正す。改善可能な点は改善検討を伝える。
- ポジティブ変換:改善策を積極的に打ち出すことで逆に企業姿勢を評価されるケースも。
企業アカウントやサポート担当がSNS上でやり取りする場合、言い訳や感情的な対応をすると一気に炎上するリスクがあります。マニュアルやトーン&マナーを事前に社内で共有し、運用方針を浸透させておくことが重要です。
コミュニティをうまく活用すれば、悪い口コミの予兆を察知し、SNSに出る前に対応できるケースがあります。
まとめ
口コミマーケティングは、広告以上の信頼性と費用対効果を生む可能性を秘めた手法です。SNS普及による拡散力を活かせば、中小企業や新興ブランドでも一気に認知度を高められるチャンスがあります。
一方で、ステルスマーケティングのリスクや悪評がコントロールできないという注意点もあります。運用にあたっては慎重さと誠実な姿勢が欠かせません。改めて、以下のようにメリットとデメリット、注意点などを整理しましたのでご活用ください。
- メリット:第三者視点の投稿による信頼度の高さ、コストの低さ、拡散力、UGC自体が資産化しうること
- デメリット:ステマ疑惑や炎上リスク、ネガティブ情報の拡散、コントロールが困難であること
- 代表的手法:SNSキャンペーン、インフルエンサー、モニター募集、レビュー促進、ファンコミュニティ
- 成功事例:ユーモアや限定感など、ユーザーが「シェアしたい」「体験してみたい」と感じる施策が鍵
- 失敗例:ステマ発覚やコピペレビュー強要は企業の信用を大きく損なう
- その他注意点:法遵守・PR表記、効果測定の仕組みづくり、ネガ対応の誠実さ
もし自社で口コミマーケティングを始める場合は、まず自社商品の品質を整え、ユーザーが自然に“勧めたくなる”魅力を高めることが重要です。そこにSNSやインフルエンサー、レビュー機能などの仕掛けを組み合わせ、良い口コミが増えやすい土壌を整備していきましょう。
逆に「口コミを操作しよう」と考えてしまうと、法令違反のリスクが高まり逆効果です。あくまで良いサービス、良いプロダクトがあり、お客様へ十分な価値提供ができていることが本施策における前提条件であることを忘れないようにしましょう。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
