コラム
カスタマーサクセス
リテンションレート(顧客維持率)とは?計算方法からLTV向上に繋げる7つの戦略まで
2025/08/29
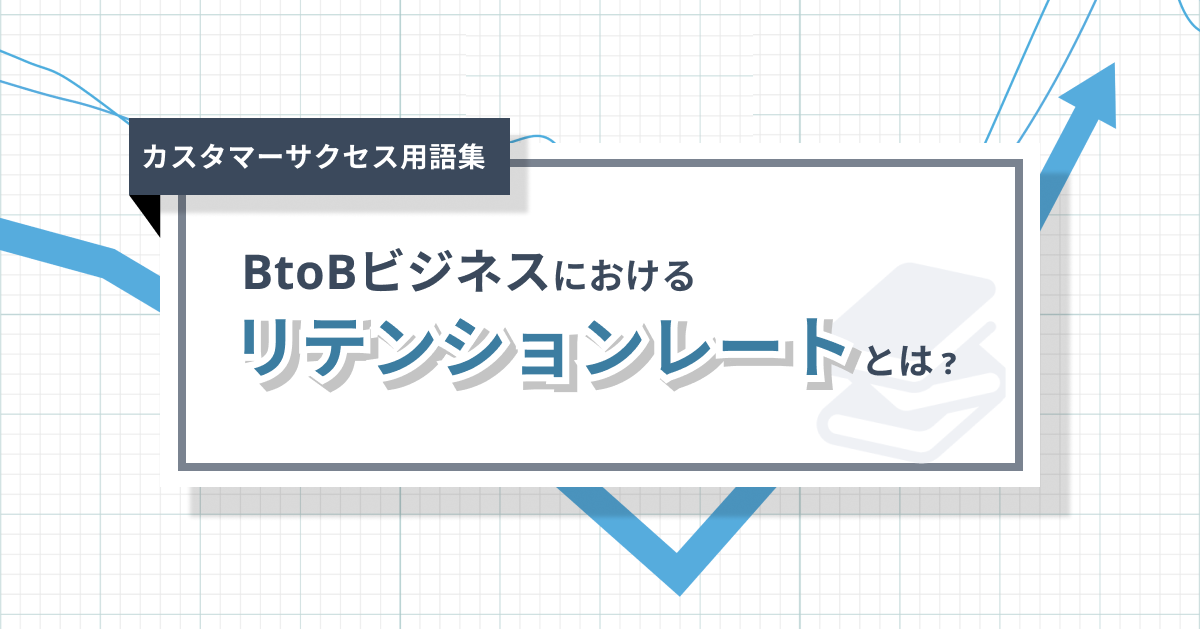
リテンションレート(Retention Rate)とは日本語で「顧客維持率」と訳され、特定の期間において、どれだけの顧客が自社のサービスを継続して利用してくれたかを示す指標です。特に、SaaSビジネスのようなサブスクリプションモデルや、リピート購入が前提となるECサイト、アプリサービスなど、顧客との継続的な関係が事業の根幹をなすビジネスにおいて極めて重要なKPI(重要業績評価指標)とされています。
この指標を正しく理解することは、自社のサービスが顧客に価値を提供し続けられているか、そして事業が健全に成長しているかを測るための第一歩となります。
本稿ではリテンションレートとは何か、という基本的な定義から、具体的な計算方法、そして明日から実践できる向上戦略まで。国内外の最新データと成功事例をもとに、持続可能な成長の設計図を描くための視点をお届けします。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
- 第3章 経営指標で語るメリット――LTV最大化の科学
- ① 収益の安定化と予測可能性の向上
- ② LTV(顧客生涯価値)の最大化
- ③ 顧客獲得コスト(CAC)の相対的削減
- ④ ブランドロイヤルティと口コミ効果の醸成
第1章 リテンションレートとは?その定義と本質
リテンションレートの計算方法
リテンションレートは、以下の計算式で算出します。シンプルですが、正確に計測するためには「期間」と「顧客の定義」を明確にすることが重要です。
計算式: リテンションレート (%) = ( (期間終了時の顧客数 - 期間中の新規顧客数) / 期間開始時の顧客数 ) × 100
具体例:
- 期間開始時(月初)の顧客数:1,000人
- 期間中(1ヶ月間)に獲得した新規顧客数:150人
- 期間終了時(月末)の顧客数:1,050人
この場合のリテンションレートは、 ((1,050 - 150) / 1,000) × 100 = 90% となり、この1ヶ月で90%の既存顧客がサービスを継続利用したことがわかります。
チャーンレート(解約率)との関係性
リテンションレートとしばしば対で語られるのが「チャーンレート(Churn Rate:解約率)」です。この2つはコインの裏表の関係にあり、両方を把握することで顧客動態をより立体的に理解できます。
| 項目 | リテンションレート(顧客維持率) | チャーンレート(解約率) |
|---|---|---|
| 意味 | 顧客がどれだけ残ったかを示す指標 | 顧客がどれだけ離れたかを示す指標 |
| 焦点 | ポジティブな側面(顧客満足度、ロイヤルティ) | ネガティブな側面(製品の問題、顧客サポートの課題) |
| 関係 | リテンションレート + チャーンレート ≒ 100% |
チャーンレート = 100% - リテンションレート |
✅ ポイント: リテンションレートを見ることで「成功要因」を、チャーンレートを見ることで「改善点」を特定しやすくなります。両方の指標を定点観測することが、健全な事業運営の鍵です。
業界別の目安は?
リテンションレートの理想値は、ビジネスモデルや業界によって大きく異なります。例えば、BtoBのSaaSビジネスでは、解約のハードルが比較的高いため、月次で95%以上、年次で80%以上が一つの目安とされています。一方、BtoCのモバイルアプリなどでは競争が激しく、3ヶ月後のリテンションレートが20%を超えれば良好とされる場合もあります。自社のビジネス特性を理解し、業界ベンチマークを参考にしつつ、自社独自の目標を設定することが重要です。
第2章 なぜ今、リテンションレートが最重要指標なのか?

かつては「いかに多くの新規顧客を獲得するか」がマーケティングの主戦場でした。しかし、市場環境の変化に伴い、その常識は大きく変わりつつあります。なぜ今、リテンションレートがこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その背景には、3つの大きな構造変化があります。
1. 新規顧客獲得コスト(CAC)の限界なき高騰
インターネット広告市場は拡大を続け、日本のインターネット広告費は3兆円を突破しました(dentsu.co.jp)。しかし、これは同時に広告出稿の競争激化を意味し、クリック単価は年々上昇。広告に依存した新規顧客獲得モデルは、利益を圧迫し、持続可能性を脅かすようになっています。前述の「1:5の法則」が示す通り、既存顧客の維持に投資する方が、はるかに効率的に事業を成長させられるのです。
2. サブスクリプション経済へのシフト
NetflixやSalesforceに代表されるように、ビジネスモデルは「売り切り型」から「継続利用型(サブスクリプション)」へと大きくシフトしています。このモデルでは、一度の売上よりも、顧客が長期にわたって支払う総額、すなわちLTV(顧客生涯価値)が事業の生命線となります。顧客が契約を継続して初めて利益が生まれるため、リテンションレートの維持・向上は、事業の存続そのものに直結するのです。
3. 顧客主導の購買行動
BtoB領域では、購買担当者の約70%が営業担当者と接触する前にオンラインで情報収集を終えているというデータがあります(openpage.jp)。顧客は広告や営業トークよりも、SNSやレビューサイト、コミュニティでの「リアルな声」を信頼します。つまり、既存顧客の満足度を高め、彼らを熱心なファン(推奨者)に変えることが、最も信頼性の高いマーケティング活動となるのです。高いリテンションレートは、顧客満足度の高さを証明する客観的な証拠と言えるでしょう。
これらの変化は、ビジネスの成功法則が「狩猟型(新規獲得)」から「農耕型(既存育成)」へと移行したことを示唆しています。リテンションレートへの注目は、この不可逆的な変化に対応するための必然なのです。

第3章 経営指標で語るメリット――LTV最大化の科学
リテンションレートの向上は、単なる「顧客離れを防ぐ」という守りの施策ではありません。LTV(顧客生涯価値)を最大化し、事業全体の収益性を高める「攻めの戦略」です。ここでは、リテンションレート向上がもたらす経営上のメリットを4つの観点から定量的に解説します。
① 収益の安定化と予測可能性の向上
高いリテンションレートは、安定した継続収益(リカーリングレベニュー)をもたらします。これにより、毎月の売上予測が立てやすくなり、人材採用や新規事業への投資といった未来に向けた意思決定を、より確信を持って行うことができます。不安定な新規獲得に依存するモデルと比べ、経営の安定性は格段に向上します。
② LTV(顧客生涯価値)の最大化
顧客との関係が長くなるほど、アップセル(上位プランへの移行)やクロスセル(関連商品の購入)の機会が増加します。Harvard Business Schoolの調査では、リテンションレートが5%改善すると、企業の利益は25%から最大95%向上すると報告されています。これは、ロイヤルティの高い顧客ほど購買単価が高くなり、長期にわたって企業に利益をもたらし続けるためです。
③ 顧客獲得コスト(CAC)の相対的削減
既存顧客はすでに自社サービスへの理解があるため、彼らへのマーケティングコストは新規顧客に比べて大幅に低く抑えられます。リテンション施策に投資することで、結果的に事業全体の顧客獲得コスト(CAC)を最適化し、マーケティングROI(投資対効果)を劇的に改善することが可能です。
④ ブランドロイヤルティと口コミ効果の醸成
満足度の高い顧客は、単にサービスを使い続けてくれるだけでなく、熱心なファンとなり、自発的に友人や同僚にサービスを推奨してくれます。このオーガニックな口コミは、広告よりもはるかに信頼性が高く、質の高い新規顧客を低コストで呼び込む強力なエンジンとなります。NPS®(ネット・プロモーター・スコア)とリテンションレートに強い相関関係があることからも、顧客ロイヤルティの重要性が伺えます。
リテンションレートは、これらすべての経営メリットの源泉となる、まさに事業成長の「先行指標」なのです。
第4章 よくある3つの失敗パターン
リテンションレートの重要性を理解し、いざ改善に取り組もうとしても、多くの企業が陥りがちな落とし穴があります。ここでは、代表的な3つの失敗パターンとその克服戦略を解説します。
① 短期的な成果を追い求め、すぐに諦めてしまう
リテンション施策は、広告のように即効性があるものではありません。顧客との信頼関係を築き、それが数字として表れるまでには、少なくとも6ヶ月から1年程度の時間が必要です。
克服戦略:先行指標(KPI)を設定し、小さな成功を可視化する
最終的なリテンションレートの改善だけでなく、そこに至るまでの中間指標を設定しましょう。例えば、「オンボーディング完了率」「特定機能の利用率」「コミュニティへの投稿数」といったエンゲージメント指標を先行KPIとすることで、施策の進捗を定量的に把握し、チームのモチベーションを維持できます。
② 全体の平均値だけを見て、顧客セグメントを無視する
「リテンションレートが95%」という数字だけを見て安心してしまうのは危険です。実際には、ロイヤルティの高い優良顧客と、すぐに離反してしまう顧客が混在している可能性があります。
克服戦略:コホート分析で顧客グループごとの定着率を把握する
コホート分析とは、顧客を「利用開始月」などの共通項でグループ分けし、その後の定着率を時系列で追跡する手法です。これにより、「2024年1月に登録したユーザーは定着率が高いが、4月に登録したユーザーは低い」といったインサイトを発見できます。特定のグループの離反率が高い原因(例:プロダクトのバグ、サポート体制の変更)を特定し、的確な対策を打つことが可能になります。
③ 顧客維持を「特定部門の仕事」だと捉えてしまう
「リテンションはカスタマーサクセス部門の仕事」といったように、顧客維持を特定の部門に押し付けてしまうと、根本的な解決には至りません。顧客の離反理由は、製品の使いにくさ(開発部門)、期待値と実態の乖離(マーケティング・営業部門)、サポートの質の低さ(CS部門)など、複数の部門にまたがっていることがほとんどです。
克服戦略:全社でCX(顧客体験)向上に取り組む文化を醸成する
顧客からのフィードバックやNPSスコア、解約理由といったデータを、部門の垣根を越えて共有する仕組みを構築しましょう。経営層が主導し、CXを全社共通のKPIとして設定することで、「すべての部門が顧客の成功に責任を持つ」という文化が醸成され、組織全体でリテンション向上に取り組む体制が整います。
第5章 国内外の成功事例と数字――“顧客との絆”が利益を生む
理論だけでなく、実際にリテンションレートを向上させ、事業成長を加速させた企業の事例を見ていきましょう。ここでは、BtoCとBtoBの代表的な成功事例を2つ紹介します。
✅ 事例1:カインズ(BtoC・ホームセンター)
ホームセンター大手のカインズは、オンラインコミュニティ「DIY Square」を運営しています。このコミュニティは、単なる商品販売の場ではなく、DIY好きのユーザー同士が作品を投稿し、ノウハウを教え合い、交流するためのプラットフォームです。
成果:
- エンゲージメントの向上: ユーザーはコミュニティを通じてDIYの楽しさや成功体験を共有し、カインズブランドへの愛着を深めています。
- 来店・購買促進: コミュニティで得たアイデアを形にするため、ユーザーはカインズの店舗やオンラインストアを訪れます。結果として、コミュニティ参加者の来店頻度と購買単価は、非参加者に比べて有意に高いというデータが出ています。
- 顧客インサイトの獲得: ユーザーの投稿から「どんな商品が求められているか」「どんな使い方に困っているか」といった貴重なインサイトを得て、商品開発や店舗改善に活かしています。
カインズは、商品を売るだけでなく「DIYを通じた豊かな暮らし」という体験を提供することで、顧客との長期的な関係を築き、高いリテンションを実現しています。
✅ 事例2:Sansan(BtoB・名刺管理サービス)
法人向け名刺管理サービスを提供するSansanは、ユーザーコミュニティ「Sansan Innovation Community」を積極的に活用しています。このコミュニティでは、活用度の高いユーザーが登壇するセミナーや、ユーザー同士が情報交換を行う分科会などを定期的に開催しています。
成果:
- チャーンレート(解約率)の大幅な低減: コミュニティに参加し、他のユーザーの成功事例や活用ノウハウを学ぶことで、サービスの価値を再認識し、活用度が向上。これが結果として解約率の低下に直結しています。SansanのARR(年間経常収益)における解約率は1%未満という驚異的な水準を維持しており、その背景にはコミュニティによるリテンション向上が大きく貢献しています。
- アップセルの促進: ユーザー同士の交流の中から「こんな使い方があったのか」という発見が生まれ、より上位の機能やプランへのアップセルに繋がっています。
- 製品開発へのフィードバック: コミュニティは、ユーザーの生の声を聞く貴重な場です。ここで得られた要望や課題は、製品開発チームにフィードバックされ、サービスの継続的な改善に役立てられています。
両社に共通するのは、一方的な情報提供ではなく、顧客同士がつながり、価値を共創する「場」を提供している点です。この”顧客との絆”こそが、現代における最も強力なリテンション戦略なのです。
第6章 リテンション向上ロードマップ――顧客中心経営への4ステップ
リテンション向上は、単発の施策ではなく、組織的な仕組みとして定着させることが不可欠です。ここでは、顧客中心の取り組みを組織に根付かせるための、実践的な4段階のロードマップを紹介します。
ステップ1:現状把握と目標設定
まずは自社の現在地を正確に知ることから始めます。前述の計算式でリテンションレートを算出し、可能であれば業界ベンチマークと比較してみましょう。その上で、「半年後にリテンションレートを3%改善する」「主要顧客セグメントのチャーンレートを半減させる」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定します。この目標が、今後のすべての活動の羅針盤となります。
ステップ2:顧客理解と離反要因の特定
次に、なぜ顧客が離反するのか、その根本原因を深掘りします。解約アンケートやNPS調査といった定量データに加え、解約した顧客へのインタビューといった定性データを組み合わせることで、顧客の「声」と「行動」の両面から課題を立体的に捉えます。「価格が高い」という表面的な理由の裏にある、「価値が伝わっていなかった」「オンボーディングでつまずいた」といった本質的な原因を突き止めることが重要です。
ステップ3:顧客体験ジャーニーに沿った施策の立案・実行
特定した課題を解決するため、顧客のステージ(認知→検討→導入→活用→定着)に合わせた施策を設計・実行します。
- 導入初期: スムーズなオンボーディングプログラムの提供、ウェルカムメールの配信
- 活用中期: 活用度に応じたTipsの配信、成功事例の共有、ユーザー会の開催
- 定着後期: 上位プランの提案、新機能の先行案内、ロイヤルティプログラムの提供 重要なのは、すべての施策が分断されず、一貫した顧客体験として提供されることです。
ステップ4:効果測定と改善サイクルの確立
実行した施策がリテンションレートにどのような影響を与えたかを、データに基づいて検証します。MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客管理システム)、コミュニティツールなどを活用して成果をダッシュボードで可視化し、週次や月次でレビューを行いましょう。「施策Aはエンゲージメント向上に繋がったが、解約率改善には至らなかった。次はBの切り口で試そう」といったように、高速でPDCAサイクルを回す文化を組織に根付かせることが、持続的なリテンション向上の鍵となります。
この4ステップを仕組みとして回せるようになったとき、企業は真の「顧客中心経営」を実現し、揺るぎない競争優位性を手に入れることができるのです。
第7章 まとめと行動プラン:あなたの次の一手は?
新規顧客獲得の競争が激化し、顧客が自ら情報を選択する時代において、「いかに顧客と長期的な関係を築くか」がビジネスの成否を分ける決定的な要因となっています。本記事で解説してきたように、リテンションレートは単なる一指標ではなく、顧客満足度、事業の健全性、そして未来の成長可能性を示すバロメーターです。
- ROI効果: 顧客維持率5%改善で利益が25%以上向上
- 市場トレンド: 「売り切り」から「継続利用」へのシフトが加速
- 成功の鍵: 顧客とのエンゲージメントを高め、ロイヤルティを醸成すること
この変化の波に乗り、持続可能な成長を実現するために、まずは今日からできる小さな一歩を踏み出してみませんか。
✅ 今日からできる!リテンション向上の3ステップ
① まずは自社のリテンションレートを計算してみる
何よりも先に、現状を数字で正確に把握しましょう。期間を定め、計算式に当てはめてみるだけで、これまで見えていなかった課題や機会が明らかになるはずです。
② 直近で解約した顧客3名に、正直な理由を聞いてみる
アンケートの数字だけではわからない、顧客の生々しい「本音」に耳を傾けてみましょう。「なぜ解約したのか」「何が不満だったのか」だけでなく、「どこに期待していたのか」を聞くことで、改善のヒントが必ず見つかります。
③ 顧客が最も喜んだ瞬間(成功体験)を社内で共有する
ネガティブな側面に加え、ポジティブな側面にも光を当てましょう。カスタマーサポートに届いた感謝の声や、営業担当者が聞いた成功事例を全社で共有することで、「顧客の成功とは何か」という共通認識が生まれ、組織全体のモチベーションが高まります。
これらのステップを通じて顧客との関係性を深めていく上で、オンラインコミュニティは極めて有効な手段です。顧客同士がつながり、成功体験を共有し合う場は、エンゲージメントを高め、解約の兆候を早期に察知し、ロイヤルティを育む土壌となります。
Commune (コミューン) は、そうした顧客との理想的な関係構築をノーコードで実現するコミュニティサクセスプラットフォームです。DM、イベント管理、ナレッジ共有といった多彩な機能を通じて、顧客の能動的なアクションを促し、リテンションレートの向上とLTVの最大化に貢献します。
Commune (コミューン) がどのように貴社のビジネス成長に貢献できるか、詳しい情報が気になる方は、以下のフォームからお気軽に資料をダウンロードしてください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
