コラム
社内コミュニティ
心理的安全性とは?その理論的背景・組織パフォーマンスへの影響・実践的アプローチ
2024/04/08
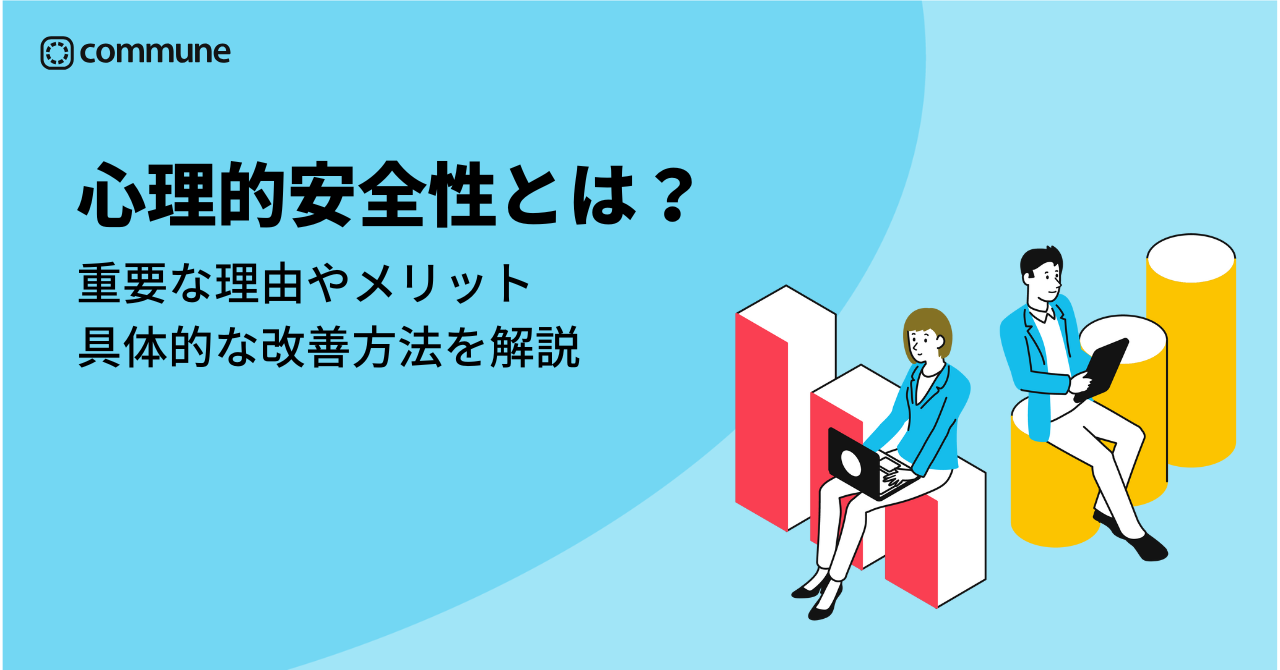
心理的安全性(Psychological Safety)」とは、職場の中で自分の意見や疑問、心配事、失敗などを、まわりの目を気にせずに安心して話せる状態のことです。最近の研究では、心理的安全性が高い職場ほど、社員の多様な考えやアイデアが活かされ、組織の成長や新しいことへの挑戦が進みやすいことが分かっています。この記事では、心理的安全性の基本的な考え方や、組織の成果への影響、実際にどうやって高めていくかを分かりやすく説明します。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次

心理的安全性(Psychological Safety)は、1990年代後半から注目されている考え方です。単に「話しやすい」「仲が良い」だけではなく、チームの中で「対人リスク(interpersonal risk)」、つまり「こんなことを言ったらどう思われるか」といった不安を感じずに発言できる雰囲気があることが大切です。
ポイントは、みんなが安心して意見を言える「チームのルール(team norm)」があるかどうかです。さらに、心理的安全性は個人の性格や能力だけでなく、組織全体の文化やリーダーシップのあり方、日々のコミュニケーションの質にも大きく左右されます。心理的安全性が高い職場では、メンバー同士が互いの違いを尊重し、失敗や異論を恐れずに率直な意見交換ができるため、組織全体のパフォーマンスや創造性が向上します。
エイミー・C・エドモンドソン教授による理論的定義
ハーバード・ビジネス・スクールのエドモンドソン教授は、1999年の論文で「チームの中で自分が無知・無能・否定的・邪魔だと思われるリスクを取っても、不安を感じずに発言・行動できる状態」と心理的安全性を定義しました。これは「学習する組織(Learning Organization)」の土台であり、知識や経験をみんなで共有し合うために欠かせません。
エドモンドソン教授は、心理的安全性が高い組織では、メンバーが自分の弱みや失敗を隠さずにオープンにできるため、組織全体の学習速度が上がり、イノベーションが生まれやすくなると指摘しています。また、心理的安全性は単なる「仲良しグループ」ではなく、建設的な対立や率直なフィードバックが活発に行われる環境であることが重要です。
心理的安全性が高いチームでは、メンバーが失敗や疑問を素直に話せるので、「エラー・マネジメント」や「知識共有」が進みます。逆に心理的安全性が低いと、みんなが黙ってしまい(サイレント・コンプライアンス)、新しいことに挑戦しにくくなります。さらに、心理的安全性が低い職場では、情報が隠蔽されやすく、問題の早期発見や改善が遅れる傾向があります。これにより、組織の成長や変革が阻害され、最終的には業績の低下や人材流出につながるリスクも高まります。
Google「プロジェクト・アリストテレス」とエビデンス
Google社は2012年から4年間、180以上のチームを調べて「成果の出るチームの条件」を分析しました。その結果、最も大事なのは「心理的安全性」だと分かりました。個人の能力やスキルよりも、安心して発言・質問・失敗できる環境が、成果や生産性、離職率の低下に直結していることが証明されています。
Googleの調査では、心理的安全性が高いチームほど、メンバー同士の信頼関係が強く、情報共有や協力が活発であることが明らかになりました。また、心理的安全性は、イノベーションや新規事業の創出、顧客満足度の向上にも寄与することが示されています。さらに、心理的安全性が高い職場では、従業員のウェルビーイング(心身の健康)やエンゲージメントも高まる傾向があります。
「心理的安全性」と「ぬるま湯組織」の違い
心理的安全性は「何でも許される甘い組織」とは違います。大事なのは、建設的な意見のぶつかり合いや異論を歓迎し、変化を目指すチームのルールがあることです。ぬるま湯組織は、対立やリスクを避けて現状維持になりがちですが、心理的安全性が高い組織は、失敗や対立も「学びのチャンス」として受け止め、みんなで率直にフィードバックし合う文化があります。
心理的安全性のある組織では、メンバーが互いに高い期待を持ち、目標達成のために積極的に意見を出し合います。一方、ぬるま湯組織では、表面的な調和が優先され、問題が見過ごされやすくなります。心理的安全性は「優しさ」だけでなく、「率直さ」や「挑戦」を両立させるバランスが重要です。
心理的安全性が求められる理由

今の時代は、VUCA(変化が激しく、先が読みにくい時代)と言われています。昔ながらのトップダウンや、みんな同じ考え方の組織では、変化に対応できません。いろいろな経験や考え方を持つ人が協力するには、心理的安全性が欠かせません。
心理的安全性が高いと、みんなが「否定されるかも」という不安なく意見を言え、活発な議論や新しいアイデアが生まれやすくなります。これがイノベーションや業績アップ、エンゲージメント向上、離職率低下につながることが、最近の研究でも分かっています。
さらに、心理的安全性は、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂)の推進や、働き方改革、リモートワークの普及など、現代の多様な働き方にも不可欠な要素です。心理的安全性が高い組織では、異なる価値観やバックグラウンドを持つ人材が活躍しやすくなり、組織の競争力や持続的成長にもつながります。
働き方改革と心理的安全性の関係
働き方改革やダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を進める上でも、心理的安全性はとても大切です。制度やオフィス環境を整えるだけでなく、心の面での安心感がなければ、本当の意味で多様性を活かしたり、新しいことに挑戦したりするのは難しいです。心理的安全性があれば、社員は失敗や異論を恐れずにチャレンジでき、組織の「回復力(レジリエンス)」も高まります。
D&Iの観点では、心理的安全性が低いと、マイノリティや新しいメンバーが意見を言いにくくなり、組織の多様性が形骸化してしまうリスクがあります。逆に、心理的安全性が高い職場では、全員が自分らしく働けるため、イノベーションや顧客価値の創出にもつながります。また、心理的安全性は、メンタルヘルスの維持やワークライフバランスの向上にも寄与します。
リモートワーク時代における心理的安全性の重要性
リモートワークやハイブリッドワークが増えると、ちょっとした雑談や表情・しぐさなどの非言語コミュニケーションが減り、心理的安全性を保つのが難しくなります。物理的な距離が心の距離になりやすく、孤立感や誤解も生まれやすいです。
これを防ぐには、定期的な1on1やオンラインでのチームビルディング、デジタルツールを使った「意図的なコミュニケーション設計」が必要です。さらに、リモート環境では、情報共有の透明性や、メンバー同士の信頼構築がより重要になります。オンライン会議では、発言しやすい雰囲気づくりや、チャット・アンケートなど多様なコミュニケーション手段の活用が効果的です。また、リーダーはメンバーの状況をこまめに把握し、孤立やストレスのサインを見逃さないようにすることが求められます。
心理的安全性が低い職場で生まれる4つの不安

心理的安全性が低い職場では、社員は次の4つの「対人リスク」に不安を感じやすくなります(Edmondson, 1999)。
- 無知だと思われる不安(質問や確認がしにくい)
- 無能だと思われる不安(失敗や弱みを隠してしまう)
- 邪魔だと思われる不安(提案や発言を控えてしまう)
- ネガティブだと思われる不安(異論や反論を避けてしまう)
こうした不安が広がると、みんなが黙りがちになり(沈黙のスパイラル)、知識の共有や問題発見ができず、最終的には業績悪化や離職増加につながります。さらに、心理的安全性が低い職場では、メンバー同士の信頼関係が弱まり、チームワークや協力が難しくなります。
これにより、個人のパフォーマンスだけでなく、組織全体の成果や顧客満足度にも悪影響が及びます。また、心理的安全性が低い環境では、ハラスメントやパワハラなどのリスクも高まるため、組織としての健全性が損なわれる恐れがあります。
心理的安全性の高い職場をつくるメリット

心理的安全性が高い職場には、次のような良いことがあります。
- 情報やアイデアが活発にやりとりされ、組織の学びが進む
- エラーや課題を早く見つけて直せる(エラー・マネジメント文化)
- メンバーの自信ややる気(エンゲージメント)が高まり、成果も上がる
- 離職率が下がり、人材が定着しやすくなる(人的資本経営にも重要)
- いろいろな視点が集まり、イノベーションが生まれやすい
- メンバーが自分の強みや個性を発揮しやすくなり、キャリア開発や成長機会が増える
- 心理的安全性が高いことで、メンタルヘルスの維持やストレス軽減にもつながる
- 組織のブランド価値や社会的信頼も向上し、優秀な人材の採用にも有利になる
心理的安全性の高い職場を作る上での経営者・管理職の役割

心理的安全性を高めるためには、日々のコミュニケーションや組織文化の在り方が重要です。まず、異論や疑問を自由に表明できるオープンなコミュニケーションの場を設けることが大切です。リーダー自身が「分からない」「間違えた」と率直に話すことで、メンバーも安心して発言できる雰囲気が生まれます。
また、定期的な360度フィードバックなどを通じて双方向のやりとりを増やし、共通の目標や役割を明確にすることで、協力しやすい環境を整えます。メンバー同士で感謝や称賛を伝え合う文化を育てることも、信頼関係の醸成に寄与します。
さらに、失敗や課題をオープンに共有し、責めるのではなく学びの機会とする姿勢が重要です。多様な意見や価値観を尊重し、少数派の声にも耳を傾けることで、組織全体の心理的安全性が高まります。こうした取り組みを支えるために、心理的安全性に関する研修やワークショップを定期的に実施することも有効です。
心理的安全性を高めるための具体的なアクション
心理的安全性の状態を正確に把握し、継続的に改善していくためには、サーベイや各種指標を活用した「見える化」が不可欠です。
たとえば、Googleが提唱する「チームの効果性」調査指標や、エイミー・エドモンドソン教授による7項目サーベイ、社員エンゲージメントサーベイなどを用いることで、信頼や透明性、役割の明確さ、対人リスクへの認識、チーム内の心理的な障壁の有無など多角的な観点から現状を測定できます。加えて、360度フィードバックによる多面的な評価や定期的なパルスサーベイ、1on1ミーティングの記録を活用して現場のリアルな声を可視化することも非常に有効です。
さらに、離職率やエラー報告件数、社内SNSの投稿数、従業員満足度スコアなどの定量的なデータも組み合わせて分析することで、組織の健康状態をより客観的に診断できます。これらの測定結果は経営層や現場リーダーが積極的に共有し、具体的なアクションプランや改善施策に落とし込むことが重要です。PDCAサイクルを回しながら、継続的な改善を図ることで、組織全体の心理的安全性を高めていくことが可能となります。
組織の心理的安全性を高める方法

組織の安全性を高めるためには、チームリーダーやマネージャーが積極的に働きかけることが重要です。
まず、メンバーが気軽に質問や相談を持ちかけられるような、心理的なハードルの低い雰囲気を日頃から意識して作り出しましょう。例えば、日常的に「何か困っていることはないか」と声をかけたり、意見を求める場を設けることで、メンバーが自分の考えや疑問を率直に表現できるようになります。
また、意見の違いやミスがあった場合でも、否定や非難ではなく、相手の立場や背景を理解しながら建設的な議論を心がけることが大切です。これにより、失敗を恐れずにチャレンジできる環境が生まれます。
さらに、すべてのメンバーに対して公平に発言の機会を与えることも欠かせません。会議やディスカッションの際には、発言が少ない人にも意見を求めたり、発言しやすい雰囲気を作ることで、多様な視点を引き出すことができます。
加えて、組織内の風通しを良くし、個々の価値観やバックグラウンドの違いを尊重する姿勢を示すことで、メンバー一人ひとりが自分らしく働ける環境が整います。最後に、困っている人がいれば自然と手を差し伸べる、助け合いの精神を日常的に大切にすることで、信頼関係が深まり、組織全体の結束力や安全性がより一層高まります。これらの取り組みを継続的に行うことで、心理的安全性の高い強い組織を築くことができるでしょう。
心理的安全性を可視化する指標・測定方法

心理的安全性を強化するためには、まず状況を正確に把握することが重要です。心理的安全性を可視化する指標や測定方法として、いくつかの方法があります。
Googleが用いる「チームの効果性」調査指標
Googleの「チームの効果性」調査指標は、チームが高いパフォーマンスを発揮するために必要な要素を明確にし、評価するための指標として知られています。
指標を用いた調査の結果、Googleはチームの効果性に最も寄与する要素は「心理的安全性」と結論付けました。心理的安全性が高い環境では、チームメンバーが自由に意見を述べ、ミスを恐れずに新たな挑戦をすることができ、その結果としてチームの成果が最大化されるのです。
この調査指標での測定項目は、「信頼関係」「透明なコミュニケーション」「明確な役割分担」「各メンバーの貢献度」となっており、これらの要素が揃った組織では、心理的安全性が自然と高まり、社員が意欲的に業務に取り組むことが可能となるのです。
社員エンゲージメントサーベイの活用
社員エンゲージメントサーベイは、従業員と会社とのつながりの強さを数値化して把握するための調査ツールです。定期的に実施することにより、組織内の現状を正確に把握し、改善が必要な点を見つけることができます。
例えば、エンゲージメントが低い部門では、社員が意見を表明しにくい環境があるか、またはリーダーシップに関する改善が求められている場合があります。このような結果を基に、経営層や管理職は的確な改善策を講じることができるため、心理的安全性を可視化するうえで非常に役立つ調査方法です。
360度フィードバックによる評価
一人の従業員に対して、様々な立場の関係者(上司、同僚、部下など)から多角的に評価し、その結果を本人にフィードバックする制度が360度フィードバックです。
例えば、あるプロジェクトチームが360度フィードバックを実施し、その結果として「指示が曖昧で、チームメンバーが不安を感じている」といった課題が浮き彫りになった場合、リーダーは具体的な目標設定やコミュニケーションの改善が必要と気づけます。
その結果としてチーム全体の心理的安全性が向上し、パフォーマンスの改善が期待できます。このように、360度フィードバックは、心理的安全性を測る上で非常に有用なツールです。定期的に実施することで、企業全体の心理的安全性を高められるでしょう。
心理的安全性を高めるために効果的な施策

組織の安全性を高めるために、経営陣や人事担当者は次のような施策の導入を検討してみましょう。
・1on1ミーティング
・OKR
・ピアボーナス
・社内コミュニティサイトの開設
1on1ミーティング
1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で行う面談です。人事評価面談とは異なり、業務や人間関係に関する不安や悩みなどについて話し合います。上司からの一方的な指示や指導ではなく、双方のコミュニケーションを行うことがポイントです。1on1ミーティングを通じて上司と部下の信頼関係を構築することで、心理的安全性が高まりやすくなります。
OKR
OKRとは、「達成目標(Objectives)」と「主要な成果(Key Results)」を設定し、組織と個人が同じ課題に取り組むための制度です。まずは組織全体の大きな目標を設定し、次にそれを実現するために必要な個人目標を設定します。チームで成果を出すための個人の役割が明確化し、全体が同じ目標に向かって進みやすくなるため、心理的安全性の向上が見込めます。
ピアボーナス
ピアボーナスは、従業員同士で報酬やギフトのやり取りができる制度です。心理的安全性の向上には、「チームやメンバーから認められている」という実感も大切です。ピアボーナスの導入によってお互いを認め合える機会が生まれるため、組織の心理的安全性が高まります。さらに、個々のメンバーの「もっと貢献したい」という意欲も刺激できるため、成果も向上するでしょう。
社内コミュニティサイトの開設
社内コミュニティサイトは、従業員同士が気軽にコミュニケーションを取れる場所です。業務用のチャットツールではなく、敢えて別の場所でコミュニケーションを取ることで、SNS感覚で社内の人と繋がりを持つことができます。普段、業務では関わることのない人とも繋がることで、従業員同士の信頼関係や連携を強化できるでしょう。
心理的安全性を高い組織をつくるためのポイント・注意点

組織の心理的安全性を高めるための施策を実施する際は、次の3つのポイントに注意しましょう。
・まずは組織の心理的安全性を測定する
・責任感や緊張感をなくさないようにする
・意見やアイデアの衝突を恐れないようにする
まずは組織の心理的安全性を測定する
まずは自社の心理的安全性を測定してみましょう。Googleのリサーチによると、チームメンバーに次の7つの質問をすることで、チームの心理的安全性のレベルが分かります。
1. チームの中でミスをすると、たいてい非難される。
2. チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。
3. チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。
4. チームに対してリスクのある行動をしても安全である。
5. チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。
6. チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。
7. チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。
(引用元:「効果的なチームとは何か」を知る)
1・3・5の質問に「いいえ」、それ以外に「はい」と答える数が多いほど、心理的安全性が高い状態だといえます。その数が少ない場合は、積極的な改善施策が必要となるでしょう。
責任感や緊張感を無くさない
心理的安全性が高い組織は、決して「無責任に何を言っても許される」というものではありません。むしろ自身の言動がチームに与える影響が増すため、これまで以上の責任感や成長意欲が求められます。「コミュニケーションを取りやすい環境」は、友達のような距離感とは異なります。常に一定の緊張感を保つように、リーダーがコントロールすることが大切です。
意見やアイデアの衝突を恐れない
多様な意見を取り入れることは、「何でも無条件に肯定する」ということではありません。むしろチームの成果を高めるためには、建設的な意見の衝突が欠かせません。そのため、相手の発言に対して異議がある場合は、それを合理的に伝えるようにしましょう。ただし意見の衝突が発生したときは、メンバーが感情的にならないようリーダーがコントロールすることも重要です。
働きやすい職場の構築には社内コミュニティ「Commune for Work」がおすすめ
社内コミュニティ「Commune for Work」には、社内コミュニティに必要な機能が網羅されています。社内コミュニケーションの活性化はもちろん、従業員エンゲージメントの向上や人材育成効果の最大化も実現でき、働きやすい職場の構築に役立ちます。この機会にぜひ、Commune for Workの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
以下のフォームから「3分でわかるCommune for Work」資料をダウンロードできます。社内コミュニティのメリットや具体的な事例をご確認いただけます。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
