コラム
マーケティング
ファンマーケティングとは?意味・効果・実践方法までわかりやすく解説!
2025/07/09
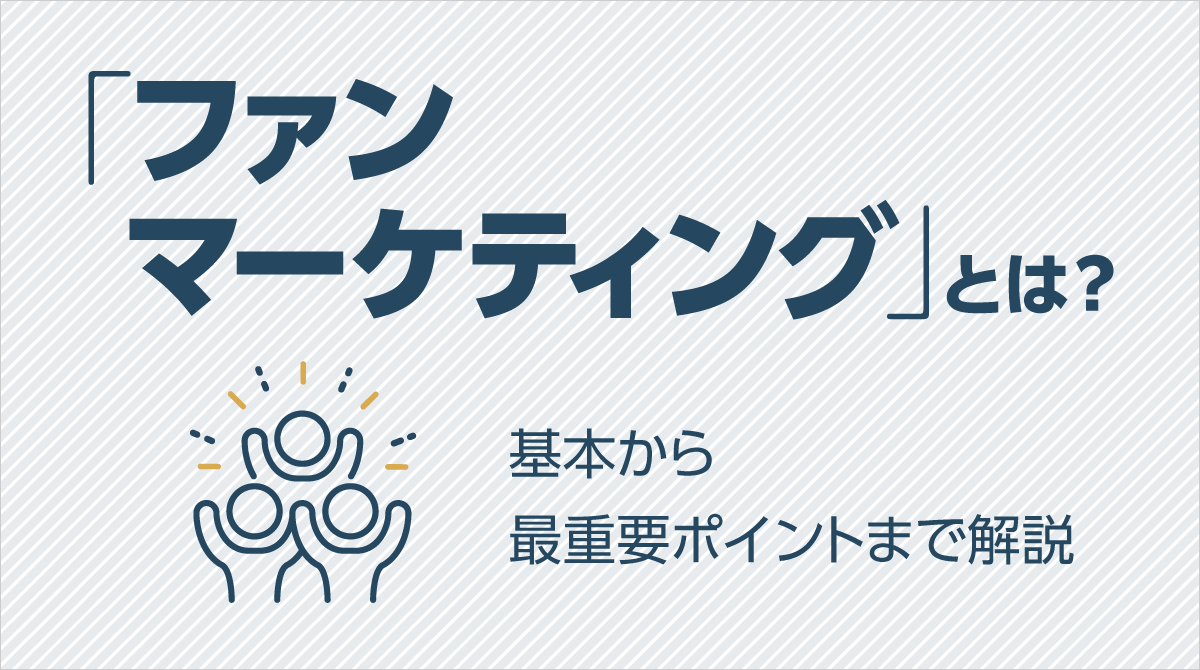
「ファンマーケティングって最近よく聞くけど、実際どんなことをするの?」
「広告やSNSマーケと何が違うの?」
「うちの事業にも使えるのか知りたい!」
そんな疑問に応えるため、本記事ではファンマーケティングの基本から、他マーケ手法との違い、期待できる効果、具体的な施策までをわかりやすく解説します。
BtoC企業やSaaSなどLTVを重視するビジネスには特に有効とされる“ファンマーケ”。まずは意味や仕組みを理解し、貴社の事業にどう活かせるかを一緒に見ていきましょう。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
- 4. ファンマーケティングで得られる効果
- 4-1. 顧客ロイヤルティの向上
- 4-2. 口コミや紹介による自然な広がり
- 4-3. 顧客からのフィードバックが得やすくなる
- 4-4. ブランド価値の向上と共創の可能性
1.ファンマーケティングとは顧客との継続的関係性を築くマーケティング手法
ファンマーケティングとは、商品やサービスの“ファン”と呼べる顧客と継続的な関係を築き、中長期的な売上やブランド価値の向上を目指すマーケティング手法です。
ここでいう“ファン”とは、単に商品を購入した人だけではなく、ブランドの世界観に共感し、応援してくれる存在のこと。企業が一方的に発信するのではなく、ファンと双方向のコミュニケーションを通じて、共にブランドを育てていく姿勢が特徴です。
たとえば、商品購入後にSNSで投稿してくれたり、口コミで広めたり、アンバサダーとして自発的に動いてくれる顧客などが該当します。こうした顧客発の熱量ある情報は、広告にはない深い信頼と影響力を持ちます。
なお、「ファンマーケティング」と似た表現に「ファンベースマーケティング」がありますが、基本的には同じ概念と考えてよいでしょう。
- ファンベースマーケティング: 佐藤尚之氏が提唱した概念で、哲学的・思想的な側面が強い
- ファンマーケティング: 企業が実践する戦略や施策として使われることが多い
補足として、電通デジタルでは次のように定義されています。
ファンマーケティングとは、ブランドや商品、サービスのファンに着目し、彼/彼女らと密接にコミュニケーションをとることで、「中長期的な売り上げの増大」や「ブランドやそのカルチャーの共創」を図るマーケティング方法、またはその概念です。
出典:電通デジタル
2.ファンマーケティングと他のマーケティング手法の違い
ファンマーケティングは、広告やインフルエンサーマーケティングなどの従来の手法と比べて、「関係性の長さ」や「長期的な視点」に重点を置くという部分が大きな特徴です。
2-1広告との違い:アプローチの方向性
広告は、企業から顧客へ情報を届ける一方通行のアプローチが基本です。短期的な認知拡大やCV獲得には効果的ですが、顧客との関係性は築かれづらく、価格や機能などで競合と比較されやすい傾向があります。
一方、ファンマーケティングは、すでに関心を持つ顧客との関係を深め続けるアプローチです。企業の提供価値に共感し、「応援したい」と思わせる関係性を築くことで、価格競争に巻き込まれず、ロイヤル顧客を育てることができます。
2-2インフルエンサーマーケとの違い:広げる“人”の質
インフルエンサーマーケティングは、影響力のある人物を介して広くリーチする施策。話題性や瞬発力に優れていますが、インフルエンサー本人がブランドに共感していない場合、信頼性が低くなるリスクもあります。
ファンマーケティングでは、すでに愛着を持ってくれている顧客を起点に広がるため、伝わる情報の熱量が段違い。紹介やクチコミも、リアルな体験や感情がベースになっているため、信頼性が高く刺さりやすいのです。
つまり、
- インフルエンサーマーケティング:インフルエンサーのファンが対象
- ファンマーケティング:自社のファンが対象
この違いが、本質的な差と考えることができます。
2-3従来マーケとの違い:ファネル構造とその先
従来のマーケティングは、「認知 → 興味 → 購入」というファネル型モデルが前提。とにかく接点を増やして、購入につなげるのが目的でした。
しかし、ファンマーケティングはその先。購入後の関係構築や共創フェーズまでを見据えた、“逆ファネル”のような発想に近いです。
- 接点 → 関係性(応援)→ 共創
- 購入 → シェア・投稿 → ファンコミュニティ参加
こうした流れの中で、顧客は「単なる購買者」から「ブランドの共犯者(仲間)」へと変わっていきます。これこそが、ファンマーケティングの最大の魅力です。
3.なぜ今、ファンマーケティングなのか?
ファンマーケティングが注目されている背景には、社会構造や顧客行動の大きな変化があります。従来のマーケティング手法では、ユーザーに「響きにくくなっている」現実があり、企業は新たなアプローチを模索しています。
3-1. 人口減少と新規顧客獲得の難化
日本では2008年をピークに人口減少が続いており、2024年時点で約1億2,380万人と14年連続で減少中です。さらに、総人口に占める生産年齢人口の割合も低下しており、購買力を持つ層の縮小も進んでいます。
これにより、新規顧客の獲得競争が激化。限られた市場での「刈り取り」ではなく、今いる顧客と長く付き合うマーケティングが求められています。
※出展 nippon.com 「日本の人口、14年連続で減少」
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02382/
3-2. 広告疲れと信頼性の低下
経済産業省の調査やPR TIMESのレポートによると、70%超の消費者がウェブ広告にストレスや不快感を抱いているというデータがあります。
また、日本広告審査機構(JARO)への広告に関する苦情も年間4,000件を超えており、ネット広告への不信感は継続中です。
一方的なPRでは、ユーザーの共感を得るのが難しくなっている現実が浮き彫りになっています。
※出展 日本広告審査機構「2024年度上半期審査状況」
https://www.jaro.or.jp/news/20250107.html
3‑3. SNSの普及と「共感」の重視
総務省のデータによると、日本のSNS利用者数は2023年時点で約1億580万人に達しており、年々増加傾向にあります。
SNSの大きな特徴は、企業発信よりも「身近な人の体験や共感」が届きやすいという点。ファンの感想や口コミに基づくUGC(ユーザー生成コンテンツ)は、購買行動に直結する信頼の証となっています。
※出展 総務省「令和6年版 情報通信白書の概要」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd217100.html
3-4. LTV(顧客生涯価値)重視への転換
新規顧客の獲得コスト(CAC)は年々高騰しており、特に広告費用の上昇が顕著です。
一方で、リピーターや紹介による顧客は獲得コストが低く、LTVが高い傾向があります。
特にSaaSやサブスク型ビジネスでは、継続利用=収益源となるため、「関係性を深めていくマーケティング」が欠かせません。
ファンマーケティングは、顧客との接点を“関係性”へ変えることで、事業の安定化とLTV最大化につながる手法といえます。
4. ファンマーケティングで得られる効果
ファンマーケティングは、単なる顧客獲得施策ではありません。
ファンとの信頼関係を深めることで、企業にとって多面的なメリットが得られます。
4-1. 顧客ロイヤルティの向上
ファンマーケティングでは、顧客との接点を「一度の購入」で終わらせず、継続的な関係構築を重視します。
たとえば、アパレルブランドが購入後にファン限定イベントを開催したり、商品の開発裏話をSNSやメルマガで共有することで、「購入した後の体験」を提供することができます。
こうしたアプローチは、リピート率や顧客満足度(CS)の向上につながるだけでなく、ブランドに対する信頼や愛着=ロイヤルティの向上にも貢献します。
また、自分が「好き」や「共感」できるブランドであれば、価格や条件に関係なく選ばれたり、SNSで自発的に紹介されるケースも多く、競合との差別化にもつながります。
4-2. 口コミや紹介による自然な広がり
ファンマーケティングの魅力のひとつが、ファンによる自発的な発信や紹介によって、自然とブランド認知が広がる点です。
たとえば、コスメブランドがSNSでユーザーの投稿を紹介したり、購入者の体験談をInstagramやXなどでシェアすることで、共感や信頼を生み、結果として新たな見込み顧客にリーチできる可能性があります。
広告ではなく「実際に使った人の声」として伝わるため、説得力や信頼性が高くなりやすく、商品・サービスの価値がリアルに届きやすいという特徴があります。
4-3. 顧客からのフィードバックが得やすくなる
ブランドやサービスの成長に関心を持ってもらえるようになると、改善のための意見やアイデアを届けてもらえる関係性を築きやすくなります。
たとえば、飲食店が新メニューを開発する際に、常連客などお店のファンを対象に試食会を開催し、味や価格に関する率直なフィードバックを得るといった取り組みがあります。
こうした双方向のコミュニケーションによってサービスの質が高まり、顧客の「関与感」も強まりやすくなります。その結果、より深く長い関係性を築いていくことが可能になります。
4-4. ブランド価値の向上と共創の可能性
顧客がファンになることで、単なる「顧客と企業」という枠を越えて、ブランドの世界観や文化を一緒につくっていく視点が生まれます。
たとえば、アーティストやアパレルブランドが、ファンの声をもとにグッズを企画したり、限定コミュニティで先行情報を共有したりすることで、「一緒に育てている」という実感が得られることがあります。
このような共創的な関係性は、顧客にとっての特別感や愛着を高め、結果的にブランド自体の価値向上にもつながっていきます。
5. ファンマーケティングで実際に行われている施策
ファンマーケティングでは、ファンに「どんな行動をしてもらいたいか」を明確にすることが成功の鍵になります。ここでは、実際に企業が導入している代表的な施策を紹介します。
5-1. SNSでの顧客参加型キャンペーン
ファンがSNSで商品やサービスについて発信することで、自然な口コミが広がります。特に、ハッシュタグ投稿や企業アカウントによるリポストなどを含む参加型キャンペーンは、「共感」を起点にした拡散力が魅力です。
たとえば、食品ブランドが「アレンジレシピ投稿キャンペーン」を行い、ファンが投稿した内容を公式アカウントで紹介するような取り組みは、参加のハードルが低く、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を生み出しやすい施策の一例です。
企業側がSNSアカウントを運用していれば、気軽に取り組めるのも大きなメリットです。
5-2. ファンコミュニティの運営
オンライン・オフラインを問わず、ファン同士がつながる場・ファンコミュニティを提供することは、ブランドへの愛着や関与度を高めるうえで非常に有効です。
たとえば、SaaS系企業がSlackやDiscordを活用してユーザーコミュニティを運営し、製品の活用法を共有したり、アップデート情報を発信したりする取り組みがあります。質問・相談の場として機能することで、サポートコストの削減にもつながるという副次的効果も期待できます。
リアルな場としては、ブランドがファン限定イベントや交流会を開催し、顧客同士のつながりを促進することで、より深いロイヤルティを育てるケースもあります。
また、コミュニティを通じて寄せられたフィードバックを商品改善に活かしたり、ファンの声をコンテンツとして紹介するなど、ファン参加型のブランドづくりを実現できるのも特徴です。
このように、ファンコミュニティは企業と顧客の関係を“対話型”に進化させ、ブランドとファンが共に価値を生み出す土台となります。
5-3. アンバサダー制度の導入
ブランドの理念に共感し、自発的に発信してくれるファンに対して「アンバサダー」という役割を付与することで、熱量のある拡散が生まれます。
「アンバサダー」というと著名人を思い浮かべるかもしれませんが、最近では、実際に商品やサービスを愛用している一般のファンを起用する企業も増えています。
たとえば、美容ブランドがアンバサダー限定のイベントや製品の先行モニター制度を実施し、リアルな使用感をSNSで発信してもらうなど、ファンとの接点を深める取り組みが広がっています。
5-4. ファンの声を反映した商品開発・サービス改善
実際のファンの声を取り入れた開発プロセスは、関与感を高めるだけでなく、商品の納得感や満足度を向上させるうえでも非常に効果的です。
たとえば、カフェチェーンがファンからのリクエストに応えて復刻メニューを期間限定で提供したり、小売店が顧客の声をもとに商品企画を行うなど、実践例は多岐にわたります。
このような「声が届いた」経験が、ファンのさらなる愛着やロイヤルティを高める要因となります。
6. ファンマーケティングが向いている企業とは?
ファンマーケティングは多くの企業にとって有効な手法ですが、「とにかく誰でもやればいい」というものではありません。
効果が出やすい業種や企業フェーズがあり、逆に、今はまだ向いていないというケースもあります。
6-1. ファンマーケティングが特に効果を発揮しやすい企業
ファンマーケティングが力を発揮するのは、「顧客との関係性」がビジネスの鍵となる企業です。特に、以下のような特徴をもつ企業では、ファンとの繋がりがそのまま売上やブランド価値につながりやすい傾向があります。
ブランドの世界観を重視するビジネスモデル
たとえば、アパレル、コスメ、ライフスタイル系など、「共感」が購入動機になる業種では、ファンの存在そのものがブランドの魅力を支える要素となります。
LTV(顧客生涯価値)を重視するビジネスモデル
SaaSやサブスク、D2C、オンラインスクールなど「継続利用=売上」となる場合、ファンとの長期的な関係構築は欠かせません。
顧客との対話チャネルをすでに持っている企業
SNSやメール、コミュニティなど接点がある企業は、ファンの声を拾いやすくスモールスタートがしやすい環境が整っています。
顧客の気持ちとつながりが売上に影響するビジネスほど、ファンマーケティングとの相性が良いと言えます。
6-2. 今はファンマーケティングが機能しにくいケース
一方で、すべての企業が今すぐファンマーケティングに取り組むのがベストとは限りません。次のようなケースでは、成果が出にくかったり、優先順位が低くなる可能性もあります。
短期で成果を出す必要がある場合(キャンペーン中心の事業など)
ファン施策は中長期の視点が必要なため、「今月中にCVを増やしたい」などの短期勝負には向きません。
低価格で大量販売が前提の業態(例:ディスカウントECなど)
「価格の安さ」や「利便性」が主要な判断軸になる場合、ファン化よりも価格訴求や利便性の向上の方が優先される傾向があります。
ブランドの軸や世界観がまだ定まっていない状態
共感を集めるには、「何を届けたいのか」「どんな価値を提供したいのか」が明確であることが不可欠です。
ただし、これらの企業もファン視点の発想を持っておくことで、いずれの成長フェーズで活かせる土台が築けます。「今はやらないけれど、将来を見据えて備えておく」という選択肢も立派なマーケティング戦略の一部です。
7. まず何から始める?ファンマーケティングの第一歩
「ファンマーケをやってみたいけど、何から手をつけたらいいか分からない…」そんな方は、まず以下のステップから始めてみてください。
7-1. 小さなコミュニケーションから始める
最初から大きな施策を考える必要はありません。まずはSNSでユーザーの投稿にリアクションしたり、メルマガで開発秘話をシェアしたりといった、小さなアクションでOK。
こうした一歩が「企業との距離感」を縮め、ファン化の第一歩になります。
7-2. 顧客の声を集めて活かす
ファンの声は、企業にとって“財産”です。アンケート、SNS投稿、カスタマーサポートの問い合わせなど、既に集まっている声を見直してみましょう。
そこには、「どんな想いで選ばれているのか」「どこに共感されているのか」のヒントが眠っています。
7-3. 社内の体制を整える(兼任 or 専任)
取り組みを継続させるためには、社内体制の整備も必要です。小規模であれば兼任でもスタートできますが、「誰が責任をもってやるのか」を明確にしておくのがポイント。
少しずつ成果が出てきた段階で、専任チームやツール導入も検討していくと、より本格的な展開が可能になります。
8. まとめ:ファンマーケティングは“選ばれ続ける”ための戦略
ファンマーケティングは、単なる流行ではなく、「選ばれ続けるブランド」になるための本質的なアプローチです。
認知を広げる施策と違い、“すでに出会った顧客”とどう関係を深めていくかにフォーカスすることで、ブランドの信頼・共感・愛着が育まれていきます。
まずは「ファンの声に耳を傾けること」から。
自社にとってできそうなことを、小さく試しながら積み重ねていくことが成功への第一歩です。
「commune」のサービス資料では、ファンマーケティングの概要や機能、導入事例などを1冊にまとめてご紹介しています。
「自社にも活かせるかも?」と感じた方は、ぜひこちらから資料をご覧ください。
ファンマーケティングの資料を無料でダウンロードする
https://commune.co.jp/wp/commune_introduction/
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
