コラム
マーケティング
262の法則とは?組織の人材分布を可視化し、強みを最大化するヒント
2025/05/23
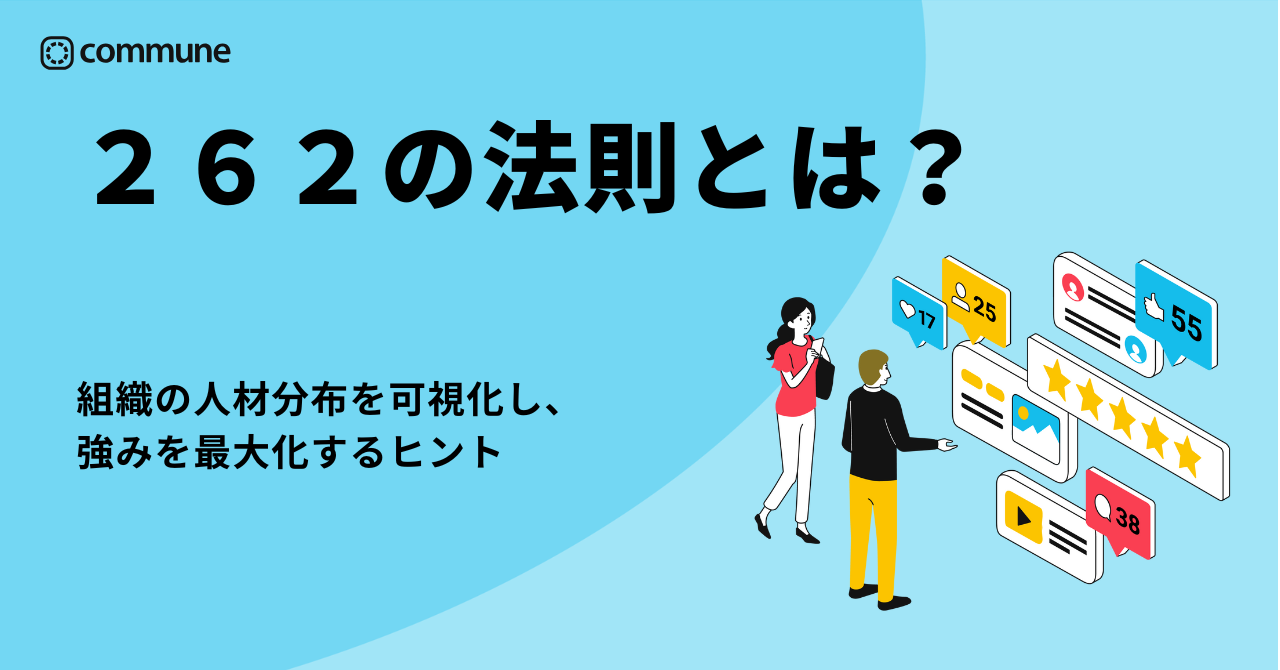
「うちの部署は、デキる人と普通の人、そして正直ちょっと問題のある人に分かれている気がする──」。そんな肌感覚を言語化したのが “262の法則” です。およそ2割がハイパフォーマー、6割が平均的なメンバー、残り2割がパフォーマンスに課題を抱える層──このシンプルな比率は、人材配置や評価制度を考えるうえで便利な “ものさし” になります。
とはいえ、数字だけを鵜呑みにすると落とし穴も。262の法則はあくまでモデルケースであり、組織のカルチャーや事業フェーズによって最適解は変わります。本記事では、法則の成り立ちと限界、活用シーン、他の組織論との比較、マネジメント施策への落とし込み方まで、全7章で立体的に解説。自社チームや自身のキャリアに照らし合わせながら、「強い組織」をつくる具体的なヒントを手にしてください。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
目次
第1章:262の法則とは何か
262の法則は、組織やチームのメンバーを 「上位2割・中位6割・下位2割」 の3層に大まかに区分し、パフォーマンスや行動特性を可視化するフレームワークです。
- 上位2割 ─ ハイパフォーマー
目標達成を牽引し、文化づくりでも模範となるコア人材。 - 中位6割 ─ アベレージパフォーマー
業務を安定的に回し、組織全体の生産量を支えるボリュームゾーン。 - 下位2割 ─ ローパフォーマー
成果が伸び悩み、場合によっては組織全体の足かせとなり得る層。
「どのチームにも“突出した数名”と“大多数のそこそこ”、そして“扱いに悩む少数”がいる――」という現場感覚を、シンプルな比率で言語化したのが本法則の強みです。理解しておくと、
- ハイパフォーマーの維持・引き上げ策
- ボリュームゾーンの底上げ施策
- ローパフォーマーへの支援・配置転換
といったマネジメントの論点が整理しやすくなります。
ただし “2:6:2” はあくまで目安。組織規模・業種・企業文化によって比率は変動し、定期的な検証と調整が欠かせません。また、しばしば混同される パレートの法則(80:20) や 働きアリの法則 とは出自も適用範囲も異なります。262の法則を盲信するのではなく、「現状を俯瞰するレンズの一つ」として活用することが、健全な組織運営につながります。
第2章:262の法則がもたらすメリットと注意点
262の法則は、組織の現状を俯瞰する「荒削りだが強力なレンズ」です。適切に使えば意思決定をスピードアップできますが、乱用すれば数字が人を裁く危うさも孕みます。ここでは メリット と 注意点、そして 現場での工夫 を整理します。
メリット — 活用すると得られる4つの効果
- 注力ポイントが一目瞭然
どの層に時間やリソースを投下すべきかが明確になり、施策の優先順位付けがしやすい。 - ハイ&ロー層の特性が浮き彫り
上位2割に共通する成功要因、下位2割に共通する障害要因を抽出しやすく、具体的な支援策を設計できる。 - 評価基準のブレを可視化
「なぜAさんは上位でBさんは中位か」を対話することで、指標の曖昧さやバイアスが顕在化する。 - マネジメントコストの最適化
全員に同じ研修を施すより、層ごとに打ち手を変えるほうが投資対効果を高めやすい。
注意点 — 落とし穴になり得る4項目
- “ローパフォーマー=問題児” という決めつけ
環境要因や一時的な事情を無視すると、本来伸びる人材を見逃すリスクがある。 - 中位6割の軽視
組織の屋台骨を担う多数派のモチベーション低下は、生産性全体の急落に直結する。 - 比率の固定化
人の成長や事業フェーズの変化を反映せず、毎年「2:6:2」で仕分けし続けるのは硬直的。 - レッテル貼りの温床
一度貼られた「下位」のラベルが内面化され、学習性無力感を招く恐れがある。
現場での工夫 — 健全に運用するための3ステップ
- 評価指標を言語化し、定期的に検証する
売上だけでなく、顧客満足度やプロセス改善貢献度など複数軸で測る。 - 流動性を担保する仕組みをつくる
OKR・ジョブローテーション・メンタリングで、層の行き来を促す。 - “ラベル” ではなく “行動” に注目する文化を醸成
フィードバックは「事実と行動」に基づき、個人の価値を固定化しない。
262の法則は万能ではありません。“数字はツール、人は主役” の視点を忘れず、状況に合わせて柔軟に運用することが、長期的な組織力向上の鍵となります。
■関連リンク:
企業の離職率が高い原因とは?離職率を改善する方法を徹底解説
第3章:優秀層(上位2割)をさらに伸ばす戦略
ハイパフォーマーは、組織がレバレッジをかけるうえで最も投資対効果の高い資産です。彼らが成長フェーズで頭打ちになると、組織全体のポテンシャルまで停滞しかねません。ここでは 「責任・裁量・報酬・刺激」 の4軸で、上位2割をさらなる高みに導く施策を整理します。
- キャリアパスの透明化と高速昇格帯の設定
昇給・昇格条件を数値と行動例で開示し、「この成果を出せば半年でリーダー層へ」という 明快な上り階段 を示す。見通しが立つことで離職リスクが低減し、長期スパンでのスキル投資を後押しできる。 - ハイインパクト案件への優先投入
新規事業や難易度の高い POC(概念実証)など、「失敗しても学習価値が大きい」プロジェクトをアサイン。挑戦の場こそ最大の報酬となり、成長カーブを一段引き上げる。 - リターン連動型インセンティブ
変動賞与やストックオプションを設け、成果が組織価値に直結した瞬間に即時還元。外部オファーとの比較で“経済的逆転現象”を起こさないよう、市場水準を常にモニタリングする。 - オープンネットワーク&コミュニティ参画支援
業界カンファレンス、学会、専門コミュニティへの参加費や登壇サポートを負担し、外部知見と人脈を獲得させる。社内外をつなぐアンテナ役となることで、イノベーションの触媒効果を生み出す。
上位層のモチベーションは「さらなる成長機会がある」と感じられるかに大きく左右されます。“抜擢と応分の報酬” をセットで用意することが、彼らを惹きつけ続ける鍵となるでしょう。
第4章:中間層(6割)のモチベーションを高める方法
組織の屋台骨を支えるのは、実はハイパフォーマーではなく ボリュームゾーンの中間層 です。彼らの生産性がわずか10%向上するだけで、全体成果が大幅に跳ね上がる――262の法則を最大化する鍵はここにあります。以下では、「目標・手本・学習・横のつながり」 を軸に、モチベーションとスキルを底上げする4つの打ち手を紹介します。
- SMARTゴール & 高頻度フィードバック
抽象的な「頑張ろう」ではなく、Specific/Measurable な指標を週次で確認。達成度合いをこまめに伝えることで、「今、自分は前に進んでいる」という心理的報酬を積み重ねる。 - ロールモデルの可視化
上位2割の優秀層が実践するプロセスや思考法をドキュメント化し、勉強会やシャドーイングで共有。「自分にも再現可能」という認知が成長意欲を喚起する。 - 自律型ラーニングパス
社内大学やオンライン研修、資格取得補助を用意し、「学習→実践→フィードバック」のループを自走できる環境を整備。習得スキルを評価に直結させると投資対効果が明確になる。 - クロスファンクショナル交流
部署横断プロジェクトや社内コミュニティで、得意分野を補完し合う場を創出。異なる視点を取り込むことでマンネリを防ぎ、「仕事が面白い」という情緒的価値を提供できる。
中間層のエンゲージメントは、“明確な成長実感” と “横の連帯感” で飛躍的に高まります。ボトムアップの活力を引き出すことで、262の法則は単なる分類ではなく、組織全体を押し上げるレバレッジとなるのです。
第5章:下位2割の問題層と向き合うために
最も頭を悩ませるローパフォーマー層も、適切な介入次第で貴重な戦力に変わることがあります。“烙印を押す” のではなく、“可能性を探る” 視点で次の4ステップを回しましょう。
- 原因診断:1on1で「事実」と「背景」を切り分ける
成果不足の背後には、スキル・マインド・環境・私生活など複合的な要因が潜む。面談では批判を控え、問いかけで自己洞察を促す。「なぜ出来ないか」より「何が壁になっているか」を探ることが肝要。 - 改善ロードマップと伴走体制の構築
3〜6か月を一区切りに、具体的かつ測定可能な行動目標 を設定。メンターやチームリーダーが進捗レビューを担当し、「小さな成功体験」を積み上げさせる。成果指標より“学習指標”に比重を置くと効果的。 - 適所適材の再検証:ジョブローテーション/異動
ミスマッチ型のローパフォーマーには “職務⇔強み” の再マッピング が有効。事務職→カスタマーサポート、営業→データ分析など、適正が劇的に開花するケースは少なくない。 - 最終判断:配置転換・退職支援も選択肢
充分な支援にもかかわらず改善が見られず、チーム全体に悪影響が及ぶ場合は、人事異動やキャリアアウトプレースメント を検討。本人にとっても「向かない環境で消耗し続ける」時間を短縮できる。
ローパフォーマー対応は 「人を活かす」vs「組織を守る」 の均衡点を探るプロセスです。レッテルではなくデータ、叱責ではなく対話 を基本姿勢としつつ、最後は組織全体の健全性を最優先に判断しましょう。
第6章:262の法則と他の組織論との比較
262の法則は「人材分布」を俯瞰するうえで強力なレンズですが、成果構造や行動特性まで立体的に把握する には、他フレームと組み合わせて眺めることが不可欠です。ここでは代表的な三つの理論──パレートの法則、働きアリの法則、ABC分析──と比較し、併用する際の着眼点を解説します。
- 主な対象:成果とその集中度合い
- 示唆:売上や利益の約8割は上位2割の要素(顧客・製品・プロジェクトなど)が生み出す。リソースを「少数精鋭」に集中する重要性を説く。
- 262との補完関係:262が「人材の層」を示す一方、パレートは「アウトプットの層」を示す。ハイパフォーマー上位2割が、本当に成果の8割を担っているのかをクロスチェックすると、投下資源の妥当性が検証できる。
2.働きアリの法則
- 主な対象:行動パターンとダイナミクス
- 示唆:常に一定割合が“サボり役”に回るという生態観察から、集団には余力やバックアップが必要であると示す。
- 262との補完関係:下位2割を単なる“不要な存在”と切り捨てるのではなく、「余剰キャパシティ」「緊急時の代替要員」といった機能的価値を再評価する視点を与える。
3.ABC分析
- 主な対象:数量化できる資源・顧客・在庫など
- 示唆:数値指標を用いて項目をA・B・Cの三層に振り分け、コストや施策の優先順位を決定する。
- 262との補完関係:262が質的・感覚的な層別に強みを持つのに対し、ABC分析は定量ドリブンで層移動をモニタリングできる。評価指標をKPI化し、四半期ごとに再分類すると、中位から上位へ何%がシフトしたかを具体的に追跡できる
併用時の3つの着眼点
- 人材 × 成果のクロス分析を実施する
262で区分した「人材層」と、パレートで示す「成果層」を掛け合わせて、「どの層のだれが成果のどこを担っているか」を可視化する。 - “怠惰”の機能的価値を認識する
働きアリの法則を参考に、ローパフォーマーを“余剰”として追い出すのではなく、リスキリングや緊急プロジェクト要員として再配置する可能性を探る。 - 定量トラッキングで層移動を促進する
ABC分析のロジックで、人材評価をスコア化→四半期ごとに再分類。中位→上位への移行率や、下位→中位への改善率をOKRに組み込むと、具体的な変化を継続的に測定できる。
関連記事:
パーセプションとは?「認識」の本質と実践
第7章:262の法則を活かして組織を進化させる
最後に、262の法則を単なるフレームワークにとどめず、自社組織の成長へどうつなげるかをまとめます。数字にとらわれすぎず、実際の人材データや声を反映しながら柔軟に活用するのがポイントです。
-
実際の人材分布を定期的に見直す
-
一度区分したら終わりではなく、半年や1年ごとにメンバーの成長度合いを評価する。
-
-
個々の“強み”を引き出す視点
-
2割の優秀層にさらに権限を与え、6割の中間層が挑戦できる枠を用意し、2割の問題層には別の活路を探るなど、個性を最大限活かす。
-
-
データ活用とHRテックの導入
-
社員の目標達成率やスキル診断結果をデータ化し、必要に応じて組織配置を変えていく。
-
-
法則の盲信ではなく、あくまでヒントとして
-
「2-6-2」はあくまで一つの目安。人材の可能性は数字だけで決まらないことを忘れない。
-
まとめ
「262の法則」は、組織を大まかに3つの層に分けることでマネジメントのポイントを分かりやすく示す便利なフレームワークです。優秀層の伸ばし方や、問題層へのアプローチ、中間層のモチベーション向上など、焦点を絞った施策を打つうえで有益な示唆を与えてくれます。
一方で、数字に縛られすぎると、人材の多様性や個別事情を無視してしまうリスクがあります。定期的に検証と修正を行いながら、個々の成長を促す仕組みを整えることが、最終的に組織全体のパフォーマンスを引き上げるカギです。あなたの職場やチームでも、262の法則を出発点に据えて、より効果的な人材マネジメントに取り組んでみてはいかがでしょうか。
コミュニティ運用、お困りではありませんか?
コミュニティ運用、
お困りではありませんか?
- 顧客の声やインサイトを拾いたいが、やり方がわからない
- そもそもコミュニティ構築が難しい、うまく設定できない
- コミュニティを作ったものの、うまく活性化できない
- 担当者の感覚や属人的な対応に頼りがち etc..
Communeは専門家による手厚い支援で、戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、戦略設計からKPI設定、運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
Communeは専門家による手厚い支援で、
戦略から運用までを伴走。
豊富な経験を持つ専任チームが、
戦略設計からKPI設定、
運営実務の代行まで一貫サポート。
成果につながるコミュニティ運営を実現します。
